「ホラー業界の可能性が広がった」7万人来場『行方不明展』と200万PV『つねにすでに』が書籍化&同時発売【ホラー作家・梨×株式会社闇・頓花聖太郎インタビュー】
更新日:2024/12/26

2024年12月16日、ホラー作家・梨さんと株式会社闇が手掛けた『行方不明展』(太田出版)と『つねにすでに』(ひろのぶと株式会社)が書籍として刊行される。
『行方不明展』は2024年夏に開催された“行方不明”をテーマに作られた展示会をまとめたもので、『つねにすでに』は2024年春にネット上で連載されていた怪談をまとめたもの。どちらもSNSを中心に大きな話題となった。
今回は、そんな『行方不明展』と『つねにすでに』を仕掛けたホラー作家・梨さんと株式会社闇のCCO・頓花聖太郎さんに話を聞いた。
※取材は12月上旬に実施

■ホラーのいいところは「実験的なものを受け入れてくれる土壌」
ーー『行方不明展』と『つねにすでに』のいずれも、お二人が手掛けられていましたが、まずはそれぞれの誕生の背景を伺えますか。
梨:『行方不明展』のいきさつから話すと、2023年3月に渋谷で実施した『その怪文書を読みましたか』という怪文書の考察型展覧会が非常にご好評いただいていて、この“展覧会”というフォーマットでなにか作れないか、というところからはじまったのが『行方不明展』でした。
頓花聖太郎(以下、頓花):『その怪文書を読みましたか』をさらに拡張したら東京中の人をあっと言わせられるのではないか、というところで再度梨さんとタッグを組ませていただくことになりました。実は、『つねにすでに』は『その怪文書読みましたか』の直後くらいにははじまっていたプロジェクトだったので、『行方不明展』よりずっと前から構想自体はあったんです。忙しくて寝かせてしまっていた時期もあるのですが、1年くらいかけてようやく生み出せたものでした。
ーーでは、お二人にとって、(リアルの)『行方不明展』と『つねにすでに』はどういう存在でしたか。また、いずれもSNS上では大きな話題となっていましたが、会期中/連載中、また終了後のお二人の手応えなどをお伺いしたいです。
梨:『行方不明展』は射程を広くして、新しい体験型のコンテンツが好きな人に向けて。『つねにすでに』は、『行方不明展』よりすこし狭く、あの頃のインターネット怪談が好きな人を中心に、洒落怖をまとめサイトなどで見ていた若い世代の人たちなど、ネット怪談(ロア)が好きな人に向けてリーチする層を明確に分けていたんです。
頓花:結果、それぞれのターゲットにはしっかり楽しんでいただけたんですが、予想以上に両方とも楽しんでくださった方がとても多かったんです。
おかげさまで『行方不明展』は7万人来場、『つねにすでに』は200万PVを突破し、どちらもありえないくらいバズって、『つねにすでに』ではさらに6,000人規模の濃いコミュニティ(Discordというコミュニケーションツールを使用したもの)も出来上がり、ホラーもここまできたな、という感覚とともに大きな手応えを感じることができました。
想定していたターゲット層を超え、いままでホラーとは縁遠かった人にも多く楽しんでいただけたので、手前味噌で恐縮ですが、ホラー業界の可能性を伸ばせたんじゃないかな、と感じています。
梨:そうですね。ホラー好きな人もそうではない人たちも楽しんでくれたので、そこはよかったと思います。一方で、ある種のムーブメントは起こせたと思うのですが、これが文化となって根付くためにはさらなる時間と良質なコンテンツが必要だとも思っています。
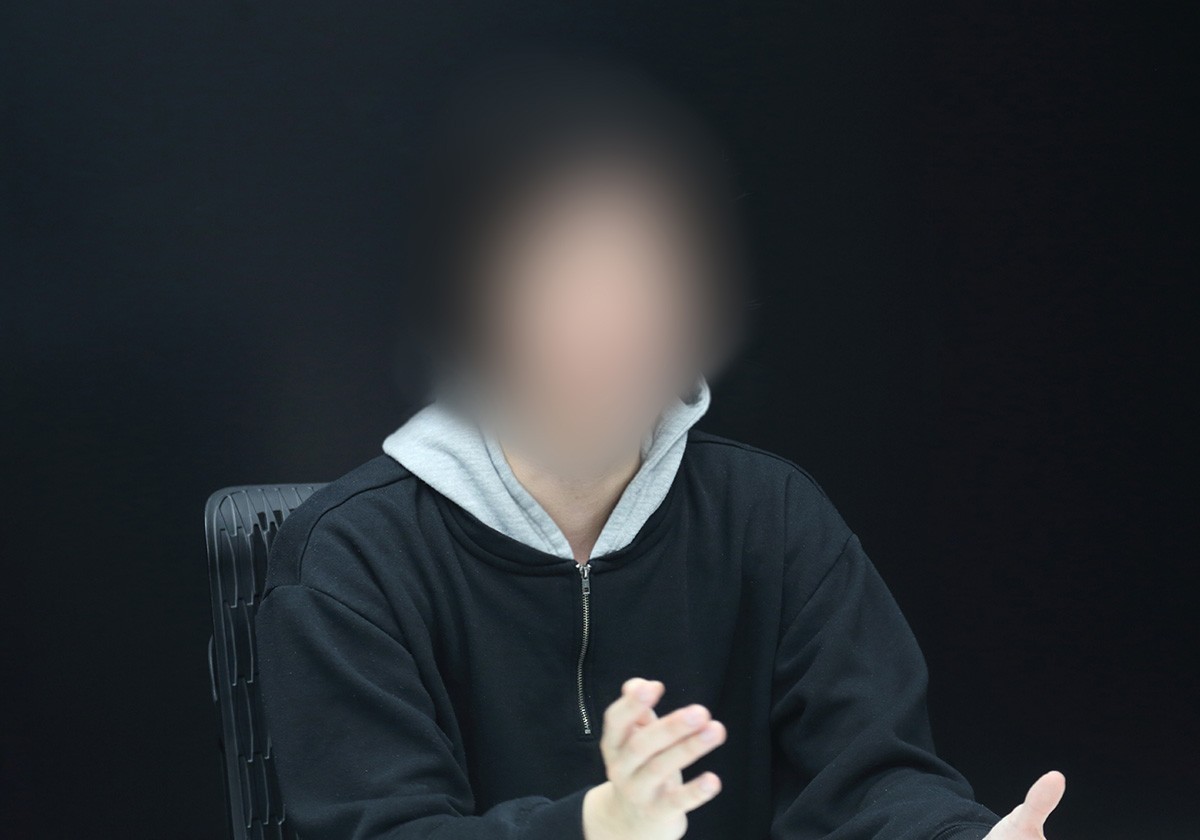
頓花:良質なコンテンツ……たしかに、マネしたらできそうと思われてしまう弱点はあるんですよね。コンテンツとしてはすごく大事なことではあるのですが……!でも、いろんな人の「作ってみよう!」が、結果コンテンツが集まることになり、それがホラー業界の可能性をさらに伸ばすことにもなるので、割と楽しみではあります。
ーーいずれもホラーに縁遠かった人も巻き込んで盛り上がったということですが、当初から射程を広くしていた『行方不明展』は予想通りとして、ここまで大きく『つねにすでに』が話題になったきっかけはどこだったのでしょうか。
頓花:梨さんがギミックを仕込んでいるタイミングがいくつかありまして、例えば、連載の途中で突然サイトの記事が全部消えるとか、復活したら情報が戻っているとか、いきなり無関係と思われていたDiscordが舞台になって物語がはじまって、みんなで乗り込めるとか……。そういうギミックのところでわかりやすくバズっていたと思います。
一番起爆力が大きかったのは、Discord内で現れた怪異と直接対話できる状況だったと思います。これは株式会社闇が独自に作ったAIを活用したシステムで、ユーザーが怪異との対話を疑似体験できる時期がありました。
梨:ホラーのすごくいいところって、実験的なものを受け入れてくれる土壌だと思っているんです。ジャンプスケア(びっくり要素)的なホラーは苦手だけど、インターネット上で擬似体験できるホラーには興味を持っている層がいて、その人たちに対して体験型コンテンツとして理解してもらえて、巻き込めたのが大きかったと思っています。






