「質問」は自分のことを知るツール! “質問で人生が変わる”理由
公開日:2018/8/17
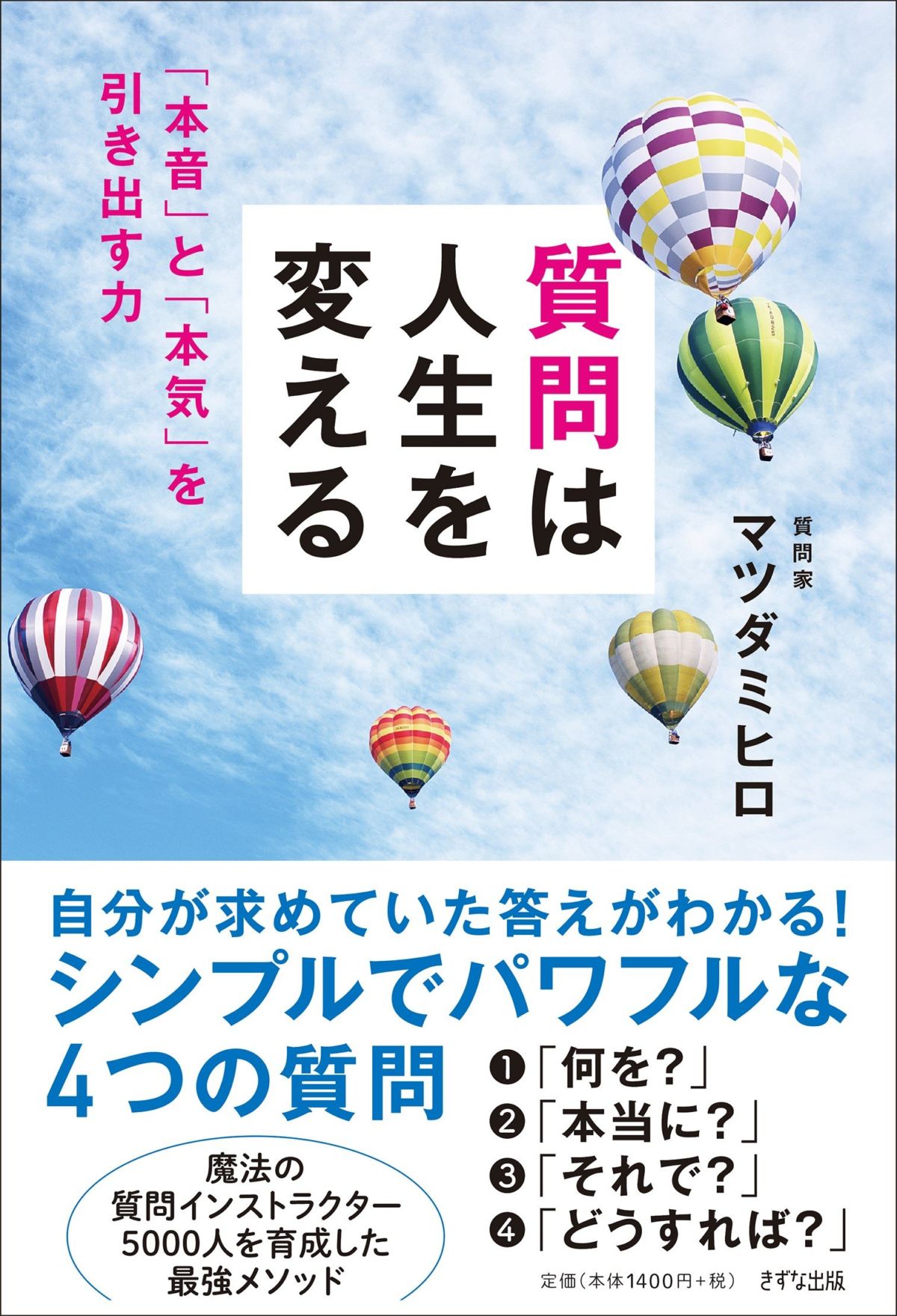
私は人と話をすることが多い仕事をしている。会話がきっかけで新しい仕事に結びつくこともあるため、会話は重要だ。もっと相手に気持ちよく話をしてもらうコツはないだろうか、と思っていた。そのようなときに出会ったのが『質問は人生を変える 「本音」と「本気」を引き出す力』(マツダミヒロ/きずな出版)である。
本書は、他人に与えるには自分が満たされることが先決だ、というスタンスで書かれている。質問は自分のことを知るツールであり、自分にたくさん質問をすることが大切だ。なぜなら質問は無意識を意識化するものだから。よい質問を繰り返すことで、自分がなにをしたいのか、なにを大切にしたいのかが明確になってくる。「質問は人生を変える」ものである、というのが要旨である。
たとえば、パーティー会場のようなところで大勢の中から短時間で自分が求めている人を見つけたいなら「私は今、どんな人と出会いたいのか」ということがはっきりしていていなければ目的を達することは難しいだろう。「人生はなにごともなさぬには長いが、なにごとかをなすにはあまりにも短い」というのは『山月記』の中島敦の言葉だ。長いようで短いからこそ、付き合う人を選ぶことが求められるといえる。
参考になったのは、よい質問とは自分の主観を捨てて事実だけを見るというもの。私たちは主観で生きている。その主観は今までの経験に基づいて出来上がっている。過去の体験や知識によって正しいことと正しくないことの判断をしているのだ。主観の奥には事実や出来事があるだけで、本来、その事柄そのものには何の意味もない。ところが、私たちはその事実に対して自分の過去の経験から意味づけをしているため、人と意見が合わないとか価値観が違いすぎるといったことを感じるのだ。
フラットな状態で人と接するためにはどうすればよいのか。そのヒントが「事実だけを見る」ことなのだ。本書では、登校拒否をしている子どもに対する質問が例にあげられている。「どうして学校に行かないの?」というのは多くの人がやりがちな質問だろう。しかし、これは主観が入った質問だ。その質問の裏には「学校には行くべきだ」という主観があるため、質問された子どもは行かない「言い訳」を答えてしまうようになるという。事実は学校に行っていないという状態なのだから、「学校に行くかわりに何をしたい?」など学校に行っていないという事実だけを取り出すような質問をするのがよいらしい。
自分は偏見が多いと思って生きている人はほとんどいないと思う。しかし、こうして考えてみると、私たちは「~べきだ」「~しなければならない」など多くの偏見を持っていることに気づく。そうした常識といわれているものを違う角度から見直すためにも、質問は重要な役割を持つのだ。
あの人と話をしていると楽しい、そう思ってもらえるようになりたいなら、質問を計画しないことも大切だ。計画どおりに会話が進まなければ「ならない」という考え方をする時点ですでに偏見が入っている。相手の話を聞く中で柔軟に質問を考えたい。よい質問は、相手の話をよく聞いていなければすることができないからだ。
質問をするなら、「返ってくる答えはすべて正解」という姿勢で受け止められる心の余裕が欲しい。答えは出なくても正解、そういう度量の広さだ。本書を読めば、よい質問をしようという小手先のテクニックを覚えるよりもよい質問を使うことの方がずっと意味があるのだということに気づく。
文=いづつえり





