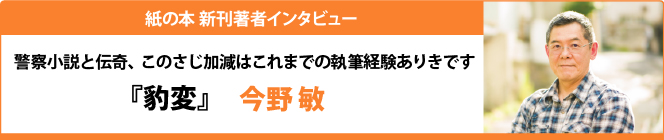警察小説と伝奇、このさじ加減はこれまでの執筆経験ありきです【今野敏インタビュー】
更新日:2015/7/6
あるべき姿を小説で示していきたい
「年をとったんですよね、私も。ついつい若い人たちに説教したくなっちゃって(笑)」
“狐憑き”現象の解明に乗り出す富野。その捜査は狐憑きとなった中学生たちの話に耳を傾け、対話をするという地道なものだ。そこには中学生、学校、父兄に対する率直な苦言も入り交じる。
「今の学校では、教師が父兄に何も言えないとか。それってヘンですよね? 先生はかつて怖い存在だった。それが教育の場のあるべき姿だと思う。今、どこか学校というものの立場がずれている。それが子どもたちにとって、いい影響であるはずはないという気がしているんです」
環境破壊問題を扱った「潜入捜査」シリーズを執筆した際、その原動力となったのは“怒り”であると以前のインタビューで語っていた今野さん。子どもたちを巡る問題が息づく本作を書き進める力となっていったものは何だったのだろうか。
「何でしょうね……でも嘆いてはいないんですよ。やっぱり理解したいという気持ちかな。中学生くらいの子どもたちを。私には子どもがいませんし、直接触れ合う機会はなかなかないんだけど、理解したいという気持ちはあるんです。それと同時に、大人たちも子どもと接することをあきらめないでほしいという想いが強くある。こういう接し方もある、ああいう接し方もあるというパターンを、富野を通じ、書いていったつもりです」
厳しいことであっても言うべきことはきちんと言う。「それが本当の優しさなんじゃないか」と語る。そうした姿勢を反映した富野と子どもたちとの対話のなかから浮かびあがってきた“狐憑き”の真実──その驚きの展開はやはり今野敏だ!
「私はプロットを作らないので、実は“この先、どうしよう”とドキドキしていたんです(笑)。ただ、潜在意識っていうのはものすごくデカいということを常に意識しているので、そのなかに何があるのかわからないということも含め、安心しているところがあって。私の小説を好きで読んでくださっている方たちは、ご自身のその部分が刺激されている人なのではないかという確信みたいなものもあります」
事件の核となる、ある人物との対話は「拳銃を撃ち合ったり、殴り合ったりするくらいの緊迫感を持たせた」と語る通り、命を懸けたような静謐な戦い。奇妙な会話のずれや余白は読む者に不安定な心地を与えていく。
「実は、この人物にはモデルがいるんです。スティーブ・ジョブズです。アップル社製品って、トリセツもなければ、どこにファイル管理されているのかもわからないでしょう? “そんなの知らなくていいんだ、俺にまかせとけ”っていうあの発想が本当に嫌で。最後に“お前ら、バカなんだから”と付くような」
自分に興味のあることにしか関心がわかない、彼のとりつくしまのない言葉に、富野、鬼龍、安倍が斬り込んでいく。その心理戦の末に迎えた結末は──。
「今、小説というものが、裏へ、裏へというか、期待を裏切る方向へ、という書き方が主流になっているじゃないですか。本来、お手本となる姿が見えなくなってきちゃったという気がずっとしていたんです。だから、予定調和、勧善懲悪と言われてもいいから、あるべき姿をちゃんと書くべきじゃないかと。本作にはそういう想いが色濃く出ているかもしれません」
受け入れているわけではないけれど、目の前で起きていることを否定し続けても仕方がないという富野の目線も、何が起きてもおかしくはない、今の世を生きる標となる。
「現実と非現実って何だろう?と思いながら書いていた小説です。非現実的だと思っていたことだって現実になることはありうると。本作を読み、そんなことも少し考えていただけたら」
取材・文=河村道子 写真=干川 修
『豹変』
今野 敏 KADOKAWA 1600円(税別)
東京・世田谷の中学校で、3年生の佐田が同級生の石村を刺す事件が起きた。だが取り調べで佐田は何かに取り憑かれたような物言いと行動で警察署から忽然と消えてしまった──少年事件課の富野は祓師・鬼龍光一とともにその不可解な事件を追っていく。『野性時代』連載中から話題となっていた一作、待望の書籍化!