朝ドラ「スカーレット」で話題! 女性陶芸家・神山清子の半生を描いた『緋色のマドンナ』作家・那須田淳インタビュー【前編】
更新日:2020/2/28

9月30日より放送開始するNHK連続テレビ小説『スカーレット』。戸田恵梨香さんが演じる主人公・川原喜美子のヒントになったのは、実在する信楽焼の陶芸家・神山清子さんだといわれているが、彼女は、作家・那須田淳さんがずっとその生涯を書きたいと願っていた人物でもある。彼女の伝記的小説ともいえる『緋色のマドンナ』(ポプラ社)はどのように紡がれたのか? 神山さんの魅力とともに、その裏側を那須田さんにうかがった。
■時代の異端児でもあった父の教育が神山清子の“自由”の礎となった
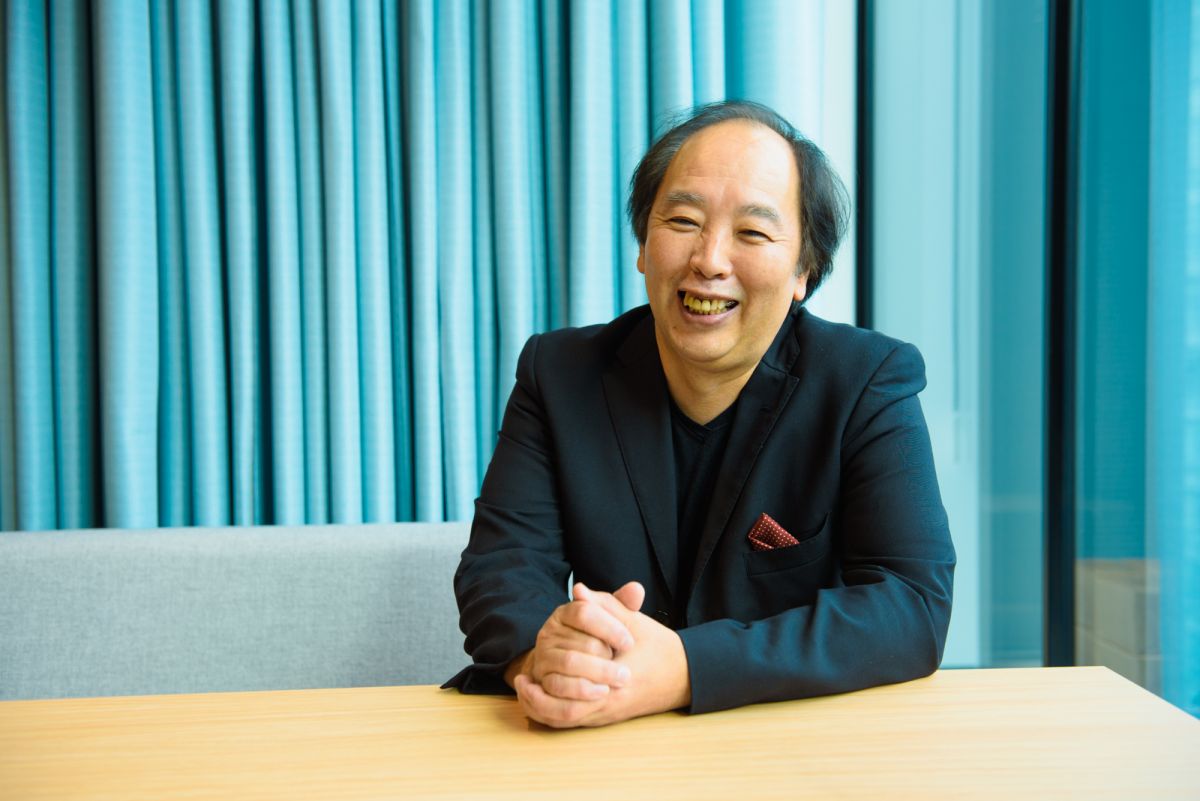
――2005年にも神山清子さんの半生を描いた映画『火火』が公開されましたが、原作となった小説『母さん 子守歌うたって』の作者が、那須田さんの父・那須田稔さんと叔母の岸川悦子さんなんですよね。
那須田 淳氏(以下、那須田) はい。僕も当時、編集の手伝いをしていたので、神山さんのことは強く印象に残っていたんです。神山さんは、白血病に倒れた息子の賢一さんのため、そして他の患者さんを救うために骨髄バンクの立ち上げに尽力された方。小説も映画もその過程が重点的に描かれているんですが、僕は“神山賢一の母”としてではなく、女性が窯に触れることも許されなかったような時代に、陶芸家の道を切り開いていった、神山清子という一個人の人生を、いつか物語として描きたいと思っていたんです。
――もともと神山さんとのご面識はあったんですか?
那須田 いえ、お電話でお話しする程度でしたね。今回、書きはじめるにあたって初めてお会いして、お話を伺ってきました。僕は彼女の陶芸作品が大好きで、そこから漏れ出る魅力からいろいろ想像していたんだけど、ご本人と作品はかなり一致している、という印象でした。ただ、取材するうちに、その半生がまあ波瀾万丈というか、想像以上に濃くてびっくりしてしまって(笑)。
――『緋色のマドンナ』も次から次へと苦難や事件が起こりますが、読んでいて、おそらく削られたエピソードが途方もなくあるんだろうなと感じました。むしろその、削る作業が大変だったのではないかと。
那須田 全部書こうとすると、原稿用紙2000枚にはなると思います(笑)。ただ僕は、彼女の人生の細部をつまびらかにしたいわけではなく、何を見て、どんなものに影響を受けて、今の作品をつくるに至ったか、彼女の芯となる部分を描きたかった。お話を聞いているうちに、お父さんの存在がずいぶんと大きいようだと感じられたので、彼女の人生という縦糸に、お父さんの教えや生き様を横糸として編み込んでいくことを決めました。
骨髄バンクのことも、すでに書かれているのだから、僕はそれ以前のことに重点を置こうと。そう決めてからは、余分なものが自然と削ぎ落とされていった感じですね。
――なかなか強烈なお父さんですよね。まだ7歳の清子に家計を預けるし、人並み以上に稼いでいるはずなのに博打好きのせいかいつもお金はないし、あげく妻と長女(清子さん)を賭けて負けてしまうし。
那須田 でもなぜか憎めない。神山さんがお話しされるのも酷い目にあったエピソードばかりで、悪口しか出てこないんだけど、でも本当はお好きなんだろうな、という印象を受けました。神山さんはボランティア活動もされる方なんですが、そういう意識はどこから生まれたんだろうと聞いてみると、お父さんが実はそういう人だった、と言われたことがあって。
――小説でも、清子を連れて8時間歩き、戦争孤児たちにおにぎりを配りに行く場面がありますね。〈いつだって腹八分目にしておけ。で、残りの二分は人に分けてやれ。それぐらいなら無理せずできるやろ。それにみんながみんな八分目なら世の中はうまくいく〉っていうセリフは沁みました。
那須田 神山さんはおにぎりをつくるとき、たくさん食べたいからお米もたくさんぎゅっと握るんだけど、お父さんは少しの量をふわっと握れとおっしゃるんですって。そうすると嵩が大きくなって、なおかつ残った分を誰かにわけてあげられるから。そういうところのある人だった、って神山さんは言っていました。
だから神山さんも、ボランティア活動をボランティアと思わず、するのが当然と思って生きてきた。お父さんは、博打もやめられない困った人だったけれど、昔から周囲からはとても慕われていた。それは彼の根っこが、人に手を差し伸べずにはいられない人だったからなんじゃないか、というのは、神山さんはあまり意識していなかったようだけれど、僕はそう感じたので、物語のなかに組み込みました。
――冒頭、清子とお母さんが売られていくシーンなんかは、なんてやつだと腹が立つんですが、読んでいると少しずつ好きになってしまう……。ずるい人です。お嬢さん育ちのお母さんも、幼い清子に家庭を丸投げするなよ! って思うものの、やっぱり憎めないし、むしろ言うことがいちいち魅力的なんですよね。
那須田 神山さんは「封建的な家庭だった」と言っているけど、時代に照らし合わせるとまったくそんなことはないんだよね。むしろお父さんは、異端児。たしかに「女は、家でおとなしく飯の支度をしていればよい」なんて言っていたけど、清子の絵の才能もいちはやく気づいて、絵描きになるといいと思っていたらしいし、清子に絵の特訓をしてくれる先生には、お礼代わりにご飯を出してくれていた。
これは小説には書ききれなかったけれど、先生が家まで来てくれたのは、清子の才能を認めていたからだけでなく、お父さんの人柄に惹かれていたのもあるんじゃないかな。お金のある家ではなかったけれど、稼げないからじゃなくてお父さんが使っちゃってない、っていう理由のせいか、子どもの教育はわりと惜しまないし、才能を伸ばす土台はつくられていた。それが神山さんの自由な作風に繋がっていったんじゃないかと思います。

■男中心の封建的な焼き物の世界で、好きなことを貫くために重ねた努力
――神山さんの陶芸作品はどういうところが魅力的なんですか。
那須田 彼女の焼く物って、すごく、あったかい感じがするんですよね。彼女は、自分の作品に全部名前をつけているんですよ。息子の賢一さんは、陶芸家としての才能を開花させる前に亡くなってしまったけれど、名づけず残した作品にも全部「これ見てどう思う?」「これは○○なあ」と無邪気に語りかけている。そんな愛情深さを見せる一方で、完全に封建的な男社会である焼き物の世界にあっても「男と勝負して勝たなきゃいけないというよりどうやったら認めてもらえるんやろか」とどこか淡々としたところがある。双方を抱いている神山さんの魅力が、作品にも出ているのかなと思います。
――女というだけで高校にも行かせてもらえず、絵付けをしたいのに職人から門前払いを食らい、弟子にもしてもらえない……。その苦境を行動し続けることで切り開いていく姿は、現代女性の勇気にもなると思いました。
那須田 男性に勝とうとは思っていないけれど、厳然として横たわる封建的な焼き物の世界において、自分が絵付けを学ぶには、作品を世に出していくためにはどうしたらいいか、ということを彼女は理性的に考える。そこから見えてきたものをまた、作品にも生かしていく。その姿はまさに、現代社会の問題にも繋がっていくだろうなという予感は、書きはじめる前からありました。
――〈女が外で仕事をするには確かに根性がいる。これはすなわち、男女が平等ではない証だった〉というところも打たれました。そのことに社会が気づきはじめて、変化しつつある、とはありましたし、今もずいぶんと改善されていますが、「家庭と仕事を両立させるには、人並み以上に頑張らなきゃいけない」という意識が、女性自身にも残っているケースが多いと思うので。
那須田 ずっと続いている問題ですよね。問題になっているということは、社会が成熟してきてようやく男女の話ができるようになった、ということでもありますが。もともと平等だったはずの男女の価値観は、とくに江戸期あたりの封建的な社会によって変容してしまったと思うんです。
家長がしっかり稼がないと家族が食べられなかった時代だから、ピラミッド型のヒエラルキーをつくらざるをえなかった。女性も稼いで家族を支えることができるのならば、そういうことはなくなりますからね。僕はね、ふだんドイツに住んでいるんですけれど、ドイツでは男性が育休をとるのが当たり前、というかだいたい男性がとるケースが多いんですよ。
――え、そうなんですか。
那須田 国が給料を保証してくれるので。男性の給料のほうが高いことが多いので、得なんです。会社復帰も、以前と同じ条件でなければいけないと決まっているから。そうすると男性は当たり前に育休をとるし、育児のことも自然と理解する。社会全体で意識を育てていけるんです。
日本ではまだ、男性が育休をとるというのがわりと特別なことでしょう。家庭のことは女性に、という意識がまだ根深い。僕は料理をしたり子どもたちの面倒も妻と変わりなく見たりするんだけど、日本でそれを知られると「お母さんしてるんですね」って言われるんです。お母さんの仕事だと刷り込まれたことを脱却していくのには、時間がかかるだろうなと思います。若い世代はずいぶんと変わってきているでしょうけどね。
――だからこそ神山さんの「勝とうとは思わないけど、やりたいことを貫くために、自分の好きなことに邁進していく」という姿勢が、読んでいる側の勇気になるのだと思います。悔しい思いはたくさんする、よけいに頑張らなきゃいけないこともたくさんある、だけど自分が好きだという気持ちを何より大事に生きていく、それでいいんだ、って思わせてくれる。
那須田 そう感じていただけたなら嬉しいですね。僕も、そこは書かなきゃいけないと思ったことのひとつですから。認められるために頑張るのは大事だけど、男性より頑張らなきゃ認めてもらえないというのはやっぱり不平等。でも、その不平等を乗り越えた神山さんのような人たちがいて、今がある。努力すればなんとかなるかもしれない、なんとかなるなら頑張りたい、と思える自分の好きなことを貫いていくのも大事だろうな、と。そして、頑張り続けているとやっぱり、応援してくれる人も現れるもので。
神山さんは、「自分には師匠はいない」って話をよくされるんですが、たしかに職人としての師弟関係は誰とも明確に結んでいませんが、人生の折々で彼女は人生の師匠とも呼べる人に出会っている。最初はお父さん、次に絵付けの白柳先生、会社に入ってからも導いてくれる人はいた。
小説では、神山さんが現実に出会った人を何人か融合させて人物造形しましたが、彼らの話を聞くにつけ、総じて感じたのは、技術ではなく生き方に通じる哲学を教えられたこと、それを神山さんが吸収し続けたことが彼女のオリジナリティに繋がっていったのだということ。どうすれば自分の理想とする表現ができるのか、どうすればもっとおもしろくなるのか、その発想の源泉は師匠たちの教えによって培われたんじゃないかと思います。
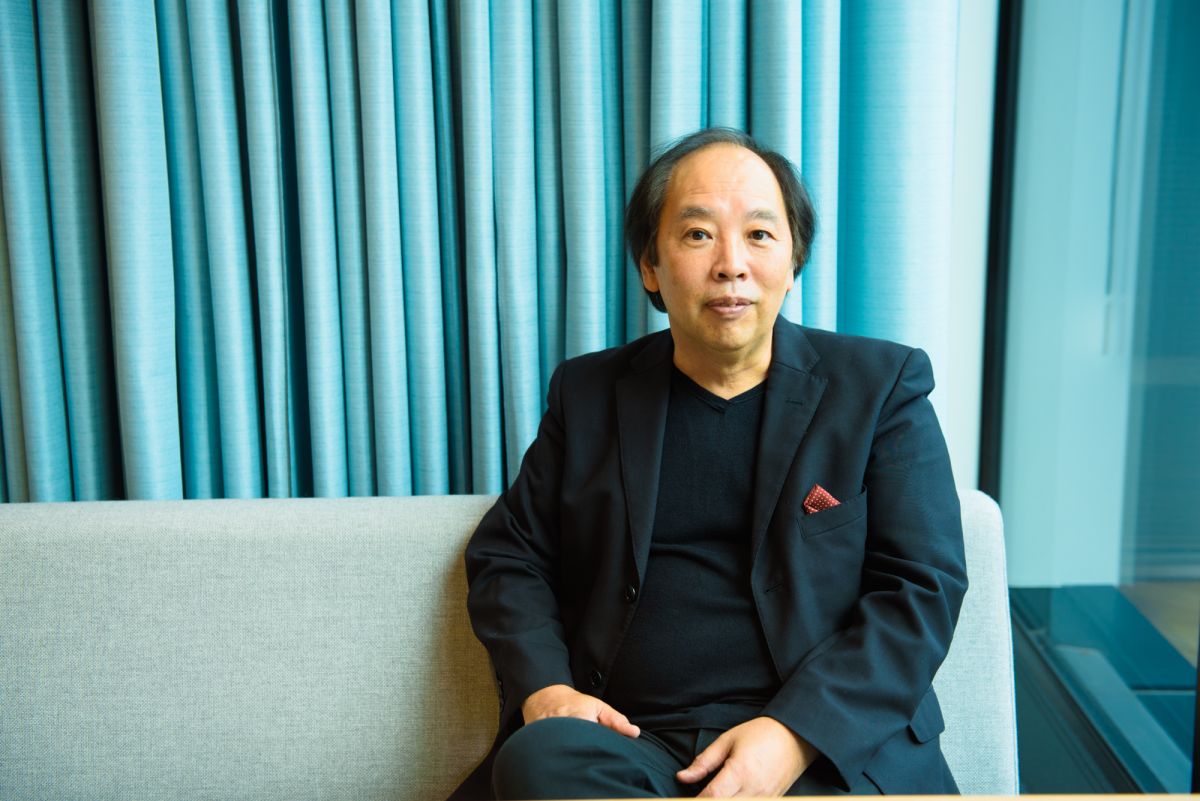
【後編】朝ドラ「スカーレット」で話題、注目の陶芸家! 男中心の世界で道を切り開いた神山清子のただならぬ才能とは?
取材・文=立花もも 撮影=岡村大輔





