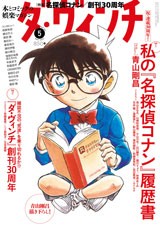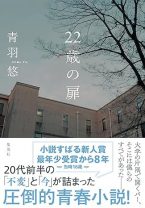毎晩1時間超“悪夢の寝かしつけ”が→10分に!! 驚きの変化をもたらした、“寝かしつけ方法”とは!?
更新日:2019/4/11
「子どもが寝たがらない」「夜泣きがひどい」「横にいてやらないと寝ない」――乳幼児のママたちに話を振ると、子どもの眠りに関する恨みつらみが出てくる出てくる。
「世間には『5分で寝る』なんていう信じられない話もあるようですが?」 と半信半疑のお悩みママに試してもらった、さまざまな寝かしつけのコツ。育児雑誌Baby-mo編集部が読者モニターに行った「寝かしつけトライアル」から、1才11カ月の男の子、Aくんのケースを紹介しよう。
■「一日まとめ」と「おやすみツアー」。2種類の入眠儀式をやってみた!
入眠儀式とは、「これをやったら眠る」と子どもにインプットするための、決まって行うワンパターンな行動。寝る時に必ず子守歌をうたう、絵本を読むなども、入眠儀式といえる。Aくんのママが取り入れたのは、2種類の入眠儀式だ。

【一日まとめ】
子どもを布団に入れたら、今日一日のできごとを物語風に語りかける。
お話のスタートは「今日、○○ちゃんは7時に起きました」。続けて「○○ちゃんは朝ご飯をたくさん食べました」「○○ちゃんは公園でブランコをしました」と、今日を振り返る。ポイントは「○○ちゃんは」と、必ず子どもの名前を入れること。こうすることで、子どもが真剣に耳を傾ける。また、感情を込めすぎると子どもも楽しくなってしまうので、あくまで淡々と事実を並べていくような語り口調で。最後は「○○ちゃん、今日も楽しかったね。さぁ、おやすみ」でしめくくればカンペキだ。

3日目までは、入眠まで40分ほどかかったようだが、4日目にいきなり大変化。

なんと、この日は15分で入眠。同時に試した「おやすみツアー」との相乗効果があったのか。
【おやすみツアー】
まずは、まだ起きている家族に「おやすみなさい」。家族へのあいさつが終わったら、テレビや冷蔵庫、ペット、お気に入りのおもちゃ、観葉植物など、家の中にあるあらゆるものに順々に「おやすみなさい」をして回る。
「おやすみなさい」のあと寝室に向かう時には、リビングやキッチンの明かりを消して、より眠りに向かう雰囲気を演出。子どもが動き回って興奮しないように、なるべく抱っこでのツアーがおすすめだそうだ。

初日から5日目まで、あまり効果を実感できなかったのが、6日目。

今まで「眠い」なんて言葉が出てきたことがないので驚愕。8日目には……

なんとなんと! 目を疑う光景。耳を疑うセリフ。「入眠儀式の威力は、すごいです!」