「まるで異世界転生もの」――約50年前に出版された本が、今14万部に迫る大ロングセラーに!
公開日:2021/4/9
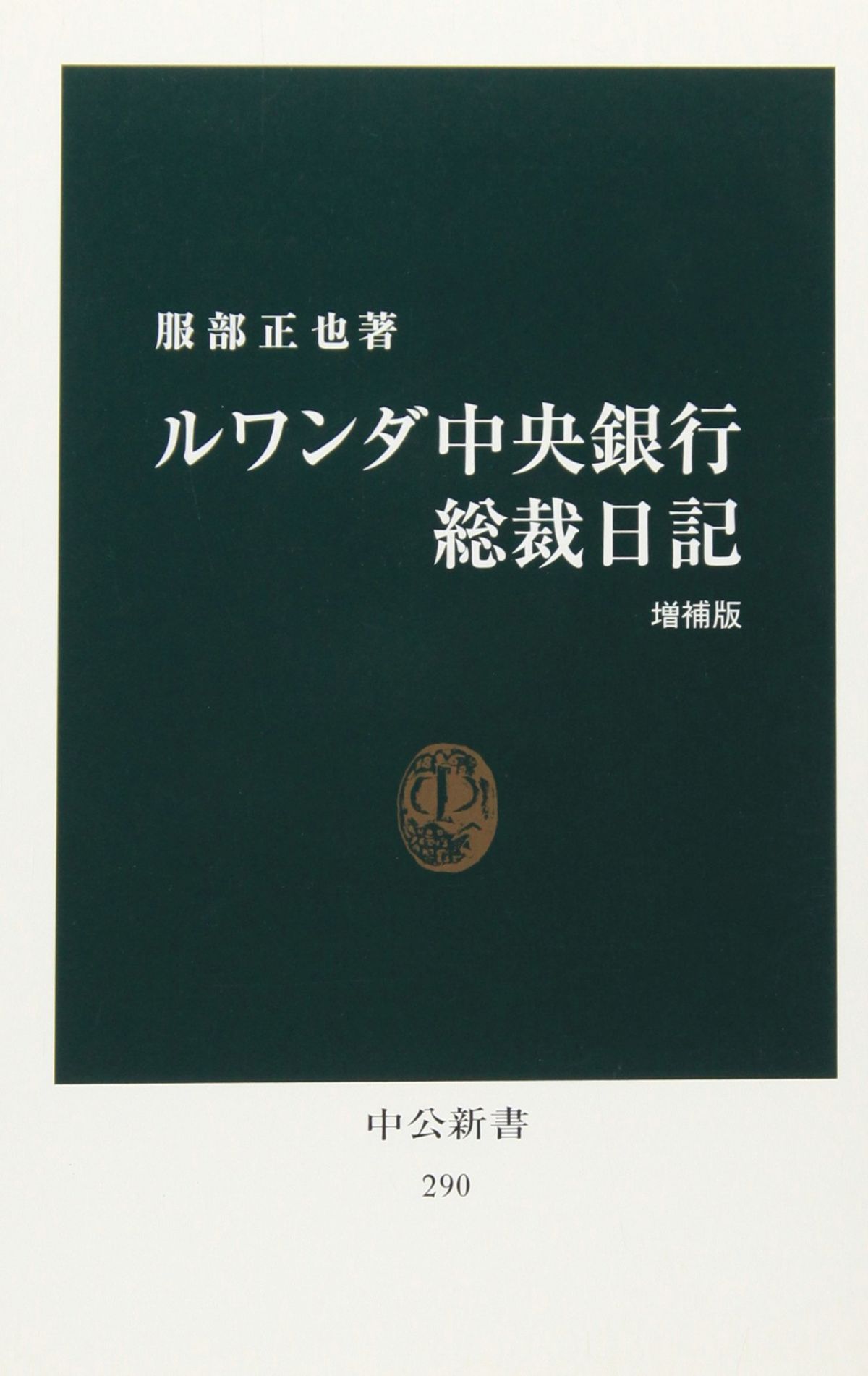
今、一躍脚光を浴びている『ルワンダ中央銀行総裁日記』(服部正也/中央公論新社)をご存じだろうか。初版出版は約50年前の1972年だが、2009年に増補版が登場したことで人気が再燃。昨年、Twitterでさらに火がつき、現在14万部に迫る大ロングセラーとなっている。しかし、なぜそこまで人気なのだろう? まずは本書の内容をひとことで言い表している秀逸な帯コピーを紹介しよう。
「46歳にしてアフリカの小国ルワンダの中央銀行総裁に突然任命された日銀マンが悪戦苦闘しながら超赤字国家の経済を再建しつつ国民の生活環境を向上させた嘘のような実話」
著者の服部氏はこのコピーにある「46歳の日銀マン」の本人であり、国際通貨基金の依頼で著者もそれまで「聞いたこともない」ルワンダの中央銀行に総裁として赴任した1965年からの6年間を記録したのが本書だ。
ルワンダは1962年にベルギーの委任統治から独立するも、ツチ族とフツ族の抗争といった内政問題や大幅な財政赤字を抱え、服部氏が経済立て直しのために中央銀行総裁に着任した1965年当時は世界の最貧国のひとつだった。首都・キガリに到着してまず目にした風景は「空港ビルはなく、滑走路の横の電話ボックスのような金属製の小屋が二つあるのが、それぞれ検疫と入国管理の事務所で、小さな机のうしろに役人が一人坐っているだけ」という簡素すぎるもので、あとの状況も推して知るべし。ファックスもメールもない時代(国際的な速報手段は「電報」だ!)、そんな地に「単身乗り込む日本のエリート」の心は簡単に折れてしまいそうに思える。が、どっこい服部氏は人間的に太かった。「現に人間が住んでいるところなら、自分が生きてゆけないわけはない」「戦争中にいたラバウル(パプアニューギニア)を思い出した」とあまり意に介さず、「これ以上悪くなることは不可能であるということではないか。(中略)要するになんでもいいから気のついたことからどしどしやればよいのだ」とどっしり前を向き、意欲的に経済改革に突き進む。
ところで植民地から独立した国は大抵外国人(主に欧米人)が既得権益を貪っているもので、ルワンダも例外ではなかった。「ルワンダ人はなまけもので、まかせておくと大変なことになる」という偏見が横行し、ルワンダを援助する名目で赴任しているのに誰も真剣にルワンダの未来を考えていない――そんな状況に怒りを覚えた服部氏は「途上国の屈辱的な地位を考え、またそれに対抗できる日本人という立場の強さを思った」と、欧米人相手にもプライドを持って決してひるまず、相手を真剣な議論に巻き込み時には対決も辞さない。さらに偏見に惑わされることなく、服部氏はあくまでも「自分」で現場を見て多くの声を聞くことでルワンダ人のポテンシャルを確信。彼が推し進めた経済政策はいずれも自ら実感したルワンダ人の力をベースにした民衆に寄り添うものであり、紆余曲折はありながらもきっちり結果を出していく。SNSには「まるで異世界もの」「ラノベにできそう!」との声もあるが、その肝のすわり方と実行力、なにより使命感を持って一国を立て直すというスケールの大きさが多くの人を魅了するのは間違いない。
なお服部氏が去ったのち、ルワンダは一貫して発展を続け「アフリカの模範生」として国際的に評価されるにいたった。だが1990年代、映画『ホテル・ルワンダ』でも描かれた「ルワンダ大虐殺」にいたる武力闘争が激化し、多数の難民を生み出し苦難の時代を迎えてしまう(2009年の増補版ではこの動乱をめぐる「ルワンダ動乱は正しく伝えられているか」が加えられている)。だが動乱期の以前にはルワンダにこんな黄金期があったこと、しかもその興隆に日本人が大きな役割を果たしていたことは案外知られていないのではないだろうか。まだまだやれる! ――世界を舞台にタフで誠実に活躍した服部氏の姿が、鬱々としがちな心にがつんと爽快な一撃を与えてくれる1冊だ。
文=荒井理恵























