人間の本性を暴きたくなる欲望を抑えられない――才能を開花させていく探偵が辿りつくのは…ビターなミステリ連作短編集
公開日:2022/1/28
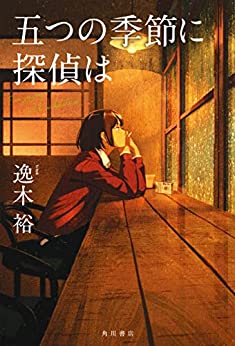
わたしはね、〈人間〉を見るのが好きなんだよ。他人の皮を剝いで、その奥にいる〈人間〉を見たい。そういうものにずっととり憑かれてる――『五つの季節に探偵は』(逸木裕/KADOKAWA)の主人公・みどりのセリフである。高校時代、熱中できるものが何も見つからなかったみどりは、みずからのことを〈常温の水道水〉と表現していた。口当たりがよく、温度もちょうどよく、それなりにミネラルも入っていて、まあまあ美味しい水道水。そんな自分に大きな不足を感じることもなく、自分はこのままたんたんと生きていくのだろうと思っていた彼女だが、唯一、他人と比べて少し変わっていることがあった。父親が調査会社を営んでいる、いわゆる探偵だということだ。
同級生もそれを知っているから、ときどき「お父さんに調査してもらってよ」なんて頼まれることもあったみどりは、同級生の怜から持ち込まれた「教師の弱みを握ってほしい」という依頼も当然、無理だと退けた。けれど怜は「だったらみどりが調査してよ」と食い下がる(父親の仕事を見たことがあるんだからできるでしょう、という理屈なのだが、小説に限らずこういうことを言う人たちは、父親がたとえば車の故障を直しているのを見たことがあるからといって、父親を真似て自分も車を直せるのか?と思ってしまう…)。さらに「調査してくれなきゃ、先生の家に火をつける」とも。そこまで怜が追い詰められている背景に、クラス内のいじめがあると知っていたみどりは、脅される形でしぶしぶ承諾。教師の尾行をはじめるのだけれど、ここで思わぬ才能を発揮し、味をしめてしまうのである。
その後、本腰を入れて受験勉強をはじめてみたら京都大学に受かってしまったくらいだし、そもそも若いときから常に冷静でいられる人は、頭の回転が人よりはやいということ。観察力と洞察力を自覚的に磨きはじめたみどりは、大学卒業後、父親の調査事務所に就職し、探偵として次々と成果をあげていく。
本作では、2002年高校時代の春、2007年大学時代の夏、そして社会人になってからの2009年秋、2012年冬、2018年春という5つの年代と季節を描き、みどりが解決した事件を通じ、彼女自身の変遷を追っていくのだが、真実が常に依頼人を幸せにするとは限らない。むしろ、誰かがひた隠しにしてきたことを、どんなものでも暴き立てるのが探偵の仕事だ。情に流されて真実を伏せては、露見したときの信用問題にもかかわってくる。だからみどりが、誰に恨まれても、誰も望んでいなくても真実を明るみに出すのは職業倫理上、当然のことなのだけど……彼女をかりたてるのは、〈人間〉を見たいという己の欲望だ。そんな自分は人として間違っているのではないかと葛藤する彼女が、最終的にどこに辿りつくのかが、読みどころのひとつである。
個々の事件も非常に練られていて、とくに稀少な香料をめぐる調香師の事件は、香りをこんなふうに事件に絡ませるのかと驚かされる。旅先で出会った女性から聞かされた指揮者とピアノ売りの恋の顛末を、聞いただけで解決してしまうみどりの安楽椅子探偵物語も構成の妙にはっとさせられる。これでもかというほどさまざまな要素が詰め込まれ、驚きに満ちた贅沢な1冊である。
文=立花もも





