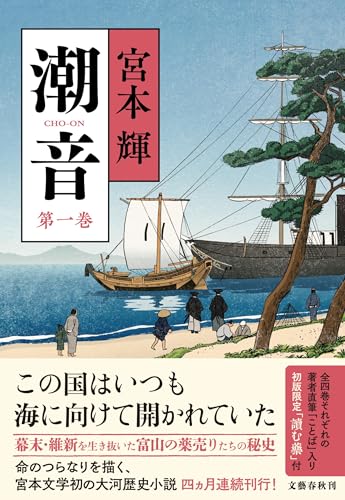まさに“読む薬”……幕末・維新の激動に立ちむかう「富山の薬売り」を熱く描く、宮本輝、初の大河歴史小説・開幕篇【書評】
PR 公開日:2025/1/20
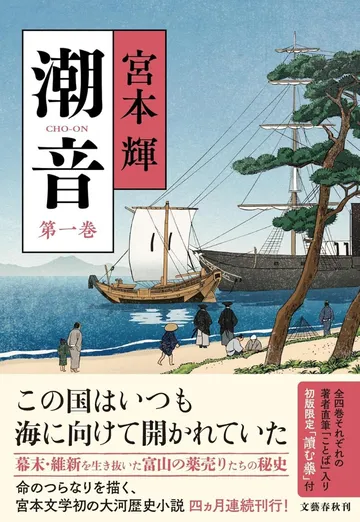
山裾の、寒く雪に閉じ込められたような場所から、常に外を、世界を目指す人たちがいた。「富山の薬売り」——その存在は知らぬものはいないだろうが、想像したことはあるだろうか。まだ交通網が発達していなかった時代、彼らは東北や蝦夷、四国、果ては九州の薩摩まで、自らの足で薬を売り歩いた。そこにどんな苦労があったのか。どんな思いを抱えていたのか。今、あるひとりの男の熱き生き様が鮮やかに浮かび上がる。
そんな作品が『潮音 第一巻』(文藝春秋)。宮本輝、初の大河歴史小説、開幕篇だ。4カ月連続で刊行されるこの作品を読むと、「富山の薬売り」となった男の誇り高い姿に胸打たれずにはいられない。人間を描き続けてきた宮本文学の集大成といえるのではないだろうか。まさに“読む薬”。英雄ではなく、一職業人の視点から描くこの歴史小説は、ページをめくればめくるほど、心にじんわりと温かいものが広がっていく。
はるばるこのような山裾の、町とも村ともつかない片田舎までご足労下さいまして、ありがとうございます。
そんな一文で幕を開けるこの物語は、幕末の越中八尾、今でいう富山市の南部に生まれた川上弥一の優しい語りで紡がれていく。越中八尾を訪れた私たちに弥一はこの町を案内しながら、町の歴史を、自身のこれまでを語るのだ。代々の家業である紙問屋の長男として生まれた弥一は、16歳の時、学問所の成績が良かったためだろうか、「富山の薬」を守るための役所・反魂丹役所の重職の方から半ば命令のようなお達しを受けて、富山城下の薬種問屋・高麗屋に奉公することになった。弥一は意気揚々と高麗屋の暖簾をくぐったが、忌まわしいもののように扱われ、与えられたのは、作業所前の廊下に座っていることだけ。だが、その苦境を耐え抜き、やがて、薩摩藩を担当する行商人として、次第に薩摩藩の内情に通じていくことになる。
ときは幕末。国が大きく変わろうとしていた時代だ。阿片戦争による清国の屈辱、オランダの特使による警告、アメリカの捕鯨船の日本周辺での活発な操業……。全国津々浦々を歩くことで日本全体の事情に常に接していた薬売りたちは、早くから異国の脅威を感じていた。開国となれば、薬売りにとっても一大事。鎖国時代、出島だけが唯一世界との接点だったと思っている人も多いだろうが、越中富山の売薬と廻船問屋は手を組んで、蝦夷地、富山、薩摩、琉球、清国という秘密の交易路を作り上げていた。清国が求めていたのは、風土病の唯一の特効薬になる昆布。弥一の薩摩組は、それを蝦夷地で買いつけて薩摩まで運び、その見返りとして琉球経路で輸入される唐薬種を入手していた。そこで得られる大量の唐薬種は「富山の薬」を支える根幹。だが、開国となればどうなるのか。弥一をはじめとする薬売りたちはあれこれと思索を巡らしていく。
そんな密貿易で結ばれた富山の薬売りと薩摩藩との関係は複雑だ。財政難に苦しむ薩摩藩と唐薬種がほしい薬売りとの間では、常に駆け引きが行われている。薩摩は富山の薬売りに「行商禁止」を言い渡してきたり、はたまた富山の薬ではなく薩摩の薬を売れなどと言ってきたりする。だが、彼らはめげない。
一途で誠実なものだけが勝つ。策ではない。そのときそのときで知恵の限りを尽くす。そして忍耐、忍耐、忍耐だ。
この本にみなぎる、「富山の薬売り」の矜持、その辛抱強さに思わず圧倒させられてしまうだろう。
薬売りたちは全国各地で商いをする。遠路を歩くのだから、体が頑健である必要はあるし、読み書き、算盤ができることは当たり前。その場その場での臨機応変な知力や判断力も必要になる。だが、何より大切なのは、売り手たちの人柄なのだろう。温厚で忍耐強く、一途。だからこそ、「富山の薬」は信頼されてきたのだ。誠実に生きる弥一の姿に、ビジネスに必要なものは何か、その真髄をみせられた気がする。
時代が移り変わるなか、弥一は、「富山の薬」の未来をどう導くのか。めまぐるしく時代が変わるのは、現代も同じ。幕末・維新の激動に立ちむかう青年の姿を描いたこの本は、悩めるあなたのこれからにきっと「効く」に違いない。
文=アサトーミナミ