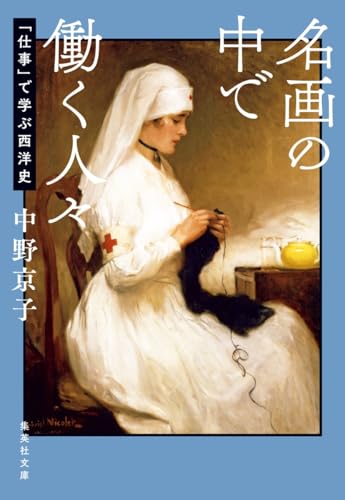「女性なら誰でもできる」と認識されていた看護の仕事の変遷は? 「怖い絵」シリーズの著者が記す、西洋絵画の中で働く人々の変化【書評】
PR 公開日:2025/9/19
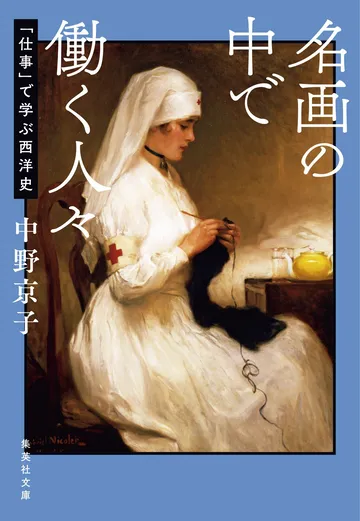
あなたは「絵の展覧会」にいったとき、作品をどんなふうに味わっているだろう。もちろん楽しみ方は自由だから、「有名な作品」「有名な作者」といった価値を意識したっていいし、「美しい!」「なんか気持ち悪い」など自分の感覚ファーストだっていい。だが、少し絵に描かれていることを「読み解く」視点を持つとさらに楽しめるのかも。そんな絵の鑑賞の面白さを広げてくれるのが、「怖い絵」(KADOKAWA)(「恐怖」という観点で絵を読み解く面白さを教えてくれた人気シリーズ)で知られる中野京子さんの一連の著作だ。
このほどそんな中野さんの著書『名画の中で働く人々 「仕事」で学ぶ西洋史』(中野京子/集英社)が文庫化された。西洋絵画にはさまざまな人間が描かれてきたが、こと作中の人物の「仕事」に注目してみると、意外な西洋史のストーリーが見えてくるという。本書が取り上げるのは「大工」や「警官」「政治家」といった日本でも馴染みのある仕事に加え、「闘牛士」「道化」「羊飼い」といった西洋ならではの仕事など全20職種。それらの仕事のルーツや歴史を、現代アメリカ絵画まで幅広いジャンルから50点以上の作品をベースにして読み解いていく。
たとえば我々にも身近な「看護婦」(作中の表記ママ。以下同)をみていこう。かつて看護や介護は家庭で母が娘に教える家事労働の一つとしての「女なら誰にでもできる仕事」として認識されており、病院や救貧院、戦場看護婦は「老いた娼婦の行く先」とまで言われて軽蔑されていたという。だが医学の急速な進歩は看護婦の専門性を次第に必要としはじめる。そんな時期にディケンズは長編小説『マーティン・チャズルウィット』(1844年)の中に戯画的にステレオタイプの看護婦「セイラ・ギャンプ」を登場させた。これは現場の実態がひどい有様で、早急に看護改革を進めなければいけないという時代の空気の反映だ(その恐ろしいヤバさは本書で紹介されている『マーティン・チャズルウィット』アメリカ版の挿絵(画:ソロモン・アイティンジJr.)が伝えてくれる)。そんな状況を大きく変えたのは、あのナイチンゲールの登場。クリミア戦争における彼女が率いた商業看護婦&修道女たちの衛生的かつ献身的な活躍は世間で大注目となり、一気に看護婦のその存在意義を高め、結果的に女性たちの「新しい職業選択の道」も切り拓くことになる。本書にはそんな新しい女性たちを描く2作も紹介されている。「白衣の天使」の強い使命感と慈悲の心が伝わる『善きサマリア人』(ガブリエル・ニコレ)は女性たちの静かな「希望」を、近代的病院に彼女たちがしっかり働いている姿を描く『手術室のエヴゲーニ・パヴロフ』(イリヤ・レーピン)は女性たちの「自信」を伝えるかのようだ。
このように「当時、なぜ彼(彼女)が描かれたのか」「どのように描かれているのか」を深読みすると見えてくる歴史がたくさんあるのだ。とはいえ、そんな学びを得ることができるのは、中野さんのような名ガイドがいてくれるからこそ。本書で中野さんの視線&思考を追体験しつつ、いつか自分でも「?!」を探せるようになったら、より絵画鑑賞が面白くなりそうだ。
文=荒井理恵