ホラー作家・梨が激推しする“知的好奇心を満たす”モキュメンタリーホラー小説とは? コンテスト受賞作から考える、新たなヒットの作り方【梨×スターツ出版編集者対談】
公開日:2025/10/8
得意分野と接続することで、新たなモキュメンタリーホラー小説が生まれる
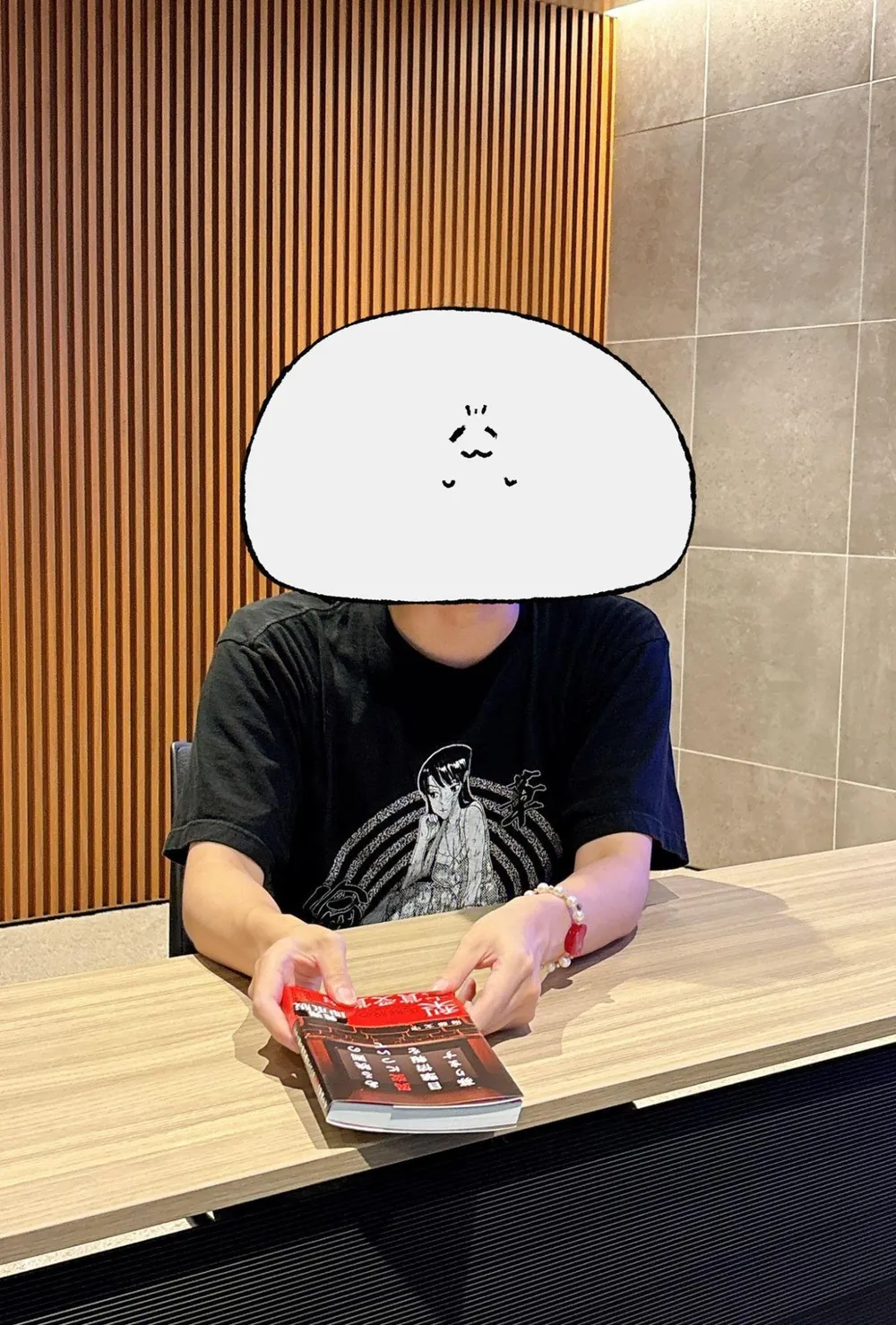
──今回、コンテスト開催にあたって梨さんが寄せた解説には、「『モキュメンタリーホラー小説コンテスト』はとても難しい縛りである」という一文がありました。とはいえ、250作品近い応募があり、大きな手ごたえを感じているのではないでしょうか。
梨:この解説文では、「みんな難しいと思っているから安心して」と最初に言っておきたかったんです。モキュメンタリーは、意外とやれることが少ない。じゃあ、どうやって発想を飛ばせばいいかということを書いたつもりです。
私はもともとSCP財団で活動していましたが、そこで何度か怪談コンテストを主催したことがあり、主催者の立場でどうすれば参加者を増やせるか、ずっと考えていたんですよね。ホラー小説を書くにあたり、一番難しいのはオチを考えること。山場になる怖いストーリーはいくらでも思いつくのに、風呂敷が畳めないことがよくあって。
しかも今回は「モキュメンタリー=方法論」「ホラー=ジャンル」「小説=表現媒体」「コンテスト=発表時期」という4つの縛りがあるわけです。最初に聞いた時は「むずっ!」と思いました(笑)。
林:梨さんの解説を読んで、あらためて「難しい縛りだったな」と思いました。
梨:だからこそ、自分の得意分野をそこに接続させてほしいと思ったんです。サイコ系が得意な方なら「復讐系サイコホラー×モキュメンタリー」が書けるでしょうし、SFが好きな方なら「宇宙人が出てくる2300年のモキュメンタリーホラー」を書いたっていい。「好きなジャンル、得意なジャンルと接続させた時にシナジーが生まれるんだよ」と、解説文で後押しできたらと思いました。
──梨さんもモキュメンタリーホラー小説を執筆されていますが、やっぱり難しいジャンルだと感じますか?
梨:難しいです。なぜかと言えば、オチのバリエーションが少ないんですね。情報をいろいろなところから集めた時に何が起こるのか、もしくはその情報を集めているのは誰なのか。要はハウダニットとフーダニットの2種類しかオチがないので、着地が難しいんです。
そもそもモキュメンタリーは、表現手法のひとつに過ぎません。表現手法を縛ったら、オチも縛られますよね。作り手側からすると、そこでどうやって味を出すかが非常に難しい。音楽にたとえると、ロックやクラシックで飯を食っていくことはできますよね。どちらもジャンルですから。でも、「イントロがなくていきなり歌から始まる曲1本で食ってます」なんて音楽家はいません。同じように、モキュメンタリーホラー小説1本で40年食い続ける作家はたぶん現れないと思っています。なので、先ほどお話ししたように、自分の得意ジャンルと接続して、新しい可能性を探るしかないんです。
新たなアイデアを生むには、幅広いインプットが重要
──第1回「モキュメンタリーホラー小説コンテスト」は成功を収めました。第2回を開催する予定はありますか?
林:ぜひ開催できたらうれしいです。梨さんがおっしゃるように難しい側面もありますが、第1回で初めて「ノベマ!」に投稿してくださった方もいらっしゃいます。こうした作家さんにもまた投稿していただけるよう、2026年には第2回を開催したいと考えています。
──梨さんは、日々膨大なコンテンツに触れてインプットされています。今後コンテストに応募される方に向けて、インプットに関するアドバイスはありますか?
梨:モキュメンタリーホラー小説コンテストに応募するからと言って、モキュメンタリーホラー小説ばかりをインプットするのはやめたほうがいいと思います。発想の幅が狭くなりますから。
むしろ、まったく関係ないものを見ている時に、「これとホラーを結び付けたら面白いな」というアイデアが生まれると思うんです。例えば、炊飯器の取扱説明書がだんだんおかしくなっていったら怖いじゃないですか。「保温したまま放置しないでください」「濡れた手でコンセントに触らないでください」という文章に交じって、「保温後2時間経過するとアラームが鳴ります。その時、絶対に後ろを振り返らないでください」とあったら怖いですよね。そこから炊飯器を販売している家電量販店店員へのインタビューが始まり、「日本人にとって米とは?」という歴史、「昔はお賽銭の代わりに米を撒いていた」という米にまつわる習俗から呪術的な話に発展させることもできるはず。
いろいろなジャンルを分け隔てなく読んでいくと、フックになる面白いアイデアが浮かぶことがあるので、今この記事を読んでいるホラー好きはスターツ出版の作品を20冊読んでください(笑)。
──コンテスト以外にも、今後スターツ出版ではホラージャンルを拡大していく予定はありますか?
林:ぜひ広げていきたいと思っています。スターツ出版文庫アンチブルーの『センタクシテクダサイ その絆、本物ですか?』などのデスゲーム系や復讐系、サイコ系は、すでに中高生を中心に人気を得ています。それに加えて、モキュメンタリーホラー小説にも力を入れていきたいですね。
実は、梨さんにもスターツ出版から著書を刊行していただく予定があり、現在企画を進めているところです。
──梨さんは、この先どんなことに挑戦する予定ですか?
梨:大阪・関西万博会場で開催されている「Study:大阪関西国際芸術祭」で、新曲を出しました。知り合いのボカロPや歌い手と音楽を作り、ホラー的なインスタレーションと音楽の融合として展示を行っています。
これからもジャンルを越境して、いろいろなところからホラー沼に引きずり込みたいですね。広義のホラーや不気味なものを「こんなに面白いんだよ」と、ロビー活動で広めていきたいです。
取材・文=野本由起 写真=編集部






