佐藤優が説く「21世紀の新しい愛国心」とは。「国家」「国民」「民族」の概念を整理し、現実の諸問題を考える『愛国の罠』【書評】
PR 公開日:2025/10/16
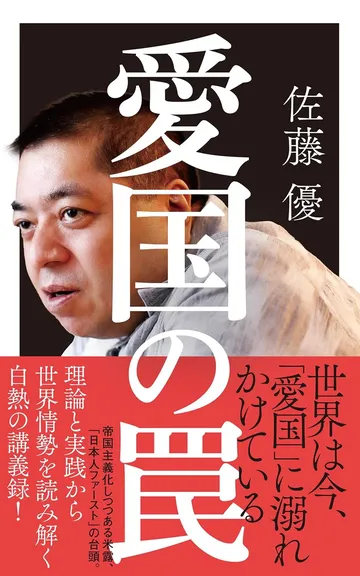
今、欧米を中心に、世界のあらゆるところで右傾化、排外主義的な動きが勢いを増している。7月の参院選挙で参政党のスローガン「日本人ファースト」が注目を集めたように、もちろん日本も例外ではない。是非はともかく、今、なぜ世界はそうした状況になっているのか。「日本人ファースト」の「日本人」とは何を指すのか?――このほど、そんな疑問渦巻く脳をスッキリさせてくれそうな一冊が登場する。その知識量と世界を読み解く鋭い視点に定評のある、元外務省主任分析官で作家の佐藤優さんの新刊新書『愛国の罠』(ポプラ社)だ。
本書はもともとそうした世界的傾向の中で「愛国心」にどう向き合えばいいのか、「21世紀の新しい愛国心」をテーマにした佐藤さんの7時間にわたる講義録だ。
「今後、どのように変化していくのかを正しく予測するために必要なことは何か。それは『現状分析』です。そして、正しく現状を分析するためには、国家や国民、あるいは民族といった基本的な概念をいくつか整理していかなければいけません。なぜなら、国家や国民というものは、実は「生き物」だからです」と佐藤さん。そのため本書ではまず古典的な書籍をもとに「国家」や「国民」、「民族」などの〈概念〉をあらためて整理していき、現実の諸問題を実例に解説していく形を取る。
取り上げるのはマルクスの『資本論』、アーネスト・ゲルナーの『民族とナショナリズム』、スターリン思想といった国家論・民族論の古典的な名著から、柄谷行人の『帝国の構造』やエマニュエル・トッドの『西洋の敗北』といった優れた書籍の数々――というと取っ付きにくさを感じる方がいるかもしれないが、講義という「耳」で聞く情報をもとに編まれた本なだけに、最初から「本」として書かれた著作より論理的組み立てをつかみやすく、わかりやすいのでご安心を。さらに本書では、こうした抽象的な理論を踏まえた上で、まさに今、起きている問題を取り上げながら具体的に考えていく。それはウクライナ問題であり、トランプ大統領であり、イスラエル問題であり、日本の現状であり…この視点が実にビビッドで面白い。
中には「古い概念が本当に役立つのか?」と思う方もいるかもしれない。だが、たとえばスターリン主義は今も私たちの社会への影響がさまざまに残っていたりする。たとえば彼の民族に関する理論および民族政策の枠組み(民族を「独立国」「自治共和国」「文化自治」という3段階に分けてヒエラルキーを固定化した)は、今の世界のほとんどの民族政策のベースになっているのだ。スターリンというと「大粛清を行った残虐な政治家」のイメージが先行しがちだが、実は哲学者、経済学者、歴史学者、言語学者、そして専門ではないが生物学にも関与した知識人。広範な知識を持っていただけに、私たちの気付かない部分でまだまだ影響力があるのだという。そんな視点から世界を見直すと、あらためて「納得」することが多いのは予想できるだろう。
日本では「愛国心」という言葉をどうしても避ける傾向があるが、こんな時代だからこそ、「愛国」「国民」「民族」という言葉の定義、現在の枠組みにいたる思想などをイチから考え直すのは大事なことだ。この先、私たちはどうすべきなのか、そのヒントも見えてくる一冊だ。
文=荒井理恵




