「街そのものが過去よりも未来を多く持つ」札幌に近代都市を作った人々を直木賞作家が描く『札幌誕生』【書評】
公開日:2025/11/26
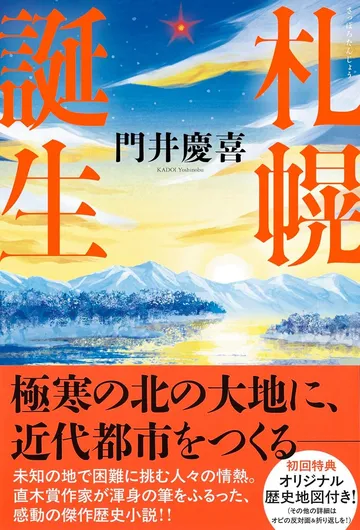
雄大な自然、地平線まで続く畑、真っすぐな道路、そして整然とならぶ街区。北海道を訪れると目にするこれらの景色はしかし、たった百数十年前には一面原野であった。
『札幌誕生』(門井慶喜/河出書房新社)は、明治期に原野から人の手により作り上げられた北海道最大の「札幌」を軸に、この人工都市と関わった実在の人物たちを描いた歴史小説である。
第一話「開拓判官」では佐賀藩出身の島義勇を主人公に、明治2年(1869年)に開拓判官として北海道に着任した島が、札幌と銭函を結ぶ新道の敷設や、碁盤の目にならぶ街区の下地を作るなど札幌の礎を築くまでを描く。島は松浦武四郎と出会い、北海道開拓のための首都は「まんまんなか」である札幌の地でなければならないとして、札幌の開発に魅せられていく。佐賀では江藤新平らとともに起こした「佐賀の乱」で知られる島義勇だが、北海道では「北海道開拓の父」と呼ばれ、その人物評の振り幅の大きさから、幕末から明治における時代のダイナミズムを感じられる物語である。
また北海道の開拓は無人の地を切り拓いてきたのではなく、そこには先住民であるアイヌの存在があった。第三話「人の世の星」ではアイヌの歌人、バチラー八重子の眼差しから、“和人”によって急速に変化する故郷や札幌の街が映し出されていく。八重子の故郷である有珠村(現伊達市有珠町)は戊辰戦争で負けた旧仙台藩領・亘理から入植した伊達氏による開拓が進められていたが、そこには歴史の敗者である和人と先住民であるアイヌの差別構造が描かれる。八重子が後の養父となるアメリカ人伝導師ジョン・バチラーに会うために訪れた札幌の印象を「和人の、和人による、和人のための街」と表す場面では、札幌だけでなく北海道開発の歴史では決して忘れてはならないものがあることに読者は気付かされる。
そのほか、新渡戸稲造とともに札幌農学校(北海道大学の前身)二期生であった内村鑑三を描く「ビー・アンビシャス」、同じく札幌農学校出身でのちに『カインの末裔』で知られる作家・有島武郎の「流行作家」など、時に登場人物の時代が重なりながら札幌の地と結ばれた人々の物語が描かれていく。
なかでも札幌が函館の人口を抜き、名実ともに北海道の“首都”へと飛躍するきっかけともなった石狩川の治水工事を描いた最終話「ショートカット」は、北海道への敬意と人のために自然を改良するという土木技師・岡崎文吉の葛藤が心を打つ。札幌と北海道開拓の長い歴史と岡崎の葛藤を重ね見ることができる物語は、本書の最後を飾るにふさわしいエピソードである。
本書でとても印象に残った言葉がある。
“街そのものが過去よりも未来のほうを多く持つ”(第二話「ビー・アンビシャス」)
幕末から明治にかけて開発・開拓された札幌、そして北海道は、つねに未来を見つめることで発展してきた近代日本でも稀有な歴史をもつ場所であると、この言葉とともに本書『札幌誕生』を読んで強く感じたのである。
文=すずきたけし




