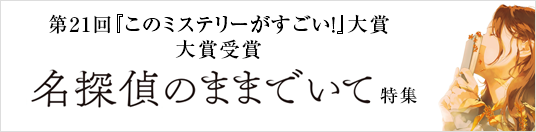祖父の影響でミステリマニアとなった楓。古本で購入したミステリ評論集をめくると…/名探偵のままでいて③
公開日:2023/2/1
本格ミステリには、珈琲がよく似合う。
赤地にサイケデリックな白文字で『珈琲専門 モンシェリ』と抜かれた縦長の看板は、まるで〝ミステリ専門家〟以外の客をシャットアウトするような感があったという。
底が見えない謎のような泡が渦を巻く、濃厚かつビターな珈琲。
ルルーの『黄色い部屋の秘密』を彷彿とさせる、タイル張りの黄色い外壁。
二階の小劇場から響く劇団員たちの靴音は、さしずめチェスタトンの『奇妙な足音』か、はたまた乱歩の『屋根裏の散歩者』か。
モンシェリがない今となっては、想像の羽を伸ばすほかはない。
だが、瀬戸川氏や祖父を語り手としていたその店はきっと、コミック界におけるトキワ荘、あるいは水滸伝における梁山泊のような熱量と光芒を放っていたのではないだろうか。
(ふたりの本格ミステリ談義……聴きたかったな)
もはや店が存在しないがゆえに、楓の夢想は余計に大きく膨らむのだった。
残念ながらモンシェリは、もはやない。
だが――本ならば、ある。
大好きな本は、やはり手元に置いておきたくなる。
ましてや祖父の家の本は、半透明のグラシン紙のブックカバーで丁寧に保存されていて、どのページにも折り目ひとつ付いていないものだから、借りるとなるとどうにも気が引けてしまう。
そんなわけで楓は、瀬戸川氏の評論集のすべてを大人買いすることに決めたのだった。
(良かった、まるで新刊だ。帯まで付いてる)
楓は、本の状態を見て嬉しくなった。
本音をいえば、新刊で揃えたいところだ。
だが、この遺作はすでに絶版となっていたため、やむなく中古専門のネット書店で買い求めたのだった。
これで著作の全冊が揃ったことになる。
(こういうのをコンプリートする二十七歳の女ってどうなんだろ)
自然と笑みがほころぶのを自覚しながら、立ったままぱらぱらとページをめくってみる。
そのとき――
本の間から四枚の小さな紙が、銀杏の葉のようにカーペットの上へ舞い落ちた。
(ん。なんだろう)
楓は、慎重に四枚の紙を拾い上げ、テーブルに並べてみた。
そして、それら大小さまざまな長方形の紙を、じっと見つめたまま考え込んだ。
(栞にしては多すぎる)
(だけど)
(付箋にしては〝重すぎる〟――)
四枚の紙は、雑誌や新聞の切り抜き記事だった。
そしてそのどれもが、瀬戸川氏の逝去を伝える訃報記事だったのである。
<第4回に続く>