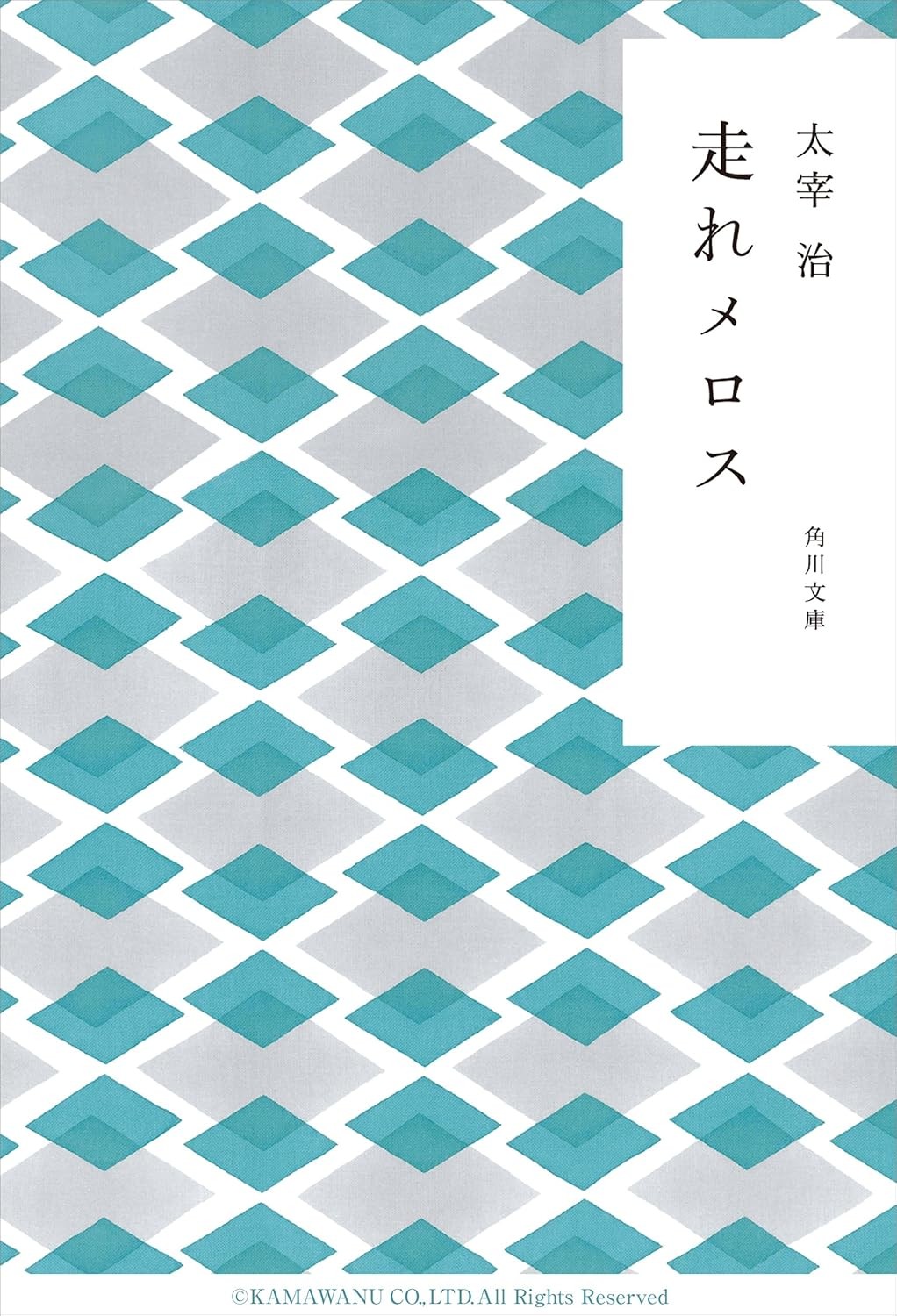「走れメロス」が最高に笑える理由を考察。最大の親友を残虐な王様に売った男/斉藤紳士のガチ文学レビュー⑨
公開日:2024/7/15
太宰治の名作「走れメロス」と聞くとだいたいの人は「友のために走り続けた男の友情物語」と答えると思います。
もちろんそういった側面もある小説ではありますが、僕の中ではボケ数の多いコントのような小説、という印象が強い作品となっています。
なぜそういう印象を待つかというと、表面的な「友のために走り続けた男の話」にしては物語の設定自体が絶妙に粗く、ツッコミどころが満載だからです。
荒唐無稽な設定、というのは不条理小説やマジックリアリズムの作品と相性が良いのですが、「走れメロス」は古代ギリシャが舞台のいわゆる神話のような体裁をとっています。
なのに無茶苦茶だから余計に面白いのかもしれません。
笑いは落差のあるところに生まれます。
そこらへんのおじさんがズッコケるより、権威のある要人がズッコケる方がずっと面白くなるものです。
とりあえず内容を紹介していきますが、ところどころ我慢できず指摘という名のツッコミを入れていきますがご容赦ください。
主人公は曲がったことが大嫌いで人一倍正義感の強い牧人のメロス。
そんなメロスが「激怒した」ところから話は始まる。
ところがもうすでにその怒りがややズレている。
何かのっぴきならない災難でもメロス自身にふりかかったのかと続きを読むが、どうやらそうでもないらしい。
買い物のために久しぶりに訪れた街の雰囲気がおかしかったので、老人を捕まえ理由を訊ねると「人を信じることができなくなった王が次々に人を殺している」と教えてくれる。
そこで「激怒」するわけだ。
確かに腹立たしいことだが、「よくその体温で怒れるな」とも思う。
ちなみにこの「王」はメロスの住む街の王ではない。つまり、今の感覚で言うと東京都に住んでいながら千葉県知事に「激怒」しているようなものである。
さらにメロスは「呆れた王だ。生かして置けぬ」と言う。安直に殺そうとする短絡的な発想は王と大して変わらない。
そしてなんとメロスは買い物袋をぶら下げたまま、片手には短刀を持ち、王のいる城に入っていき、今で言うところの「秒で」捕まってしまう。
これは「まっすぐな性格」というより「ただの馬鹿」に近い。
「人の心を疑うのは、最も恥ずべき悪徳だ。王は、民の忠誠をさえ疑って居られる」
「疑うのが、正当の心構えなのだと、わしに教えてくれたのは、おまえたちだ。人の心は、あてにならない。人間は、もともと私慾のかたまりさ。信じては、ならぬ」暴君は落着いて呟き、ほっと溜息をついた。「わしだって、平和を望んでいるのだが」「なんの為の平和だ。自分の地位を守る為か」こんどはメロスが嘲笑した。「罪の無い人を殺して、何が平和だ」
「だまれ、下賤の者」王は、さっと顔を挙げて報いた。
とても激しい口調でのやり取りが続くが、突然買い物袋と短刀を持って侵入してきた完全なる不審者の話を王はそこそこ聞いてあげている。
実は良い人なのではないか、ある意味聞く耳を持つタイプのトップなのでは、と思わせる。
そしてここでメロスから衝撃の一言が発せられる。
「処刑するのはいいけど、三日待ってください」王は「馬鹿な」と嘲笑するが、至極全うな反応だと思う。
「逃した小鳥が帰ってくるというのか」と言う王に「妹が結婚式を挙げるんです! 私を三日間だけ許してください」と返すメロス。
賢明な読者なら思うだろう。
元から三日後に王のところに来たらよかったのに、と。
買い物途中ではなくて、買い物は済ませて、妹の結婚を見届けて、それから短刀を持って王のところに行ったらよかったのに、と。
そしてさらにメロスは畳みかける。
「私が信じられないなら身代わりにこの市に住む無二の友人のセリヌンティウスを人質としてここに置いていく!」
この提案に関してはセリヌンティウスの意向など完全に無視している。
ここで太宰は「無二の友人」と「竹馬の友」と二つの異なった表現を用いることによって、よりメロスの提案がぶっ飛んでいることを際立たせているように思える。
結局セリヌンティウスは深夜に王城に呼び出される。
無二の友人であり竹馬の友であるセリヌンティウスと会うのは実に二年ぶりである。
いや、二年も会ってないの? 本当に無二の友人で竹馬の友なの? という疑問はもはや無粋なのかもしれない。
結局、セリヌンティウスは縄に打たれ、メロスは村に出発した。
翌る日、村に到着すると妹に「明日、結婚式をするぞ」と言うメロス。
いや、もともと結婚式の予定なかったんかい! と思うが、妹は渋々了承する。
しかし婿の方は「それはいけない。こちらはまだ何の支度もできていない」と当然の反応を示す。
ところが我の強いメロスは「待つことはできぬ」と夜明けまで粘って自分の意見を押し通してしまう。
結局、急造の結婚式を挙げることになるが、途中から車軸を流すような大雨となる。
祝宴に列席していた村人たちは不吉なものを感じ、むんむん蒸し暑いのにも耐えた。
村人も妹も婿も思っていた筈だ、「絶対に今日やるべきことではない」と。
そして祝宴の最中メロスは思う。
「一生このままここにいたい」
賢明な読者ならこう思うだろう。「どの口が言うとんねん」と。
メロスはその後眠りにつき「南無三、寝過ごしたか!」と思うほど、割としっかりと睡眠をとる。
そして気持ちを奮い立たせ雨中、矢の如く走り出る。
「走れメロス」というぐらいだから、まさにここから王城へ友のために駆け抜けたのだろう、とみなさんは思うだろうが、メロスはしばらく走ると、「そんなに急ぐ必要もない、ゆっくり歩こう」と好きな小歌を良い声で歌いながらぶらぶら歩く。
忘れてほしくないのは、この間中ずっと突然深夜に呼び出されただけのセリヌンティウスは縄で板に縛りつけられているという事実。
ぶらぶら歩いているとメロスの足が、はたと止まる。
前方の川が昨日の豪雨で氾濫して橋を破壊していた。メロスは川岸にうずくまり、男泣きをする。
泣いてしまうほど絶望的な状況なのかと思いきや、結局メロスは川を泳いで渡る。
しかし、一難去ってまた一難。
今度は山賊に襲われたメロスはなんとか走って逃げ切り、疲れたメロスはその場に倒れ込んでしまい、立ち上がることもできなくなる。
「ああ、もうどうでもいい。これが私の定った運命なのかもしれない。セリヌンティウスよ、ゆるしてくれ。(中略)セリヌンティウス、私は走ったのだ。」
「もうどうでもいい」は絶対に言ってはいけないセリフだと思うが、メロスはどうでもよくなる。
正直、歌歌いながらぶらぶら歩いて、ちょっと泳いでちょっと走っただけなのでそこまで頑張ってないようにも思えるが、学校でプールの授業があった日は眠くなっていた記憶があるので、まあ疲れたのだろうとは思える。
で、ここでメロスは再びしっかり睡眠をとります。そして、起きたらそこそこ回復していたので、また走りだす。途中、セリヌンティウスの弟子に「あなたを恨みます」と並走されながらなんとか処刑執行寸前に王城に到着する。
そこでメロスはセリヌンティウスにこう言う。
「私を殴れ。私は途中で悪い夢を見た」
セリヌンティウスは全てを察した様子で頷き、思い切りメロスを殴る。殴ってから優しく微笑み、「メロス、私を殴れ。私はこの三日間、たった一度だけ、ちらと君を疑った」と言った。
メロスは腕に唸りをつけてセリヌンティウスを殴りつけた。
賢明な読者なら「よく殴れるな」と思うことでしょう。
無茶苦茶な提案を黙って受け入れて殺される寸前までいったのだから当然「疑う」権利はあるだろう、と。
しかし、二人は「ありがとう、友よ」と同時に言い、抱き合う。
その様子を見た王は二人に近づき、顔を赤らめ「どうかわしの願いを聞き入れて、おまえらの仲間の一人にしてほしい」と謎の申し入れをする。
まったく意味がわからない展開だが、どっと「万歳、王様万歳」の歓声が起こる。
するとひとりの少女が緋のマントをメロスに捧げた。
良き友は、「メロス、君はまっぱだかじゃないか。早くそのマントを着るがいい」とメロスに言い、話は終わります。
最後まで何がなんだかわからないシュールなコントを見せられている感覚に陥るのですが、それはあくまでひとつの読み方です。
小説は読者にとっては合わせ鏡のようなもの。
読む人によって捉え方は変わってきます。
「走れメロス」が友人を助けるために時に挫けそうになりながらも直向きに走り続ける男の物語として読むこともできます。
そしてそこから何かしらの教義を得ることもあると思います。
何にせよ、どんな読み方をしても「面白い」と思える小説を書く才能こそが太宰治の最大の魅力なのかもしれません。