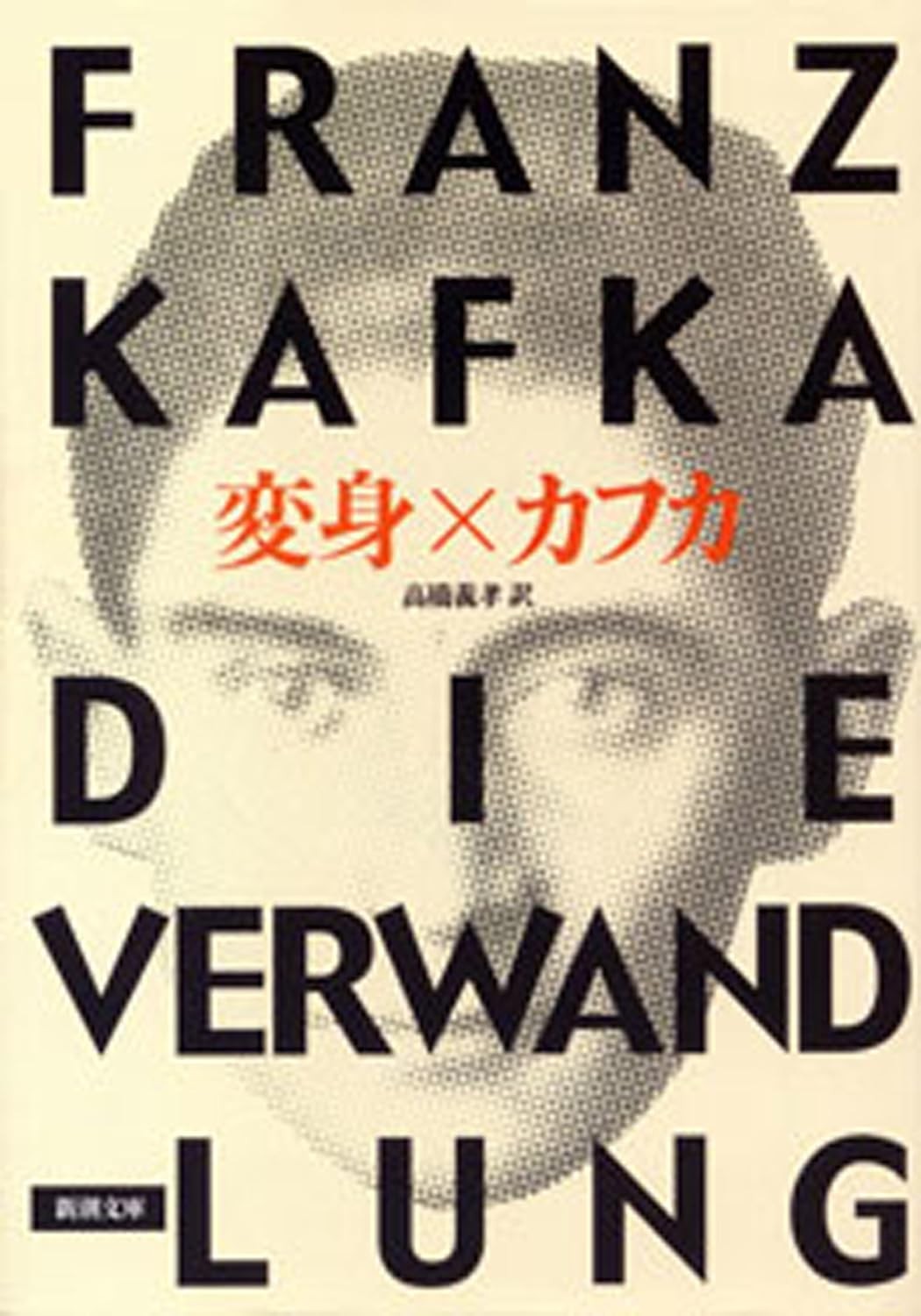「朝起きたらでかい虫になっていた」シュールすぎるお笑い満載の文学作品を考察/斉藤紳士のガチ文学レビュー⑪
公開日:2024/8/12
フランツ・カフカは現在のチェコ出身の小説家で世界的文豪である。
文学を自分の天職だと考えていたカフカはしかし表面的には平凡な一市民として一生を終えることになる。
小説を書きあげると友人のマックス・ブロードにすぐに見せに行き「ここ面白いだろ」と笑いながら紹介していたという逸話もある。
そんなカフカの代表作が「変身」である。
いわゆる変身譚であるが、そこには計算し尽くされたシュールな笑いとアドリブ的な笑いが内在している。
ある朝、グレゴール・ザムザが何か気がかりな夢から目をさますと、自分が寝床の中で一匹の巨大な虫に変っているのを発見した。
みなさんがもし、朝起きたら自分が巨大な虫に変身していたらどうするだろうか?
半狂乱になり、飛び起きたり泣き叫んだり、逆に冷静に現状を把握しようと深呼吸をしたりするのではないだろうか?
このいきなりのシュールな展開に主人公のグレゴールが最初にしようとしたことはまさかの「二度寝」である。
嘘やろ、と思うのだが実際グレゴールは二度寝しようとする。
残念ながら「二度寝」は未遂に終わるのだが、その理由が「寝返りがうてない」というふざけた理由なのである。
いや、もちろんそれって意外に大事なことかもしれない。みなさんも寝入りやすい姿勢はあると思う。
グレゴールにとってそれは右半身を下にする姿勢なのだが、仰向けになり、手足をばたつかせてもうまく横になれない。
なんとか寝返りをうつチャレンジを百回ほど行うのだが、結局諦める。
正直、百回も挑戦していたら疲れて寝落ちしそうだが、グレゴールは二度寝を諦める。
そしてこんな物思いに耽る。
「ああ、しかし外交販売員という仕事は辛いなぁ。年がら年じゅう旅、旅だ。たっぷり寝たいなぁ。早起きすると人間はうすばかになるなぁ」
いや、虫になったことは受け入れてんのかい! とも思うが、現実逃避しているのかもしれない。
出張に出発する時間になっても起きてこないグレゴールを心配した母が「グレゴールや、6時45分ですよ」と起こしにくる。
グレゴールは「はいはい、今起きるところです」と答えるが、そのとき自分の声にぴいぴいという声が混じるようになっていることに気がつく。
しかし、母が去ると今度は父が「グレゴール、どうした?」とやってくる。グレゴールはぴいぴい言わないように慎重に「もう支度しました」と答える。
しかし、父が去ると今度は妹が「お兄さん、ここを開けて!」とドアをノックする。
過保護か!成人男性なめてんのか! と言いたくなるが、それほどに愛の溢れる家庭なのである。
グレゴールもなんとか起きようと体を左右に転がしたりするのだが、その動きが徐々に面白くなってきて、無駄にしばらくゆらゆら体を揺らしたりする。
呑気か! と思うが、実際人間というものは自分の力だけでは解決できないような問題に直面したら、これぐらい呑気になり無力化してしまうのかもしれない。
もぞもぞともがいていると玄関のベルが鳴り、仕事場の支配人がやってきたことがわかる。
「グレゴールはおそらく体調が悪いんです」と言う母に支配人は聞こえよがしに「そうでしょうなぁ! 我々商売人はよっぽど体調を崩しても職務を全うするもんですからね!」と言う。
腹が立ったグレゴールはなんとかドアまで移動し、アゴで鍵を開ける。
そして、ドアの隙間からデカい虫の顔がのぞく。
母は「ぎゃー!」と叫んでその場にへたり込み、父はなぜか号泣し、支配人は逃げていってしまう。
親父はなんで泣いてんねん、と思うが、その後父は一応頑張って「この野郎!」と言いながらステッキで攻撃してきて、グレゴールは自室に追いたてられる。攻撃を受けたグレゴールは血だらけになる。
気持ちはわかるが我が子かもしれない、という躊躇を微塵も感じさせないほどの強めの暴力を父はふるってくる。
その日以来グレゴールは自分の部屋に閉じこもって生活するようになった。グレゴールの世話は妹のグレーテがするようになるのだが、それまで両親はグレーテのことを「役立たずの小娘」くらいに思っていたらしい。
ひどすぎない? 我が子に対してそんなこと思う? と思うのだが、まあ、ある意味厳しい両親なのだろう。
グレーテはグレゴールの食事を運んできてくれたりするのだが、毎回グレゴールの姿を見るたびに驚いてしまう。
そんなグレーテにグレゴールは思う。
そろそろ慣れろや、と。
しばらくするとグレゴールは天井や壁を移動するようになる。
グレーテは邪魔になるだろうと部屋にある家具を運び出しはじめる。
グレゴールも最初は喜んでいたが、次第に「あれ、このまま人間だった頃の痕跡を無くしてもいいの? 虫カゴみたいな部屋になってしまう」と不安になる。
そしてグレゴールは再び部屋から這い出る。
お笑いで言うところの「テンドン」である。
母は「ぎゃー!」と叫び、父は林檎を二回も投げつけてくる。
もう親父攻撃しかしてこんやん!
そして、この林檎の攻撃によりグレゴールは重傷を負う(一つの林檎は背中にめり込んでいる)。
父は女中にお暇をだし、代わりに年老いた大女がくるのだが、この大女、グレゴールを怖がらないどころか寧ろからかってくるような人間だった。
父は収入を得るために部屋の一室を三人の紳士に貸し出し、母もグレーテも働き口を見つけて働くようになる。
そんなある日グレゴールはグレーテのヴァイオリン演奏に導かれて部屋を出てしまう。
ここまでくると「テンドン」ではなく「お約束」になる。
「くるぞ、くるぞ」と期待させて「来たー!」という緊張の緩和で笑いをつくる手法である。
吉本新喜劇での定番ギャグや、バンビーノの「ダンシングフィッソン族」、ロッチさんの「試着室」のコントなどに使われている手法である。
部屋を出たところにたまたま居た紳士に見つかってしまい、「なんだあの化け物は! こんなところに家賃など払えるか!」と当然のお叱りを受けてしまう。
そしてついにグレーテは吹っ切れてしまう。
「もう潮時だわ。あたしたちはこれを振り離す算段をつけなくっちゃだめです。これの面倒を見て、これを我慢するためには、人間としてできるかぎりのことをやってきたじゃないの。だれもこれっぽっちもあたしたちをそのことで非難できないと思うわ。ぜったいに、よ」
「これ」呼ばわりしてるやん! と思うが、グレーテの言い分もわかる。
「これはお父さんとお母さんを殺しちゃうわ」
グレゴールは結局、何も食べない日が続き、死んでしまう。
翌日、グレゴールの死体は手伝い女によってすっかり片付けられ、父と母とグレーテは郊外に電車で出る。
車内で三人の働き口での仕事が意外に順調なこと、グレーテもよく見たら年頃の女性へと成長しているのでそろそろ婿でも探さないと、などと話しているところで物語は終わる。
とてもシュールで上質なコントのような巧みな構成の小説というような読みはあくまで一つの読み方で、当時のヨーロッパ各地であった世界大戦の影響による不穏な閉塞感を「巨大な虫」という異形なものが密室に閉じ込められている、という設定で書き表した社会派で重厚な文学作品とも読める。
色々な解釈や読み方ができることもこの小説の魅力でいまだに研究を続けているカフカ研究家は多い。
ひょっとしてグレゴールはただ仕事が嫌になり、巨大な虫の模型を作って家族を騙して遊んでいただけかもしれない。
そう想定して読むとまた新しい発見があるかもしれませんね。