『光る君へ』彰子はやがて強大な権力を手にし、後の「女性権力者」のルーツともなった――武家社会にいたるまでの平安後期に女性たちが政治に果たした役割
PR 公開日:2024/11/3
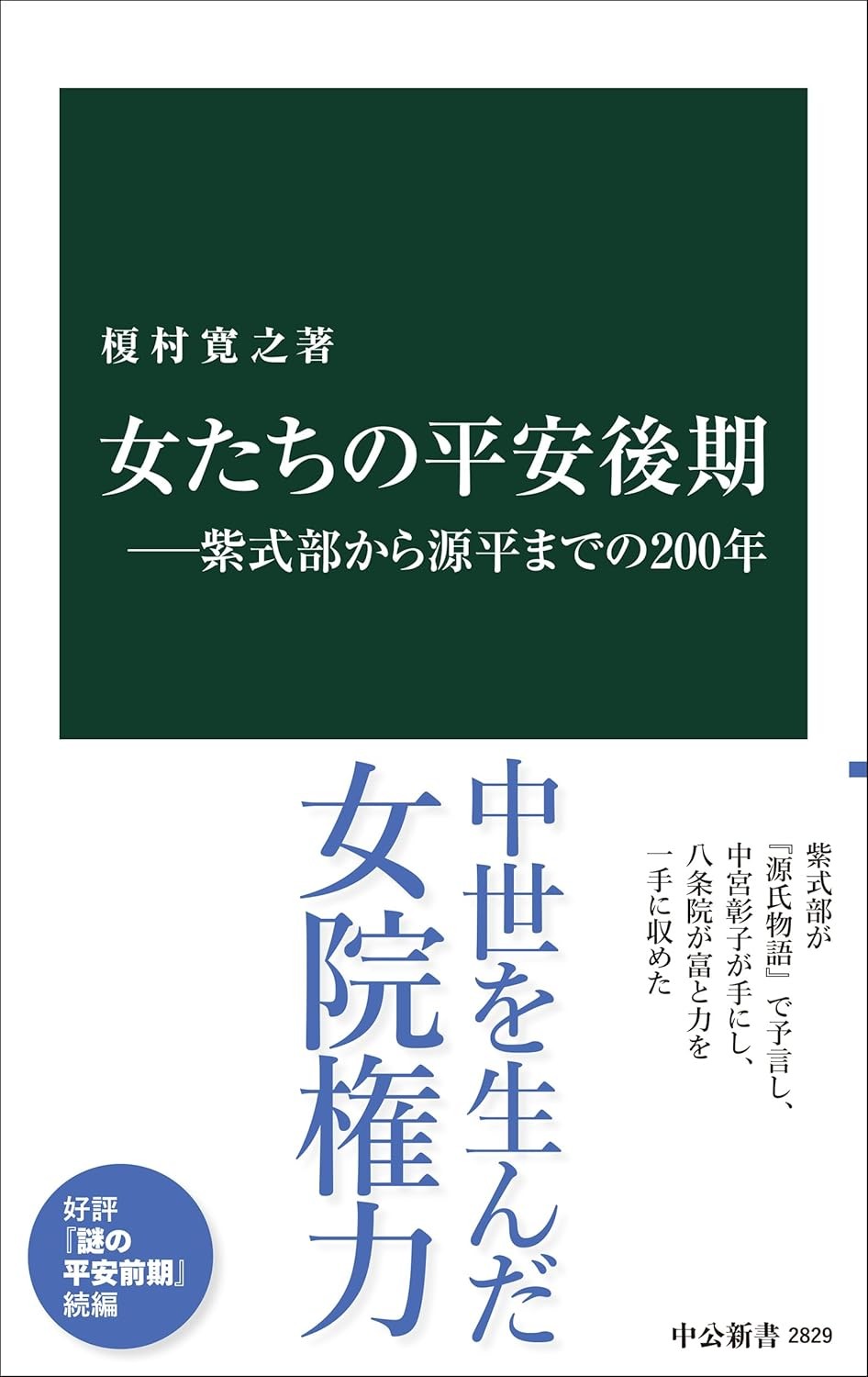
紫式部の人生を描く大河ドラマ『光る君へ』、物語は藤原道長からの要請で書き始めた『源氏物語』が貴族たちの間で大流行し、年末の最終回へ向けていよいよ佳境に入ってきた。ドラマの舞台は道長が摂関政治を行った平安時代の中頃、西暦1000年前後だ。平安時代は8世紀の終わり、794年に長岡京から平安京へ遷都して始まり、12世紀の終わりの1185年に壇ノ浦の戦いで平家が滅亡、1192年に源頼朝が征夷大将軍となって鎌倉時代へ入るまで、なんと約400年もの長きにわたって続いた時代である。現代から400年前は江戸時代初期、三代将軍家光の治世であることを考えると、どれほど長い期間であったかよくわかるだろう。
平安時代は日本が古代から中世へと移り変わる過渡期であり、紫式部が生きていた時代以降の200年の平安後期は、特に古代から中世への転換期に当たるという。平安時代は始まりから終わりまで貴族が束帯や十二単を着ていたように思われるかもしれないが、その長い長い時間の中でさまざまなことがダイナミックに変化していった時代だ。そんな時代について「武士も貴族も民衆も入り混じって、それぞれに歴史がありじつに面白いことを知っていただきたい」というのが、本書『女たちの平安後期──紫式部から源平までの200年』(中央公論新社)だ。タイトルの通り、歴史上の出来事とその時代を生きた女性たちについて、最新の研究に基づいた情報が数多く収められている。ここ最近放送された大河ドラマで言うと『光る君へ』~『平清盛』~『鎌倉殿の13人』という時代(南北朝時代の女性を紹介する記述もあるが、主として平安中期~鎌倉時代)についての内容となっている。
男性と肩を並べ、ときにそれを凌駕するほどの力を手にした女性たちには、女院(天皇の生母など、朝廷から称号を与えられた女性)、皇后(天皇の妻)、斎王(伊勢神宮や賀茂神社に奉仕した未婚の内親王、皇族の女子)、乳母(生母に代わって貴人の子を育てる女性)、女房(朝廷に仕える女官)、武人貴族の妻などがおり、子を産むことで強大な力を手にしたり、未婚のまま権力を握る女性がいたり、知識と仕事でのし上がったり、市井でのネットワークを構築するなど、政治的な役割を担っていたケースがあったという。
中でも『光る君へ』にも登場する道長の娘・彰子についてのパートが興味深かった。一条天皇の中宮(天皇の妻)になったばかりの頃はまったく心を開かず、ひたすら地味な存在だったが、紫式部らのサポートもあって、やがて一条天皇の子を産んで徐々に明るい表情を見せている。その彼女が後々「上東門院」として強大な権力を手にしていくのだ。しかも女院のルーツは彰子にあるという話も詳しく書かれているので、いかにしてそのような存在になったのかを理解すると、ドラマの今後の展開も楽しみになるだろう。ところが後に滅茶苦茶な振る舞いをする白河院(院政を確立した白河天皇)によって、院のお気に入りの得体の知れない女が寵愛を受ける「玉の輿」が発生、それまでとは違ったルートで権力を握る女性たちが出てくるなど、平安後期になればなるほど前例無視が横行(ドラマでおなじみ、『小右記』を書いた藤原実資が生きていたら卒倒ものだろう)、やがて女性の立場が変化し、武家社会が生まれる下地が出来上がっていく。
個人的に本書で面白かったのは、道長の詠んだ「この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば」という有名な句について、「望月」は天皇の后となった娘たちのことであろうという論考だった。『光る君へ』では事あるごとに月を眺めるシーンがあり、この句が物語の展開で重要な意味を持つはずなので、本書はドラマの中で光る「女たち」の活躍を理解するための一冊となるだろう。
最後にひとつ注意点を。本書にはとにかく多くの人物が出てくるため、理解の一助となる家系図が多く所収されている。その図と突き合わせながら、また本で調べネット等で検索をしながら(もちろん大河ドラマで演じた役者の顔やエピソードを思い出しながらでもOKだ)ゆっくり、じっくり読み進めてほしい。
文=成田全(ナリタタモツ)




