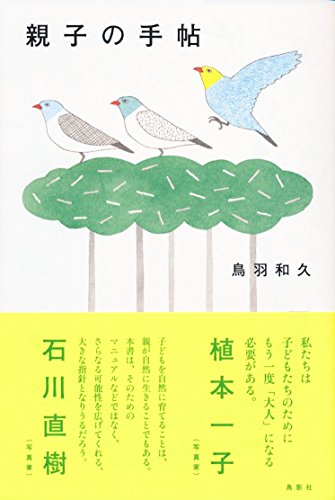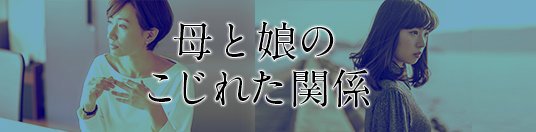叱るつもりが喧嘩になっていませんか? 思春期の子どもを叱るときの大切なポイント
公開日:2018/6/6
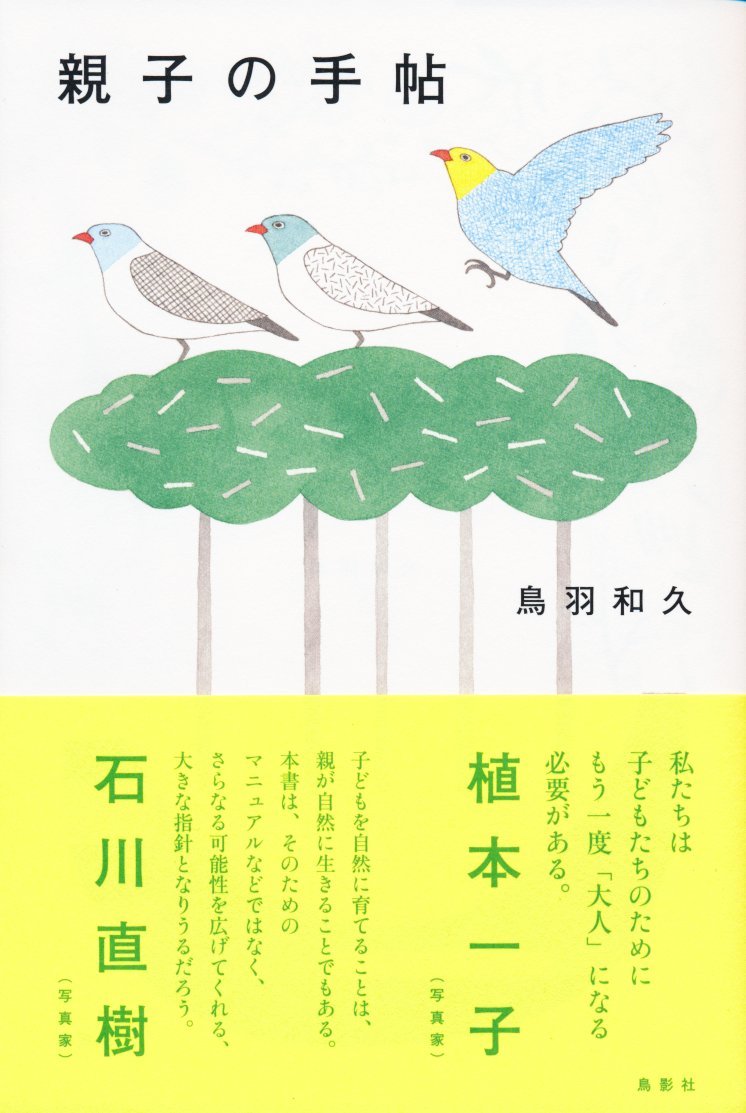
あなたは思春期の子どもを叱るとしたらどうやって叱るだろうか。子どものために叱っているのに、反発されたり、そのまま喧嘩になったりという展開は十分考えられる。本当にお互いのためになる接し方はないのだろうか?
『親子の手帖』(鳥羽和久/鳥影社)は、教師である著者がその経験を元に色々な親子の問題を紐解いている。10代の思春期、特に中高生が、親と共に幸せを見つけていくための道しるべとなる1冊だ。今回は、その中に載っている「叱り方のポイント」を紹介しよう。
■いつ叱るべきか?
叱るタイミングは、問題が起こった直後が良い。問題のあった直後に叱ると、子どもは自分の何が悪かったのかを体感できる。それに、後から思い出したように叱ると「ネチネチ怒っている」といった印象もつきまとうだろう。
また、問題行動が起こるたびに叱ること。「あのときは怒ったのに、今は怒られない」と子どもが認識してしまうと、親は自分の都合で怒っているのだ、というイメージを与えてしまう。子どもには、一貫したメッセージが必要なのだ。
■行動を叱るのであって、人格を叱ってはいけない
たとえば「あなたはだらしない」と言うと、子どもは人格を否定されたような気分になる。そしてそのイメージを自分に植え付ける。「あなたの人格は信用している」というメッセージを伝えることは大切だ。
さらに、叱りながら過去のことを持ちださないことだ。過去のことを持ちだすと、子どもは自分が昔も今も相変わらずダメなままと思い込んでしまい、「人格の否定」に繋がりかねない。
■自分の責任で叱る
叱るときは、他人と比較して叱らないこと。これは自分の子ども時代にも覚えがあるはず。比較して叱るというのは、相手は反発しやすいうえに深く傷つきやすい。叱る基準が相対的に流動するものであってはならないと著者は言う。
また、「お父さんに叱られるよ」と他人に責任を転嫁すると説得力を持たない。お父さんに叱られるからやってはいけないのではなく、その行動自体をやってはいけないと伝えるべきだ。
■叱る理由を説明し、理解させる
子どもは親が思う以上に叱られる理由を理解していない。子ども本人が納得して自分の頭で考えられるように仕向けるべきだ。
だが、叱るときは短めに。長々と説教しないこと。子どもは長々と喋られても面倒くさいと感じる。長い説教は途中で空気が緩んでしまう。退屈と思わせないためにも短めに叱ることが必要。
■叱った後で、そのことについて謝らない
感情的すぎたことについては謝って良いが、叱った内容そのものについては謝らないこと。次に叱るときに「取るに足らない内容だ」と思わせてしまう可能性がある。
いったん叱ったら、なるべくその後はそれについて触れないこと。子どもがせっかく反省しているのに、またそのことに触れると、反省する気持ちを損ねてしまう。叱った後は気分を切り返させ、前を向かせることが大切だ。
以上、叱るときのポイントを紹介したが、著者は「この叱り方であればいつでもうまくいくというものではない」という。方法論にこだわりすぎて子どもの「今の」状態に合わせられないと本末転倒だ。まずは子どもに近づいて心を寄せる、そばにいる、ということを心がけること。無理になんでも判断しようとせず、できるだけ自然な気持ちで子どもに寄り添うということが大切だ。
文=ジョセート