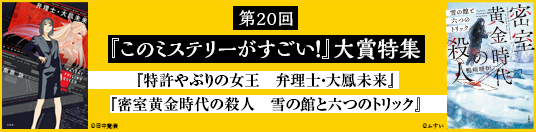国民的女優に中学時代の同級生…。ホテルのロビーに次々と宿泊客が集まりはじめて…/密室黄金時代の殺人 雪の館と六つのトリック④
公開日:2022/3/6
*
「香澄くん、この子は?」
僕と蜜村の関係が気になったらしく、夜月がぴょこぴょこと寄ってくる。「何というか」と僕は言った。
「中学の時の同級生だよ。同じ文芸部に所属してたんだ」
と言っても文芸部の部員は、僕と蜜村の二人だけだったが。そのせいで、彼女が文芸部を辞めるまで、僕は放課後のほとんどの時間を彼女と一緒に過ごしていた。
そんなことを夜月に話すと、彼女は、ははーんという顔になった。
「なるほどねぇ」と夜月は言う。「つまり、元カノということね」
いや、違うから。何を聞いてたんだ、こいつ。
「じゃあ、友達以上、恋人未満?」
「何を聞いてたんだ、お前」
「葛白くん、その人は?」
今度は蜜村が僕に訊ねた。どうやら僕と夜月の関係を訊ねたらしい。
「うーん、何ていうか」答えづらい質問だな。「いちおう、幼なじみってことになるのかな? 僕の隣の家に住んでいて、小さいころは姉代わりで」
「なるほど」と蜜村は頷く。「つまり、幼なじみ以上、姉未満というわけね」
何だか、妙なことを言い出した。
僕は彼女に訝し気な視線を向けた後で、純粋に気になっていたことを訊ねる。
「ところで蜜村、今日はどうしてここに?」
「やっぱり、イエティを探しに来たの?」と夜月。
「イエティ? いえ、ただの旅行で来たんですけど」と蜜村。「えっ、イエティが出るんですか?」
夜月は得意気に胸を張った。
「出るよ」
「いや、出ないだろ」と僕。
「いったい、どっちなの?」
蜜村は戸惑ったように言った後で、やがて小さく噴き出した。首を傾けた僕たちに、「いや、何だか懐かしくて」と彼女は笑む。「葛白くんと話すの、久しぶりだから」
「そっか、それは懐かしいよね」夜月がそう相槌を打つ。そして興味を惹かれたように、「香澄くんって中学ではどんな感じだったの?」と訊ねた。蜜村は「そうですねぇ」と記憶を辿るように答える。
「何というか、けっこうイキってましたね。いつも『俺は一匹狼だぜ』みたいな面構えで歩いていたような」
いや、どんな面構えだよ。いくら中学の時とはいえ、そんな顔で歩いてはいないような。
「あと、こんな噂も聞きました。『僕は一度見たものを、写真のように記憶できる。そういう特殊能力があるんだ。でも脳に負荷が掛かりすぎるから、普段のテストとかでは使わない。使う時は唯一─、世界に危機が訪れた時だけだ』そんなことを自慢げに、友達に言いふらしていたとか」
中学時代の僕、痛すぎだろっ! いや、確かに言ってたけどもっ! そういうのって、ある程度時間が経ったら時効になるって約束では?
そんな僕の心の叫びを無視して夜月が言う。
「その話、詳しく聞かせて」
「いいですよ、じゃあ、一緒にお茶でも飲みながら」
僕の悪口で意気投合した二人は、一緒にテーブルの席に着く。僕もそこに同席した。蜜村は見た目はクールで真面目そうだけど、けっこう適当なところがあるからな。あることないこと話されないように監視しておく必要がある。
僕が二人に目を光らせていると、そのタイミングで西棟から一人の男が戻ってきた。眼鏡姿の冴えない男─、朝ドラ女優の長谷見梨々亜のマネージャーだ。名前は真似井だったか。真似井はソファーでくつろいでいる梨々亜の向かいの席に座った。そして手にしていた仕事鞄から、ぺら紙を一枚取り出す。それをテーブルの上に置いた。
グレープフルーツジュースを飲んでいた梨々亜は、その紙を眺めて言う。
「真似井さん、それは?」
「バラエティ番組のアンケート用紙です」
「げっ」
梨々亜はあからさまに嫌そうな顔をした。ジュースのストローに口を付けて言う。
「梨々亜、今そういう気分じゃないの。真似井さん、代わりに書いといて」
「ダメです、ちゃんと書かないと」
「でも、梨々亜、箸より重いもの持てないし。ペンって箸より重いでしょ?」
「材質によりますね」
それはそうだろうと思う。
梨々亜はだんだんと、不機嫌になってきたようだ。
「わかんない? 書きたくないって言ってんの」
「でも、バラエティ番組のアンケートは大事です」真似井は、意外と毅然とした態度で言った。「アンケートの書き込み次第で、チャンスの量が変わるんです。いっぱい書けば、いっぱいMCが振ってくれるんです。逆にアンケがスカスカだと、MCやスタッフさんにやる気がないやつだと思われます」
「うん、わかってる。だから、真似井さんに書いてって言ってんの」
「話がループしてますね」
「そういう魔法が掛かってるのかな?」
梨々亜はジュースを飲み干すと、真似井の手から乱暴にアンケート用紙を奪い取る。
「わかった、じゃあ、書いてくるよ。部、屋、で、ねっ!」
ガタッと勢いよく立ち上がった。そのまま梨々亜は不機嫌な足取りで西棟の方へと去っていった。真似井は深く溜息を吐く。
そんな真似井と梨々亜のやり取りの間も、夜月と蜜村は僕の中学時代の話で会話に花を咲かせていた。出るわ出るわの黒歴史。でも、二人は突然そのやり取りをやめる。梨々亜がロビーから出て行ったタイミングで、雪が降り始めたのだ。
窓の外に─、雪が。
きらきらと、勢いよく空を舞って幻想的に降り積もる。庭が白く覆われていく。そういえば、雪を見るのは今年初めてだったか。しかも、旅行先で見る雪だ。否応なくテンションが上がる。ロビーに集まった他の客たちも、窓の外に視線を向けていた。
社長の社も医師の石川も、探偵の探岡も。先ほど梨々亜と揉めた真似井も、気晴らしのように雪を眺める。コーヒーを運んでいた迷路坂さんも窓の外を見つめていた。支配人の詩葉井さんだけが、フロントのカウンターでパソコンを叩いている。
今夜、このホテルに泊まる客は、全部で十二人だと聞いている。今はそのうちの七人が、このロビーに集まっている。僕の知っている客の中で、ここにいないのは梨々亜と─、イギリス人のフェンリル・アリスハザードだけだ。
そんなフェンリルも、雪が降り始めて十分後くらいにロビーへと現れた。コートを着ていて肩に雪が積もっているので、庭を散歩していたらしい。これでロビーに集まった客は八人だ。銀髪を雪で濡らしたフェンリルは、しばしロビーをきょろきょろしていたが、僕のことを見つけると嬉しそうに近づいてくる。
「葛白さん」彼女はテーブルの上にそれを置いた。それは雪でできたウサギだった。
「お土産です」
ちょっこりとした雪ウサギが、木目のテーブルの上にたたずんでいる。かわいい。
フェンリルはにっこりと笑った。
「ぜひ、お召し上がりください」
「えっ、食べるの?」
「中にあんこが入っていますから」
「……、まじで?」
恐る恐る齧ろうとしたところで、フェンリルが「冗談です」と笑った。彼女はいたずらっ子のように僕らの席を離れると、トテトテと窓際に移動してスマホで庭の撮影を始めた。窓の外の雪はいっそう激しさを増していた。
それから二十分ほどで雪はやんだ。短い雪だったが、庭はすっかり銀世界だ。高い塀に囲まれた館の箱庭を真っ白に染めている。
雪が降りやんだのを切っ掛けに、ロビーに集まった八人の客たちは、ぽつぽつと席を立ち始める。ずっとカウンターで働いていた詩葉井さんも、大きく伸びをして食堂棟の方に向かって行った。入れ替わるように、迷路坂さんがカウンターに入る。
僕も部屋に戻ることにする。フェンリルに貰った雪ウサギが、少し、ぐだーっとなっていた。融けないうちに部屋の冷凍庫に入れて延命させる必要がある。