「高齢者の性、母親の性。タブー視されているものに挑戦した」紗倉まな、待望の新作『春、死なん』で見せる新境地
公開日:2020/3/3
現役のAV女優として第一線で活躍しながらも、作家としての快進撃を続ける紗倉まなさんが、待望の第3作目となる小説『春、死なん』(講談社)を上梓した。

紗倉さんが作家としてデビューしたのは、2016年2月のこと。『最低。』と題した作品で、自身も所属するアダルト業界を舞台に、性と向き合う人々の姿を詩的な文章で瑞々しく綴った。同作の評価は高く、2017年11月には実写映画化もされ、話題を集めた。
続く第2作目は2017年3月に発表した『凹凸』。母と娘、そして父との関係を軸にした物語は、チャレンジングな構成が光り、紗倉さんの作家性の鋭さを世に知らしめたと言えるだろう。
そして、今回の『春、死なん』でも紗倉さんの進化は止まらない。70歳の高齢男性を主人公に据え、孤独な老人が性と向き合う姿を真摯に描いている。また、同時収録されている「ははばなれ」では、“母親の性”に言及した。老人の性と母親の性。多様な意見が尊重されつつある現代においても、これらはまだまだタブー視されがちな話題だ。紗倉さんはなぜ、敢えてそこに切り込もうと思ったのか。先日開催された『春、死なん』のリリース会見を通じ、紗倉さんの想いを探っていこう。
■誰もが感じる普遍的な孤独感を盛り込んだ
新作でまず知りたいのは、なぜ70歳の高齢男性を主人公にしたのか、ということ。紗倉さんはまだ26歳。約50歳も離れている人物を主人公にするうえで、苦労はなかったのだろうか。

「私が所属するアダルト業界では、AVリリースイベントというものは定期的に開催されるんです。そこには若い方はもちろんですが、60~80代くらいの男性も来てくださることが多くて。だから、もともと高齢男性が身近な存在だったんです。彼らのことを直接取材したわけではないんですが、なかには『妻がいなくなってから、(性的に)おかしくなっちゃって……』と気持ちを吐露してくださる方もいらっしゃって、彼らのそういった日常的なお話はモチーフとして取り入れました。
ただ、年齢の離れている男性を主人公にしたからといって、書きにくさはなかったんです。むしろ、自分の年代の子を主人公にするよりも投影しやすい部分が多かった。たとえば、『春、死なん』の冒頭で主人公の富雄が医師から適当に扱われてしまうシーンがありますが、それは私自身も体験したことです。他者からおざなりにされることへの憤りやもどかしさは年齢を問わずに感じる部分だと思うので、富雄には私自身が感じたことや人格が宿っていると思います」
富雄は息子家族の近くに住んでいるが、妻を亡くしたことから孤独感を募らせている。妻に触れたくても、その願いは叶わない。アダルトDVDを観ながら性を発散する富雄の姿からは、ただ性欲を持て余しているだけではない、人間としての孤独が浮き彫りになる。
「富雄が感じる孤独を描くうえでは、私も感じている寂しさみたいなものを投影したつもりです。もちろん、悩み方や悩むポイントは違うけれど、空虚さを感じるというのは普遍的だと思うんです」
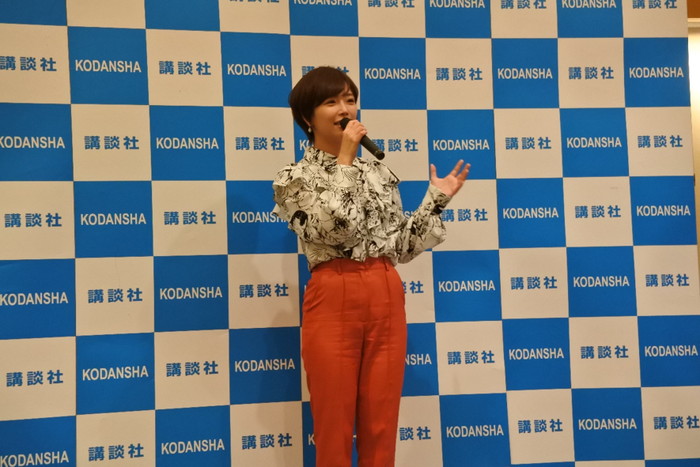
人間が感じる普遍的な孤独――。それを作品に落とし込み、文章にしたことで紗倉さん自身も救われたという。
「寂しさや孤独を言語化することで昇華される部分もありますし、なによりもそれを読んでくださった方々から共感できたという声をいただくたびに、仲間意識のようなものが芽生えて、寂しいのは自分だけじゃないんだなと思えるんです」
■「作家」の肩書に自信はないけれど、これからも書いていく
雑誌『群像』に掲載された「春、死なん」は、紗倉さんにとっての文芸誌デビュー作でもある。名だたる作家が作品を寄せる文芸誌で書くことができて、「作家」としての強い意識が芽生えたのかというと、紗倉さんは少し照れながらも口を開いた。
「うーん……、『作家』という肩書が増えることについては、やっぱりまだ恥ずかしいというか違う気がしているんです。世のなかには書店でコーナーができるくらい書かれている作家さんが大勢いらっしゃって、しかもどの作品も素晴らしい。書くことを専業にしている方々を目の当たりにするたびに、短編を書くだけでヒイヒイ言っている自分なんて……と思います。なので、私はやっぱり『エロ屋』です。ただ、書きたいことはどんどん浮かんでいるので、今後も定期的に書いていきたいとは思っています!」

まだ「作家」としての自分に自信なさげな顔を見せる紗倉さん。しかし、デビュー作から読んでいる読者からすれば、確実に進化を遂げていることがわかる。その一つが彼女の文体だ。デビュー作『最低。』では独特の句読点の打ち方が、とても詩的な印象を与えた。『凹凸』ではより客観性のある文体になり、巧みな構成も相まって、純文学としての精度を増した。そしてこの『春、死なん』。主人公と一定の距離を保つ三人称を駆使しつつ、時折、心情を的確に表現する比喩を織り交ぜる。それを追いかけていくうちに、読者は70歳の富雄の内面に深く呑み込まれていくような錯覚すら覚えるだろう。まさに富雄の人生を追体験しているかのようだ。
けれど、紗倉さんは自身の文体についても、まだ掴みきれていないとこぼす。
「これまで書いてきて、持って回った表現が多いとか、一文が長くてくどいとか、さまざまなご意見をいただいたんです。そして、確かにそうかもと思うことも多くて。だから今回は、削る作業に専念しました。結果として、最初に編集さんにお渡しした原稿よりも、半分くらいの分量になったんです。もしかしたら、それが文体にも表れているかもしれないですね。でも、やっぱり自分の文体はわからない。無意識に書いている部分があるので、褒められるとうれしい反面、次も同じ文体で書けるのか不安にもなります。もしかしたら、次回作はまた違う文体になるかも……。ゴーストライター説が出ちゃうくらい、全然違う文体になる予感もしているんです(笑)」
順風満帆なようで、とても苦心しながら作品を生み出している紗倉さん。しかし、待望の第3作目を出すことができて、その表情は晴れやかだ。
「次のテーマもなんとなく浮かんではきています。ただ、まだホワホワしていて、形にはなっていないんです。それを小説に落とし込むために、きっとヒステリックに自分と戦う時期が始まるんだと思います」

一作ごとに印象を変える紗倉さんの小説。次回作では一体どんな世界観を見せてくれるのか、文芸の世界でも注目の作家の快進撃は、これからも続くのだろう。
取材・文=五十嵐 大





