縄文時代に生きた少年の戦いと愛 人間の根源を描く歴史ロマン『二千七百の夏と冬』
更新日:2017/11/12
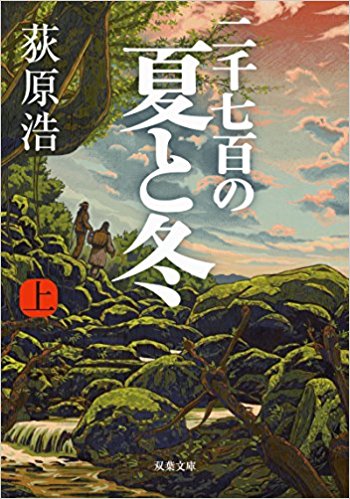
北関東のダム建設予定地で、縄文人の古人骨が発見された。推定される年齢は10代半ば、性別は男性。新聞記者の佐藤香椰は、この発見を連載企画にできないか検討を始め、発掘を進める地元の国立大学准教授・松野から情報を集めていく。やがて、古人骨は約2700年前のもので、その左手には米の稲らしきものが握られていたことが判明。さらに、縄文人の古人骨のすぐ隣に同じく10代半ばの女性と推定される渡来系弥生人の古人骨も発見された。縄文人の右手は弥生人の左手にしっかりと重ねられ、2体は互いに向き合った姿で寄り添うように横たわっていた。この男女に何があったのか。ふたりは縄文と弥生の間をつなぐミッシングリンクなのか?
第5回山田風太郎賞を受賞した荻原浩の『二千七百の夏と冬』。主人公は、この古人骨として発見された縄文人、15歳の少年ウルクだ。ピナイと呼ばれる村の集落で狩猟採集をする部族のひとりとして生きるウルクは、一人前の男として認められるため、狩りで手柄を立てることに懸命になっていた。そしてウルクは知りたかった。死んだ父は皆がいうように本当に“勇気なし”だったのか。入ってはならない南の森の向こうには何があるのか。ピナイの外、この世の涯はどうなっているのか。
やがて、病に倒れた弟が悪霊に連れていかれないよう、薬となる“クムゥ”の肝をとるために南の森に足を踏み入れたウルクは、禁忌を犯した罰としてピナイを追放される。帰還の条件は、神の実とも、災いの種ともいわれる“コーミー”を持ち帰ること。荒野を彷徨しながらウルクは、初めて自らの意思と選択によって生きることを学んでいく。そして、圧倒的な力と巨躯(きょく)を持つ金色の陽の獣・キンムクゥとの戦い、ピナイとはまったく異なった様式の共同体を営む人びととの出会いを通じて、ウルクは“世界”を知り、“愛”を知る――。
荻原浩は豊かなイマジネーションとリアリティのある描写の積み重ねによって、古代人たちの生活や文化、価値観を生き生きと浮かび上がらせ、当然のことながら誰も見たことがない縄文人たちの“世界”を見事に物語の中で再現していく。そこに未開地の探検記を読んでいるような興味と興奮を呼び起こされる一方で、「鳥の巣に卵」で「たぶん」、「生肉と焼き肝」で「贅沢」、「夏の羽這え」で「元気」、「神の決めた日和」で「こんにちは」を表すといった小説ならではのユニークな言語表現の数々もまた何とも楽しい。
物語としての“大きさ”も特筆すべきことだろう。本作は2700年という時を超えて描かれる壮大な歴史ロマンであり、自然が猛威をふるう荒野での冒険サバイバルを描くロードノベルであり、ひとりの少年が大人へと成長していく様を描く教養小説であり、若い男女のほとばしるように熱い愛を描いた切なく美しいロマンスでもある。そして、この物語は縄文と弥生の狭間の時代を舞台としていながら、現代社会にまで通じる人間の営みの根源的な問題をも描き出す。「人間らしさ」とはいったい何なのか。何が人間の社会に富と権力を作り上げ、戦争を引き起こすのか。何より人間の歴史は“恋”が作ってきたのだという真実――2700年前に生きた15歳の少年の人生が、それを教えてくれる。
文=橋富政彦
今月のおすすめ書籍を紹介中!






