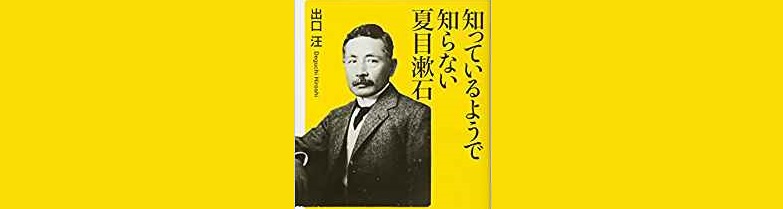「道徳に加勢する人は永久の敗北者だ」。不倫バッシングが加熱中の今こそ響く、夏目漱石の言葉
公開日:2017/12/21

ここ数年、ワイドショーを賑わし続ける著名人の不倫報道。加熱するバッシングを見ると、「そりゃ悪いことだろうけど、そこまで寄ってたかって責め立てなくても…」と思ってしまう。
そんな問題を考えるにあたって、奥深い視点を与えてくれたのが『知っているようで知らない夏目漱石(講談社+α新書)』(出口 汪/講談社)。本書は漱石作品の解説書だが、漱石は不倫が姦通罪という犯罪だった時代に、男女の三角関係を多く描いてきた作家でもある。本書ではそんな漱石の作品も丁寧に解説しており、特に興味深かったのが『行人』の読み解きだ。
『行人』の主人公・一郎は、妻である直の自分への愛情は本当のものなのか…と確信できずに苦しんでいる。そして弟の二郎に「直は御前に惚れてるんじゃないか」と言い、妻の貞操を確かめてほしいと頼む。
結局、直の貞操は分からずじまいだったが、二郎と話し合う過程で一郎は激怒。夫の弟と慕い合った結果、夫に殺されることになった「パオロとフランチェスカ」の逸話(ダンテの『神曲』に登場)を引き合いに出し、「二郎、なぜ肝心な夫の名を世間が忘れてパオロとフランチェスカだけ覚えているのか。その訳を知ってるか」と弟を問い詰める。続く一郎の言葉は以下の様なものだ。
おれはこう解釈する。人間の作った夫婦という関係よりも、自然が醸した恋愛の方が、実際神聖だから、それで時を経るに従がって、狭い社会の作った窮屈な道徳を脱ぎ棄てて、大きな自然の法則を嘆美する声だけが、我々の耳を刺戟するように残るのではなかろうか。もっともその当時はみんな道徳に加勢する。二人のような関係を不義だと云って咎める。しかしそれはその事情の起った瞬間を治めるための道義に駆られた云わば通り雨のようなもので、あとへ残るのはどうしても青天と白日、すなわちパオロとフランチェスカさ。どうだそうは思わんかね(『行人』より)
上記の文章を引用した後、著者の出口氏は、「人を好きになるというのは自然の行為に他ならず、それ自体は善でも悪でもありません」とし、結婚した夫を愛せなくなることも、夫の弟を愛してしまうことも、「本来どうしよもないこと」と解説。さらにこう続ける。
ところが、世間はそれを不義だと責め立てます。なぜなら、二人は道徳を犯してしまったからなのです。道徳とは社会全体を円滑にするために便宜的に人間が作ったもので、人びとは当然その時は道徳に加勢するものです。なぜなら、不義を認めたら、家族制度が崩壊する可能性があるのですから。
出口氏は、ワイドショーなどが芸能人の不義を暴き立てるとき、不倫=悪と決めつけていることについて「そうした態度自体が思考停止の状態に思えます」と警鐘を鳴らす。そして漱石は『行人』の一郎を通じて、「結婚という制度では人の心を縛れないということ」「だからこそ愛する人の魂を掴みたいと狂おしいまでに願ってしまうこと」などを描いているのだと解説している。
ちなみに出口氏は、本書で『行人』からこんな言葉も引用していた。
道徳に加勢するものは一時の勝利者には違ないが、永久の敗北者だ。自然に従うものは、一時の敗北者だけれども永久の勝利者だ……(『行人』より)
道徳を盾に、多くの人がさまざまなバッシングに加勢してしまう今の時代だからこそ、漱石を読み返す価値はある。そう感じられる一文だ。
文=古澤誠一郎
レビューカテゴリーの最新記事
今月のダ・ヴィンチ

ダ・ヴィンチ 2024年5月号 私の『名探偵コナン』履歴書/『ダ・ヴィンチ』創刊30周年
特集1 祝・連載30周年! 私の『名探偵コナン』履歴書/特集2 雑誌不況の“荒波”を乗り切れるか!? 『ダ・ヴィンチ』創刊30周年 他...
2024年4月6日発売 価格 850円
人気記事
-
1
-
2
sumika片岡健太のエッセイ連載「あくびの合唱」スタート!「“あくびぐらい”と許し合える関係でいられる人と生きていきたい」
-
3
-
4
竹を切るときは慎重に! 翁が光る竹を切ると、中から美しい子ねこが現れて… 【竹取物語なねこ】/みっけ!ねこむかしばなし⑥
-
5
人気記事をもっとみる
新着記事
今日のオススメ
-
![]()
レビュー
TVアニメ第2期決定・累計3300万部『薬屋のひとりごと』。最新15巻は医療ドラマと大人の愛憎劇が見どころ!
PR -
![]()
インタビュー・対談
「大切な人を想う気持ちに国は関係ない」台湾人作家が日本の子どもたちに読み聞かせた『ママはおそらのくもみたい』〈レポート&インタビュー〉
-
![]()
インタビュー・対談
芸人の描くコミックエッセイはなぜこんなに面白いのか? 矢部太郎とバッドボーイズ清人が執筆後の感情を語り尽くす【インタビュー】
-
![]()
レビュー
20代前半の焦燥感、もがき続けたあの時間が詰まった青春小説。上手くいかない日々が綴られる『22歳の扉』
PR -
![]()
レビュー
異能力×学園ファンタジー漫画『群青のストレンジャー』。見た目は人間…中身は狼、天使、人ならざる“亜人”の正体とは
PR
電子書店コミック売上ランキング
-
Amazonコミック売上トップ3
Amazonランキングの続きはこちら -
楽天Koboコミック売上トップ3
楽天ランキングの続きはこちら