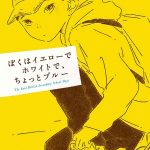「元底辺中学校」に入学した息子と母の直面した社会/2019年ノンフィクション本大賞受賞『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』①
公開日:2019/11/29
優等生のぼくが進学した「元底辺中学校」は、いじめもレイシズムもある、イギリス社会を反映するかのようなリアルな学校。多様な人種や貧富の格差に直面しながら、ぼくと母はともに考え悩み、乗り越えていく。子どもならではのやり方で、大人の常識を飛び越える姿に落涙必至。第2回「Yahoo!ニュース|本屋大賞 2019年ノンフィクション本大賞」大賞受賞作。

はじめに
隣の部屋から、やけに軽快なギター・リフが聞こえてくる。もうすぐ「ザ・ファンク・ソウル・ディスコ」というコンサートに出演する息子が、本番に向けてギターの練習をしているのだ。
ファンキーなタイトルだが、それはプロのコンサートではない。中学校の講堂で行われる音楽部の発表会だ。演奏するのは11歳から16歳までの中学生たちで、息子は下級生グループの中にいる。だから、コンサートでもその他大勢的なパートを与えられているだけなのだが、まじめな性格なので日曜の朝から練習に没頭している。
「おめえ、ちょっとアンプの音量を落としてくれねえか。テレビが聞こえねえぞ!」
と階下から叫んでいるのはわたしの配偶者だ。夜間シフトでダンプを運転して帰ってきたばかりなので気が立っているのだろう。23年前にわたしが知り合った頃は、ロンドンの金融街シティというところにある銀行に勤務していたのだが、数年後にリストラされ、また同じような仕事に就くのかなと思ったら、
「子どもの頃にやりたいと思っていた仕事だから」
と言って大型ダンプの運転手になった。わりと思いきったことをする人である。
わたしはこの配偶者と一緒に英国の南端にあるブライトンという街にもう20年以上前から暮らしている。そして息子が誕生してからは3人暮らしになった。
息子が生まれるとわたしは変わった。それまでは「子どもなんて大嫌い。あいつらは未熟で思いやりのないケダモノである」とか言っていたくせに、世の中に子どもほど面白いものはないと思うようになって保育士にまでなったのだから、人生のパラダイムシフトと言ってもいいかもしれない。
とはいえ、保育士になったおかげで、わたしは自分の息子とは疎遠になった。
彼が1歳になるとすぐに、わたしは(「底辺託児所」と自分で勝手に呼んでいた)保育施設で見習いとして働き始めたからだ。職場には息子も一緒に連れて行っていいことになっていたが、保育士の資格を取るために実習を行っているのだから、自分の子どもと遊んでもしょうがない。そのため、託児所で彼はほとんどわたしから引き離されていた。
こんなことをすると「なんでうちの母ちゃんはよその子とばかり遊んでいるのか」という嫉妬心で子どもがひねくれ、素行が荒れるので、保育士は職場に自分の子どもを連れて行くべきではないという人も多い。
だが、うちの息子はすくすくと育った。託児所の創設者であり、地元では伝説の幼児教育者だった師匠アニーが、わたしが心おきなく実習できるよう、ほとんど専属保育士のように息子の面倒をみてくれたからだ。
幼児時代の息子は、わたしではなくアニーに育てられたと言ってもいい。わたしの子どもにしてはバランスの取れた性格になったのはそのおかげだと思う。いまでも、いったい誰に似たのかと驚くほど沈着冷静なことを彼が言うときには、彼の中から師匠が喋っているような気になることがある。
そんな風にして底辺託児所で幼児期を過ごした息子は、地元の公営住宅地の中にある小学校ではなく、カトリックの小学校に進学した。
そこは市のランキングで常にトップを走っている名門校だった。公立だったが裕福な家庭の子どもが多く通っていて、1学年に1クラスしかない少人数の教育を行っていた。森の中に建てられたこぢんまりとした煉瓦の校舎に机を並べ、7年間を同じクラスで過ごす子どもたちは卒業する頃には兄弟姉妹のように仲良くなっていた。
ふわふわしたバブルに包まれたような平和な小学校に、息子は楽しそうに通っていた。たくさん友達もでき、先生たちにもかわいがられて、最終学年になったときは生徒会長も務めた。すべてが順調で、うまく行きすぎて、正直、面白くないぐらいだった。
わたしには、彼の成長に関わっているという気があまりしなかった。幼児のときは師匠アニーが育ててくれたし、その後は、牧歌的な小学校が育ててくれた。わたしの出る幕はなかったのである。
ところが。
息子が中学校に入るとそれが一変することになった。
彼はカトリックの中学校に進学せず、「元底辺中学校」に入学したからである。
そこはもはや、緑に囲まれたピーター・ラビットが出てきそうな上品なミドルクラスの学校ではなく、殺伐とした英国社会を反映するリアルな学校だった。いじめもレイシズムも喧嘩もあるし、眉毛のないコワモテのお兄ちゃんやケバい化粧で場末のバーのママみたいになったお姉ちゃんたちもいる。
これは11歳の子どもにとっては大きな変化だ。大丈夫なのだろうかと心配になった。
ようやくわたしの出る幕がきたのだと思った。
とはいえ、まるで社会の分断を写したような事件について聞かされるたび、差別や格差で複雑化したトリッキーな友人関係について相談されるたび、わたしは彼の悩みについて何の答えも持っていないことに気づかされるのだった。
しかし、ぐずぐず困惑しているわたしとは違って、子どもというものは意外とたくましいもので、迷ったり、悩んだりしながら、こちらが考え込んでいる間にさっさと先に進んでいたりする。いや、進んではいないのかもしれない。またそのうち同じところに帰ってきてさらに深く悩むことになるのかもしれない。それでも、子どもたちは、とりあえずいまはこういうことにしておこう、と果敢に前を向いてどんどん新しい何かに遭遇するのだ。
「老人はすべてを信じる。中年はすべてを疑う。若者はすべてを知っている」と言ったのはオスカー・ワイルドだが、これに付け加えるなら、「子どもはすべてにぶち当たる」になるだろうか。どこから手をつけていいのか途方にくれるような困難で複雑な時代に、そんな社会を色濃く反映しているスクール・ライフに無防備にぶち当たっていく蛮勇(本人たちはたいしたこととも思ってないだろうが)は、くたびれた大人にこそ大きな勇気をくれる。
きっと息子の人生にわたしの出番がやってきたのではなく、わたしの人生に息子の出番がやってきたのだろう。
この本はそんな息子や友人たちの中学校生活の最初の1年半を書いたものです。
正直、中学生の日常を書き綴ることが、こんなに面白くなるとは考えたこともなかった。