2025年本屋大賞受賞作『カフネ』はどう生まれた? 著者・阿部暁子が語る、執筆の原動力と自身の体験【インタビュー】
更新日:2025/5/2
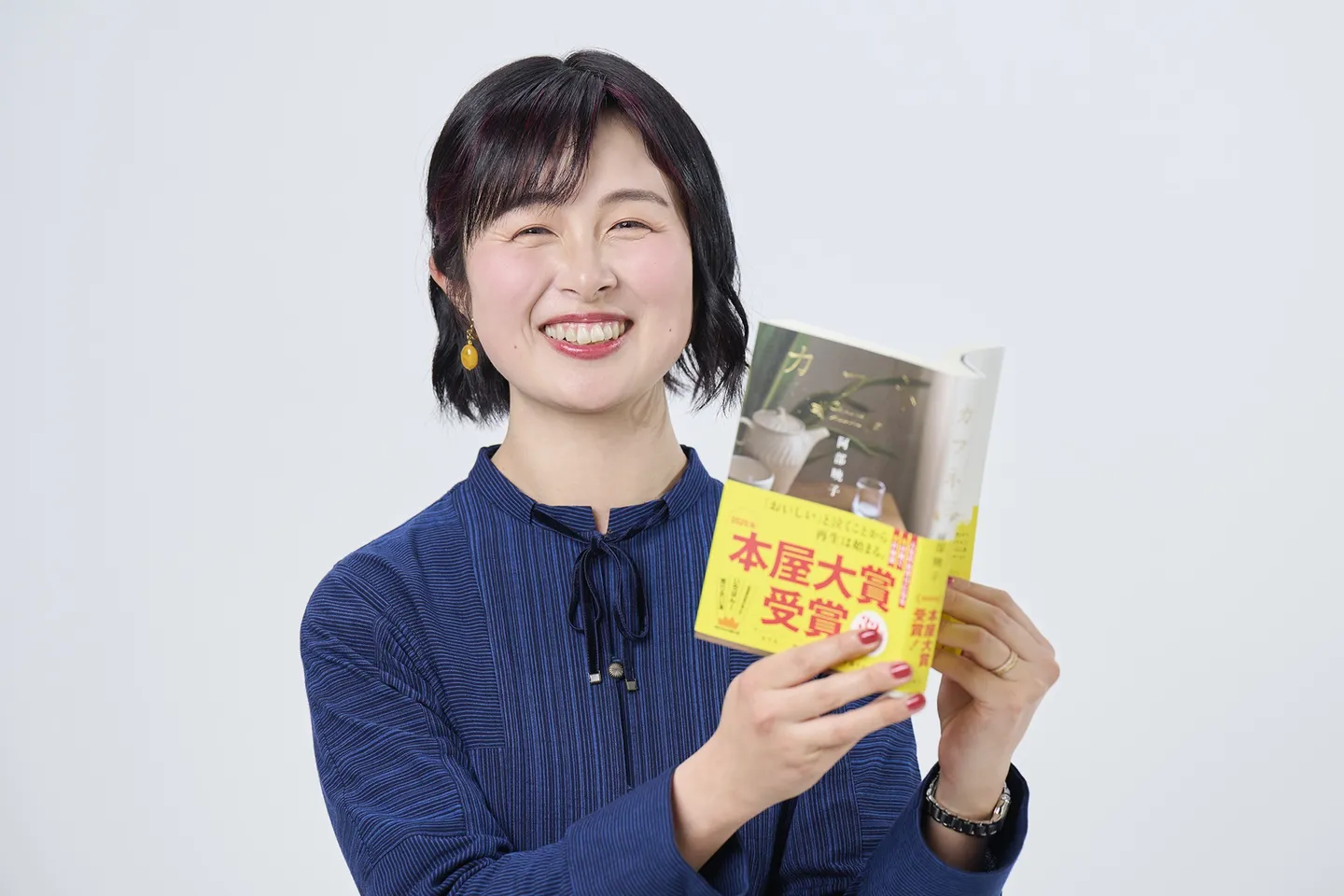
最愛の弟を亡くし、夫とも離婚。アルコール漬けの日々を送っていた薫子が出会ったのは、弟の元恋人で料理人のせつな。相容れぬタイプの二人だったが、せつなに誘われ、家事代行サービスのボランティア活動を手伝うなか二人の距離は次第に縮まっていく。散らかった部屋を片付け、あたたかい料理を用意する活動で、薫子が見つけた光、生きる力とは――。感動の声のなか、2025年本屋大賞を受賞した「今を生きる人々に寄り添う、食と愛の物語」について、そして今の心情を著者の阿部暁子さんに伺った。

――本屋大賞受賞、おめでとうございます! 今、どんなお気持ちでしょうか。
阿部暁子(以下、阿部):自分という器から溢れ出してしまうような大きなものをいただいた感があり、なかなか実感が湧かなくて。書店員さん方が選んでくださる本屋大賞は自分のなかで特別な賞。書店員さんは読者さんの代表であると私は思っているんです。読者としての真っ直ぐな声から選んでいただいたことに書き手として無上の喜びを感じています。
――反発し合っていた女性二人が様々な人との交流を通して関係を築いていく『カフネ』はどんなところから生まれてきたのでしょう。
阿部:当初は人生にくじけた41歳バツイチの薫子と、さすらいのクールな料理人・せつなが食材を担ぎ、古いワゴンに乗って依頼者のもとを渡っていく、ちょっと面白いロードムービーを想定していたのですが、執筆中、コロナ禍になってしまったんです。会いたい人に会えない人、職場に行けない人、さらには雇い止めにあってしまう人が出てくるなど、これまでの生活が崩れ、大変な思いをする人がどんどん増えていく。「この先、どうなってしまうんだろう?」という閉塞感を感じました。
何かひとつ石を投げ込まれると、人の生活はここまで急変してしまうということを目の当たりにし、身近な生活を描く話へと変わっていきました。そしてそんななかでも、困っている人々のために真っ先に動こうとする人たちがいた。その姿を見て人が人を思う姿を描きたいと強く思いました。
――コロナ禍で阿部さんに刻まれた「真っ先に動こうとする人々」の姿とは?
阿部:近所に子ども食堂があったのですが、そこが閉鎖され、日本全国でも次々と同じことが起き、その場所を拠り所にしていた人たちはどうなってしまうんだろうと胸を痛めていたとき、子ども食堂のスタッフの方たちがお弁当を作り、必要としている家庭に届ける活動を始めたというニュースを観たんです。ただ胸を痛めているだけの自分が恥ずかしくなったのと同時に、この状況で、誰かがどれほど困っているかを即座に理解し、ベストを尽くしている人たちの姿に衝撃を受けたんです。そこから物語は変わっていきました。
――最愛の弟を亡くし、悲嘆にくれる法務局に務める薫子と、弟が遺言書を遺した元恋人・せつな。薫子はせつなが勤める家事代行サービス会社「カフネ」の活動を手伝うことになります。無料の家事代行サービスであるボランティア活動「チケット」は、援助が必要なのに「助けて」と言えない人も手を伸ばしていける制度です。
阿部:子ども食堂のスタッフの方たちが、お弁当を作って届けに行く活動を始めたというニュースを観たとき、家事代行のサービスを「届けに行く」という設定につながりました。けれど自分で申し込むサービスだと、使えない人もいるんだろうなと書いているときに思って。なので、家事代行を使っている常連さんが、自分では使うことのできない無料サービスの「チケット」をもらい、誰かにあげる形なら、自分から「助けて」とは言えない、少し困っている人に届くかもしれないと思いました。
――親をひとりで介護している家、小学生のいるシングルマザーの家庭など、薫子とせつなが「チケット」で訪れる家庭はそれぞれ、生活のなかで困りごとを抱えている。そうした様々な家庭はどのように書かれていかれたのでしょうか。
阿部:私は書くときの原動力が自分の体験になりがちなんです。祖母の介護の記憶であったり、知り合いが家族との関係で悩んでいるとか、生活するなかで見たり聞いたり、体験したことが、物語につながることが多いですね。

――「薫子さんは人に頼るのが下手くそだから」と、亡き弟・春彦にも言われていた薫子は、幼い頃から努力を信条に自身の人生を切り開いてきた人。けれど弟の突然の死、長年の不妊治療もうまくいかず、夫に離婚を切り出されて別れ、人生のどん底にいると感じています。せつなと一緒に家事代行サービスに行くようになってからも、赤ちゃんのいる家に行くと、「自分は子どもを授かることができなかった」という思いが、薫子からは痛いほどに伝わってきます。
阿部:薫子の不妊治療に関する心境は、私自身の体験から書いています。あまりにもきつい時期があったので、「もう、小説に書いたれ!」みたいな気持ちになってしまって。薫子にはかなりきつい設定を背負わせてしまった部分があります。
――薫子は両親との関係もあまりうまくいっていません。重いものをいくつも背負う薫子ですが、それでも人を救いたい、人のために何かをすることで自分が助けられるという光を見つけていきます。
阿部:振り返ってみると、本作を書いていた時期の自分は、かなり悲観的になっていました。薫子には大変なものを背負わせましたが、それでも彼女が小さな光を見い出すことができたなら、自分が生きる、この現実のなかにも光を見出す可能性があるのではないかと手を伸ばすような思いで書いていました。
――薫子はもちろん、家事代行サービスで訪れる家の人々の心情など、自身と重ねて読む方も多いのではないかと。困難な状態に陥った人たちを書くとき、意識されていたことはありますか?
阿部:描くということは物語のために利用することなので、せめてなるべく調べてフェアに書きたい、と思っていました。あと、それがいいのか悪いのかはわからないのですが、重くてつらいことを書いていると、笑いを取りたくなるんです。ちょっと油っぽいものを食べてもらう間に、レモンシャーベットを入れたいみたいな感じで(笑)。それで薫子とせつなが漫才を始めてしまうようなところがありましたね。
――生真面目な薫子と、ぶっきらぼうなせつなは、コミカルな味わいを備えながらも、冒頭からかなりやり合っていますね。
阿部:死んだ男性の姉と元恋人という話はどうだろう、と編集の方からご提案いただいたとき、その一文のなかにドラマが詰まっている、と思ったと同時に、二人が言い合っている情景がぱぁっと浮かんできたんです。
――阿部さんの書かれる小説はいつも会話が活き活きとして、ストーリーをぐいぐい引っ張っていく。はじめは相容れないタイプに見えた薫子とせつなの会話を書いていったとき、どんな感覚でしたか?
阿部:この二人、自分が好かれたいという気持ちが相手に対してないので、遠慮なく喋れるんですよね。思った以上に何でも言えて、「面白いな、この二人(笑)」と思っていました。相手に好かれなくても全然構わないと互いに思っていると、面白いこと、そして思わぬ言葉が出てくるなと。
――せつなが作るごはんがどれも美味しそうで。アルコールに頼る日々を送っていた薫子の気持ちや二人の関係をちょっとだけ変えたのは、せつなが薫子のために作った「トマトとツナの豆乳煮麺」でした。
阿部:私自身、とくに料理は得意ではないんです。「トマトとツナの豆乳煮麺」は、学生時代、友だちと日本酒を一升ずつ飲んで気持ち悪くなってしまった翌朝、余っていた素麺を友だちが温かくして食べさせてくれたという印象に残る思い出がありまして。ある理由から、薫子は豆乳を飲んでいるという設定があったので、豆乳とコンソメを混ぜて素麺を入れたら美味しいのでは、と想像で書いたのですが、なんと『カフネ』の公式サイトでレシピにしていただいて。本当に美味しく食べられる料理になってびっくりしました。
――「お手軽チョコローズパフェ」「大きな骨付き肉」、など、ただ美味しいだけではない、お腹と心を満たす料理が次々と登場します。
阿部:ひたすら身近な料理ばかりなのですが、私たちが食べている普段のごはんって、毎回、おしゃれなものではないし、冷蔵庫の残り物を集めた炒め物のような名前の付けられないものなんですよね。そんなごはんを、読んでいて、いいな、美味しそうだなと思ってもらえるように書きたいなと。私自身も食べ物に救われた経験があるんです。
デビューしてからしばらく売れず、いよいよ先がない、今思い出しても苦しくなるような時期があったのですが、そんなとき、家族にハンバーグ屋さんに連れていってもらったんです。熱々のハンバーグを食べたら元気を出したくないのに、出ちゃったという体験がありまして。それが、薫子をはじめ、せつなの料理を食べた人たちの「自分を取り巻く状況は変わらないのに、なんだか元気出ちゃった」という感覚につながっています。

――本作には、薫子とせつなの他にも、様々な立場や思いを秘めた人々が登場してきます。物語に大きな展開を生んでいくことになる薫子の弟・春彦は、物語のはじめから亡き人でしたが、全編通して大きな存在感を放っていますね。
阿部:春彦はさじ加減が難しいと思いながら書いていました。ある意味、すべてのはじまりであるキーパーソンなので存在感はあってほしい、けれど深掘りをしすぎるとバランスの取れないところもあったので、小さなエピソードを重ね、カメラのフラッシュのように、彼の思いがキラッと光るように書きたいと思いました。
本作には、マイノリティと呼ばれる人物も登場してきますが、そこでことさら「多様性」というものに焦点を当てたくはなかった。世の中に「多様性」という言葉が蔓延するなか、逆に生きづらくなっている人もいると思うんです。いろいろな生き方をしているこの世界の人たちを、フラットに並べて書きたかったというところがあります。
――はじめに見えていたのとは違う面が、様々な人に現れてくるところも本作の醍醐味です。
阿部:人と人は付き合って知ることが増えていくたび、印象が変わるという考えが自分にはあるので、せつなも、春彦も、さらに一方的に薫子に離婚を切り出した元夫・公隆も話が進んでいくなかで、最初は正面しか見えていなかったものが、斜めも、サイドも、バックも見えてくるようになるという書き方をしようと思っていました。
――薫子やせつなが抱いていた幼い頃の感情であったり、「チケット」で訪問する家庭の小学生たちなど、「子どもの目線」というものも息づいている気がしました。それは意識されていましたか?
阿部:無意識でしたが、今、「そうかもしれない」と思いました。物語を書いているとき、過去の自分が跳ね返ってくる感覚がすごくあるんです。子どもの時に報われなかったこと、その頃、大人にしてしまった痛いことなどが、今の自分に跳ね返ってくる。自分の年輪を辿りつつ、いろんな立場の人間を書いているという感覚がありますね。
――“傷ついているのは、人知れず苦しんでいるのは、一見何事もなく生きているような人たちだってきっと同じだ”という言葉が前作『カラフル』のなかにもありますが、『カフネ』はそうした一見、傷ついていなそうな人や心を、こまやかに掬いとる物語であると感じました。そしてそれは阿部さんが小説で書いていきたいことのひとつなのではないかと。
阿部:そのとおりです。傷ついている、困っている、目に見える立場の人を助けるのも大事なことですが、多くの人が「何でもないよ」という顔をして、傷つきながら生活していると思うんです。そうした部分を大事に書きたい、これからも書いていきたい、という気持ちがすごくあります。

取材・文=河村道子、写真提供=講談社




