2024年の文学賞受賞作をプレイバック! 1週間で“トリプル受賞”を達成したミステリーから、障害のある息子の性処理をテーマにした作品も
公開日:2024/12/31
2024年も残すところあとわずか。今年もさまざまな小説が文学賞に輝き、読書好きの間で大きな注目を集めた。選考委員を唸らせ、満場一致で大賞に選ばれた作品もあれば、1週間で“トリプル受賞”を達成した本格的頭脳バトル小説も……。もしかしたらまだ見落としている傑作もあるかもしれない。
そこで本稿では、2024年に発表された文学賞受賞作の一部をご紹介。年末年始に読む本を探している人は、本選びの参考にしてみてはいかがだろうか。
芥川龍之介賞
2024年上半期の「芥川龍之介賞」に選ばれたのは、朝比奈秋の『サンショウウオの四十九日』と松永K三蔵の『バリ山行』。また2024年12月12日には、下半期の候補作が明らかに。安堂ホセの『DTOPIA』、鈴木結生の『ゲーテはすべてを言った』、竹中優子の『ダンス』、永方佑樹の『字滑り』、乗代雄介による『二十四五』の5作品が候補となった。
『サンショウウオの四十九日』
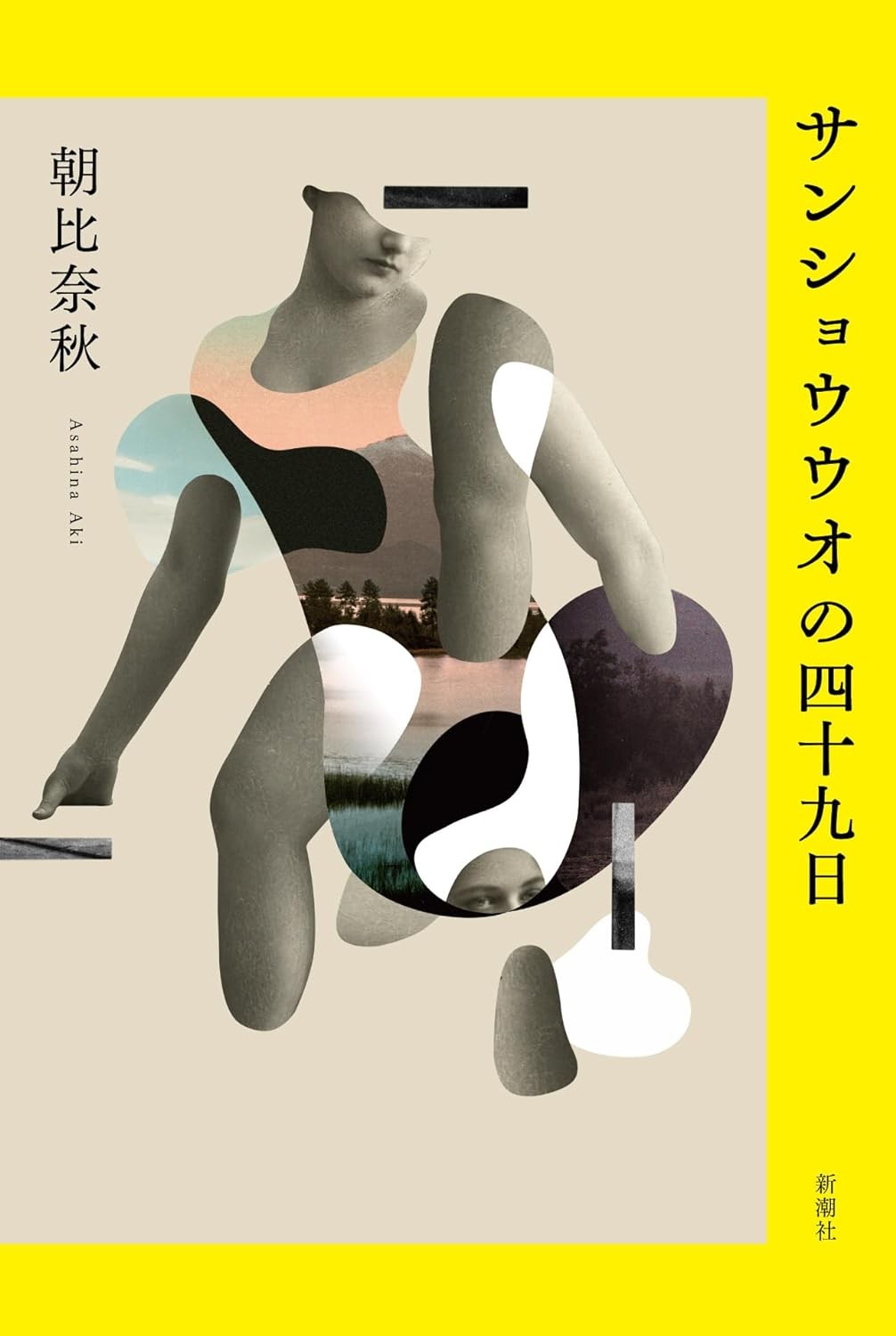
著者である朝比奈秋は、医師として働きながら小説を執筆し、2021年に「塩の道」で第7回林芙美子文学賞を受賞。2022年、同作を収録した『私の盲端』でデビューを果たした注目の新鋭だ。
『私の盲端』では“人工肛門”になった女子大生の意識と身体の変容を描き、三島賞受賞作『植物少女』では“植物状態”の母親を持つ娘の姿を通して、「親子」とは何なのかを問いかけた。そして本作『サンショウウオの四十九日』ではひとつの体を2人で共有する双子の姉妹を主人公に、医師ならではの視点で人生の普遍や生きることの尊さを伝えている。
『バリ山行』
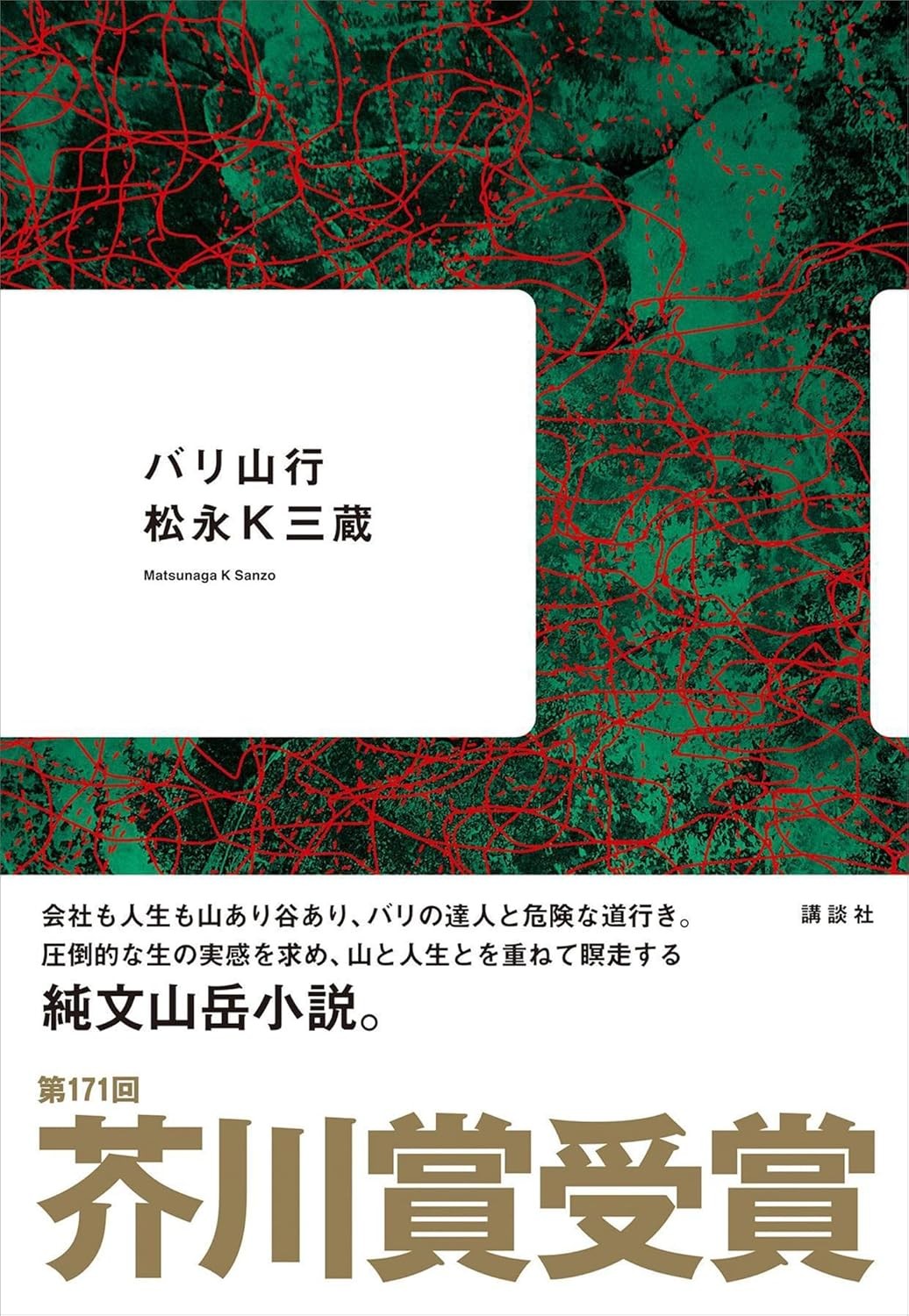
『バリ山行』は、日本三百名山の一つでもある神戸・六甲山を舞台にした物語。タイトルにある「バリ」とは“バリエーションルート”の略で、整備された登山道ではなく、やぶを分け入るなどしながら道なき道を進んでいく登山方法だ。
社内の登山部で気楽な活動を楽しむ主人公は、ひょんなことからこの“バリ”の達人である同僚に興味を持つようになる。やがて念願かなってバリ山行に同行させてもらうことになるのだが、それは想像以上に危険な道行きだった。圧倒的生の実感を求め、山と人生を重ねて瞑走する純文山岳小説。
直木三十五賞
2024年上半期の「直木三十五賞」に選ばれたのは、一穂ミチの『ツミデミック』。さらに2024年12月12日には下半期の候補作も発表され、朝倉かすみの『よむよむかたる』、伊与原新の『藍を継ぐ海』、荻堂顕の『飽くなき地景』、木下昌輝の『秘色の契り 阿波宝暦明和の変 顛末譚』(※顛の偏は、正しくは「眞」)、月村了衛による『虚の伽藍』の5作品が候補となった。
『ツミデミック』

同作は、コロナ禍で生じた犯罪をテーマに描いた短編小説集。心震える6つのエピソードが収録されており、誰もが身に覚えのある感情を巧みなストーリーテリングによって描き出している。読者からは「一編もハズレなし」と好評。作家の呉勝浩も「人間は愚かで怖く、可笑しくてたくましい。作者の細密な眼差しが、そのグラデーションをさりげなく、そして豊かに活写している」と賛辞を贈っていた。
本屋大賞
書店員の投票によって決定する「全国書店員が選んだいちばん! 売りたい本 2024年本屋大賞」、通称「本屋大賞」。大賞には宮島未奈の『成瀬は天下を取りにいく』、翻訳小説部門1位はファン・ボルム(著)、牧野美加(訳)の『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』、そして2022年11月30日以前に刊行された作品が対象となる「発掘部門」には、井上夢人の『プラスティック』が選出された。
また2025年2月には、2025年本屋大賞のノミネート作品が発表されるので、こちらも見逃せない。
『成瀬は天下を取りにいく』
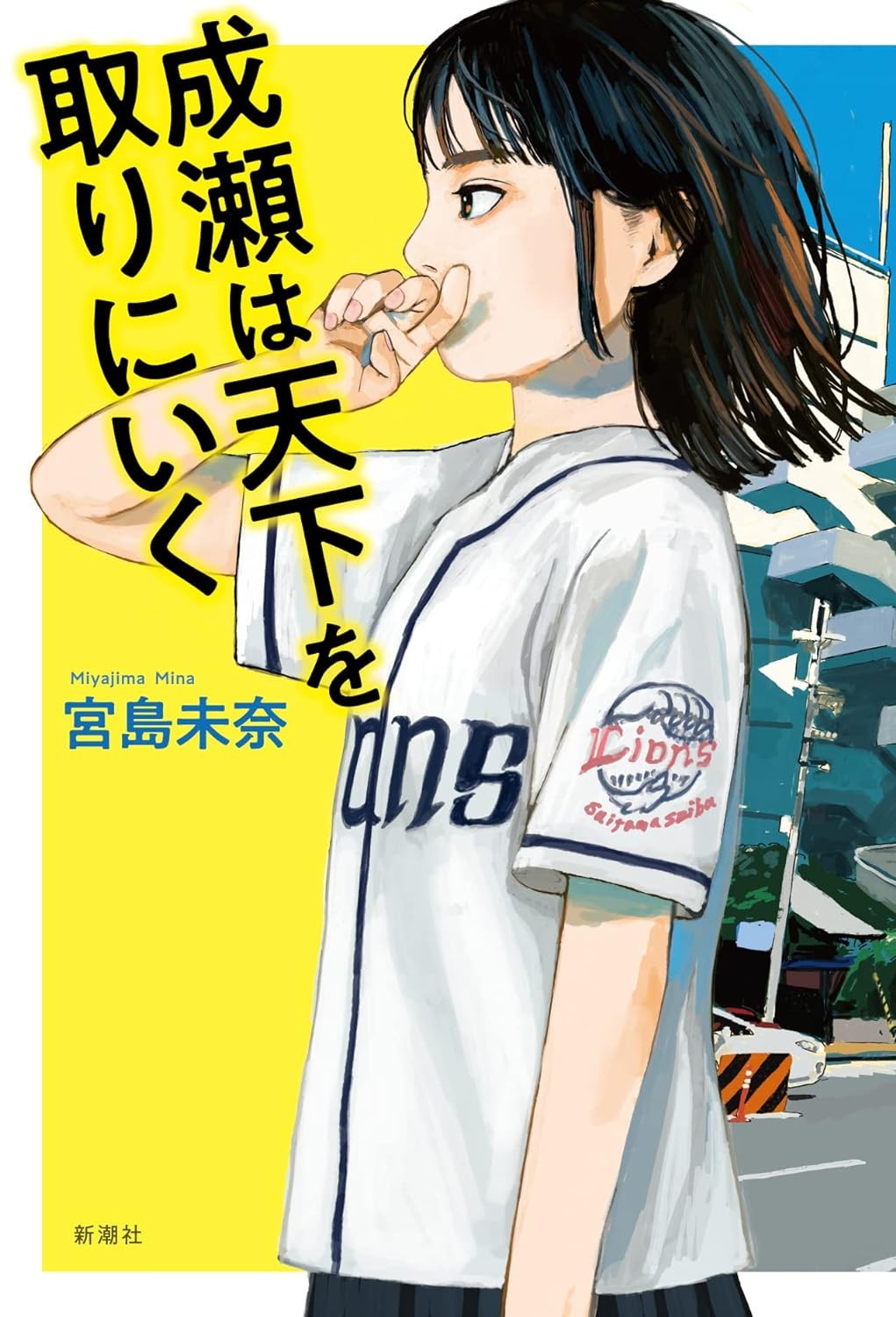
同作の魅力は、なんといっても全国の書店員を虜にした主人公「成瀬あかり」にあるだろう。コロナ禍に閉店を控える西武大津店に毎日通い、“この夏を西武に捧げる”と言い出してみたり、幼なじみの島崎を巻き込み、M-1に挑戦してみたり。今日も全力で我が道を突き進む“成瀬”から、きっと誰もが目を離せなくなるに違いない。
山田風太郎賞
過去には貴志祐介の『悪の教典』や高野和明の『ジェノサイド』などが受賞作に選ばれた「山田風太郎賞」。第15回となる2024年度は、蝉谷めぐ実の『万両役者の扇』が同賞に輝いた。
『万両役者の扇』
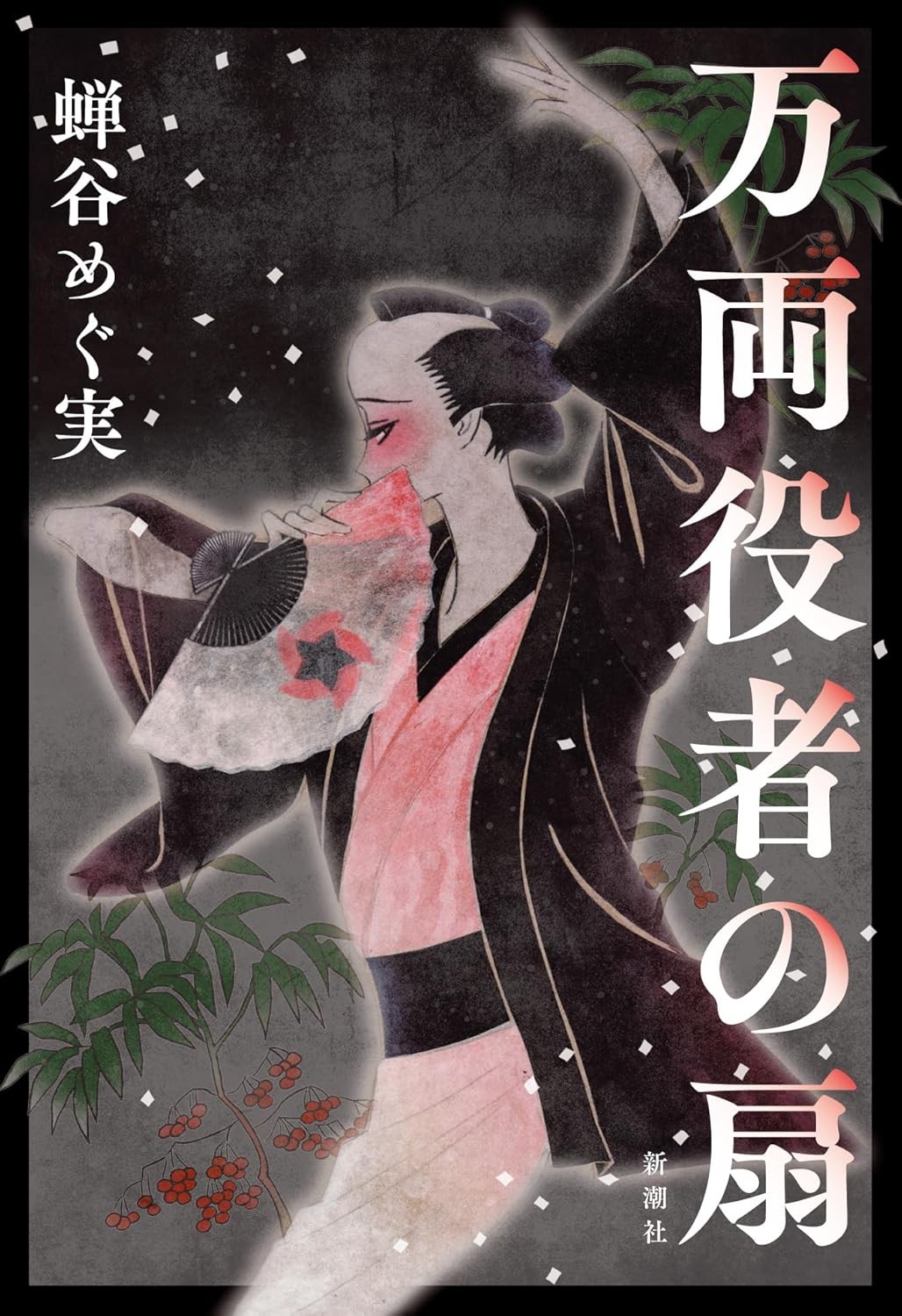
2020年10月に刊行されたデビュー作『化け者心中』以来、唯一無二の語りで“芝居”の世界を描破し続ける著者の蝉谷めぐ実。芸のためならどんな所業も許されるのか――。底なしの役者沼に沈んでいく崇拝者と役者本人の狂気を濃密に描き切る。
吉川英治文学新人賞
2024年は前回に引き続き、京極夏彦や辻村深月ら人気作家5名を選考委員に迎えて受賞作を決定。第45回となる「吉川英治文学新人賞」には、藤岡陽子の『リラの花咲くけものみち』が選ばれた。
『リラの花咲くけものみち』

「動物が好き」という理由で“獣医学”の道に進んだ学生たちが、どのような感情で動物の命と向き合うのか。理想と現実の間で葛藤する姿を知りたいという思いから、この物語を手がけたという著者。家庭環境に悩み心に傷を負った主人公が、祖母とペットに支えられて獣医師を目指し、自らの“居場所”を見つけ出す。北海道の地で、大きく成長していく少女の姿を描いた感動作。
三島由紀夫賞
第37回「三島由紀夫賞」に選ばれたのは、大田ステファニー歓人の『みどりいせき』。著者は2023年、同作で第47回「すばる文学賞」を受賞し、作家デビューを果たした。
『みどりいせき』
「私の中にある『小説』のイメージや定義を覆してくれた」「この青春小説の主役は、語り手でも登場人物でもなく生成されるバイブスそのもの」などと、選考委員が激賞する同作。型にはまらない文体&世界観は一見する価値あり。闇バイトに巻き込まれる主人公の青春を描く、超ド級のデビュー作。
日本推理作家協会賞
第77回「日本推理作家協会賞」の長編および連作短編集部門では、荻堂顕の『不夜島(ナイトランド)』と青崎有吾の『地雷グリコ』が受賞作に決定。そのほか短編部門には、坂崎かおるの『ベルを鳴らして』と宮内悠介の『ディオニソス計画』が受賞作に選出された。
『不夜島』

作家の貴志祐介も絶賛した歴史ハードボイルド超大作。密貿易が行われる与那国島を舞台に、サイボーグ密貿易人の主人公が、姿も形も知れない“含光”なる代物を手に入れるべく相棒とともに奔走する。のちに世界を巻き込む、壮絶な陰謀に巻き込まれるとも知らずに……。
『地雷グリコ』

日本推理作家協会賞のほかに、本格ミステリ大賞、山本周五郎賞を1週間で“トリプル受賞”した、と話題になり、4大ミステリランキングをも制覇した同作。勝負事にやたら強い女子高生が、風変わりなゲームの数々に挑み、強者たちを次々に打ち破る。勝負の先に待ち受けるものとは? ミステリ界の旗手が仕掛ける、本格的頭脳バトル小説。
メフィスト賞
講談社の文芸雑誌『メフィスト』から生まれた同賞は、下読みをせず、全ての応募作を編集者が直接読むことで知られている公募新人賞。過去には『すべてがFになる』の森博嗣や「物語」シリーズでお馴染みの西尾維新など、名だたる作家を世に送り出してきた。
2024年は受賞作が発表されなかったため、参考までに第65回メフィスト賞受賞作『死んだ山田と教室』(2024年5月単行本発売)をご紹介しよう。
『死んだ山田と教室』
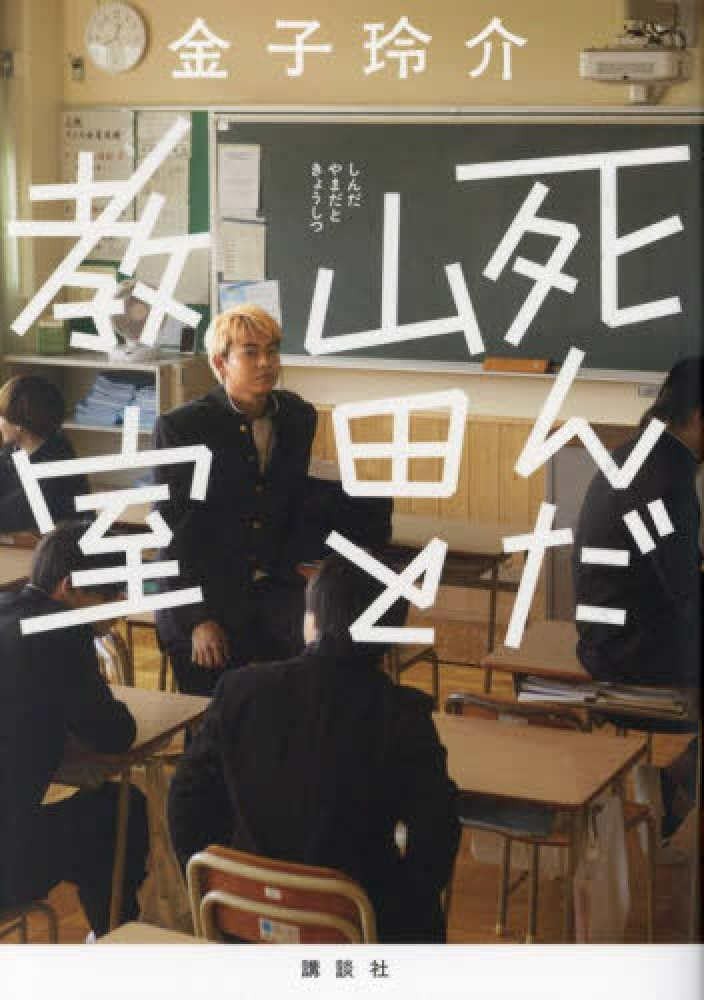
物語は、クラスの人気者である“山田”が死んだところから始まる。勉強ができて、面白くて、誰にでも優しくて……。大事なクラスメイトを失い、悲しみに沈む二年E組。何とか元気づけようと担任の花浦が席替えを提案したタイミングで、突然教室のスピーカーから山田の声が聞こえてきた。声だけになった山田と、二年E組の仲間たちの不思議な日々が幕を開ける。
江戸川乱歩賞
作家の綾辻行人や東野圭吾、湊かなえらを選考委員に迎え、第70回「江戸川乱歩賞」に輝いたのは、霜月流の『遊廓島心中譚』と日野瑛太郎の『フェイク・マッスル』。日野は2021年から4作連続で最終候補に残るも、過去の3作はいずれも落選という結果に。今回ついに悲願の江戸川乱歩賞を勝ち獲った。
『遊廓島心中譚』
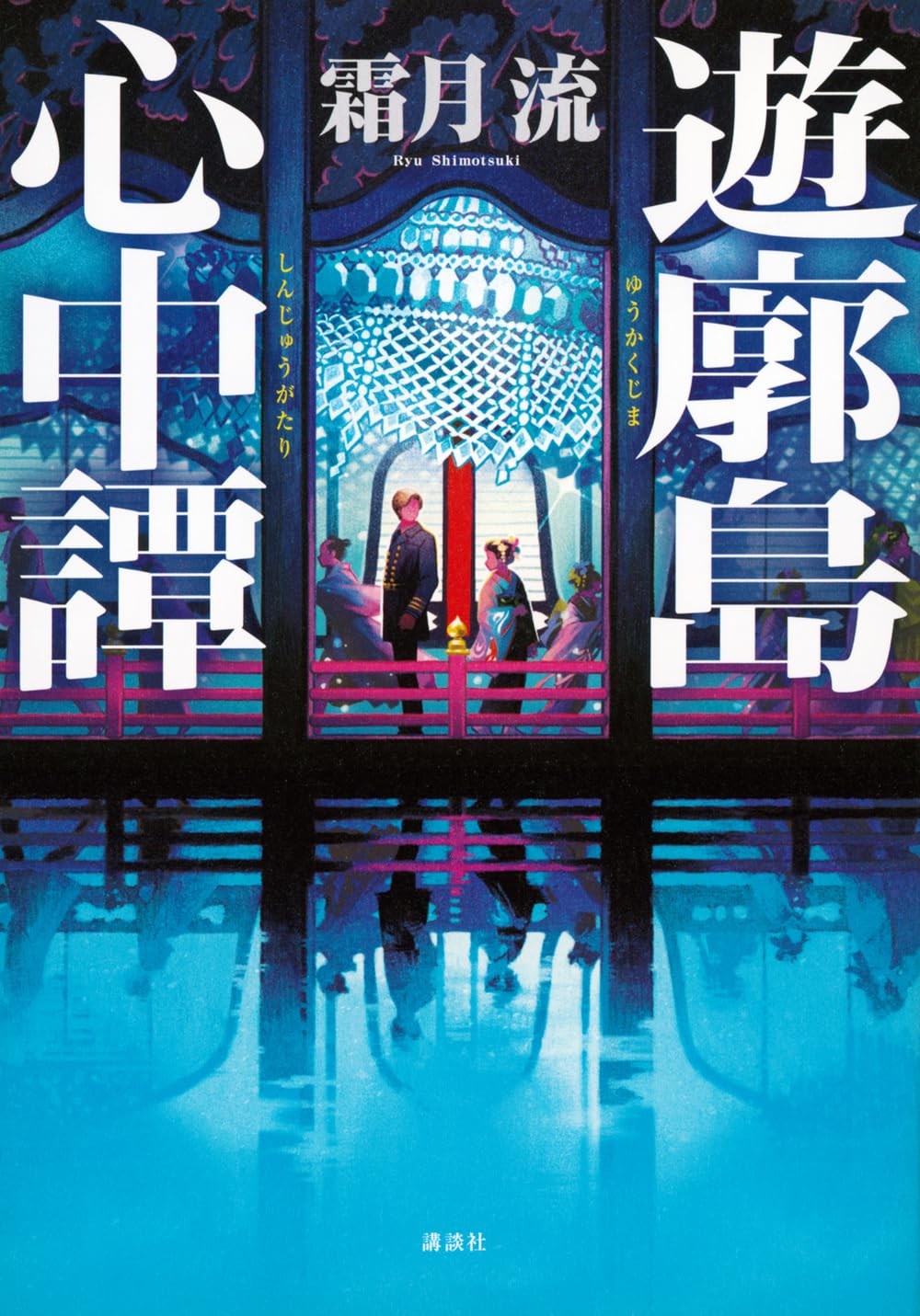
同作は、幕末に存在した「遊廓島」を舞台に描く切ない愛のミステリ。数奇な運命によって、男に身を捧げることになる女たちの生き様が描かれており、著者にとって本作が長編デビューとなる。選考委員の綾辻行人も「終盤に至ってすこぶる本格ミステリ的なクライマックスが待ち受けている。この展開には驚いた」と絶賛していた。
『フェイク・マッスル』
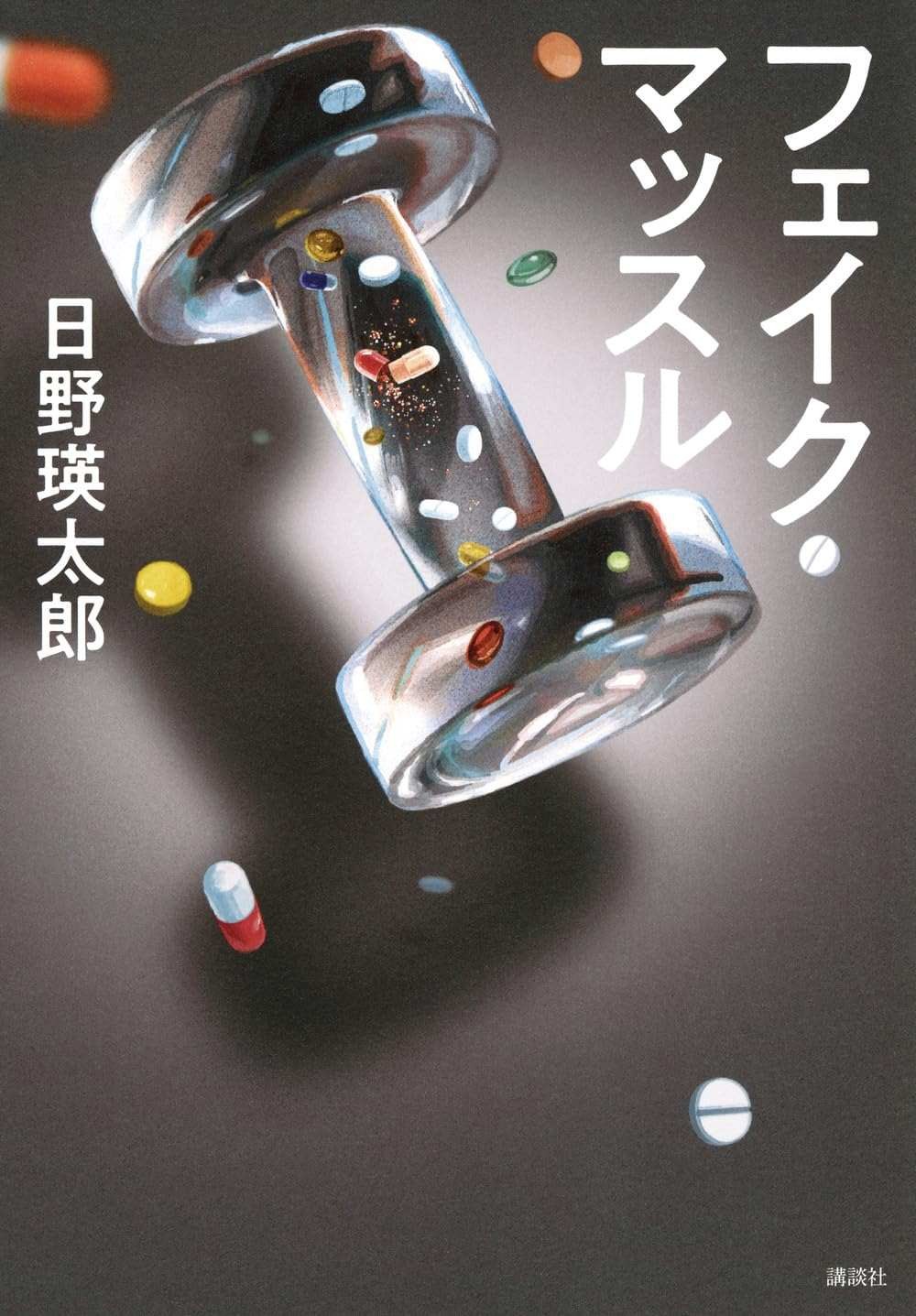
同作は、たった3カ月のトレーニングでボディビル大会の上位入賞を果たしたアイドルをめぐり、入社2年目の雑誌記者がドーピング疑惑の真相を追い求めていくミステリ作品。日本小説界を代表する東野圭吾に「独自の世界で勝負できる書き手だと思う」と言わしめた物語の結末とは――。
横溝正史ミステリ&ホラー大賞
「横溝正史ミステリ&ホラー大賞」は、ともに四半世紀以上の歴史を持つ「横溝正史ミステリ大賞」と「日本ホラー小説大賞」の2つを統合し、2018年2月に創設。第44回となる今回は、大賞こそ選出されなかったが、優秀賞には浅野皓生の『責任』が選ばれた。
『責任』

不審車両を追跡したことで、間接的に被疑者を死なせてしまった刑事の松野。ささいなきっかけでその事故の背景にあった強盗致傷事件を再捜査することになるのだが、そこで思わぬ真実が明らかになる。あのとき、俺が追わなければ――。著者の浅野皓生は、2001年生まれの現役大学生。純然たる警察ミステリでありながら、「謎が解けた後の景色こそが、一番書きたかった部分」と語る。
『このミステリーがすごい!』大賞
403作品の応募が集まった第23回「『このミステリーがすごい!』大賞」。土屋うさぎの『謎の香りはパン屋から』が大賞に決定したほか、松下龍之介の『一次元の挿し木(仮)』と香坂鮪の『どうせそろそろ死ぬんだし(仮)』が文庫グランプリに選ばれた。なお3作品とも2025年1月から順次、書籍化される予定。
『謎の香りはパン屋から』
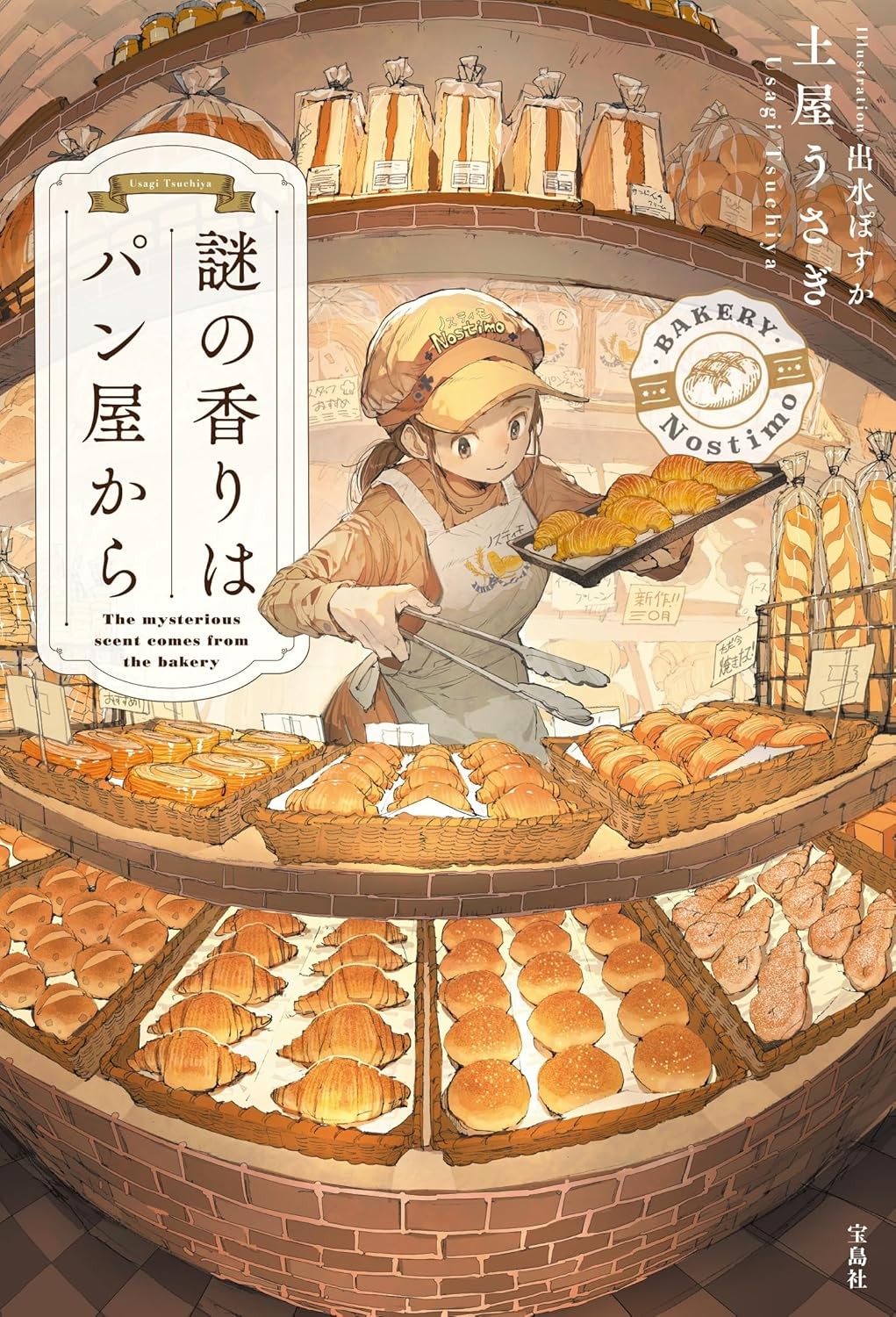
謎はクロワッサンのように折り重なり、カレーパンのように刺激的! パン屋を舞台に、大学1年生の主人公・市倉小春がさまざまな“日常の謎”を解き明かしていく。焼きたてのパンの香りが広がる“美味しい”連作ミステリー。
鮎川哲也賞
東京創元社主催の文学新人賞「鮎川哲也賞」。第34回受賞作は、山口未桜の『禁忌の子』に決定した。
『禁忌の子』
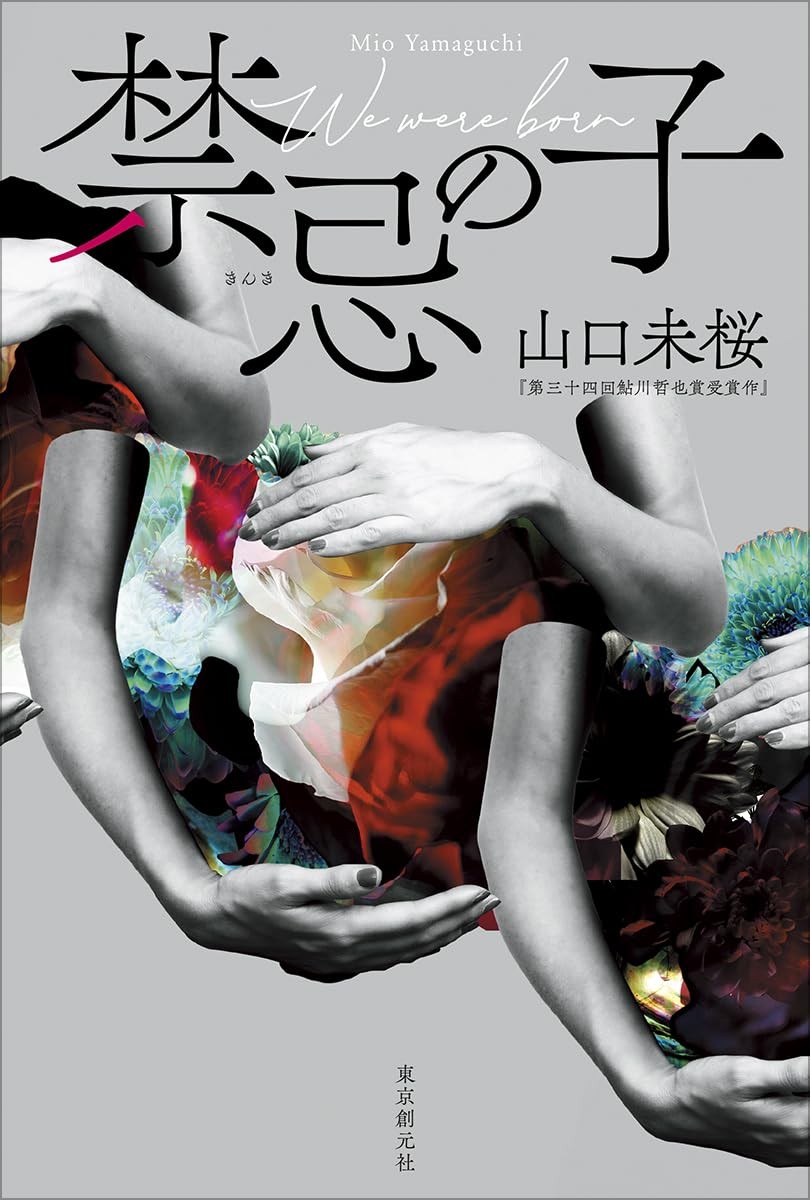
著者の山口未桜は、現役の医師として働きながら小説を執筆。医師である著者だからこそ描けた本格医療ミステリには、人気作家から絶賛の声が続々と寄せられており、満場一致で鮎川哲也賞が決定した。救急医・武田のもとに搬送されてきた自身と瓜二つの溺死体。彼はなぜ死んだのか、なぜ同じ顔をしているのか。自らのルーツを辿った先にある、思いもよらぬ真相とは。
群像新人文学賞
群像新人文学賞は、講談社の文芸誌『群像』が主催する公募新人文学賞。過去には林京子、村上春樹、柄谷行人などの作家・評論家を輩出している。第67回となる同賞に選ばれたのは、豊永浩平の『月ぬ走いや、馬ぬ走い』。また優秀作には、白鳥一の『遠くから来ました』が選出された。
『月ぬ走いや、馬ぬ走い』
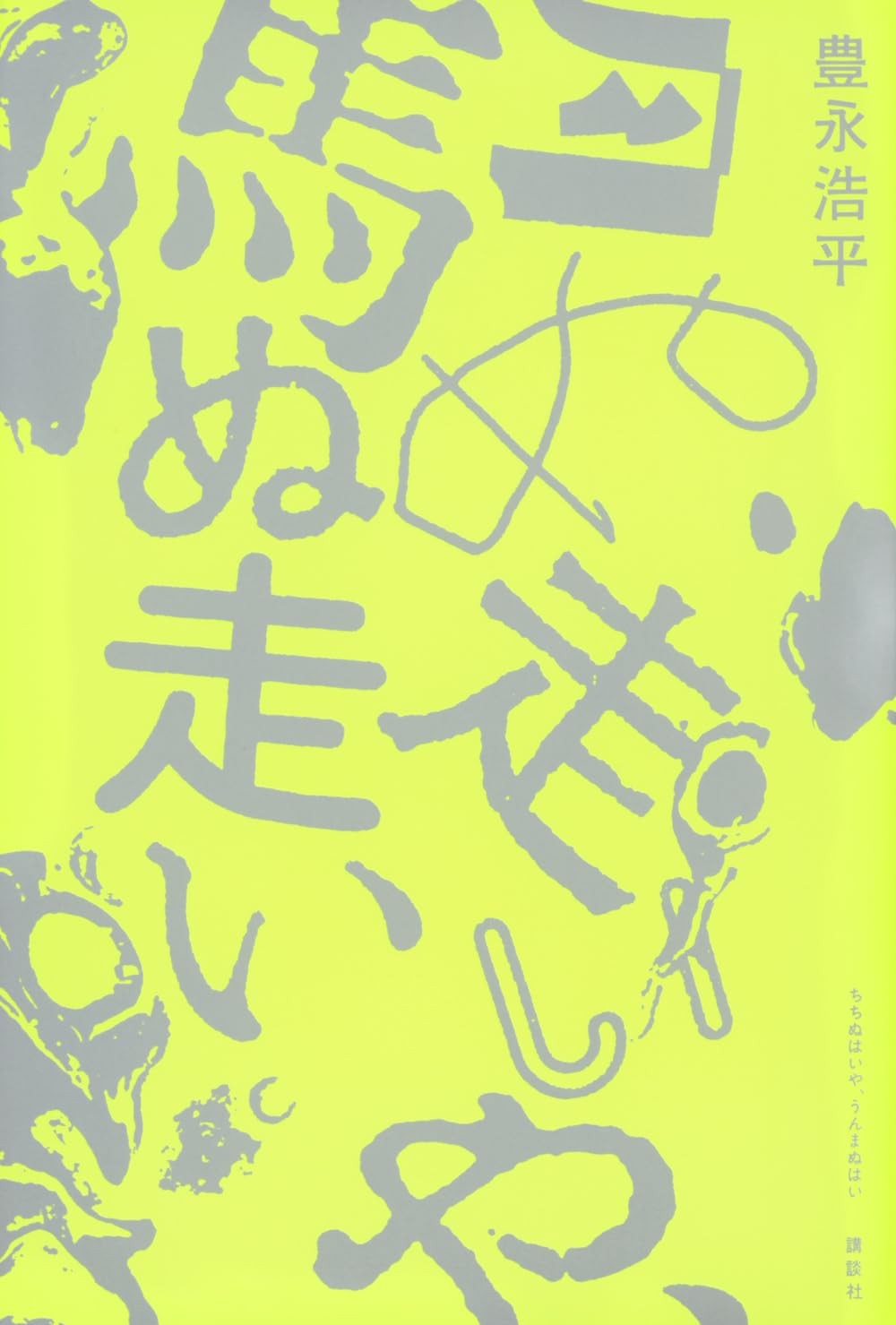
著者の豊永浩平は沖縄県出身、2003年生まれの現役大学生。パワフルな語部と型破りなスケールで、沖縄の近現代史を描き切る。衝撃のデビュー作には、全国の書店員からも「読み終えて、心が震えた」「頭ではなく心が理解するという感覚」「こんな文学は初めて」などの反響が続々。
文藝賞
1962年の創設以来、多くの新人作家を輩出してきた「文藝賞」。第61回の受賞作は、待川匙の『光のそこで白くねむる』と、松田いりの『ハイパーたいくつ』に決定した。
『光のそこで白くねむる』
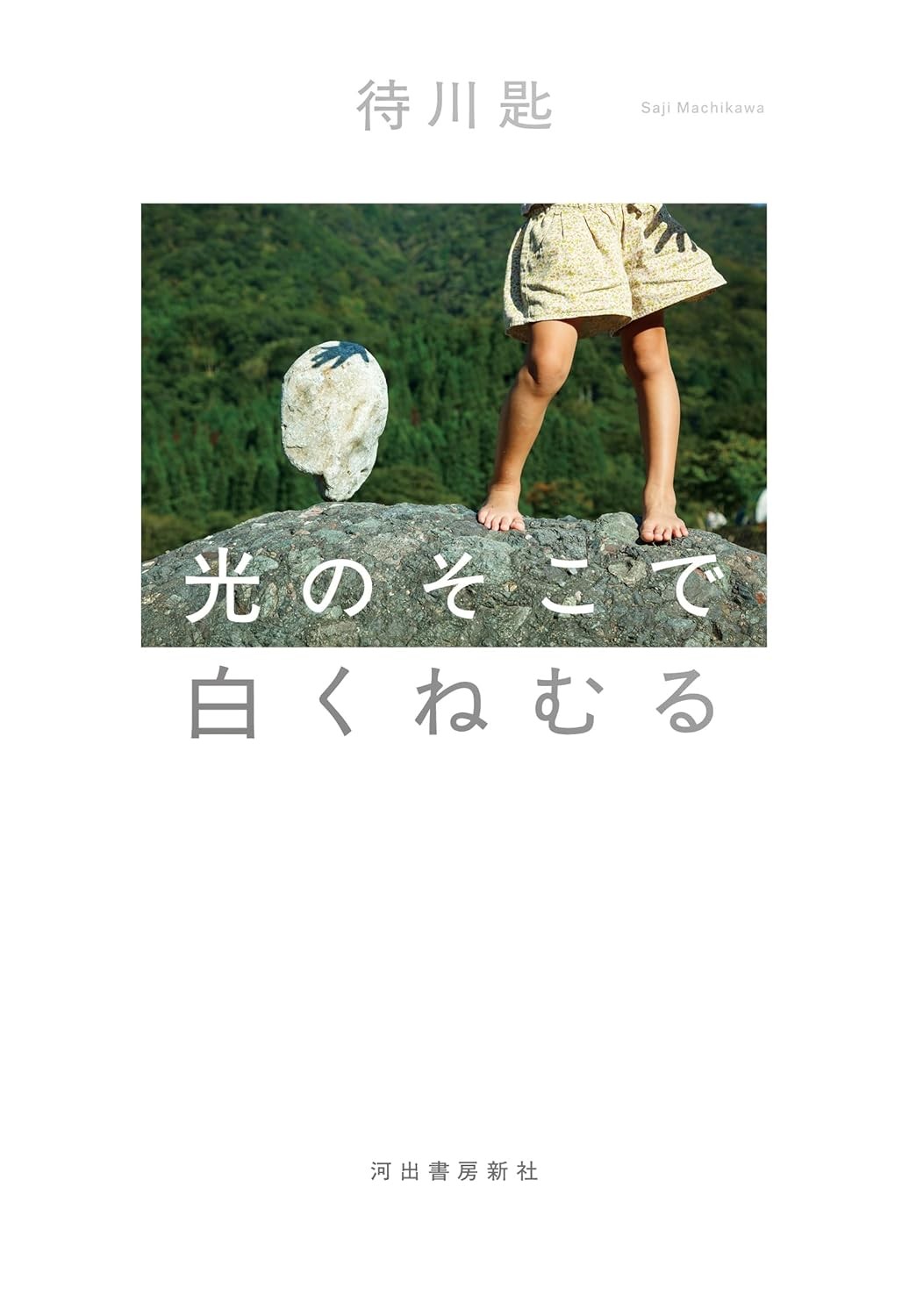
10年ぶりに故郷を訪れた「わたし」。墓地へ続く道を進むと、ふと死んだはずの幼馴染の声が語りかけてくる。行方不明の母、蒙昧な神のごとき父、汚言機械と化した祖母……。崖で隔てられた彼岸と此岸の往還により、不確かな記憶が流れ込み、平凡な田舎に呪われた異界が立ち上がる。
『ハイパーたいくつ』
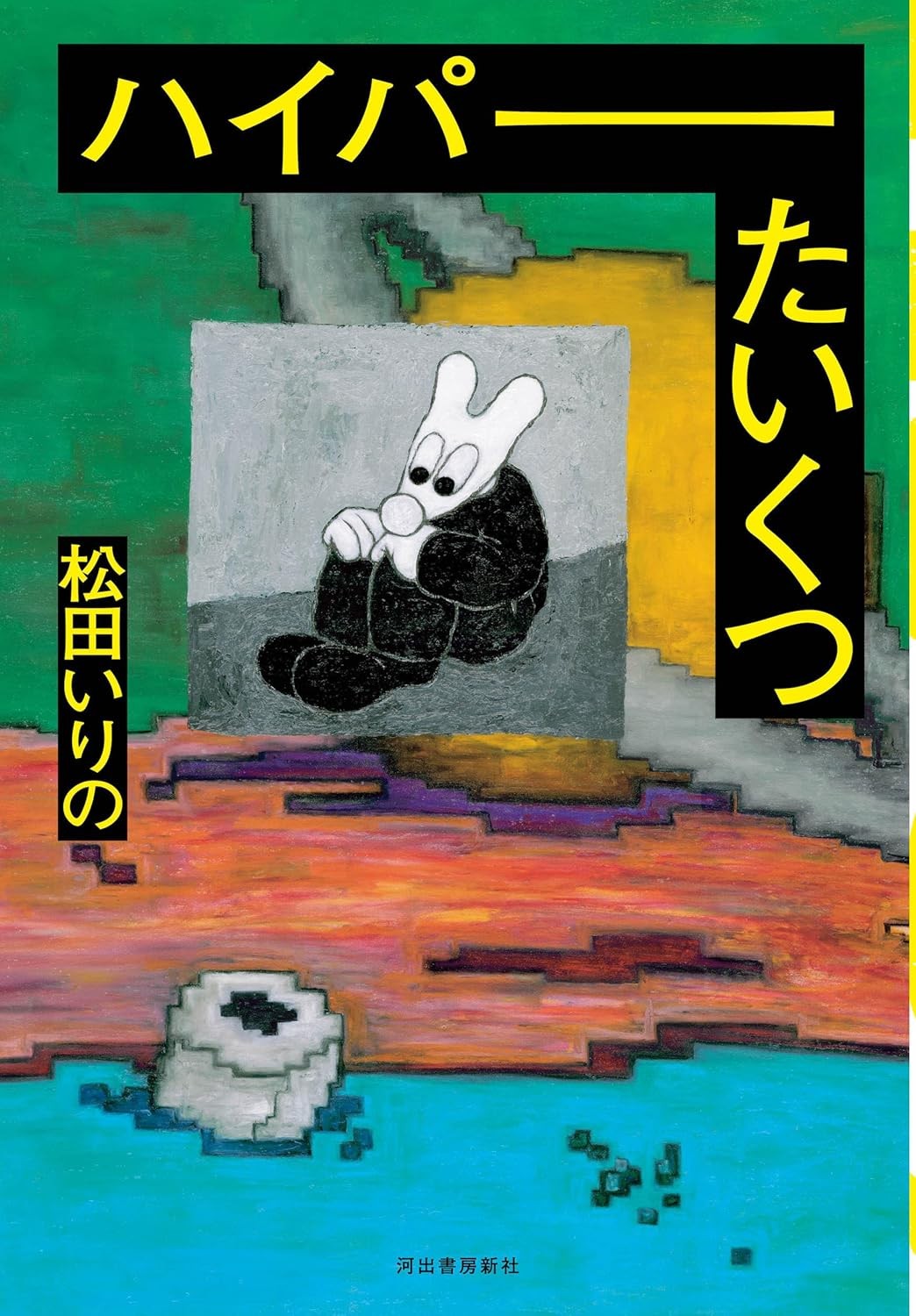
物語の主人公は、迷惑系給金泥棒として職場で疎まれている「ペンペン」。退屈な毎日が限界を迎えた時、壊れた言葉が壊れた風景を呼び起こす。俳優の仲野太賀も「壊れた感情が、もの凄い速度で事故ってる。読後感は“瀕死”だった」と激賞するリリカル系日常破壊小説。
すばる文学賞
第48回「すばる文学賞」の受賞作は、樋口六華の『泡(あぶく)の子』。佳作には新崎瞳の『ダンスはへんなほうがいい』が選ばれた。
『泡の子』
新宿「TOHOシネマズ横」、通称“トー横”を舞台にした同作。退廃的で無秩序。私はこの現実で、彼女のために何ができる――? 2007年生まれの若き著者が送る、終わってる世界で生きている“私たち”の物語。選考委員の一人、作家の田中慎弥も「危険な小説だった。それでも、ここにある描写が好きだ」と賛辞を贈っていた。
『ダンスはへんなほうがいい』
休職中のCMプランナー・大山渾はある日、「アオ」と名乗る幼なじみと再会を果たす。あらゆる社会的属性やステレオタイプから自由なアオの振る舞いに、渾の心はだんだんとほぐされていくが……。広告代理店を舞台に、若者たちの繊細な繋がりをリアルに描いた野心作。
オール讀物新人賞
文藝春秋の小説誌『オール讀物』が主催する「オール讀物新人賞」は、歴史時代小説ジャンルに特化した公募新人賞。南條範夫、藤沢周平、佐々木譲ら歴代受賞者に続き、第104回となる同賞には和泉久史の『佐吉の秩序』が選ばれた。
『佐吉の秩序』
幼い頃から歴史小説が好きだったという著者。読後には関係資料を調べ、時に舞台となった場所へ実際に足を運び、そうした経験から紡ぎ出された同作は、ネット上でも「本格的な時代小説作家の誕生に目を見張った」などと好評。見よ、これが令和の戦国小説だ!
小説すばる新人賞
1987年11月に創刊された月刊小説誌『小説すばる』。その公募新人賞「小説すばる新人賞」では、これまで篠田節子、佐藤賢一、朝井リョウなど、多数の直木賞作家を輩出してきた。今回で第37回となる同賞では、須藤アンナの『グッナイ・ナタリー・クローバー』が受賞作に決定。
『グッナイ・ナタリー・クローバー』
軽犯罪に溢れかえった町で、父親の支配下に置かれている13歳のソフィア。ある日、1週間ごとに記憶を失ってしまう少女、ナタリー・クローバーと出会ったことから、彼女の“灰色”な人生が少しずつ変わり始める――。人生に絶望し夜を恐れる少女と、週ごとに生まれ変わる少女の物語。
ポプラ社小説新人賞
応募総数915作品が集まった第13回「ポプラ社小説新人賞」。今回の新人賞は該当作なしで、奨励賞に志部淳之介の『モギサイの夏』が選ばれた。
『モギサイの夏』
物語の舞台は、模擬裁判を競技化した「モギサイ」が人気の世界。主人公の蒼汰は、廃校寸前の学校を守るために大会優勝を目指していた。内気な性格ながらも転校生の真夏や同級生たちを巻き込み、仲間を増やして、ついに大会本番を迎える。臨場感ある試合展開と、明快なストーリーラインに注目。
女による女のためのR-18文学賞
応募は女性限定、あくまで大人が楽しめる作品が求められる「女による女のためのR-18文学賞」。窪美澄、町田そのこ、宮島未奈を輩出した同賞では、第23回大賞に広瀬りんごの『息子の自立』、タレントの友近が一人で選考する「友近賞」には、神敦子の『君の無様はとるにたらない』が選ばれた。
『息子の自立』
ぎっくり腰をわずらった曜子は、突如として難題に直面する。障碍をもつ息子の性処理をどうしたらよいのか――。挑戦的なテーマを扱った同作に対し、選考委員の窪美澄は「このテーマで描く、と決めた書き手の胆力、勇気にまず拍手を送りたい」と称賛。読む者の心に風穴を開ける、繊細かつ力強い大賞受賞作は見逃せない。
電撃大賞
2024年で第31回を迎えた「電撃大賞」。全国各地から寄せられた応募総数3819作品を、約半年間かけて選考した結果、電磁幽体の『妖精の物理学-PHysics PHenomenon PHantom-』が大賞に選ばれた。また、そのほかの受賞作品は以下の通り。いずれも2025年3月以降の書籍化を予定している。
※電磁幽体先生は12月12日に急逝されたことが12月27日発表されました。ご冥福を心よりお祈り申し上げます
《金賞》神宮寺文鷹『君の電波にノイズはいらない』
《メディアワークス文庫賞》姉崎あきか『タロットループの夏』
《メディアワークス文庫賞》アズマドウアンズ『古典確率では説明できない双子の相関やそれに関わる現象』
《電撃の新文芸賞》水品知弦『明けの空のカフカ』
《銀賞》助六稲荷『怪奇! 巨大な亀に街を見た! 聖女とチンピラとデカケツ獣人VS邪悪な黒ギャル軍団』
《川原礫賞》アズマドウアンズ『古典確率では説明できない双子の相関やそれに関わる現象』※メディアワークス文庫賞とのダブル受賞
『妖精の物理学-PHysics PHenomenon PHantom-』
同作は、KADOKAWAが運営するWeb小説サイト「カクヨム」発の現代ファンタジー。宝石の瞳を持つ人形サイズの女の子、通称「現象妖精(フェアリー)」の存在が常識となった世界を舞台に、少年と妖精の少女による“約束の物語”が紡ぎ出されていく。同サイトのコメント欄には「圧倒的な世界観」「常識を覆す、衝撃の問題作」などの反響が。
星雲賞
「星雲賞」は、優秀なSF作品および周辺ジャンルに贈られるアワード。第55回となる2024年は、日本長編部門に高野史緒の『グラーフ・ツェッペリン あの夏の飛行船』、日本短編部門には久永実木彦の『わたしたちの怪獣』、そして海外長編部門にジョン・スコルジーの『怪獣保護協会』、海外短編部門にはグレッグ・イーガンの『堅実性』が受賞作に選ばれた。
『グラーフ・ツェッペリン あの夏の飛行船』
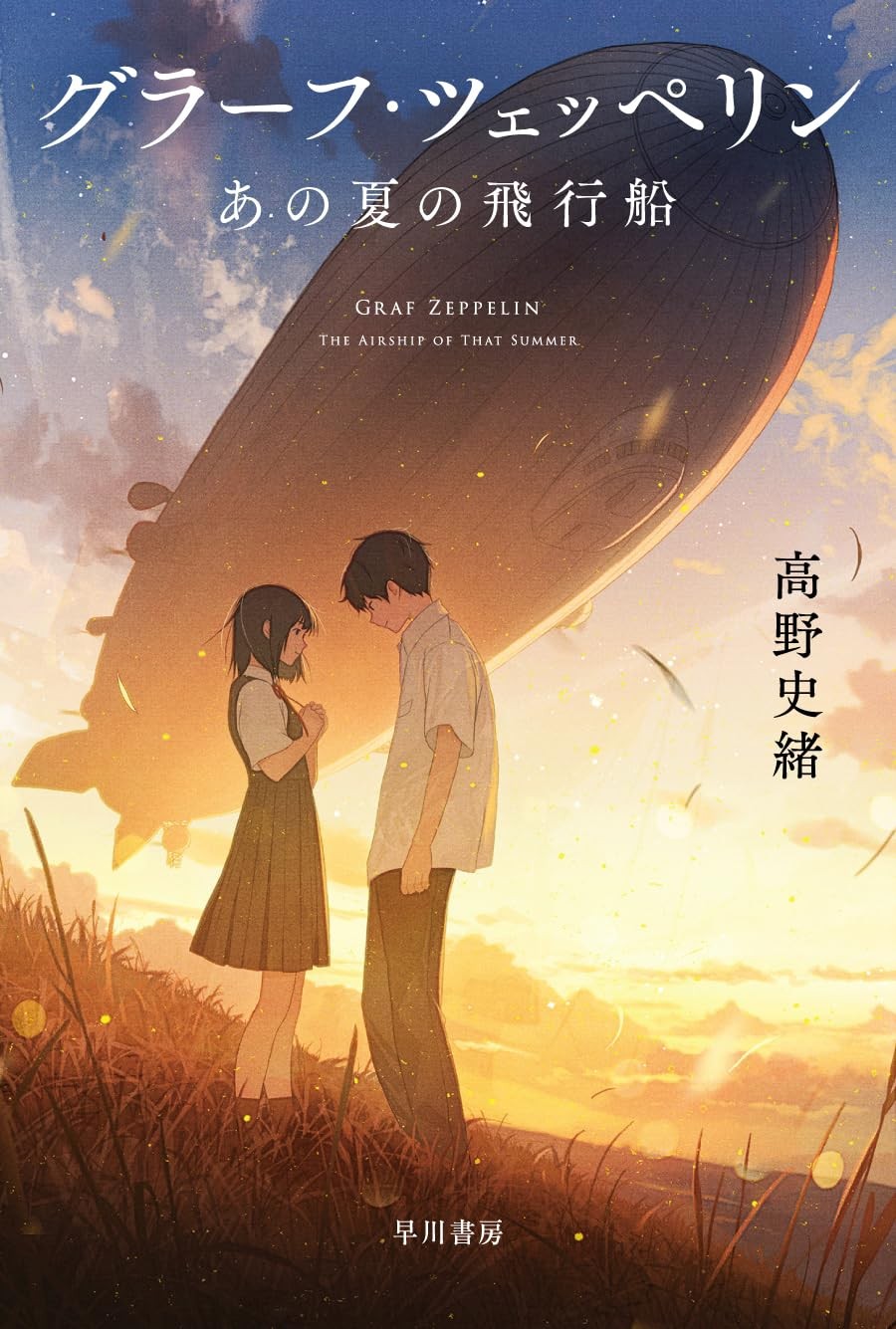
同作は、いわゆる並行世界(パラレルワールド)の2021年を舞台に描くSFボーイ・ミーツ・ガール。宇宙開発が進みながらもインターネット黎明期の世界を生きる“夏紀”と、宇宙開発は発展途上ながら量子コンピュータが実現した世界を生きる“登志夫”。巨大な飛行船「グラーフ・ツェッペリン号」が、別々の世界で生きる2人を繋いでいく。
日本SF大賞
第44回「日本SF大賞」の受賞作に選ばれたのは、長谷敏司の『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』。著者の長谷は、第6回「スニーカー大賞金賞」を受賞した『戦略拠点32098 楽園』で作家デビューを果たし、それ以降に刊行した作品もさまざまな文学賞を獲得している。
『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』
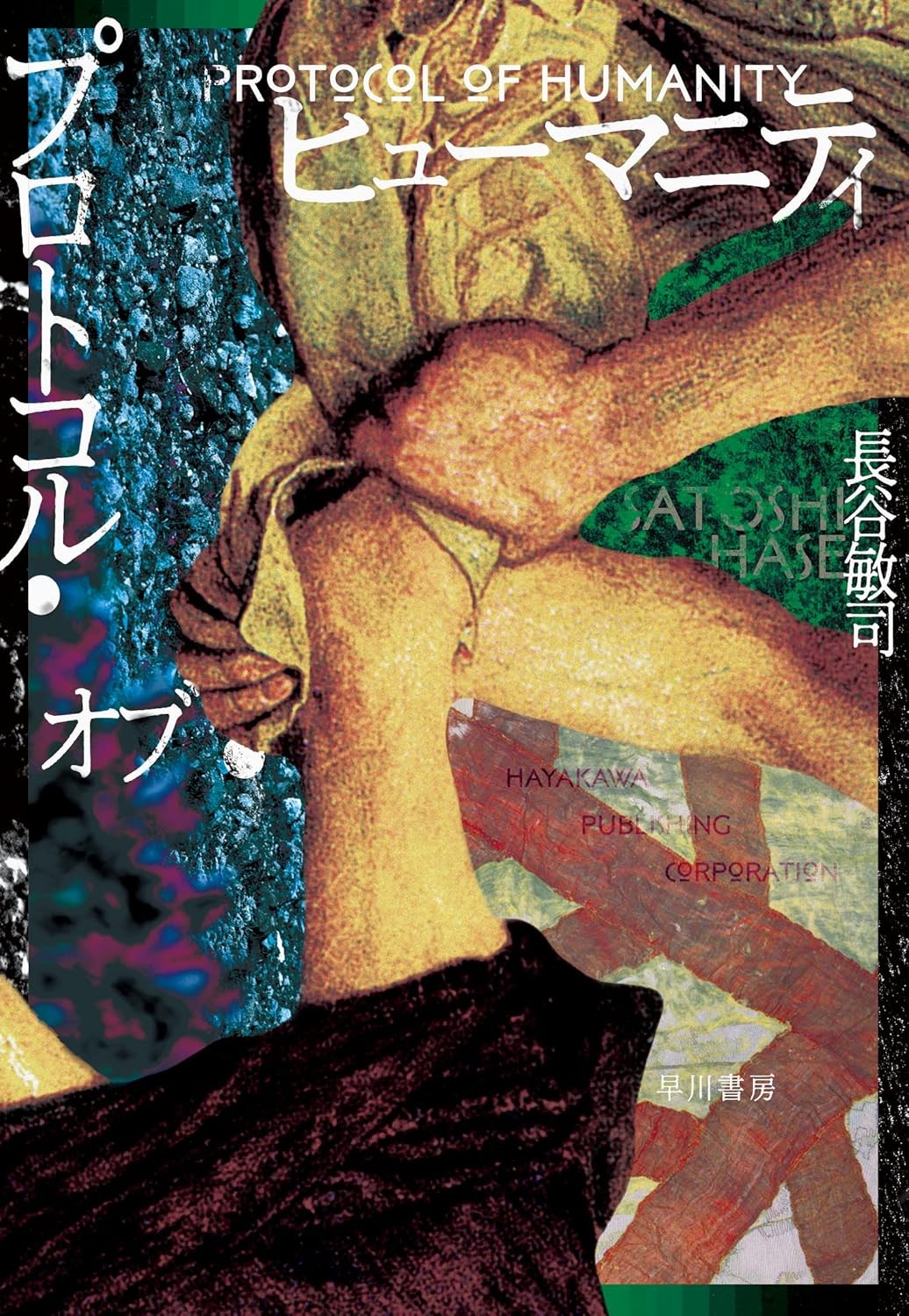
コンテンポラリーダンサーの護堂恒明は、不慮の事故により右足を失い、AI制御の義足を身につけることになる。絶望を味わいながら、それでも人のダンスとロボットのダンスを分ける人間性の手続き(プロトコル)を表現しようとする恒明だが、その先に待ち受けていたのは新たな地獄だった。SF史上最も卑近で、最も痛切なファーストコンタクトの物語。
ハヤカワSFコンテスト
「ハヤカワSFコンテスト」は、早川書房が主催するSF小説の公募新人賞。最も優れた作品に大賞を贈り、受賞作は同社より単行本および電子書籍で刊行される。第12回となる同コンテストの大賞に選ばれたのは、カスガの『コミケへの聖歌』と犬怪寅日子の『羊式型人間模擬機』の2作品。
『コミケへの聖歌』

21世紀半ばに文明は滅んだが、山奥の村で生き残った人々は農耕と封建制の下、命をつないでいる。そんな時代でも少女たちは、友情に、部活に、マンガにと、青春を謳歌する。彼女ら《イリス漫画同好会》の次なる目標は〈コミケ〉だった――。
『羊式型人間模擬機』
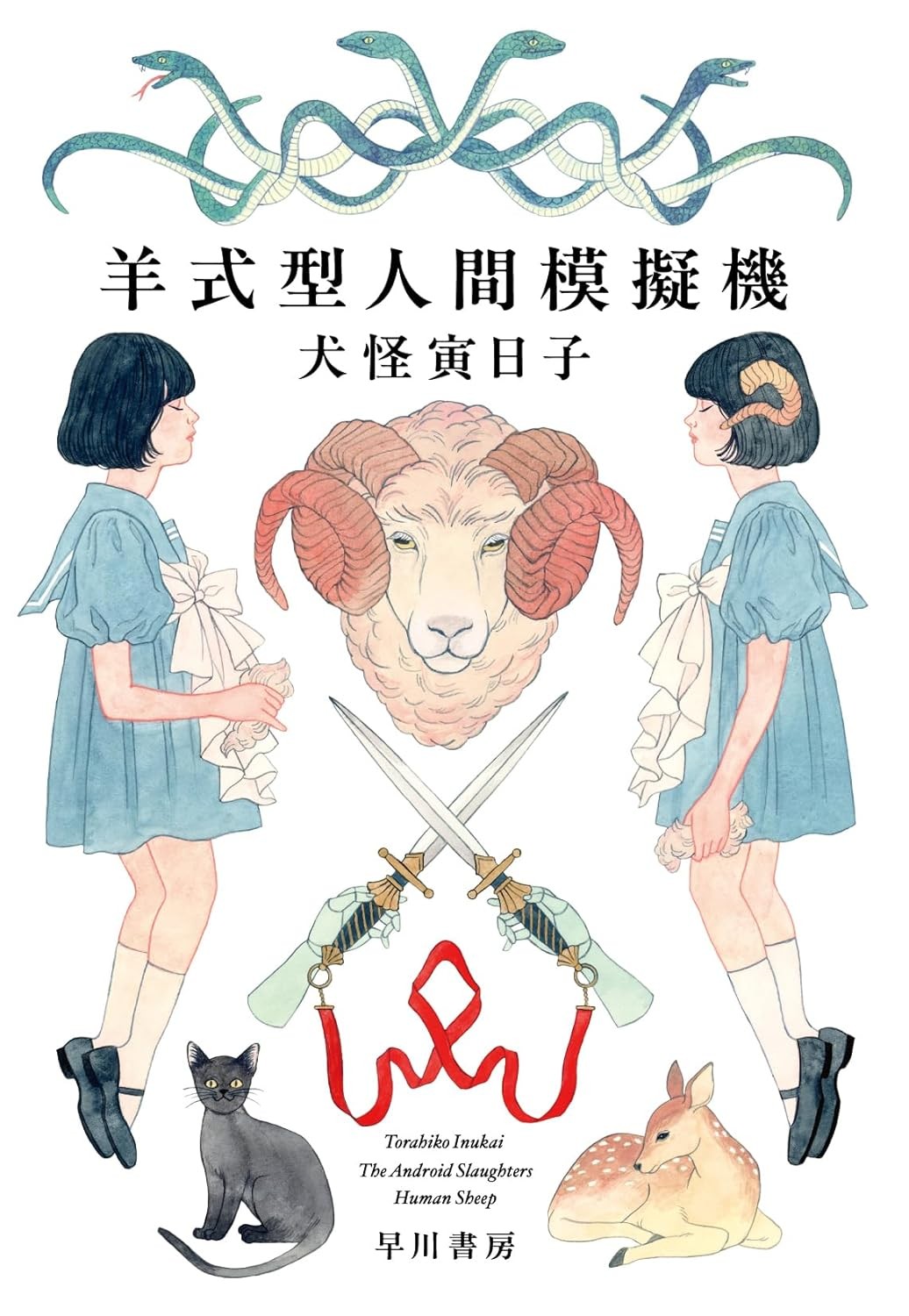
「わたくし」は男性が死の間際に「御羊」に変身する一族に仕えているアンドロイド。御羊の肉を捌き血族に食べさせることを生業としている「わたくし」は、大旦那が御羊になったある日、儀式の準備を進めるが、一族の者たちは「御羊」に対して複雑な思いを抱いていて――。
日経「星新一賞」
理系的発想力を問う文学賞、日経「星新一賞」。第11回となる同賞では、一般部門グランプリに柚木理佐の『冬の果実』、ジュニア部門グランプリに竹腰奈央の『ライトコート』が選ばれた。
『冬の果実』
物語の舞台は、氷河期を迎える未来の地球。「後天性体温調整機能不全症候群」におかされた主人公は、すでに手の施しようがなく、低体温症による死を待つばかり。彼の治療にあたる博士いわく、この病の流行は地球が再び全球凍結する前兆だという。ところがそんなある日――。
日本ファンタジーノベル大賞
恩田陸、森見登美彦、ヤマザキマリら豪華メンツが選考委員を務めた「日本ファンタジーノベル大賞」。応募総数354篇の中から、明里桜良の『宝蔵山誌』が受賞作に選ばれた。なお単行本刊行は、2025年初夏を予定。
『宝蔵山誌』
著者の明里桜良にとって、これが初めて書いた小説。誰に読ませることもなく、ひっそりと日本ファンタジーノベル大賞に応募したという。「ファンタジー作品の振り幅の広さ、現実の中に潜んでいる幻想性の豊かさを的確に感じた作品」などと人気作家たちを唸らせた同作は、公務員×地霊が織り成す新感覚ファンタジー。
文=ハララ書房
※本稿内はすべて敬称略、作品情報・刊行情報は2024年12月20日時点のものとなります




