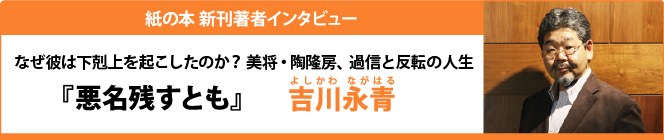なぜ彼は下剋上を起こしたのか? 美将・陶隆房、過信と反転の人生
公開日:2016/1/7
間違い、失敗にも無駄なことはひとつもない
「毛利に奇襲された大内軍の、戦にならないほどの乱れっぷりに全力を注ぎこんだ」という怒涛のクライマックスシーンは、読む者まで渦中に引きずり込む。
「合戦シーンを書く時、私はいつも兵のなかのひとりとして入り込むんです。言ってしまえば殺し合いですからね。こんなところ絶対にいたくない!という空間を出現させるために」
そしてその空間に、吉川さんは、隆房とある人物との一騎打ちを描き出した。猛々しいシーンなのに、胸に迫ってくるのはどうしようもない切なさ……。
「この場面は創作です。策に嵌り、負けただけの厳島の戦い──私はそれを、隆房にとって意味のあるものにしたかった。自分の間違いに気付くカギを手にするための」
本作を書き終え、しばし時が過ぎた頃、吉川さんは改めて、自分が思い描いた形を西国につくっていけなかったひとりの男に思いを馳せたという。
「きっとこれが隆房の限界だったんだなと。彼が様々な局面で選び取ってきたことも、おそらく間違っていた。けれど間違ってしまった選択は無駄にはなっていないのではないかと。なぜなら隆房の場合は、元就がその志を引き継いでくれたのだから。こうした形で、人は間違いつつ、失敗しつつ、それでもやったことはけっして無駄にならないのだと。それが受け継がれ、世の中は前に進んでいくんだろうなと。本作の起点となった“負けた側からの戦国史”を書く意味はここにあったんだと、その時、改めて気付きました」
そして吉川さんは言う。この物語から、今を生きるための何かを感じとってくれたら、と。
「考えるきっかけになったり、何かを変えたり。そういう方がひとりでもいてくださったら、この戦、私の勝ちかな?(笑)」
取材・文=河村道子 写真=川口宗道
『悪名残すとも』
吉川永青 角川書店 1900円(税別)
西国一の大家・大内家の若き侍大将として名を馳せていた陶隆房。幼少期に寵童となり、その後、重臣として取り立ててくれた主君・大内義隆のために東西奔走するも、大内家は内側から崩れていくばかり。家中の混乱、迫り来る隣国、毛利元就との親交、そして反転……“悪名残すとも”隆房が成し遂げたかったこととは──。