THE ALFEE・高見沢俊彦 めんどくさいものに憧れた学生時代。カミュ『異邦人』の不条理さが「心の空白」を埋めた【私の愛読書】
公開日:2023/4/22

さまざまな分野で活躍する著名人にお気に入りの本を紹介してもらうインタビュー連載「私の愛読書」。今回は、新刊『特撮家族』(文藝春秋)を出されたばかりの、ロックバンドTHE ALFEEリーダー・“タカミー”こと、高見沢俊彦さんに愛読書を3冊教えていただいた。
取材・文=荒井理恵
不条理感にやられた『異邦人』
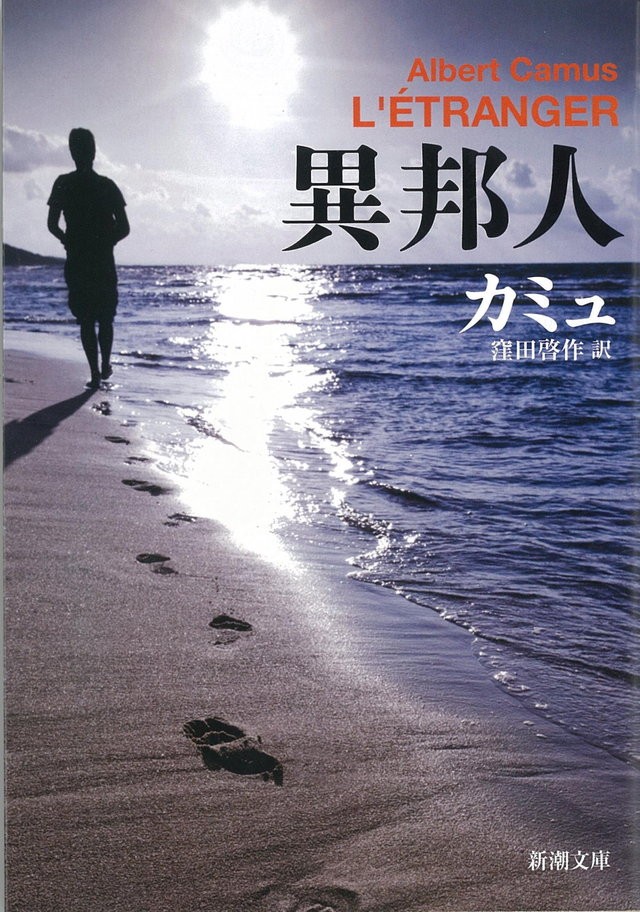
――1冊目はカミュの『異邦人』ですね。まずは選んだ理由から教えていただけますか?
高見沢俊彦さん(以下、高見沢):高校はミッションスクールに通っていて「聖書」の勉強なんかもしてたんですが、自分の中でいろんな疑問が出てくるんですよ。しかも10代って中途半端じゃないですか。大人でもなく、かといってまるっきり子どもでもない。その頃の僕にとって本や音楽は、そんな「心の空白」を埋めるものだったんですね。で、その頃に一時期はまったのが「実存主義」で。有名なところではニーチェの「神の死」とかありますけど、「神は死んだ」なんて言ったら本当は大変じゃないですか(笑)。でも「神を認めると実存ではない」ってなるわけです。それってどういうことかっていうと、「不条理の世界」になっていくわけですよね。筋道が立てられない絶対的な矛盾であるとか。それが『異邦人』を読んだときに、ピーンときたんですよね。それがすごく印象深くて。
――確かに「不条理」満載な本ですよね。
高見沢:殺人の動機が「太陽がまぶしかったから」とかね。そこで「俺やってねえよ」って言えば、死刑にならなかったのに、「罵声を浴びられることが最後の花向け」みたいなのも「こいつ何考えてんだ」とか。もちろんわからないんですけど、すごくどす黒いものが逆に爽やかに感じたんですよね。それってどこかロックにもつながるんです。そんな不条理の世界というものを、当時一番如実に表していたと感じたのが『異邦人』だったんです。サルトルの『嘔吐』も読みましたね。マロニエの根を見て、ウェ~って吐いちゃうやつ。『嘔吐』なんてタイトル、普通つけなくないですか?(笑) 『ペスト』もそうですけど、これは「なんかすげえなぁ」と思ってね。こういうのって、ほんとヘヴィメタルなんですよね。そんなところが10代の自分の心に刺さったんだと思います。
――「カッコイイ」って感じもあったんでしょうか?
高見沢:そうですね。当時は70年安保の後で、いわゆる無気力無関心無感動の「三無主義」の最初の世代なんですよ。なので、そういう空白の心みたいなものを埋めてくれるものを、やっぱり探してたんだと思います。そんな感じだったときにロックバンドが海外からやってきて、レッドツェッペリンを武道館で生で観たりなんかして、そういうものが自分の気持ちを埋めてくれた感じですね。
――何度も読み返されているんですか?
高見沢:そうですね。『異邦人』は短いですからね。自分の置かれている状況、不条理が持つもの、人生の絶望的な状況、なにこれ?みたいなやつ……自分はそこまでは陥っていないけど、ただやっぱり家や親や社会に対して、誰しも不満があるじゃないですか。そういったものが小説の中で具現化されるような気がするんですよね。ただ、ちょっとめんどくさいところはありますよね(笑)。だからめんどくさいものに憧れる年頃だったと思います。サガンだってそうじゃないですか。実はサガンもよく読んでたんですけど、「サガン読んでる」っていうとなんかバカにされそうで言わなかったな。内容ってほぼ三角関係じゃないですか。どんな恋愛しとんじゃ、みたいな(笑)。
――でも、そのめんどくささがカッコよく見えて……。
高見沢:そうなんですよ! めんどくさいものに憧れた時代ですよね。
ヘヴィメタと青春と不条理の『メタル’94』

――次は『メタル’94』ですね。
高見沢:ラトヴィアの作家の半自伝小説ですね。1994年に主人公は20代で、ニルヴァーナのカート・コバーンが死んで、優等生だった自分に我慢できなくなって、ちょっと悪いやつらと付き合う。そして、ヘヴィメタルにはまるんです。しかもデスメタルの「オェ~」ってやつで、すごく実存主義に近い不条理な感じなんですよね。ただ悪い仲間とも付き合うんだけど、なりきれないんですよ、主人公は。でもメタルにはどんどんはまっていって、それっぽい格好をしだしたり、バンドを作るかと思いきや、作らなかったり。で、卒業してメタルとは一切交流を持ってなかったんだけど、15年後にあるきっかけで、もう一度はまっていくわけです。その「メタルと自分」という感覚が面白かったですね。メタルってものすごく「特殊な音楽」のように見られる感じがあるじゃないですか。ある意味、支持するか支持しないかっていう「思想」だと僕は思っていますけど、音楽のジャンルなのに。そういうのがうまく青春群像小説として書いてあって、かなり面白かったです。
――最近の本ですよね。どういうきっかけで?
高見沢:やはりタイトルですね。なんだこれ?ってタイトルに惹かれました。
――ちょっとフィンランド映画のヘヴィメタと青春を描いた『ヘヴィ・トリップ』を思い出しました。
高見沢:あー、あの映画には笑った笑った。最後の最後で吐くかお前、みたいな。しかも噴水のようにね(笑)。
――彼らもすごく真面目なのが印象的でした。
高見沢:そう、真面目なんですよ! ただ髪が長いだけでちょっと揶揄されたりするけど。大体「どんな音楽が好きなの?」と聞かれて、「メタル」って答えると「え、なんで?」って感じになるんですよ。「ダンスミュージック」とか答えればおしゃれな感じになるけど、「ヘヴィメタル。デスですね」とか言うと「え?」って。僕はめんどくさいから説明しないけど。実は僕も最初、デスメタルは苦手だったんですよ。メロディがないし、ただ「オェ~」って唸ってるだけのようで……でも聞いていくうちにはまっていくんですよこれが。不思議ですけど。
――なにがしかの純粋さみたいなものがある?
高見沢:なんというか、『異邦人』の主人公のムルソーじゃないけど、何かやると「罪になる」と言われちゃうのと同じ不条理を感じますよね。メタルが好きだというと、絶対に「なんで?」って言われるわけですから。そういうのも含めて、『メタル’94』はヘヴィメタルを青春の中のひとつのシンボルとしてうまく描いていると思います。メタルのバンドのことを知らないと少しきついかもしれないですけど、ボン・ジョヴィとかクイーンとか有名どころも出てきますので。94年というとメタルが死んでいる時代で、最近そこからだんだん盛り上がってきましたが、やっぱりまだ特殊な音楽ではありますよね……(笑)。
――そこを高見沢さんが変えていかれると!
高見沢:じゃあ、次はメタルがメインの小説でも(笑)。
「大学生ってすげぇ」と思わされた『されどわれらが日々』
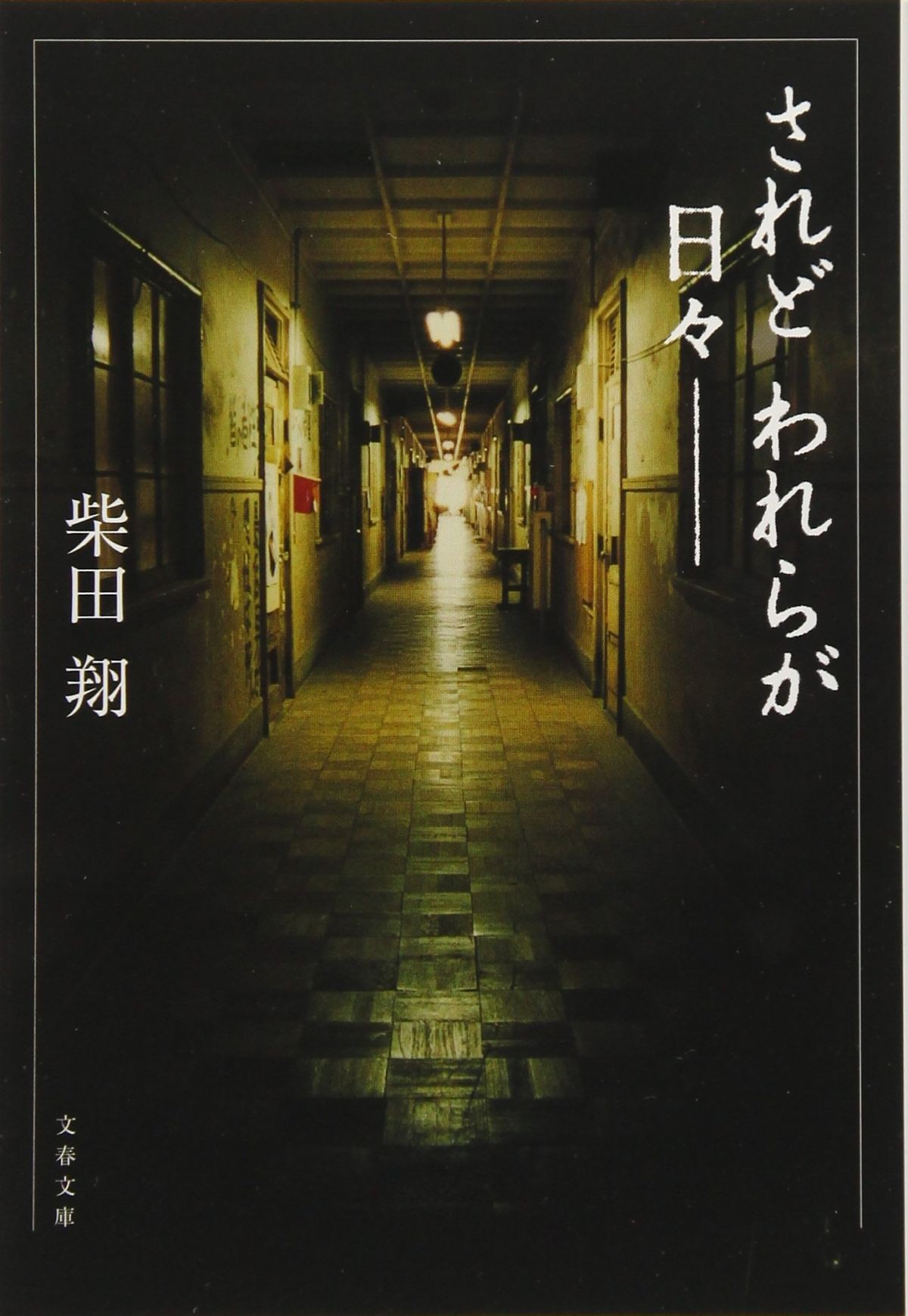
(柴田翔/文藝春秋)
――では、最後に『されどわれらが日々』について教えてください。
高見沢:60年代安保の頃の小説で、芥川賞もとった作品です。ひとつの恋愛物語でもあるんですけど、どこかこれにも不条理があるんです。最初に読んだのは中学生の頃で、これは何度も読み返しています。主人公が「どんな世代にも困難はある。でも立ち向かっていかなければならないときがある」みたいに言うラストにじわっときたことがあって。その当時の僕よりかなり年上の方の話なので、「大学生ってすげえなぁ」って思いましたね。こんなこと考えてんのかって。ただ、いざ自分がその年齢になったら全然考えてなかったですね(笑)。
――生き方に対する生真面目さというか、ちゃんと考える姿勢がある。そういうところに、昔の人ってすごいなって思いました。
高見沢:戦後、いろいろ自由になってきて、民主主義や共産主義、いろんなイズムが出てきたときに、やっぱり学生たちが今後をどのように舵を取っていけばああいう悲劇は起こらないかというのを真剣に考えてたんじゃないですか? 70年代安保もそうだし。この物語は六全協(1955年7月に開かれた日本共産党第6回全国協議会の略称。共産党が極左軍事冒険主義から先進国型平和革命路線に路線変更した)の頃を描いてて、党員の友達がいろんな話をすると「お前それ見たことあるのか。本当にそれを知ってるのか。マルクス全部知ってるのか」みたいな会話が出てくる。当時はちんぷんかんぷんでしたけど、何かこう鬼気迫るものを感じましたね。そこが興味深かった。この小説こそ何度も読み返しましたね。
――読み返すたびに、感じることが違うとかありましたか?
高見沢:自分も年を重ねてきて、最初に読んだイメージとは変わってきますしたね。だけどやっぱり「どんな世代にも困難はあるんだ」っていうのは強烈に覚えています。どんな時代でも、締め切り間際でも(笑)。そういうものの繰り返しが人生なのかな、という。人の人生ってすごく短いけれど、ものすごいことがたくさん起きるじゃないですか。小説というのは、それを凝縮してるものだなと思いますね。自分の人生だけならひとつだけで面白くないですけど、本ならいろんな人生を読むことができる。読み解くってそういうことですからね。だからみなさん、本を読みましょう!
本には作家の魂が宿る!
――ちなみに高見沢さんにとって「本」とはどんな存在ですか?
高見沢:なんだろう。常に傍にあったものなんですよね。アマチュアバンドだったときも、ギターケースの弦を入れるところにちょうど単行本が入ったので、「お前っていつも本入れてるな」って言われてましたね。そこが膨らんでると「またなんか入ってる」って。空気みたいなものですかね。当時毎日のように読んでましたけど、今は時間がなくてなかなか読めてませんが。
――でも映画も漫画も本もちゃんと楽しむ時間を作ってらっしゃるんですよね。
高見沢:映画なんて1時間半から2時間だけじゃないですか、24時間の中の。本も1時間くらい読めば十分。ただ乱読なんで、いくつも読み散らかした本が3冊くらいあって、こっち読んだら違う本へ、みたいな感じです。本屋も行きますよ。今は少なくなっちゃいましたけどね。本屋で本が並んでいるのが好きですね。図書室も好きでしたし、本の匂いとか、本がたくさんある場所というのはいいですよね。
――そんな本好きな高見沢さんですが、本を読まれるようになったのは、お父様とお兄様の影響があるそうですね。
高見沢:父が教育者だったので、本棚がありましたから。父は日本文学で兄が外国文学を読んでましたね。最初は背表紙のタイトルに興味を持ったんですが、読めない漢字が多くて。父親に「この一冊には、作家の魂がはいっているから、今読めなくてもいいけど、いつかお前もわかるようになるよ」と教えてもらったことがあります。当時はちんぷんかんぷんでしたけど、一冊一冊の中にある作家の物語というのを自分の中で読み解くというのは決して無駄ではないと思います。人生は1回だけど、本は一生かかっても読み切れないほどありますからね。そういうのを感じるのは必要なのではないかな、と。
――では新刊の『特撮家族』にも高見沢さんの魂が……。
高見沢:いや、魂はそこまで入ってないかもしれませんが(笑)。ぜひ読んでいただければうれしいです!
――でも「特撮魂」は、入ってますよね!
高見沢:はい。あと「戦国魂」ですね!(笑)
<第16回に続く>
























