今年は辻村深月デビュー20周年イヤー!2024年の年の瀬にどっぷりつかりたい“辻村作品”8選
公開日:2024/12/30
2004年に『冷たい校舎の時は止まる』(講談社)で第31回「メフィスト賞」を獲得し、鮮烈なデビューを果たした作家の辻村深月氏。2024年は彼女のデビュー20周年イヤー。本稿では、辻村氏の著作の一部を振り返りつつ、改めて彼女が紡ぐ物語の魅力に迫っていく。
スロウハイツの神様
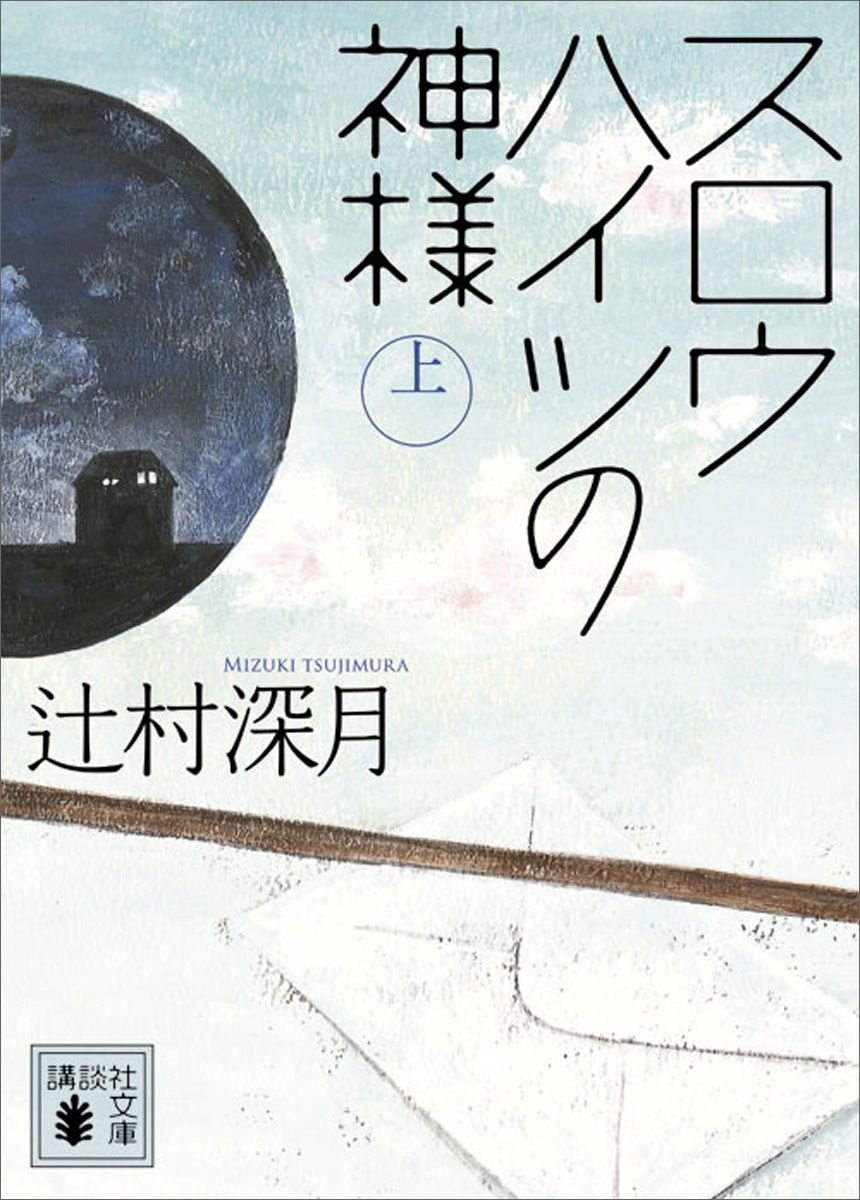
読者の感情に寄り添う巧みな心理描写に定評のある辻村氏。そんな彼女が2007年に発表した『スロウハイツの神様(上・下)』(講談社文庫)は、夢に向かうクリエイターたちを描いた物語だ。同作の舞台となるのは、クリエイターやその卵たちが集う家「スロウハイツ」。家主である主人公の赤羽環は映画監督や漫画家を志す友人たちと共同生活を送りつつ、人気脚本家として活動していた。
まるでトキワ荘のような魅力的な空間で好きなことに没頭し、時には刺激し合う住人たち。デビューしているクリエイターとその卵たち、それぞれで異なる不安や葛藤が描き出されていく。人間ドラマとしてはもちろんミステリー作品としても楽しめるので、“辻村ワールド”の入門編としてオススメしたい作品だ。
東京會舘とわたし
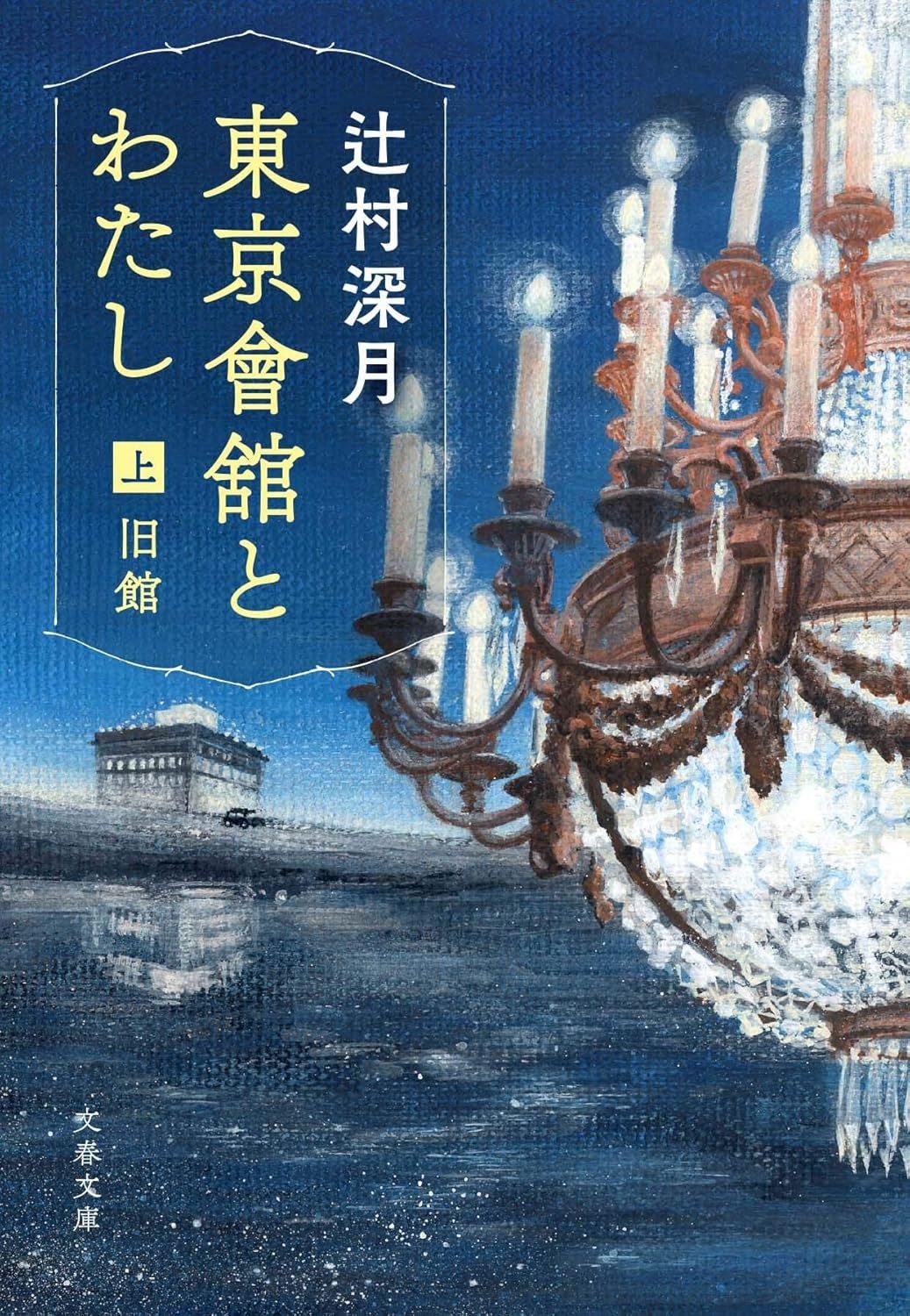
大正11年に“民間初の社交場”として建てられた東京會舘。宴会や結婚式といった催しに使用される伝統的な建物で、芥川賞や直木賞などの授賞式にも使用される作家にとっても縁深い施設である。『東京會舘とわたし(上・下)』(文春文庫)は、そんな東京會舘をテーマにした連作短編集だ。
物語は史実をなぞりながら進行し、上巻では関東大震災や太平洋戦争の影響を受けた歴史を中心としたストーリーが、そして下巻からは現代に迫りつつ各章の登場人物たちが重なり合い、驚きと喜びに満ちたミステリーが展開されていく。実在する施設ということもあり、読了後はきっと東京會舘を聖地巡礼したくなるに違いない。
かがみの孤城
『かがみの孤城(上・下)』(ポプラ文庫)は2018年の「本屋大賞」を受賞し、累計発行部数200万部を超える辻村氏のベストセラー作品。同作の主人公である女子中学生の安西こころは、ある日突如として部屋の鏡に吸い込まれ、城のような不思議な建物へと招かれる。タイムリミットまでの約1年、城に隠されている“ある部屋”の鍵を見つけ出すことができれば、どんな願いもひとつだけ叶えてくれるというのだ。
こころ以外にも6人の中学生が招かれており、各々が生々しく苦しい事情を抱えている。それらを隠しつつも鍵探しを通して心を寄り添わせ、明日へと向かう勇気を手にしていく――。君は一人じゃない、どこかに味方がいる……そんなメッセージが込められた作品だ。
噛みあわない会話と、ある過去について
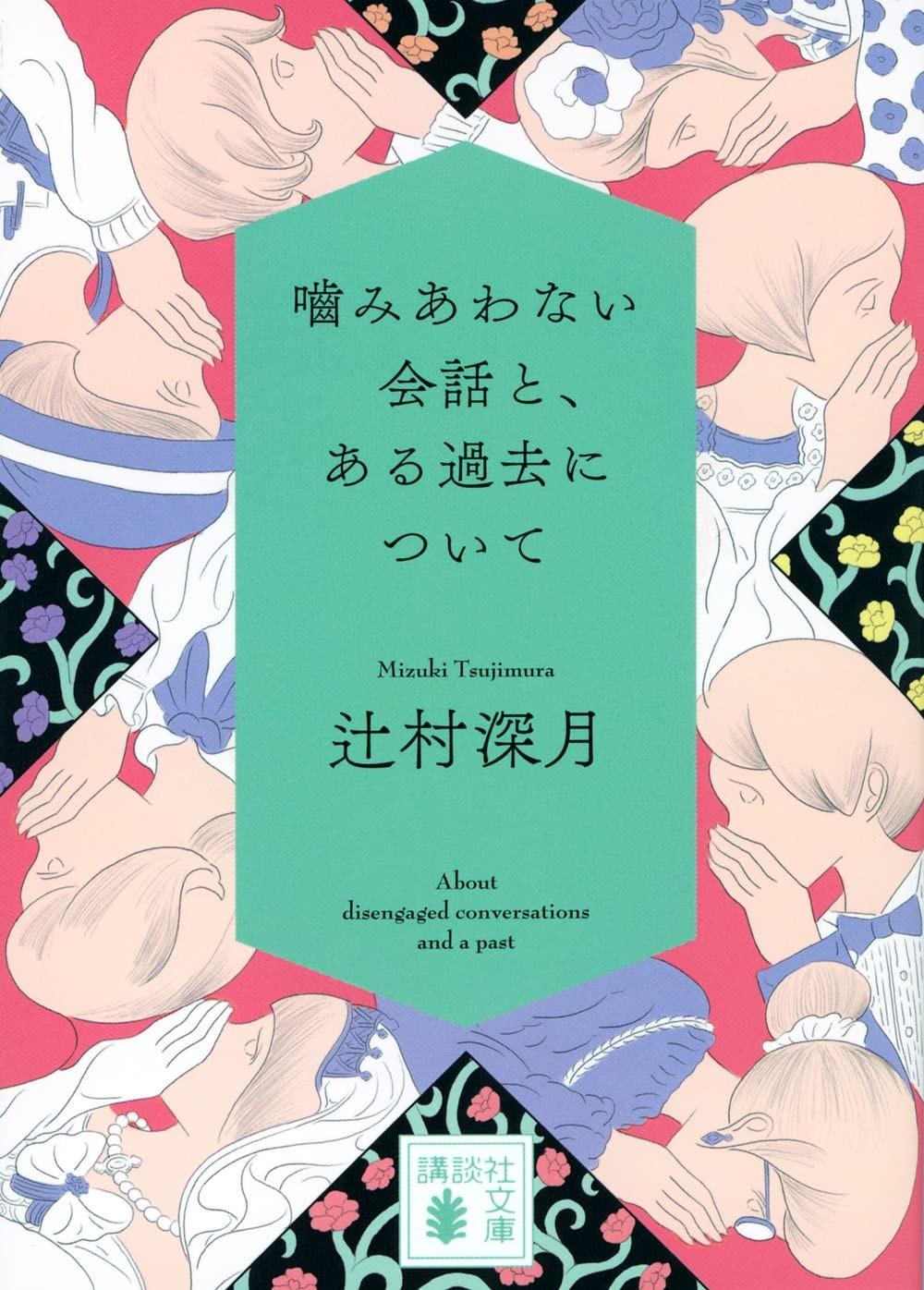
同じ言語を話しているのに、言葉が通じていない感覚。立場や価値観が違うだけで、こんなにも噛み合わないのか……と感じたことはないだろうか。『噛みあわない会話と、ある過去について』(講談社文庫)は、どうしようもなく分かり合えない人間たちの姿を映し出した短編集。
収録作のひとつである「ママ・はは」は、楽しむことを悪だと考える“真面目教”の母親と、その支配からなんとしても逃れようとする娘の関係がテーマとなっている。どんな家庭でも起こり得るちょっとしたすれ違いから世界が歪みだす、まるでSFのような展開は、辻村氏ならではの表現法といえるのではないだろうか。
なぜ言語でコミュニケーションを取れる人間が、時に動物よりも分かり合えないのか。その真理が同作には隠されているのかもしれない。
傲慢と善良
累計発行部数110万部を突破し、2024年9月に実写映画化も果たした『傲慢と善良』(朝日文庫)。同作はマッチングアプリで知り合って婚約することになった男女の、女性の方が突如として消息を絶つという摩訶不思議な出来事を巡る物語だ。
男性は婚約者を必死に探すのだが、その過程で相手の過去や嘘に直面していく。“傲慢と善良”、この言葉とマッチングアプリが重なり合った時、一体何があぶり出されるのか……。ちなみに同作は多くの読者から「人生で一番刺さった小説」という評価が相次いでいる。その理由が気になる人は、ぜひ一読してみてほしい。
琥珀の夏
大人になる途中で私たちが取りこぼし、忘れてしまったものは、どうなるんだろう――。2021年に単行本が刊行された『琥珀の夏』(文春文庫)は、かつてカルトと批判された「ミライの学校」の敷地から発見された白骨死体を巡る物語。
主人公である弁護士の法子は、30年前に「ミライの学校」夏合宿に参加していた。そこで出会ったミカという友達が物語のキーパーソンとなっており、法子の過去と学校の謎が交差することで“罪”が浮かび上がっていく。同作の最終章では、読み進めていくうちに涙がこみ上げる圧巻の展開が待ち受けている。“辻村ワールド”の新たな一面も垣間見られるので、最近の作品を追っていないという人にぜひオススメしたい。
嘘つきジェンガ
辻村作品では、時事的なテーマが扱われることもしばしば。2022年の『嘘つきジェンガ』(文藝春秋)は、いまだに社会問題として取り上げられる「詐欺」を題材にした3つの物語が展開されていく。第1話「2020年のロマンス詐欺」では、2020年の緊急事態宣言下で生活に困った大学生の加賀耀太が「メールでできる簡単なバイト」としてロマンス詐欺の片棒を担がされてしまう。
第2話「五年目の受験詐欺」は、いわゆる裏口入学がテーマ。そして第3話「あの人のサロン詐欺」では、覆面作家になりきってオンラインサロンを運営していた“子ども部屋おばさん”紡の物語が描かれる。騙す側・騙される側、双方の心理を巧みに描いた同作は、辻村作品の真骨頂を体感できる作品といえるかもしれない。
この夏の星を見る
人類を未曾有の危機に陥れた新型コロナウイルス。2023年に発表された『この夏の星を見る』(KADOKAWA)は、コロナ禍によって活動の制限を余儀なくされた茨城県立砂浦第三高校の天文部を巡る物語だ。
コロナ禍は多くの人を苦しめたが、限られた学校生活を謳歌する機会を奪われた学生たちも、被害を受けたといえるだろう。本来楽しめたはずの学校行事がことごとく中止に追い込まれ、クラスメートと顔を合わせる機会も減ってしまった。しかし、コロナ禍だからこそ訪れた出会いもあったのではないだろうか? すべてを狂わされた若者たちが手を取り合い、ひとつの目標へと突き進んでいく。あの時代を経験した人にこそ、ぜひ手に取ってみてほしい作品だ。
人間の感情に対する解像度が高く、どんな人でも楽しめるのが辻村作品の最大の魅力。20周年以降の執筆活動を応援する意味でも、歴代の著作を一読してみてはいかがだろうか?
文=ハララ書房









