ディカプリオ主演で映画化が噂されるクライム・サスペンス。小説家に扮した殺し屋が街に潜入する、奇妙な暗殺計画とは
PR公開日:2024/4/8
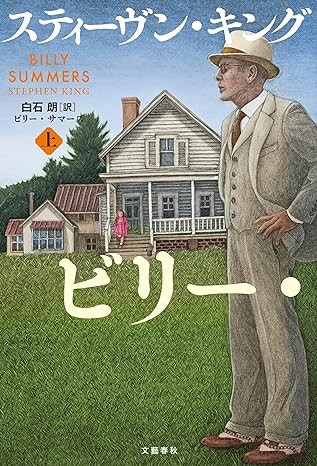
2024年、デビュー50周年を迎える“モダン・ホラーの帝王”ことスティーヴン・キング。『IT』『シャイニング』『ミザリー』など映像化された作品も多く、映画でその世界に触れた人も少なくないだろう。ホラー以外にも、超能力ものの『キャリー』、青春小説『スタンド・バイ・ミー』など、ジャンルの枠にとらわれない作品を数多く生み出している。
このたび邦訳版が刊行される『ビリー・サマーズ』(スティーヴン・キング:著、白石朗:訳/文藝春秋)は、ホラーではなくクライム・サスペンスに分類される一作だ。上下巻合わせて600ページ超、しかも上下2段組という大ボリュームだが、中盤以降はページをめくる手が止まらず一気読み必至。その序盤の展開を紹介しよう。
ビリー・サマーズは、44歳の殺し屋。悪人しか殺さないことを信条に裏稼業を続けてきたが、そろそろ引退を考えていた。そんな彼が、200万ドルという破格の報酬で最後の仕事を請け負うことに。標的はジョエル・アレン。ロサンジェルスの刑務所に拘置されている殺し屋だ。
どうやらジョエルは強力な情報を握っており、その切り札を差し出す代わりに減刑を狙っているらしい。一方で、その秘密を明かされた人物は身の破滅を免れ得ない。そこで、口封じのためにジョエルの暗殺をもくろんだようだ。狙撃のチャンスは、裁判所に移送されるタイミングのみ。しかも、いつ移送されてくるかもわからない。そこでビリーは、素性を隠して裁判所のある小さな町に潜伏することになる。
ここから、なんとも奇妙な事態に陥っていく。平日の昼間からフラフラしても怪しまれない職業と言えば、小説家(そうなのか?)。というわけで、ビリーは小説家デイヴィッド・ロックリッジを名乗り、借家と狙撃場所であるオフィスビルを往復する生活を始めるのだった。
しかもビリーは、作家のふりをするだけでなく本当に小説を書き始めてしまう。裏社会の人間に対しては“お馬鹿なおいら”を装っているビリーだが、実は文学好き。そんな彼が、裏社会の人間にパソコンを監視されている可能性も考慮し、“お馬鹿なおいら”文体で自叙伝を書き始める。この作中作が、単体の小説としても面白く、なおかつビリーの人物像に深い陰影を与えている。幼少期の悲痛な出来事、淡い恋、海兵隊での訓練、中東での戦闘など、ビリーの半生が明かされるだけでなく、執筆を進めるにつれて〈小説を書くとは戦争のようなものではないか〉など創作論も語られる。さらに終盤に向かうにつれて、この作中作がビリーの運命にますます深く食い込んでいく。詳しくは語れないが、現実を書き換えるほどの物語の力、その可能性を固く信じる祈りのように敬虔な思いに、強く心を打たれた。
ビリーの筆が乗ってくる反面、ジョエルの暗殺計画はなかなか進まない。その結果、ビリーの仮の姿であるデイヴィッドは、街に溶け込み、近隣の人々と仲良くなってしまうのも興味深い。オフィスビルで働く人たちとランチを共にし、ご近所一家とはバーベキューをしたり、子どもたちとモノポリーをしたり。正直「アメリカのご近所づきあい、距離が近すぎてしんどいな……」と思ってしまったが、気のいい人ばかりだし、子どもたちがなついてくれば無条件にかわいい。親しくなりすぎるとあとが大変なのはわかっていつつ、どんどん距離を縮めてしまう。かと思えば、今回の暗殺計画には不慣れな人物が混ざっていて、どうにもこうにも危なっかしい。サッと殺して煙のように立ち去るいつもの仕事とは、何もかもが違うことがビリーの心をざわつかせる。奇妙な暗殺依頼はうまくいくのか、そして自叙伝は書き上がるのか、読者はハラハラしながら見守ることになる。
と、ここまできてもまだ全体の1/4程度。中盤に差し掛かると事態は急展開を迎え、「え、それはヤバいって……」と危険な方向へスピンしていく。ドキドキそわそわと感情を乱高下させられた末に待ち受けるのは、胸苦しいほど切なく、どこまでも美しい幕切れ。「こういう景色を見たくて、本を読んでいるんだ」という読書の原初的な喜びに、どっぷり浸ることができる。
この作品は、すでにアメリカのワーナー・ブラザースが映画化権を獲得しており、レオナルド・ディカプリオが主演するとの噂も。こちらも楽しみだが、この物語は本というメディアで読んでこそ、そのメッセージが沁みるように思う。このうえない読書体験を、ぜひ堪能してほしい。
文=野本由起























