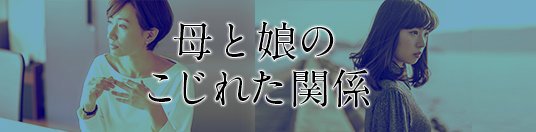「母の愛は異常だった」母との確執、放蕩の記録。人気作家の生々しい人生告白
更新日:2018/5/11

先日、横浜駅の高島屋へと出向いた。愛用の鞄が古くなったためだ。いつものようにふらふらとその重厚な入口を潜ると、そこにはカーネーションの花束やドライフラワーが所狭しと並べられている。そうか、母の日か。
母の日。母親に対して感謝や愛情を伝えるためのイベント。「母親には感謝している。だが同時に心のどこかで、複雑な感情を抱いてしまう」。そんな人も、案外少なくはないだろう。親子の関係とは、お涙頂戴の感動秘話でその全てを網羅できるほど単純なものではなかったりもするからだ。
心温まる母娘の話も良いが、禍々しい毒花のような母娘の話にもスポットライトを当ててみたい。さまざまな形態の家族が存在するこの世の中、思いの外その需要は大きいのだと思う。
そこで私はここに1冊の小説をご紹介したい。『放蕩記』(村山由佳/集英社)である。ご存じの方も多いかもしれない。娘の立場から、私小説的に母娘の確執を描き出した小説家村山由佳の名作だ。
本書の主人公は夏帆という名前の女流作家。厳しい母親の下で育った彼女は、母親に対して常に複雑な感情を抱いている。高潔な子育てを良しとする思想の持ち主の母だが、その愛は、とりわけ長女の夏帆に対しては「異常」な部分がかなりあった。幼少期の夏帆は「えらい! さすがはお母ちゃんの子や」と褒められる度に天に昇るような喜びを感じ、そうかと思えば「あんたなんてお母ちゃんの子やない!」という狂気じみた罵声で奈落の底に落ちるような恐怖も味わい、常に母親の機嫌をうかがいながら成長する。これは心理学のいうところでの「ダブルバインド」という心理状態を色濃く反映しているように私は感じた。
そんな回想を巡る物語の途中から、母親に異変が訪れる。「アルツハイマー」だ。少しずつ症状が進行し、小さくなっていく母。そんな母を、蓄積された過去からくる複雑な感情のせいで素直に愛することができず、また真っ向から攻撃することもできず、葛藤する夏帆の内面描写が凄まじい。
そして本書の終盤にかけて、母親との確執がいよいよ深刻化した10代後半から20代前半にかけて夏帆が抱えた秘密の告白がなされる。それはタイトルの通り、「放蕩」の記録だ。さまざまな「牡」と肌を重ねるごとに境地に近づいていく「おんな」としての快楽、悦び。それはまさに放蕩の生活に墜ちていく人間が味わう快楽の核心のように思えた。
その動機を、性に関して厳しい母親への復讐心や、母親によって構築された自身のモラルの破壊だと信じていた夏帆。しかし母親が認知症になってしまった後に、自分の中で疑いもしなかった母親の人間像が、一部間違っていたことに気付いていく。そこで足元を見失う夏帆の様子を読んだ私は、まさに文字通り感動した。読者として小説と肌を重ねながら、自分の感情が予測不可能なベクトルで飛び交い始める。そんな終盤はまさに圧巻だ。
「親には問答無用で感謝し、愛するのが普通」という無言の圧力を、多くの人は、もしかしたら無意識の内に感じているのかもしれない。しかし現実はもっと複雑だ。実の親を一筋縄では愛せない人もこの世界には多数存在する。そんな葛藤を、隅々まで素直に曝け出した本書。作者が執筆中に直面した「産みの苦しみ」は並々ならぬ、我々の想像を絶するものだったのではなかろうか。そして、同じ境遇にあるどれだけの人々に寄り添う本となっていることだろうか。本書の小説としての価値は相当なものであるように思える。
文=K(稲)
特集カテゴリーの最新記事
今月のダ・ヴィンチ

ダ・ヴィンチ 2025年8月号 『鬼滅の刃』受け継がれる想い/サンリオ×推し活
特集1 劇場版「無限城編」7月18日公開! 『鬼滅の刃』受け継がれる想い/特集2 楽しく、可愛く、応援! サンリオ×推し活 他...
2025年7月4日発売 価格 880円