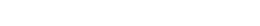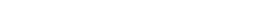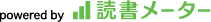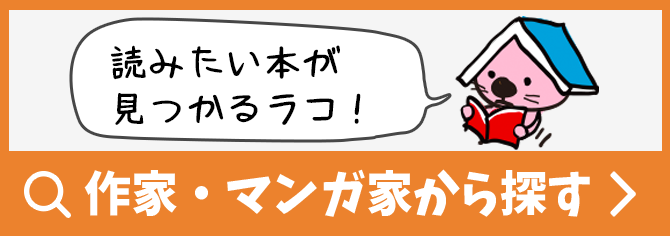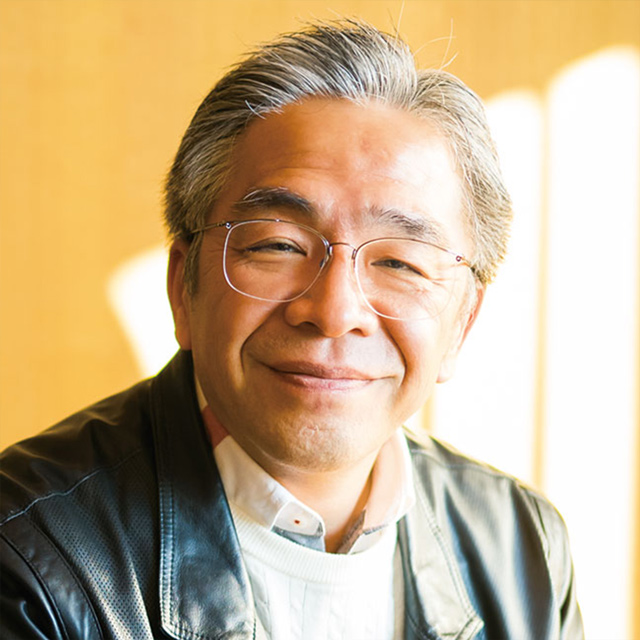先生はえらい (ちくまプリマー新書)
ジャンル
先生はえらい (ちくまプリマー新書) / 感想・レビュー
ゲンキ
本書が東大生のおすすめ本に紹介されていたので読んでみました。いゃ~流石東大生が読む本って感じです。骨太の本です。読み応えがありました。現代文のテストに出てきそうな文章で、昔なら理解出来なかったかもしれません。作者が言いたかったことは、「先生と生徒のコミュニケーションは、勘違い、誤解、誤読、一人合点の余地を残して、構造化されている。それで、生徒がその解釈に魅入り、精通することで、気づき(会得)が生まれ、学びが成立する」だと思います。私自身も納得出来ました。大変面白かったです。
2022/02/12
き
初めて内田樹氏の本を読んだのだが、「誤解の幅」「訂正の余地」のある興味深い文章だった。(作者自身がそう仕向けている。)様々な話題について述べ、最後は「先生はえらい」という言葉につながっていく。「あなたはそうすることによって、私に何を伝えたいのか」と問いを発し、学び続けることが重要だと思った。
2022/01/04
Nobu A
内田樹先生著書8冊目。期待していたのと異なると言うのもあるが、「それにしても」と言うのが正直な読後感。アクティブ・ラーニング全盛の現代、先生の仕事は教授ではなく、学習を支援する存在と言われて久しい。しかしながら、それを言ったら教師は誰にでも務まるのか。回答を期待して頁を捲ると相変わらずの内田節炸裂。本人も認める脱線ばかり。しかも何度も。そもそも「こころ」や「三四郎」は文学作品。面接官の職務は金太郎飴のような返答を評価し序列を付けること。それに創造性を求める方が無理があり、質問そのものを変える必要がある。
2022/06/19
めっし
すごい本だった。僕にも師匠がいるが、たしかに客観的に「尊敬すべき」人でなくて「僕がとにかく尊敬している」。「僕には到底到達できない何か境地にある先人」と僕が思い込んで魅了されている。「先生」を持つことは人生を豊かにする。自分がこの人こそ「先生」だ、と思うことが出発点。「自分以外は皆先生」という言葉に実感がある人は賢者だ。近年、教員は説明責任を求められ、教員は明確な回答を用意するが、「先生と弟子」という教育の本質は失われていく…等々、内田先生の文章から誤解に基づく思考が次々と広がっていく。勉強になりました。
2013/07/19
おさむ
内田センセイの師弟論。中高生向けとうたいつつ、完全な大人向け笑。話はあちこちにひろがっていきますが、結論は「そうすることで、あなたは何を伝えたいのか」。こう考えることが学びの主体性。いやいや、「コミュニケーションは、誤解の余地を残して構造化されている」のだから、この結論は、私が勝手に解釈して学んだだけ。他の人がどう解釈してもそれはそれ、ということですね。夏目漱石の作品と能楽の「張良」の中に「センセイから学ぶこと」の本質があるんですね。
2017/08/05
感想・レビューをもっと見る