日本人で2人目となる「国際アンデルセン賞」受賞の快挙! 上橋菜穂子の「守り人」シリーズ誕生の裏側とは?
公開日:2014/7/2
呼吸をするたびに、自分の中の経験が、ストーリーとして紡がれる。心の中に住む登場人物たちとともに自らの過去を振り返りながら、一緒に今の生活を楽しんでいく。作家はそうやって、どのような経験も作品づくりに活かしていくのだろう。「国際アンデルセン賞」を受賞した、児童文学作家で文化人類学者の上橋菜穂子氏の自伝的エッセイ『物語ること、生きること』を読むと、そう思える。
上橋氏が「児童文学のノーベル賞」と言われるアンデルセン賞を日本人で受賞したのは、まど・みちおさん以来、2人目。そんな快挙を成し遂げた彼女は一体なぜ物語を書くに至ったのか。自らの人生の経験を巧みに表現した時、作家の作品は強い輝きを放つに違いない。彼女の『精霊の守人』をはじめとする「守り人」シリーズをかぶりつくように読んで大人になった私のような人間は、このエッセイもあっという間に読み終えてしまった。
上橋氏の描く「守り人」シリーズは「ハイ・ファンタジー(異世界ファンタジー)」と呼ばれているが、その源となっているのは、現実世界での上橋氏の実体験にある。彼女にそんな経験をさせてくれたのは、彼女の父方の祖母の影響が大きいらしい。話上手の祖母の膝の上に頭をくっつけながら、上橋氏はたくさんの昔話を聞いて育ったのだという。話してくれたのは、絵本で読むような昔話とは異なる「口頭伝承」で、耳で覚えた土地の不可思議な話をいくつも聞かせてくれたそうだ。上橋氏の反応を見ながら、先の展開をどんどん変えてしまう祖母の話に魅せられて、上橋氏は物語を想像する楽しさを覚えた。お話は本当にあった実話のように語られた。日常から遠い話なのに、もしかしたらと思わされるところがあったのだと上橋氏は振り返る。物語は日常の中にそっと入り込んできたのだ。
「猫というのは意外とあなどれんものだから気をつけなさい。数日いなくなったなと思ったら、しっぽを見るのだよ。しっぽがふたまたになっていたら、一人前の化け猫になったということだからね」。
上橋氏が人と獣の距離が近い物語を書くようになったのは、祖母の話の中に動物が多く出てきたことにルーツがあるのかもしれない。祖母の話を毎回楽しく聞いて幼少時代を過ごした上橋氏は、物語の世界にどっぷりと浸かりこんで、登場人物になりきってしまう子どもだったという。たとえば、上橋氏は、子どもの頃、道端にある石ころを蹴飛ばすことができず、石ころがあると、道の脇にわざわざおきにいったりしていた。なぜそんなことをしていたかといえば、彼女は一瞬だけふと「石ころの目」になって「蹴られたら嫌だな」と思ってしまったからだという。この気分は大人になっていても残っているそうで、いつもあらゆるモノや動物、虫の立場に経ちながら、「その目は何を見ているのだろう」とつい考えてしまう。「アニミズム」という言葉を知る前から生物であれ、無生物であれ、すべてのものに命があるように感じていたその感性が上橋氏の物語に息吹を与えている。
身体が弱かった子供時代のこと。「強さ」に憧れて、特撮ヒーローになりきっては、「間違えるな。おまえは女だぞ」と父親に叱られたこと。小さい頃は漫画家になるのが夢だったこと。子どもの頃から大学院の博士課程に行くのだと決めていたこと。本が大好きで、特に「キュリー夫人」の伝記に勇気づけられたこと。
上橋氏のすべての経験が「守り人」シリーズの誕生に結びついているように思える。ああ、こんな感性が羨ましい。彼女の作品とともに、彼女の人生観を知れば、自分自身の感性も磨かれそうなそんな気持ちにさせられる1冊だ。
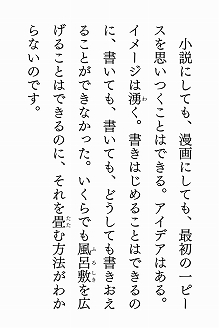
小説を書き始めた時は、想像がとまらず、完結させることができなかったという
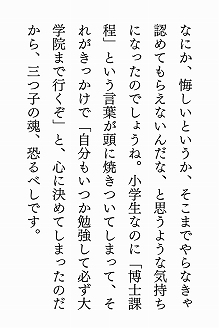
「大学院まで行くぞ」と幼い頃から決意していた
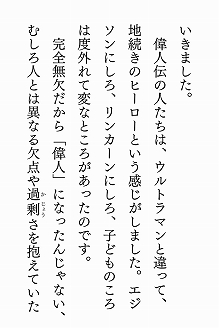
本が大好きで読みふけっていたが、偉人伝は勇気づけられた。完全無欠じゃなくていいのだ、と思うと安心したという
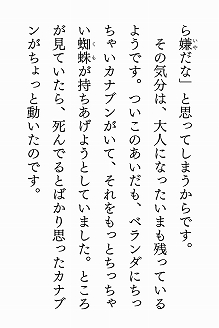
大人になっても、上橋氏は、つい、虫の気持ちになってしまうことがあるという
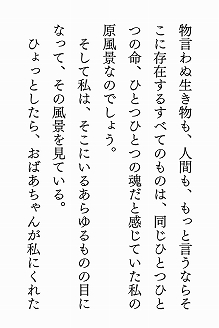
祖母から受けた影響は大きい。上橋氏の感性の鋭さに触れることができる作品


























