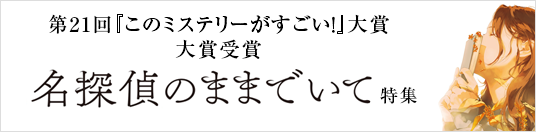自身がレビー小体型認知症だと自覚していた祖父。それでも楓に幻視の話をしていた理由は?/名探偵のままでいて⑤
公開日:2023/2/3
こういったパーキンソン症状は別として、と祖父はわずかに震える手を見ていった。
「ぼくの精神状態が、いわゆる健常者とは程遠い状態にあることには、だいぶ前から気が付いていた。そうだな――たとえばそこの書棚の壁をふと見ると、その一面に、まるで腕のいい宮大工が神輿に彫ったかのような細かい彫刻が施されているんだ。だが触ってみると、彫られている感触はまるでない。壁は極めて滑らかなんだ。では、視覚と触覚、どちらを信用すべきか。ぼくに気付かれることなくひと晩で精巧な彫刻を書棚の壁全体に施すのは、とうてい不可能じゃないか。加えて世の中の誰にも、わざわざ年寄りの部屋に忍び込み、その書棚に彫刻を施す動機はまるでない。ということは――残念ながら信用すべきは触覚だということになる。裏を返せばぼくの視覚は、まるで信用ならんというわけだ」
楓は返す言葉もないまま、祖父の告白を聞くばかりだ。
「では、この異変の原因はなんなのか。パソコンは壊れていて使えない。スマートフォンで検索しようと思ったが、このとおり手元がまるでおぼつかない。というよりも〝楓の亡骸〟を見て119番通報してしまって以来、香苗にスマートフォンを没収されているから、そもそも検索のしようがない」
祖父はいたずらっぽく、形のいい唇を尖らせた。
「そこでヘルパーさんに頼み込んで介護タクシーを呼んでもらい、図書館に行って調べてみた。なにしろ字を追うだけですぐに目はかすむわ眠くなるわで、一日がかりの作業にはなったが……ぼくがどんな病気なのかという確信は持てたよ。そういえばほら、〝灰色の脳細胞〟という言葉があるだろう」
祖父はベルギー人の名探偵、エルキュール・ポワロの口癖を引用して自嘲気味に微笑んだ。
「するとぼくの場合は濃いオレンジ色のレビー小体が脳の表面に広がっているわけだから、さしずめ〝緋色(ひいろ)の脳細胞〟の持ち主、というわけだ」
じゃあ、と楓は尋ねた。
少し声がかすれているのが自分でも分かる。
「どうしてわたしに幻視の話をわざわざ何度も聞かせてみせたの?」
「それはだね」
少しだけ祖父は、言い淀んだ。
「ぼくが幻視の話をしているときはとくに、楓の表情がくるくると変わるからだ。驚いた顔を見せてくれたり、笑顔を見せたりしてくれるからだ。なにより、声を出して相槌を打ってくれるからだ。そうするとぼくは、楓の実在を確信を持って感じ取れるんだ」
「え……どういうこと? わたしはいつだって、おじいちゃんのそばにいるよ」
「では、こういえば分かってくれるかな。ぼくは以前、楓に向かって、正直あまり長くはないであろうぼくの今後の――なんというのだろうね――いわゆる〝終活〟という言葉は耳に馴染むわりに無神経で好きじゃないから使わないとするならば、ぼくの今後の身の処し方について、とことん本音を語ったことがあったのだよ。そのときは自分でも体調が完璧に近いとうぬぼれていた。伝えるなら今しかないとさえ思っていたのだよ。それでそう……一時間ほどはたっぷりと話したかな。ところがだ。なぜか無言で、しかもずっと無表情のまま話を聞いていた楓は」
祖父は、一度言葉を切ってから目線を落とした。
「とつぜんふっと、ぼくの前から消えてしまった。その楓は幻視だったんだ」
あるいは〝煎り〟が入りすぎたコーヒーのせいかもしれない。
祖父の顔に一瞬だけ、苦みのような色が走った。
「こんなに惨めで哀しいことはないじゃないか。以来ぼくは、楓のほうから切り出すまで、病気の話はけしてすまいと心に決めたのだ。たとえ、まともな会話がまるで成立しない認知症の老人だと決めつけられたとしても仕方ない――そう思ったのだ」
(おじいちゃん)
もういちど、心の中でつぶやいてみる。
(おじいちゃん)
ひとりきりの孫娘に、自身の最期の身の振り方の話ができなかった――いや、あえてしなくなった祖父。
その苦悩に、どうしてもっと早く気付いてあげられなかったのだろう。
幻視は確実に見る。
それも、頻繁に。
記憶障害も含め、ときにさまざまな意識障害にも襲われる。
パーキンソン症状により、動作は極めて鈍い。
だが――祖父の基本的な知性には、いささかの衰えもなかったのだ。
<第6回に続く>