白泉社の社長が圧倒され再読できなかった“禁断の書”。『ベルセルク』『3月のライオン』を生む出版社のスピリットを語る【菅原弘文・私の愛読書】
公開日:2023/12/1

さまざまなジャンルで活躍する著名人たちに、お気に入りの一冊をご紹介いただく連載「私の愛読書」。今回は、白泉社の代表取締役社長・菅原弘文さんにご登場いただいた。
今年12月1日、創立50周年を迎えた白泉社。菅原社長は約40年前に少女漫画誌の編集者として白泉社に入社して以降、いくつもの編集部や販売部を経験し、白泉社と共に歩んできた菅原社長の原点となった読書体験を語った。
(取材・文=金沢俊吾 撮影=takaya miura)
再読できない「禁断の書」
――今日は菅原社長の「愛読書」を教えていただければと思います。
菅原:スタンダールの『赤と黒』です。これは愛読書というか…私にとって「禁断の書」なんです。高校生のころに一度読んだきり、一度も本を開いていません。だけど、この文庫本をいつも身の回りに置いていたんですよ。
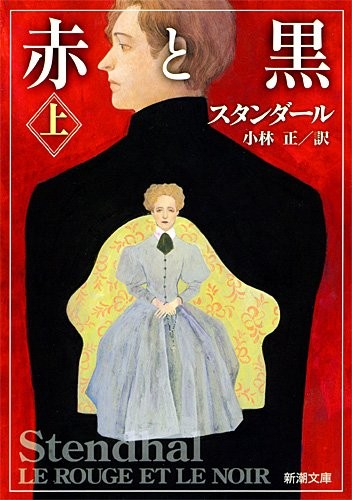
――なぜ再読しなかったのでしょうか?
菅原:教科書に載ってたのを読んですごくおもしろかったので、文庫を買って読んでみたんです。本当にああいう体験って人生で一度だけなんですが…読み終わったあと1週間ぐらい、何も考えられないほどボーっとしてしまったんです。またそうなったら仕事どころじゃなくなるので…。
――どういった点に惹かれたのか、教えていただきたいです。
菅原:とにかく心理描写に圧倒されました。人間の心と心のぶつかり合いとか、表に出さずに隠してる思いとか。「人間ってこんなに複雑な生き物なんだ」と、そこで初めて人間のおもしろさに気付かされたような感覚になったんです。
――主人公のジュリアン・ソレルは現代の読者にも響きそうな、魅力的なキャラクターですよね。
菅原:そうなんですよね。ツンデレのイケメンで、少女漫画の設定にも通じるところがあると思います。あとは漫画でいうと江川達也さんの『東京大学物語』。主人公がばーっと考えを巡らせたあとに「この間、0.1秒」とか表示されるじゃないですか。ああいった心理描写にも通じているような気がするんです。

菅原社長が白泉社に入るまで
――『赤と黒』は高校生が読破するには少し難しい気もしますが、いわゆる文学好きな高校生だったのでしょうか?
菅原:いえ、まったくそんなことはなかったです。高校の専攻は理系でしたし、それまで小説はSFしか読んだことがありませんでした。学校の読書感想文にレンズマン・シリーズを書いて提出したりね。銀河パトロール隊とか宇宙海賊とか、先生はそういうのをまったく求めていなかったと思うんだけど(笑)。
――(笑)。『赤と黒』を読まれてから、嗜好に変化はありましたか?
菅原:まず、専攻が文系に変わりましたね。サマセット・モームが『世界の十大小説』で解説している作品を読破したりと、小説をたくさん読むようになりました。
――それは大きな影響ですね。新卒採用から出版社に入られたのでしょうか。
菅原:いえ、新卒でビデオデッキを作るメーカーに入社しました。でも結局、文系で入ったので、製品開発のプロジェクトに関わることはできても、実際に作るのは研究所や技術部門なんですよね。それに対して疎外感を抱きながら働いていた記憶があります。
――そこから白泉社に転職した経緯が気になります。
菅原:あるとき駅売りの朝日新聞を読んでいたら、白泉社が募集広告を出していたんですよ。当時、好きだった白泉社の漫画もあったので応募しようと思い、それが入社に繋がりました。もう40年ほど前のことです。
『赤と黒』のような本を作りたい
――編集や販売など様々な部署を経験されたそうですが、入社時は編集職ですか?
菅原:はい、入社からしばらくは編集部にいました。それこそ、採用面接で「『赤と黒』みたいな作品を作りたいです」と言ったのを覚えています。あまりにも偉大すぎて、まだちょっと実現できていないんですけどね。
――『赤と黒』のようなスピリットを持った作品を作りたい、ということでしょうか。
菅原:そうですね。人間って、どんなに望んでも他人の心は読めないじゃないですか。それが小説や漫画の心理描写を読んで「人って、こんなことをいろいろ考える生き物なんだ」と、人生のおもしろみに気付いてもらえたらと思うんです。
――心理描写といえば『3月のライオン』はモノローグが印象的に使われていて、人間の複雑な心のなかを描いている作品だと思いました。
菅原:仰る通りですね。私は、文学のかたちの最上位にあるものは「詩」だと思っているのですが、『3月のライオン』はもう漫画というよりは詩の世界ですよね。素晴らしい作品だと思っています。

座右の銘が書かれた『小泉八雲集』
――それでは、もう1冊お願いいたします。
菅原:『小泉八雲集』です。小泉八雲の作品を上田和夫が翻訳したもので、これは『赤と黒』と逆に何度も読み返している作品です。小泉八雲は後に日本国籍を取得して名乗ったもので、出生名はパトリック・ラフカディオ・ハーンといいます。ギリシアに生まれて、アメリカの出版社の一員として来日したのがきっかけで日本に移住し、本作は日本文化を英語圏に紹介すべく書かれました。
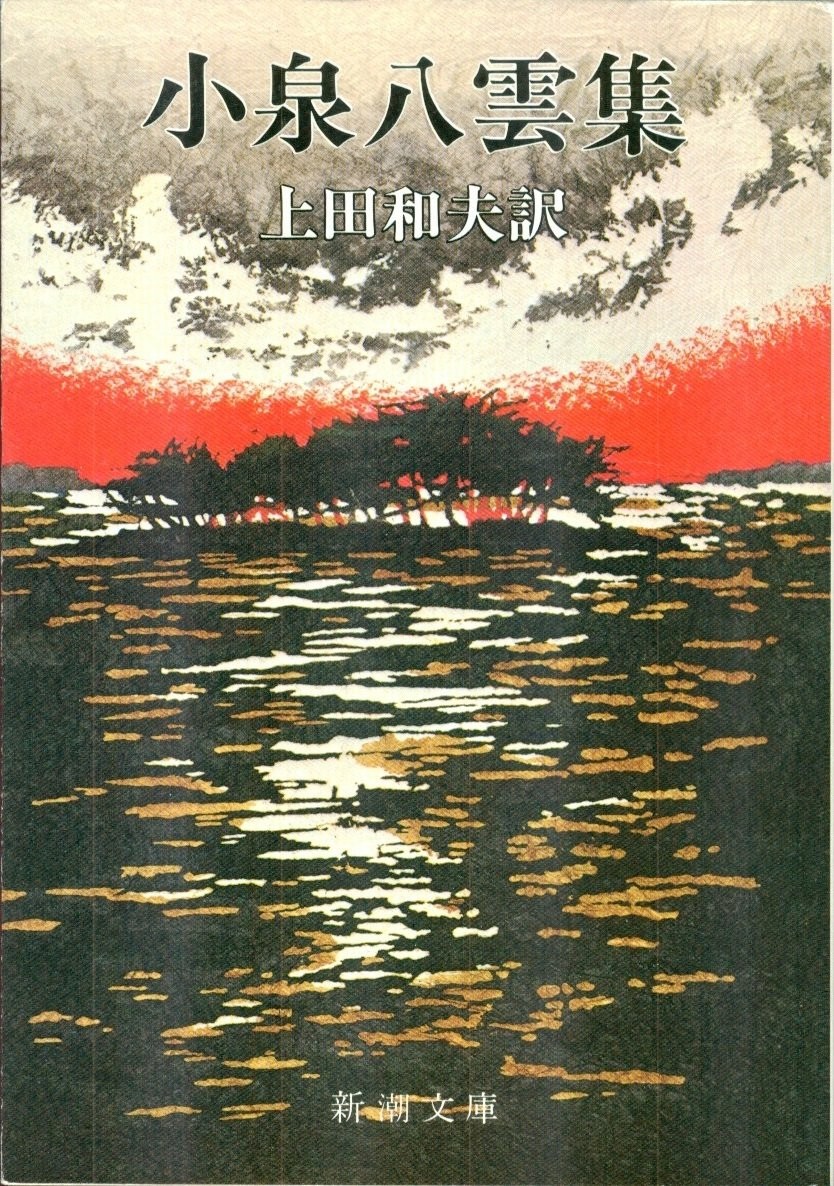
――「耳なし芳一」「ろくろ首」など日本人にはお馴染みの物語がわかりやすく描かれていますが、なぜ本作に強く惹かれたのでしょうか?
菅原:私自身が小泉八雲という人間に共感を持ったからだと思います。彼はイギリス、アイルランド、アメリカ、日本と世界中を転々とした生涯を送りましたが、私も幼稚園を2回転園、小学校は3回、それから中学校は2回転校してるんですよ。
――それは大変でしたね…。
菅原:そうすると、いくら仲がいい友達がいても、だんだん疎遠になっていくんですよね。だから、どこかにしっかりと根を下ろしてるという意識が全然なくて、いつも「よそ者」であるという感覚を持っていたんです。そんなとき、八雲の人生に心奪われたんでしょうね。
――作品をいまも読み返すのは、どういった感覚なのでしょうか?
菅原:本作に収録された『常識』という短編に、私の座右の銘があるんですよ。ちょっとあらすじをご紹介してもいいですか?
――ぜひお願いします。
菅原:優れたお坊さんと猟師の話で、ある日、お坊さんが白いゾウに乗った普賢菩薩が毎晩現れると猟師に話すんです。お坊さんが猟師を「一緒に菩薩を拝んでみようじゃないか」と誘って、寂しい風の強い夜に、寺で菩薩が現れるのを待ちます。菩薩が現れると、お坊さんは一心不乱にお祈りするのですが、猟師はおもむろに弓を菩薩に向けて放っちゃうんですよ。
で、朝になって、その菩薩がいた場所に行くと、そこに大きなタヌキが死んでいたんです。
――タヌキに化かされていたわけですね。
菅原:「お坊様はこれまでの功徳で菩薩を拝むことが出来ても、殺生を生業とする私も同じように見れるのはおかしい」と猟師は言うんです。学問に秀でて信心深い僧はタヌキにだまされたけど、無学だけど、常識で考えた猟師は危険を避けることができたわけです。この話の教訓は「1つの価値観だけで判断してはいけない」ということだと思っていて。
――それを戒めとして、いまでも定期的に再読されている。
菅原:そうですね。自分がいま持ってる考えだけで判断しない、というのは心がけています。特に、社長という立場を務めていると、判断しないといけない場面が多々あります。そうしたとき、自分の考えを盲信しないようにしています。
――一般論として、年を取るにつれて経験も増えますし、フラットに他人の考えを受け入れるのは難しくなっていくだろうなと思います。
菅原:その通りですね。だからこそ、座右の銘にして忘れないようにしています。まあ、「愛読書」ということで意味ありげなことを言いましたが(笑)、単純に、読んでいて本当におもしろい本なんですよね。
――なるほど。菅原社長自身も、本を作るうえで「おもしろい」というのは大切にされているのでしょうか?
菅原:もちろんです。もうそれが一番ですね。白泉社の経営方針は「こころを動かすおもしろさを作って届けよう」なんです。どんなにいい教訓があっても、おもしろくないと読んでもらえないわけですから。

読者に届けるまでが我々の仕事
――白泉社は12月1日に創立50周年を迎えました。菅原社長は白泉社のどんな面を誇りに感じていらっしゃいますか?
菅原:うーん…自分で言うのはなかなか難しいですね(笑)。読者の方々が「白泉社の作品はこういうところが良いよね」と思ってくださるのが一番嬉しいのですが。漫画に関していうと、雑誌よりも電子で読まれることが圧倒的に多くなり、これまで以上に一作一作が勝負になっている時代です。そんななかで、一作一作を作家さんや編集者が精魂込めて作っていることが、月並みではありますが誇れることかなと思います。
――デジタル時代以前から、一作一作を大切に作ってこられた。
菅原:そうですね。私が入社した当時、世の中には恋愛メインのいわゆる王道な少女漫画が多かったんです。白泉社はそんななかで『ぼくの地球を守って』とか大島弓子さんの作品とか、他社さんではちょっとないようなものがありました。いまもそういった、流行りや型にとらわれないDNAを持っている会社だと思っています。
――それこそヤングアニマルは『ベルセルク』も載ってれば『3月のライオン』も『ふたりエッチ』も載っているという「青年誌」といった括りでは語れない、独自の路線を走る雑誌だと思います。
菅原:そうですよね(笑)。『ベルセルク』は三浦建太郎先生が急に亡くなられて、続きが読めないのかと絶望的な気持ちになっていたんですけども、三浦先生と高校時代から付き合いがある森恒二先生が結末を知っていたんです。それを基に森恒二先生の監修で連載が再スタートしました。
――ニュースで知ったときはすごく驚きました。
菅原:再連載の前に、プロトタイプの原稿が出来たんです。それを読んで、すごく頑張ってくださっているのは伝わったけど、正直、これで読者が満足するかちょっと不安だったんです。だけど、本番の掲載原稿は、三浦先生が見守って描いているような完成度でした。先日発売されたコミックスは、もう本当に素晴らしいものができたと思います。それができた白泉社というチームは、ちょっと誇っていいんじゃないかと思いました。
――ああ、素晴らしいエピソードですね…。最後に、ものづくりにおいて菅原社長がもっとも大切にされていることを教えてください。
菅原:読んでくれる人の顔を思い浮かべるってことですかね。おもしろい作品を作ったら終わりではなく、それを読者に届けるまでが我々の仕事だと思っています。だから、先ほどの座右の銘とも重なりますが、独りよがりにならないように気を付けています。だから、ダ・ヴィンチWebさんも何か気になったことがあれば、何でも言ってくださいね(笑)。

<第39回に続く>























