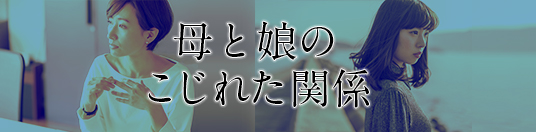「一度からまった糸って、なかなかほどけないものね…」母×娘の確執物語
公開日:2018/5/15

親子の形は、一体どこで歪みが生じてしまうのだろう。親子が理解し合うことの難しさを巧みに描いている『食堂かたつむり(ポプラ文庫)』(小川 糸/ポプラ社)はそんな想いを抱かせる。親子が理解し合うことの難しさを巧みに描いた作品だ。
物語の主人公である倫子は、同棲していたインド人の恋人に家の物をほぼ持ち去られてしまい、故郷へ帰ることに。しかし、母親・ルリコとの確執を抱えていた倫子にとって、実家に戻るということは心苦しいものだった。倫子の実家は村の人たちから、“ルリコ御殿”と呼ばれている。愛人の所有地に建てられた母屋や母親が経営するスナック、物置小屋などは目立つところにだけお金がかけられた、はりぼての城だ。久しぶりにこうした光景を目の当たりにした倫子は嫌悪感を覚えるが、物置小屋を借りて、食堂を営むことを思い付く。そして、倫子は食を通して、村の人たちの温かさや命の大切さを実感していくのだ。
本書のおもしろさは、ほっこりとした物語の裏に母親と娘の確執が隠されているところにある。
私はほとんどの人や生き物を愛することができる。けれどたったひとり、おかんだけはどうしても、心から好きになれなかった。
そんな倫子の言葉には、長年積み上げてきた母親への恨みが詰まっていた。母親という存在は世界にたったひとりしかいない。だからこそ、簡単に許すことができない。母と娘の心は、一度すれ違ってしまうと、元通りに修復することが難しくなり、いつの間にか、すれ違ってしまったきっかけすらも忘れてしまう。しかし、そんな複雑な関係に悩んでいるのは、娘だけではないのかもしれない。
それにしても、いつから私たちって、こんなふうになってしまったのかしら? 一度からまった糸って、なかなかほどけないものね。私はあなたのことが大好きなのに、どうしてもそれをきちんと伝えることができなかった。
本書のラストでルリコが送ったこの言葉からは、親側の葛藤もうかがえる。倫子とルリコのように、何が確執の始まりだったのか分からないほど、糸がからまってしまった親子は現実社会にも多く溢れているのではないだろうか。親子の縁はなかなか切れないものだ。だからこそ、親子は気持ちを言葉にすることで、からみ合った糸を解いていかなければならない。
本書は、人間の奥深さもひしひしと感じさせてくれる。倫子の目に家庭的で優しく映っていた祖母は、ルリコにとっては愛のない母親として見えていた。実は、倫子にとっては手作りのぬか床を伝授してくれた優しい祖母だったが、過去に政治家の愛人をしており、ルリコがまだ幼い頃に駆け落ち同然で家を出ていた。そのため、ルリコは母親の温もりを感じられないまま、親戚の家や施設を転々としていたのだ。
だからこそ、ルリコ自身は、娘に自分と同じような想いをさせたくないと思い、家の近くでできるスナックの仕事を始めた。こうした愛情深い一面を知ると、ルリコは母親として、きちんと我が子のことを愛しているように思える。また、ルリコには初恋の人のことを何十年経っても思い続けているような一途さもある。しかし、倫子の目には男にだらしなく、冷淡な母親としてしか映っていなかった。
このように、人はみな二面性を備えており、表だと思っていた性格が実は裏であったりすることも少なくない。だからこそ、親にも自分の知らない顔があるのではないかということを心に留めておくとよいのかもしれない。苦手な人の意外な一面探しは、心の距離を近づけるきっかけにもなるはずだ。
自分にとって毒な相手とは、自然に接触を避けてしまいたくなる。しかし、時間をかけながら距離を近づけてみると、新しい発見ができることも多い。遠ざけた距離を近づけることには想像以上に勇気がいるものだが、一歩踏み込んで苦手な相手の心を見てみてほしい。
文=古川諭香