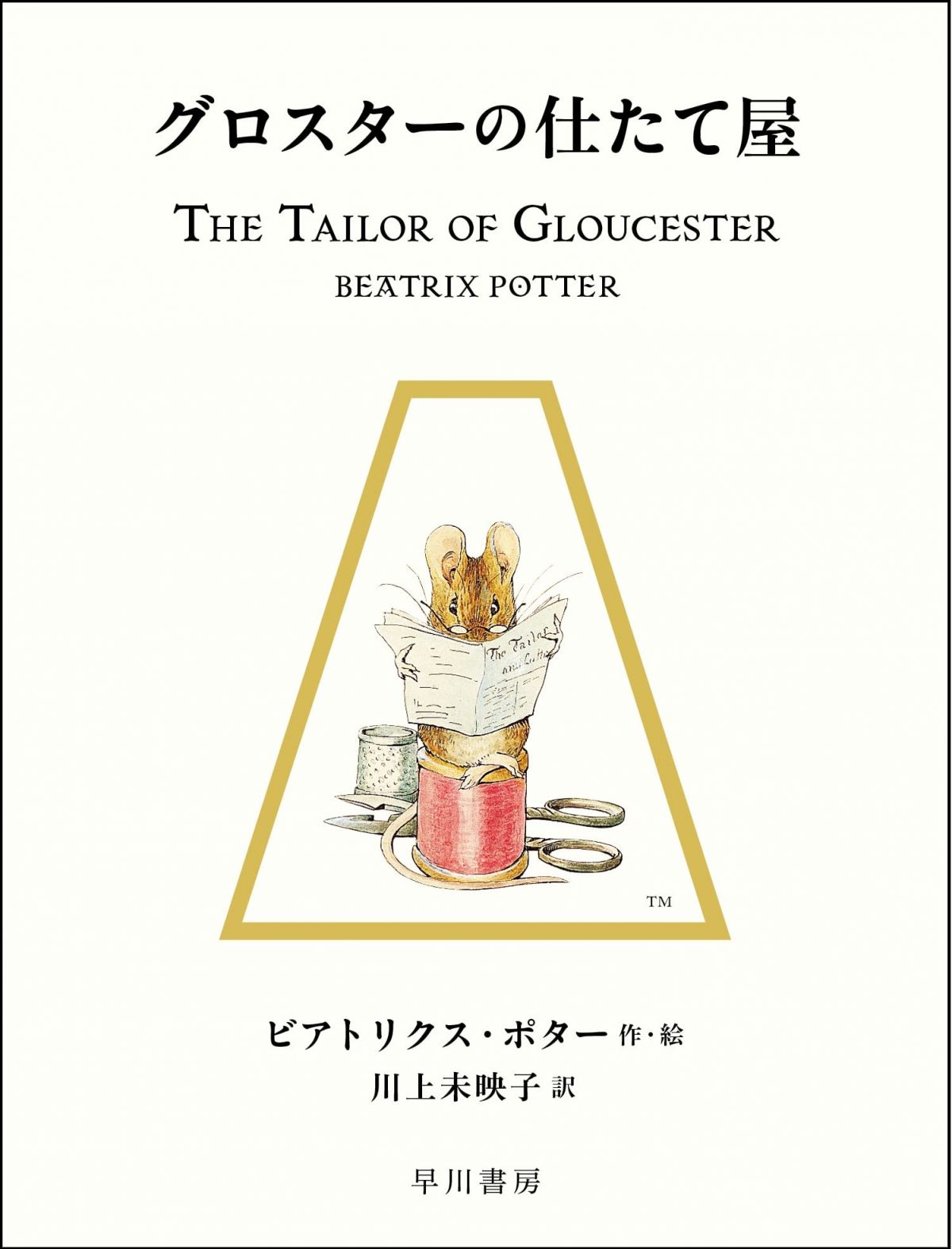愛されて120年! 絵本〈ピーターラビット™〉シリーズの新訳は何がちがう? 全23巻の翻訳を手がける川上未映子さんに聞く!
公開日:2022/4/6

世界中で愛されている絵本〈ピーターラビット™〉シリーズ。1902年にフレデリック・ウォーン社よりいたずらっ子のうさぎを描く『ピーターラビットのおはなし』(ビアトリクス・ポター:著)の初版が刊行されてから120周年を迎える2022年、早川書房がフレデリック・ウォーン社と提携し、日本における公式出版社となった。その記念すべき年の3月、早川書房は新訳版の絵本〈ピーターラビット™〉シリーズ(全23巻)の刊行を開始する。翻訳を手がけるのは、2008年に『乳と卵』で芥川賞を受賞、2019年に発表した『夏物語』が国際的な評価を受けている小説家・詩人の川上未映子さんだ。
ノーベル賞作家のカズオ・イシグロさんが「ピーターラビットとフロプシー、モプシー、カトンテールや仲間たちおめでとう。君たちが見つけたのは、温かく居心地のよい日本の新しいお家、ハヤカワです。川上未映子さんのすばらしい言葉にのって、これからもっと元気にとんだり跳ねたりいたずらしたりできますよ。」とコメントを寄せたこの一大プロジェクトに、川上さんはどのような気持ちで臨んでいるのだろう? お話をうかがった。
(取材・文=三田ゆき 撮影=干川修)

ビアトリクス・ポター™と川上未映子の共通点
──世界中で、長く愛されつづける絵本〈ピーターラビット™〉シリーズ。翻訳のお話があったとき、どのようなお気持ちでしたか?
川上未映子(以下、川上) いくつもの「びっくり」がありました。大変だろうな、わたしには荷が重いんじゃないかとも思いましたが、けれども「自分が難しいと思ったことはやりたい」という気持ちと、これまでもそうしてきたという経験がありました。それで、自宅にあったピーターラビットの絵本と、原作を取り寄せて読んでみると、詩の部分が目にとびこんでくる感じでした。お引き受けするかどうかまだ返事していなかったのに、「ここは、みっつ拾えるな」というような感じで、もう始めてしまいました(笑)。
外国語ではありませんが、樋口一葉の「たけくらべ」の新訳をやらせていただいたことがあります(『樋口一葉 たけくらべ/夏目漱石/森鴎外 (池澤夏樹=個人編集 日本文学全集13)』(河出書房新社))。こちらも、日本語とはいえ古い言葉で、難しい仕事でした。でも、それ以上に、文章の構造に、なんというか、じかにあたっていく手応えというか、驚きがいくつもあったんです。ふつうに読んでいるだけでは見えなかった言葉えらびの意図ですとか、構図とか。そういうものが、翻訳をすると見えてくるものがある。違う角度から、またべつの解像度が違ってくるという感じでしょうか。

──韻文はもちろん、たとえば「これはおはなし、しっぽのおはなし、しっぽのもちぬし、赤りすの……」という『赤りすナトキンのおはなし』のはじまりの部分も、気持ちのいいリズムがありますよね。
川上 そう言っていただけると、うれしいです。この「おはなし」って、英語だと「tale(テール)」、なので動物たちのしっぽの「tail(テール)」と掛かっていますよね。「おはなし」の「お」としっぽの「お」。かわいいですよね。リズムもとても大事だと思います。わたしは、息子が生まれて9年間、「絵本の読み聞かせ神話」があまりに幅をきかせていたのもあって、いろいろが面倒になって、読み聞かせをほとんどしていないのですが(笑)、それでも感じるところがありました。子どもは、とにかく、おもしろい音が好きですよね。調子がよくて、ひょうきんな雰囲気のもの。はじまるよ、みたいな感じのするリズムを見つけようと思っていました。
──刊行にあたっても、原文について「美しく、たくらみのある音とリズム」とコメントされていました。ほかにも、著者であるビアトリクス・ポターの「たくらみ」を感じた部分はありましたか?
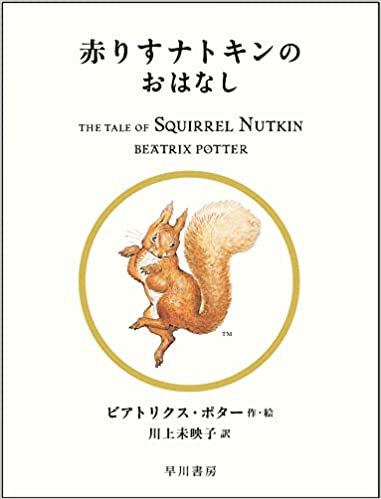
川上 たくさんありますよ。ポターの手数の多さには、わたしが理解できるだけでも、ほんとに毎日のように驚かされます。お話はもちろん、絵の素晴らしさもそうですよね。たとえば、『赤りすナトキンのおはなし』に登場するりすたちの、ぱさついた毛の質感、木の実を詰めたふくろを持つ腕の筋肉の盛り上がり……本当に重いものを持って、運んで暮らしているんだなと感じる腕ですよね。
さらには、彼らが木の実を拾わせてもらうためにおみやげを持っていくふくろうが、威厳をもってりすたちの前にいる。地主と労働者の構図ですよね。たとえば「威厳」のようなものって、文章でも演出でも、きちんと表すのはとても難しいと思います。それを、言葉と絵の合わせ技で、しかも恐るべきクオリティーでやってのける。ポターのたくらみは、まず描写ですね。本当に素晴らしいなと思います。
──そういった描写で「書き尽くそう」という観察眼は、川上さんにも共通しているように感じますが?
川上 ありがとうございます……! そう言ってもらえてうれしいけれど、でもやっぱり、ポターという作家は、エクストリームだよなあ。創作だけじゃなくて、ビジネスにも関心があったし、実践もしましたし。彼女が生きた時代を思うと、とてつもないことです。いろんなことを思いついて、すごく集中力があって、とにかく仕事ができる人だったんだろうなあと思います。
──そんな彼女の感性が、新しい訳になることで、今の子どもたちはもちろん、わたしたち大人にとっても、新しい感覚で触れられるものになりますね。
川上 そうですね、でも個人の訳がとくべつそうだというわけではたぶんなくて、 “時代”が大きくかかわるんじゃないかな。村上春樹さんもおっしゃっていましたが、翻訳にはだいたい50年くらいで賞味期限がきれるのではないかと。それは、その翻訳がいいとか悪いとかいうことではなく──原文は書かれたときから変化しないで、それを訳す言葉、読む人たちの感覚が移り変わっていくからなんですよね。新しい訳が出てくることで、以前の訳がひとつ消えるわけでもないですよね。
「石井桃子さんの訳で読んだ」ということと、ピーターラビットというものは、なんというか、それはもう多くの人の体験として分かちがたくあるわけですよね。石井さんの「大きな訳」が、もうずっと存在していてくれるという前提のおかげで、じゃあ2020年代以降ではどんなピーターラビットができるのかなと、リラックスして、楽しむことができるのだと思います。ありがたいことですよね。
──川上さんも、子どものころに絵本〈ピーターラビット™〉シリーズを読まれていますか?
川上 有名なキャラクターのものは読んでいました。すごいことですよね、1980年代初頭の大阪のストリート、本や文化資本なんて一切なかったわたしの家にも、ピーターラビットは入り込んできていた(笑)。お話の細かいところは記憶から抜けていても、絵ははっきりと覚えていましたね。
たとえば、これから刊行される『2ひきのわるいねずみのおはなし』(※)。人形の家にねずみたちが入っていって、おもちゃのごはんを食べようとするシーンがあるのですが、ハムの断面の絵、ぷっくりふくらんだ魚の絵を見たときは、もうマドレーヌ現象(味覚や嗅覚から記憶が呼び覚まされる心理的な現象)がそのまま起きました。「ほんまにこれ、わたし子どものときに、体験したよなあ」って、しみじみして。「人形の家に入っていく」って、実際にわたしたちにはできないのに、その「入っていく」という感覚に夢中になったことを覚えていたんです。
(※)『2ひきのわるいねずみのおはなし』は、2022年6月23日発売予定
わたしは文章でも、入れ子構造の設定を書くことが多いのですが、この「小さいねずみたちが小さい人形の家に入っていく」という入れ子構造の記憶は少なからず影響していると思います。絵本には、そういう「よみがえらせ」というか、時制を狂わせる瞬間がありますよね。そういうことがたびたび、あります。意味のほうじゃなくて、わたしに場合は、とくに質感のほうが。絵本は、まだ世界が分節化されるまえの、自分が感覚そのものだった時代があったんだってことを、容赦なく思いださせる力がありますね。
ポターの原文に学んだことは、今後の創作に絶対に影響がある

──お気に入りの話、お気に入りのキャラクターなどはありますか?
川上 『グロスターの仕たて屋』に出てくる、シンプキンという猫がすごくいいな、と思います。ちっとつばを吐いたりしてね、手懐けられないというか、パンクな感じ(笑)。一緒に暮らしている仕立て屋のおじいさんが自分の獲物のねずみを逃したからって、腹いせに、おじいさんの大事な糸を隠しちゃうんです。おじいさんが「糸が足りん!」「ばんじきゅうすだ、おしまいだ!」ってなってるのにスルーして。でもこの子、具合が悪くなったおじいさんを置いて外に出ると、さびしくなっちゃうんだよね。クリスマスだけど、仕立て屋とシンプキンにはお金がなくて、それなのに街はすごく浮かれてて、おんどりや猫たちが歌ってる。しゃくにさわったシンプキンは、ラップバトルみたいなことをするんだけど(笑)、やりこめられて。
それから仕立て屋のお店の前を通りかかると、ねずみたちがおじいさんのために上着を作ってるんですよ。それを見て、「そっか……おじいさんのためなんだな」なんてしゅんとして、家に帰るころには「ごめんね」みたいな気持ちになってる。彼らは二人暮らしだけど、血縁でない者同士の暮らし、そこに介護も労働も入ってくるような、かつかつの生活が描かれています。でも、なによりももう、シンプキンが本当にかわいいんですよ。日本がもっとカジュアルにタトゥーを入れられる文化だったら、訳した記念にシンプキンのタトゥーを入れてもいいなと思うくらい、いいですね(笑)。
──「翻訳をする」ということは、みずから文章を生み出されることとはまた違いますよね。
川上 違いますね。小説には正解がないけれど、翻訳には原文があるから、そこはちょっと違いますよね。預かっている感じというのが、すごくあります。
でもそうしていると、やっぱり小説もよくなりますね。学んだのは、たとえば『グロスターの仕たて屋』の最後の部分。すばらしいジャケットができましたという描写があるのですが、「ごうかなフリル、刺しゅうのついたそでぐち、うつくしいえりのかざり……」と来たら、わたしが手癖で書くと、もっともっと、言葉を詰め込んで盛りあげたくなるわけです。ところがポターは、この描写のあとに、「けれども、なによりすばらしいのは」と、すぐに次の文章に移っていく。ひかえめに抑えることで、エッセンスが際立つ、よりすばらしさが伝わるんだと学びました。
『ヘヴン』という小説を書いたとき、そのラストシーンで「美しかった」という景色を、2ページくらいだっけかな、かたまりで描写してるんですよね。あのときはあれ以外にはなかったんですけど、でも同じように物語の最後で、ポターはどんな感じで言葉を尽くして書いているかなと思ったら、すごくシンプルに表現していた。そのことによってリーチできるものもあるんだということに、原文をじっと読むことで気づけました。このことは、今後のわたしの創作にも、影響があると思います。

──このシリーズを、どんな人に楽しんでほしいと思われますか。
川上 純粋に絵や物語を楽しんでもらうことはもちろん、いろいろな楽しみ方ができるなと思っています。子どもと一緒に読むときは、人間と動物があたかも会話をしているように見える物語だからこそ、「人間と動物ってなにが違うんだろう?」みたいな話もできるし、ピーターのおとうさんが肉のパイにされているところで、「わたしたちも牛をかわいいと思うけど食べるよね」と、いのちのリレーションについて話すこともできる。
それから、やはり今回、すばらしいと思うのは、ポターという作家が作った順番でシリーズが刊行されるということですね。「こういう流れで物語を書いていったんだ」という楽しみ方もできそうです。ポターの絵からも感じるものも、きっとあります。それに、ほとんどの巻で、登場する動物たちが危機一髪に陥りますよね。それはもちろん物語の定型なんですが、ポターの場合は、「また同じことやってる」とはならないんです。
描写のちからと、キャラクター造形や関係性が、ユニークだからだと思います。魅力的ないたずらっ子たち、思惑と駆け引き、怒られたり、追い詰められたり、安心したり、みんなそれぞれ知恵をしぼって、物語がすすんでいきます。9歳の息子も、そういうところが気に入ってるみたいですね。「つぎは、どんな悪いことするの?」、「え、人形の家に勝手に入って、ベビーカーで爆走だよ」って(笑)。読んでいるうちに、「いたずら」とか「意地が悪い」といった概念も変わってきますし、わたしたちが持っている「勧善懲悪」だとか、物語の定型の「読み」のようなものを、やさしくほぐしてくれることの連続です。いろいろな人が、いろんなふうに楽しめる、懐の深いシリーズだと思いますね。
わたしは今回、翻訳という大きな役割をいただきましたが、不思議なことに「遠い昔の物語に触れている」という感じがしないんです。それは、ポターがこのお話を書いたときに生きていて、わたしたちも今、生きているからですよね。そういった感覚につながる翻訳を目指しています。ポターは、動物たちを愛玩の対象として扱っているわけではないし、かといって人間と対等に見ているわけでもない。ポターと動物とのあいだには、深いものがありそうです。わたしもこの全23巻の翻訳を通して、そこに迫れたらな、と思っています。
BEATRIX POTTER™ © Frederick Warne & Co.,2022
特典付きの全巻予約が可能なネット書店はこちら!
・紀伊國屋書店ウェブストア
・honto