村上春樹『街とその不確かな壁』は“ハルキ要素ほぼ全部入り”。『ハードボイルドワンダーランド』などを感じさせる集大成的作品をレビュー
公開日:2023/6/3
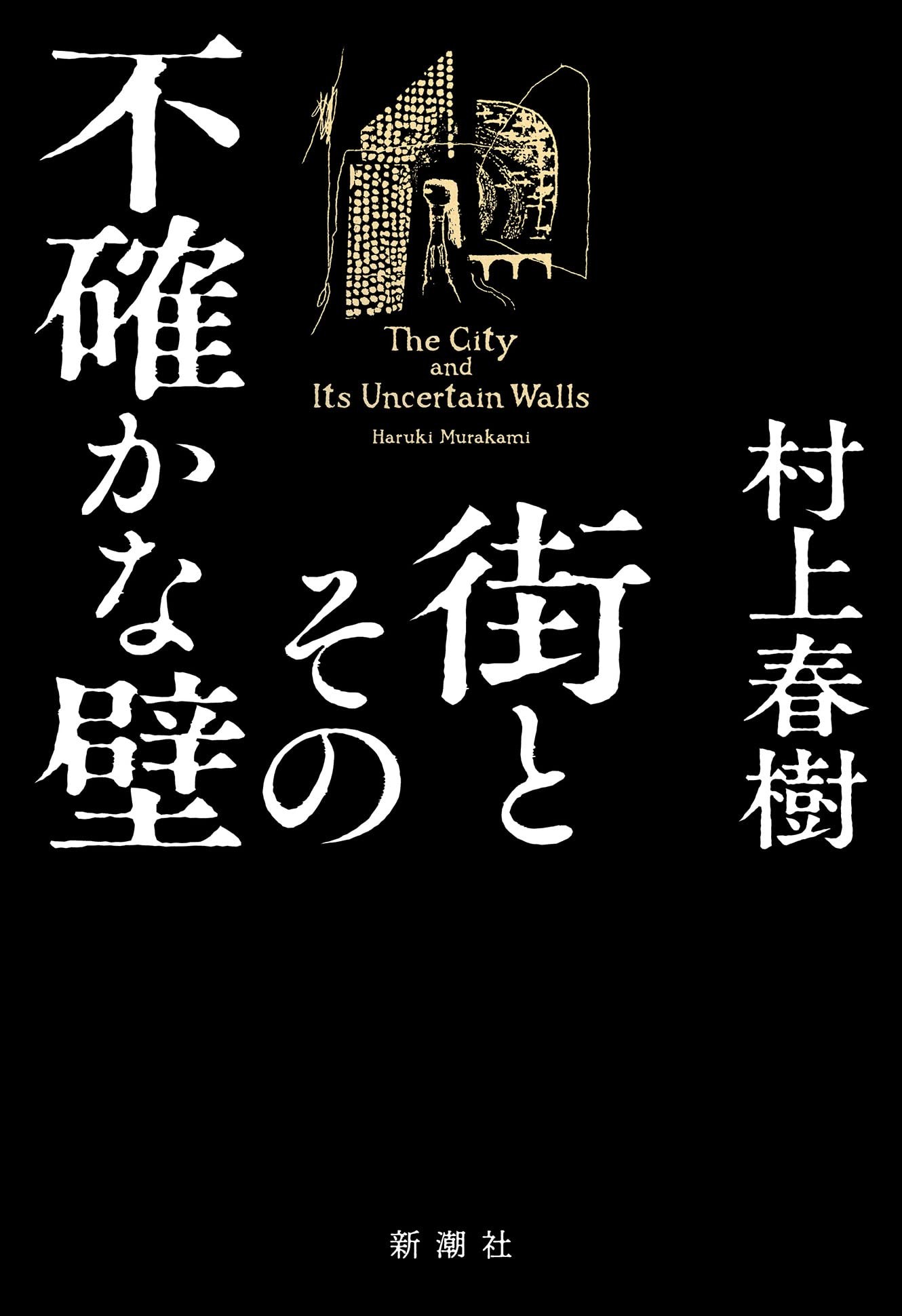
※本稿は物語の展開や結末などに関するネタバレはないものの、内容の細かい部分に触れている箇所があるため、『街とその不確かな壁』を読むことを楽しみにしている方は、ぜひ読後にお読みください。
村上春樹は過去の自身の作品がインスピレーションとなり、長編小説となることが多い作家だ。
鼠三部作と呼ばれる初期の『風の歌を聴け』『1973年のピンボール』『羊をめぐる冒険』、そして『ダンス・ダンス・ダンス』は主人公がすべて同じ“僕”である。中編『街と、その不確かな壁』をもとに書かれたのが『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』で、そこから取り除かれた部分を再構築したのが『国境の南、太陽の西』だ。『螢』は『ノルウェイの森』に、『ねじまき鳥と火曜日の女たち』は三部作の大長編『ねじまき鳥クロニクル』(『加納クレタ』の登場人物も出てくる)へとストレッチされた。さらには『人喰い猫』のエピソードが出現する『スプートニクの恋人』、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』と『ねじまき鳥クロニクル』で描かれた世界とのつながりを想起させる『海辺のカフカ』、1995年に起きた「地下鉄サリン事件」の被害者や関係者にインタビューした『アンダーグラウンド』『約束された場所で―underground 2』を思わせる『1Q84』なども生まれている(『女のいない男たち』所収の『木野』で描かれた世界は『騎士団長殺し』との共通点を感じる)。
それだけに「村上春樹の新作長編小説が出る」というニュースが出たとき、「これまでの作品が変奏して新たな物語になるのかもしれない」と期待した。しかしそれはものの見事に裏切られた。なんと1980年に文芸誌「文學界」に掲載されながら、今も単行本未収録の中編『街と、その不確かな壁』が書き直され、タイトルから句点を取り払った『街とその不確かな壁』として刊行されたのだ。
「村上春樹要素ほぼ全部入り」──これが読後の感想である。書き直した「壁に囲まれた街」の話は言うに及ばず、本作にはこれまでの村上作品に出てきたモチーフやパーツ、出来事、シチュエーション、話の展開等が次々と出現する。当て所もない街歩きの後に消えてしまう女の子(ノルウェイの森)、ロウソクのある秘密の部屋(羊をめぐる冒険)、雪かき(ダンス・ダンス・ダンス)、図書館(海辺のカフカ)、死者との会話(羊をめぐる冒険)、耳(羊をめぐる冒険)、井戸(ノルウェイの森、ねじまき鳥クロニクル)、そしておなじみのザ・ビートルズ、ウィスキー、クラシックやジャズなど音楽に関する記述なども次々と出てくる。『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』のように、章ごとに描かれる世界が行ったり来たりもする。逆にないのは、体を重ねたり、射精をする描写だ(セックスにまつわる描写はある)。
中でも一番驚いたのが、中盤以降に出てきたコーヒーショップ店主の女性が語った蟹にまつわるエピソードだった。これは短編集『回転木馬のデッド・ヒート』に所収されている「野球場」と、短編集『めくらやなぎと眠る女』所収の「蟹」で書かれたことに類似している(この2つは同じ世界の作品だ)。もちろん登場人物や場所、設定などは違っている。しかし長年“村上主義者”として作品を読んできた人であればあるほど「蟹にあたったのではなく、蟹の身に似た白い虫を食べたに違いない」と思えてしまうのだ。また「蟹」には「つまりさ、塀のこっち側に落ちるか、向こう側に落ちるかみたいに」「そして僕らは塀の内側に落ちた」といった記述もある。村上本人が意図したのかどうかはわからないが、パラレルワールドであることはほぼ間違いないだろう。
本作の刊行時、村上はインタビューで「影の本体はどちらが本体でどちらが影なのか」「影というのは、僕にとっては潜在意識のなかの自己みたいなもの。僕が小説、特に長編小説を書くことは意識から離れた意識みたいなものを掘っていく作業でもある」と語っていた。物語は作家の心の奥底から湧き上がってくる清水のようなものであり、その水源と水脈は地下の深い場所でつながっている。それが時間の経過や状況で変化し、ここではない世界においては影が本体に、また本体が影となって形を変え、違う物語として表出するのだろう。『街とその不確かな壁』は過去の作品と比較してやや硬質な文体でありながら、道具仕立てや暗喩なども含め「村上春樹要素ほぼ全部入り」の集大成のような作品であった。
文=成田全(ナリタタモツ)
























