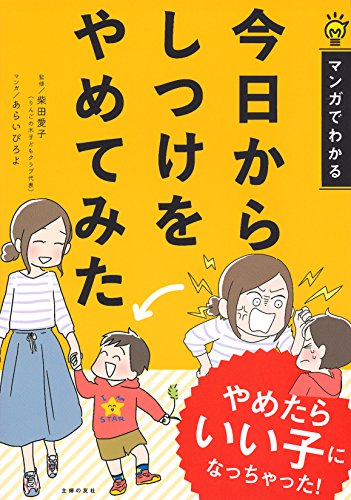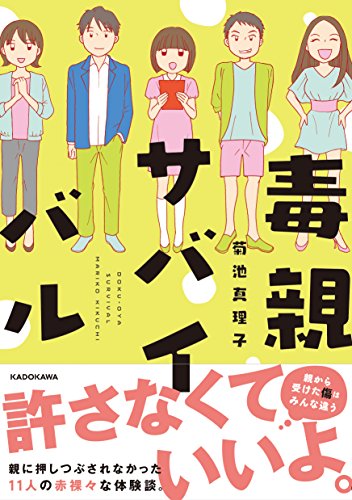【出産・子育てTOP10】令和ベイビーのために要チェック!「2019年人気記事ランキング」
公開日:2019/12/30
新しい「令和」という時代が訪れてから、子育て中、もしくは、妊娠しているという人も多いことだろう。出産・子育てに関する知識は時代を経ることに変化するため、最新の情報をチェックしておきたいもの。2019年、ダ・ヴィンチニュースでは出産・子育てに関するどんな記事が読まれたのだろうか。2019年人気記事ランキング(出産・子育て編)ベスト10を見てみるとしよう!
【第1位】「ダメ!」の代わりに使うべき魔法の言葉とは? 子どもも親もハッピーになる子育てがわかる世界的ベストセラー
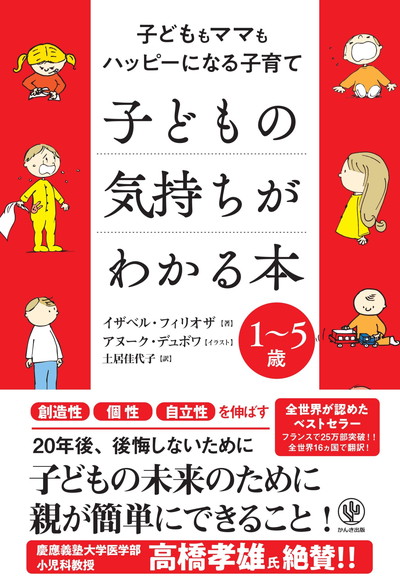
子どもの気持ちがわからない。そんなお悩みを抱える人には、『子どもの気持ちがわかる本』(イザベル・フィリオザ:著、アヌーク・デュボワ:イラスト、土居佳代子:訳/かんき出版)という育児書をオススメしたい。
本書は、フランスで25万部を突破し、16カ国以上で翻訳された世界的ベストセラー。この本を読むと、「ダダをこねる」「ルールを守らない」「ウソをつく」といった理解しづらい子どもの行為には、ちゃんと動機があったことが分かるのだ。行動の裏に隠された子どもの言い分を明らかにして、科学的に分析し、ママやパパが対応するべき簡単な方法を、著者はわかりやすく教えてくれる。
育児には不安がつきものだが、子どもの気持ちがわかると、少し気持ちが楽になる。子どもらしい行動の一つ一つは、発達や成長の証に違いないのだ。
【第2位】しつけをやめたらいい子になっちゃった! それってホントなの!?
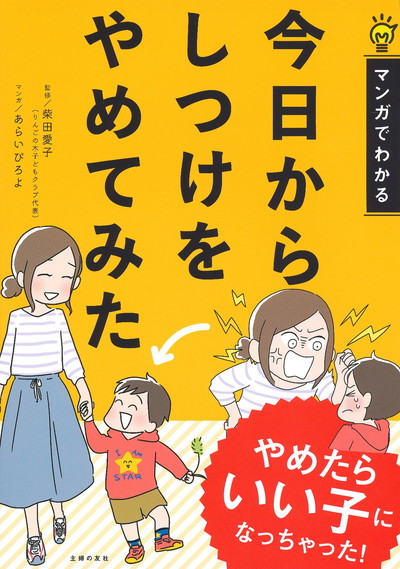
しつけは子どもにとって逆効果! そう断言するのは、40年以上にわたり多くの子どもたちと接し、『マンガでわかる 今日からしつけをやめてみた』(主婦の友社)を監修した柴田愛子さん(りんごの木子どもクラブ代表)だ。彼女によれば、特に小学校に入る前ぐらいまでの小さな子どもに、しつけは不要だという。子どもはうるさくて、汚くて、危なっかしいもの。そういう子どもらしさをしっかり体験しないと、心が育たない。親としてどうしても譲れない価値観だけを子どもに伝え、それ以外のことには目をつぶればいい。子どもには、学ぶ力、育つ力が必ずあるのだからその力を信じてあげよう。
「子どもをしつけて無理に変える必要はない」――そう考えると、気持ちがラクになるのではないだろうか。
【第3位】リアル子育てと理想のギャップに「思ってたんと違う!!」 日本全国のママの共感を呼んだ子育て絵日記
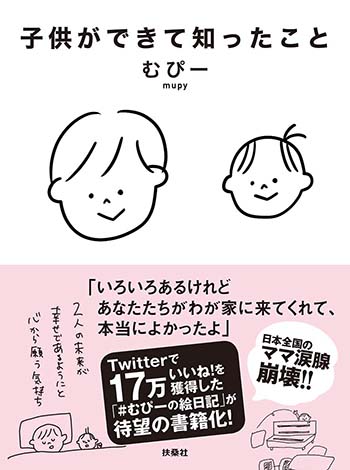
育児の大変さを美化せずに描いた『子供ができて知ったこと』(むぴー/扶桑社)は、読めばついつい涙腺がゆるんでしまうイラストエッセイ。
作者のむぴーさんはやんちゃな3歳男児とおてんばな1歳女児をもつママ。本書はTwitter上で更新していた「#むぴーの絵日記」にアップされた作品を1冊にまとめたもので、子供たちのかわいさはもちろんのこと、理想通りにはいかずイライラやモヤモヤがたまりがちな育児の難しさについても率直に描かれている。
育児をしてみると思い通りにいかないことのほうが大半で、主導権を握っている子供に親が疲労困憊させられることの連続だ。しかし、どんなに振り回されても、どんなに大変な思いをしても、我が子が幸せそうに笑ってくれたらそれだけで幸せだと思えてしまう…。この本を読んでいるとそんな当たり前の幸せに気づかされる。
楽しいときだけでなく、子育てに疲れた際や子供との向き合い方が分からなくなったときにもそっと寄り添ってくれる1冊だ。
【第4位】「家族の絆」を押し付けないで。毒親から逃げ延びた元・子どもたちの体験談
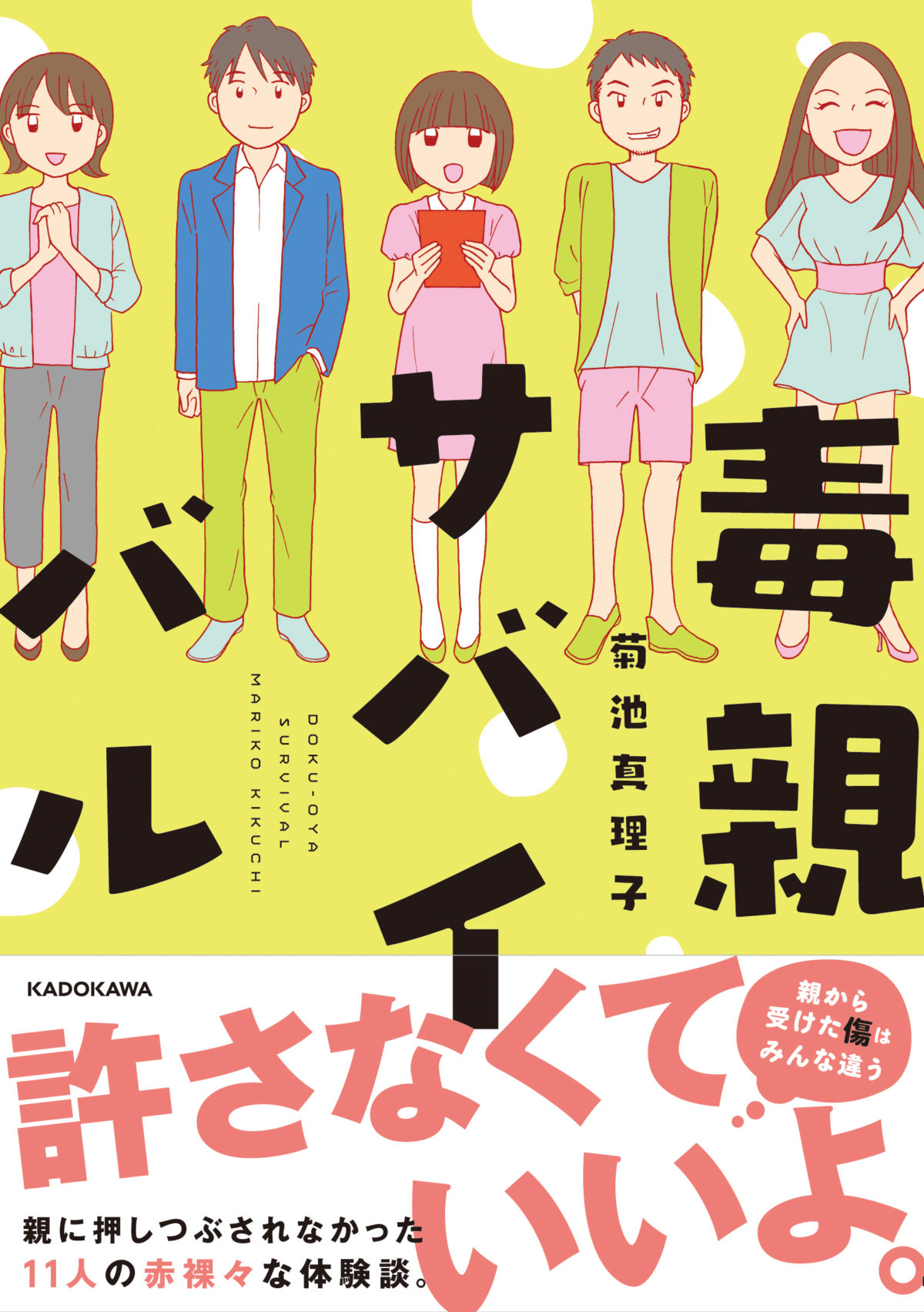
すべての家庭が愛に満ちているわけではない。『毒親サバイバル』(KADOKAWA)は実の親に苦しめられ、それでもどうにか家から逃げ延びた元・子どもたちの体験談を集めたノンフィクションコミックエッセイ。著者の菊池真理子さんも、アルコール依存症の父に振り回されて育った毒親サバイバーの一人だ。
本書に登場する元・子どもたちの物語を読んでいくと、家庭環境はそれぞれまったく違うことに気づく。一人っ子がいれば5人きょうだいもいるし、核家族、大家族、シングル家庭と家族構成もさまざま。無力だった子どもが成長した後にどんな風に自らの傷に向き合い、自分を立て直そうと奮闘してきたのか。親と決別した後の人生をどう生きるか。内容はずっしりとヘヴィだが、柔らかな線とマンガだからこその軽やかさ、そして何よりも「子ども」側に一貫して寄り添う著者の眼差しの優しさに救われる。
家族との関係に悩むすべての元・子どもたちに希望を与えてくれる一冊だ。
【第5位】「こんな子じゃなかったらよかった」自閉症の息子を愛せるようになるまでの17年間の軌跡
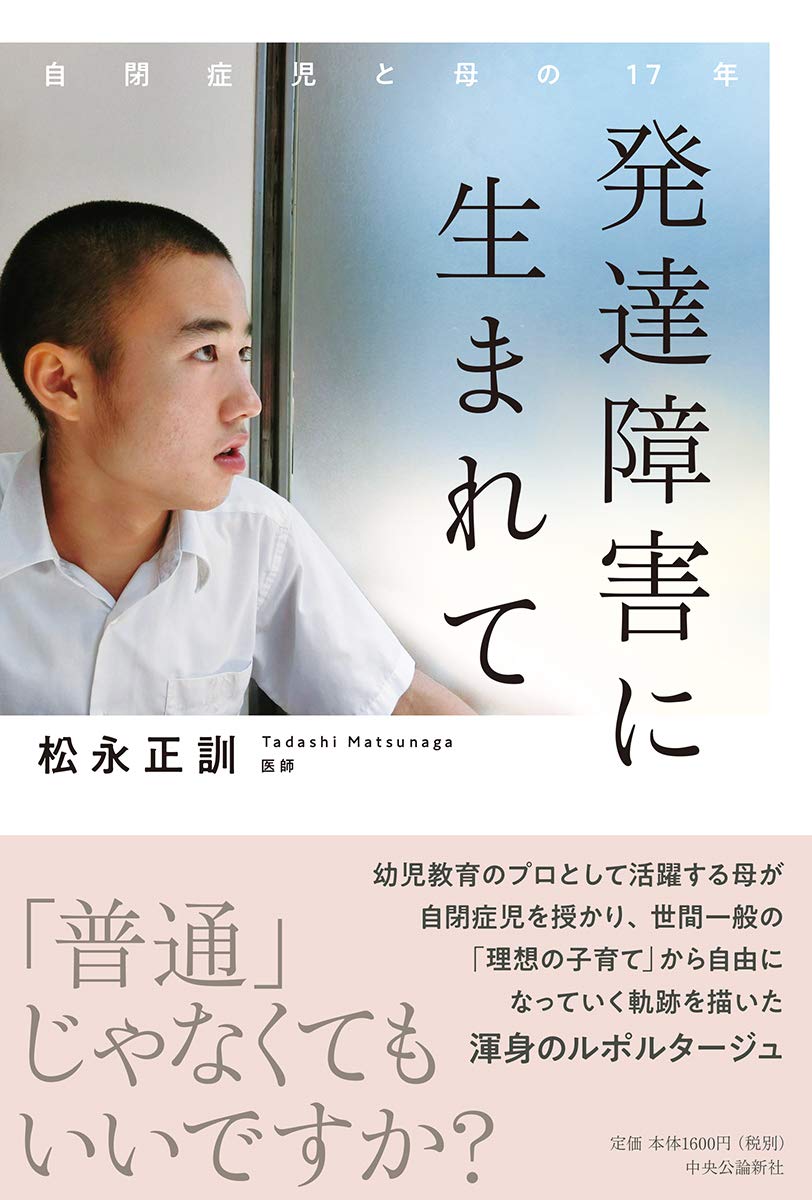
もし我が子が発達障害と判明したとき、大切に育てる覚悟を持てるだろうか。一生懸命愛情を注げるだろうか。『発達障害に生まれて』(松永正訓/中央公論新社)は、自閉症児を授かった母親が愛する息子を必死に育て上げた17年間の軌跡を記した、渾身のルポルタージュ。
本書を読むと胸がぎゅっとしめつけられる。世界で一番可愛くて大切で、立派に成長してほしい息子が、他人に関心を持てず、社会生活で困難を強いられる自閉症として生まれた。その悲しさと不安と、行き場のない怒り。現実を受け入れられない母親のはりさけそうな思い…。泣き叫んで子育てを投げ出したくなることだってあるだろう。それでも共に人生を歩めば、子どもたちの成長を感じる瞬間がある。やがて愛情だって芽生え始める。
そこには、障害も何も関係ない、“子育ての喜び”という普通がある。もし我が子が発達障害を抱えていたとき、その子育てに苦しんだとき、この母子の軌跡を読んでほしい。親子が幸せに暮らすヒントが絶対に隠されているはずだから。
【第6位】アレルギーのない子にするために、妊娠中・赤ちゃんのころにやっておきたいこと
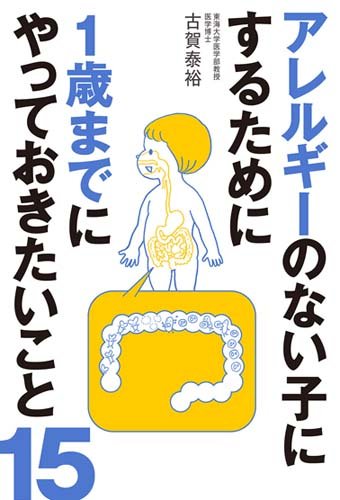
わが子のアレルギーを解決、緩和する手立てがあれば、親としては誰もが知りたいところだろう。『アレルギーのない子にするために1歳までにやっておきたいこと15』(古賀泰裕/毎日新聞出版)によると、アレルギーは腸内の環境と密接な関係があるという。赤ちゃんが生まれてから1歳までの間に腸内にビフィズス菌がたっぷりとあるようにしておけば、腸内環境が整い、アレルギーの発症が予防できるというのだ。
本書ですすめているひとつの方法は、積極的に母乳を与えること。特に母乳に含まれるオリゴ糖はビフィズス菌にとって重要なエネルギー源であり、ビフィズス菌の数を増やす働きがあるため、母乳を飲ませられない場合はオリゴ糖入りの人工乳でも可。そうすれば、わが子のアレルギー発症のリスクを下げることができるらしい。その他にも手立てはたくさん。アレルギーリスクを低減させるための方法が、この本に詰まっている。
【第7位】平均38歳でも約4カ月で妊娠! カリスマ治療院の奇跡的な妊活メソッドの秘密は、整体、漢方薬…そしてもう一つは?
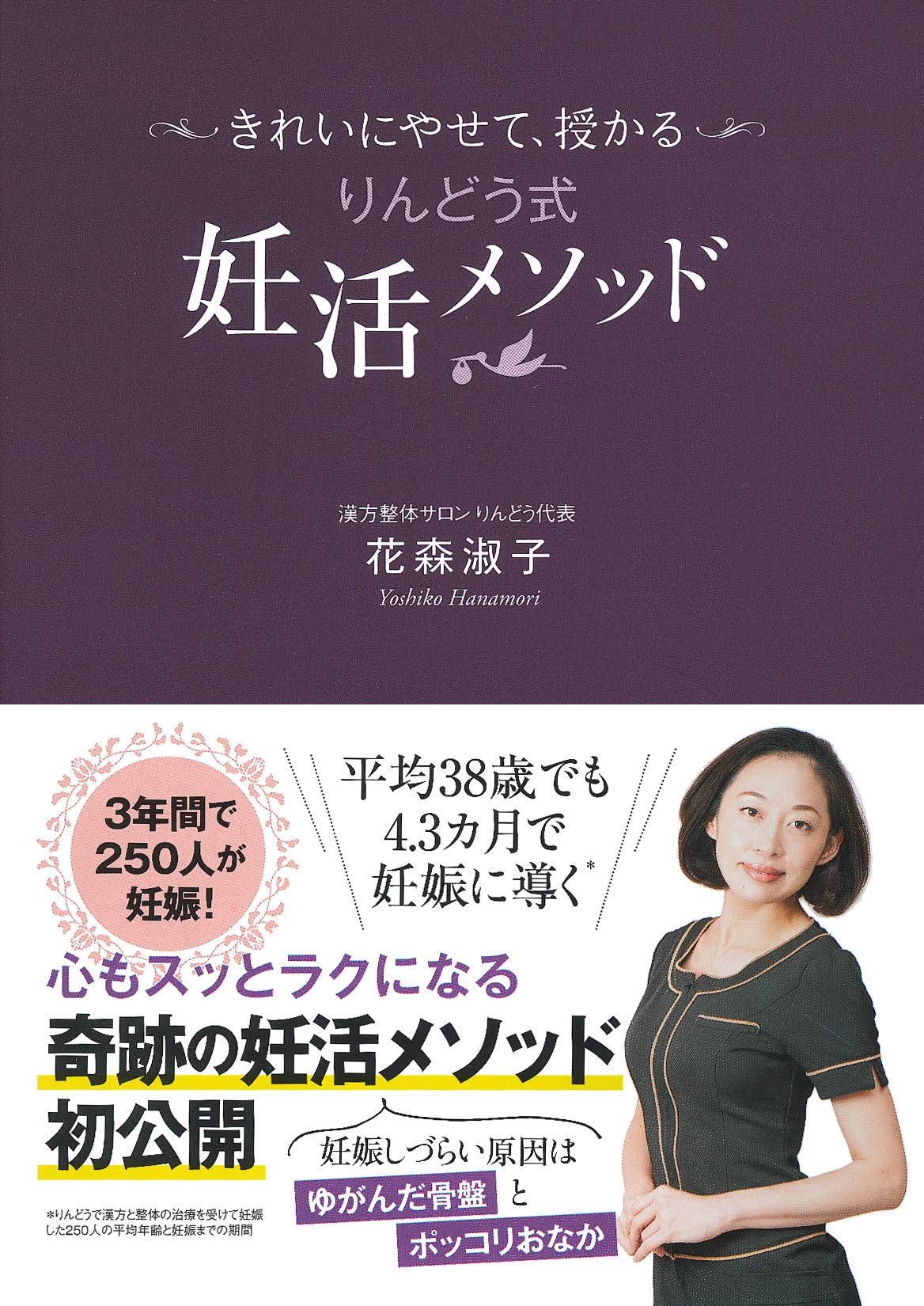
「赤ちゃんが欲しいのに、なかなか授からない」と悩んでいるカップルは、年々増加しているらしい。そんな中、整体と漢方薬と生活指導によって、高い妊娠率を誇る治療院があるという。それは漢方整体サロン「りんどう」。その代表の花森淑子さんの著書『きれいにやせて、授かる りんどう式妊活メソッド』(主婦の友社)は、妊娠しやすい身体作りの方法を教えてくれる本だ。
その一番の基本となるのは、花森さん流の「思考のレッスン」。すべての物事に対してプラスの言葉を口に出すというものだ。感情も思考も変えなくていい。ウソの言葉でも、言葉にはプラスの力があり、その言葉を耳にした自分が、気持ちをプラスにすることができるのだ。
すると、言葉を変えるだけで、自律神経が整い、血流がよくなり、免疫力も高まってくる。その他にもこの本では自分でできる骨盤調整法や、漢方的に体を整えるメソッドなども紹介。なかなか妊娠しないと悩むカップル必読の一冊といえそうだ。
【第8位】「叩く、どなる」のしつけは子どもの問題行動に… 子どもの気持ちに寄り添った「声がけ」とは?
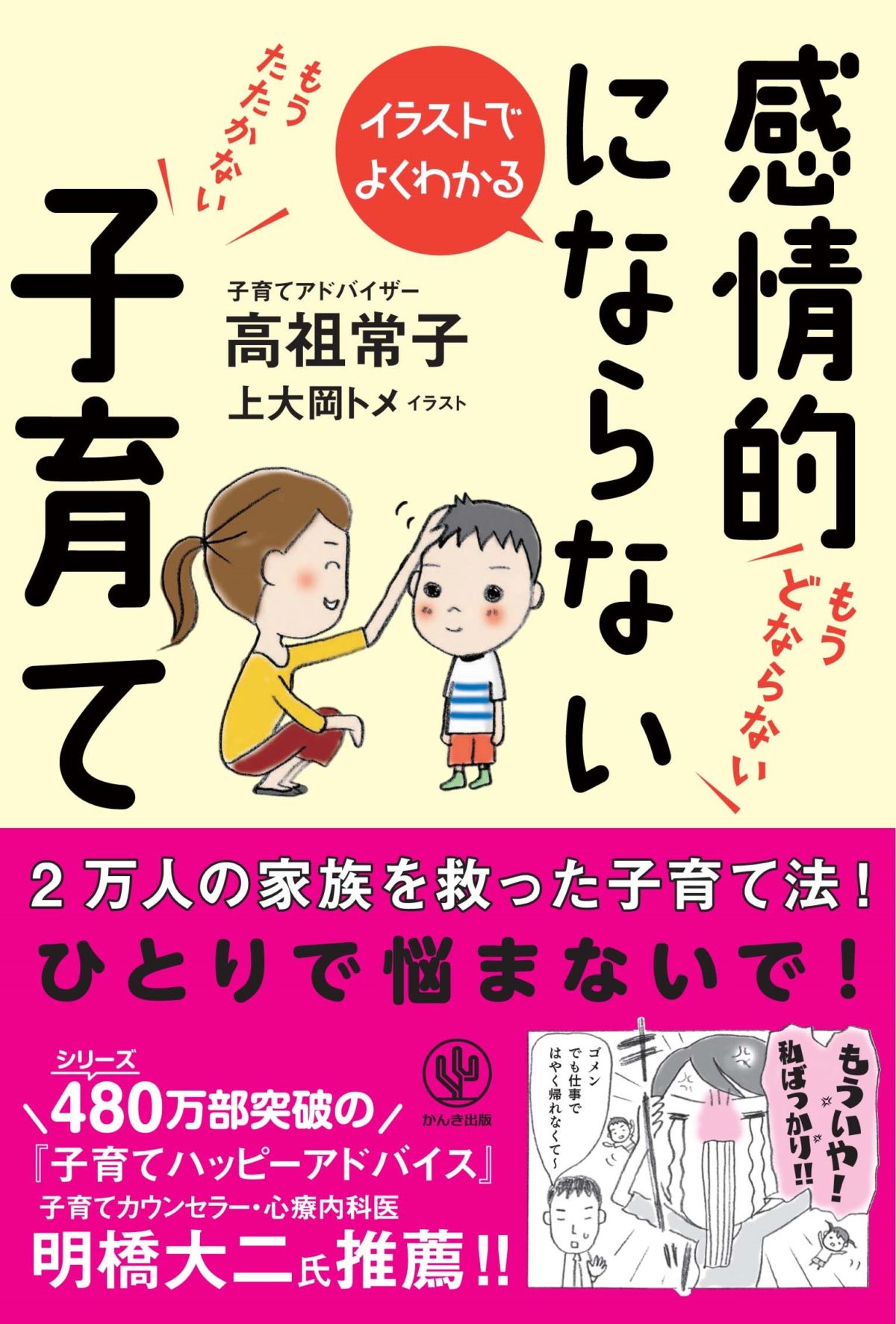
多くの親はできることなら愛情をかける子どもを叩くことなく育てたいと願っているだろう。だが、時には感情的になってしまうことも…。そんな時は「どならない、叩かない子育て」を広めている高祖常子さんの著書『イラストでよくわかる 感情的にならない子育て』(かんき出版)が参考になるかもしれない。
しつけのためと思って叩いても、低年齢の子どもには通じない。そこに残るのは、“大好きな親から叩かれた”という体や心の痛みだけだ。カッとしそうになった時、子どもにすぐに当たるのではなく、まず、親自身が気を紛らわすなどしてクールダウンすることが大切。
親の気持ちが落ち着いた後は、子どもがどうして親を怒らせるような行動を取ったのか、子どもの気持ちになって考えてみる。そうすれば、より子どもの気持ちに寄り添った声がけができる。「どならない、叩かない子育て」が実現できるのだ。
【第9位】赤ちゃんの時、おちんちんケアしないと大変なことに…!? 知っておきたい、男の子の育て方
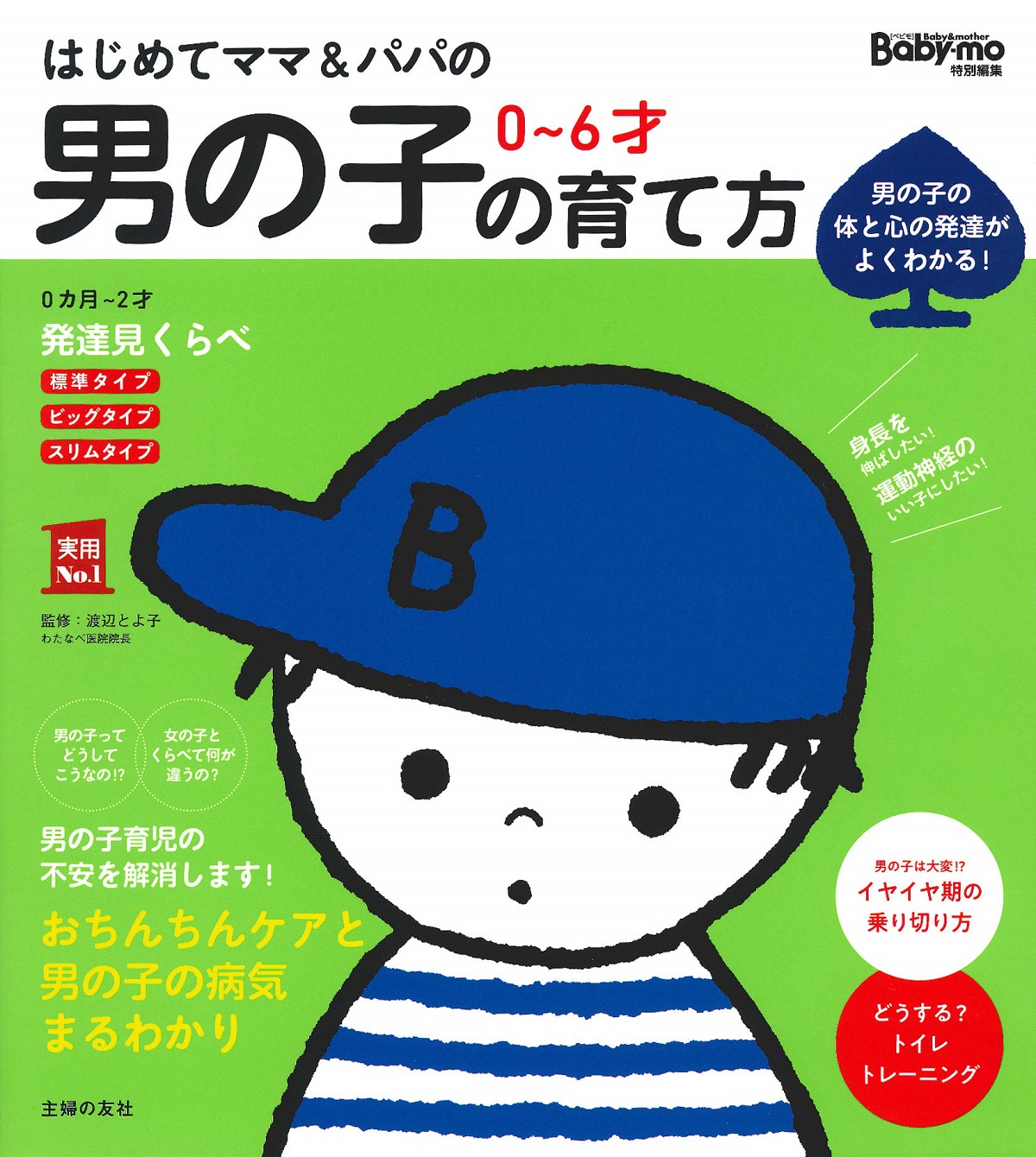
男の子はどう育てれば良いのだろうか。『はじめてママ&パパの 0~6才 男の子の育て方』(渡辺とよ子:監修/主婦の友社)を読めばその悩みは少しは軽減するかもしれない。育児本というと、保育者や教育者の体験をもとに執筆されたものが多いがこの本は、医師や学者による最新の研究データをもとにまとめられた書籍。ソースのない情報に惑わされることなく、男の子と向き合うことができる。
例えば、ママにとってもパパにとっても悩ましい男の子のおちんちんの扱い方。本書では「おちんちんはケアした方がいい」とし、その方法について、豊富な図解と写真でわかりやすく解説している。
その他、イヤイヤ期の乗り越え方や運動神経の伸ばし方、思春期前の反抗期への対処の仕方まで、この本では幅広い情報を掲載。愛しき男の子の成長をじっくりと楽しめる一冊をぜひ参考にしてみてほしい。
【第10位】話し始めると1時間止まらない…発達障害の子は何を考えている? 親子がたがいに理解して幸せになる秘訣
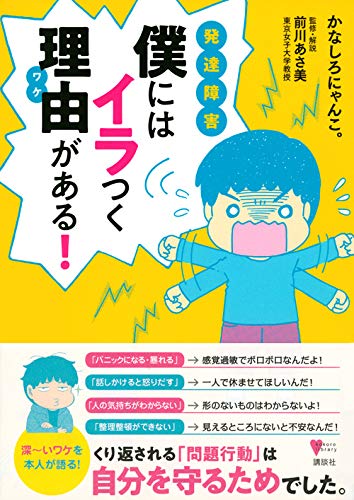
子どもの発達障害を疑う親御さんもいるかもしれない。『発達障害 僕にはイラつく理由がある!(こころライブラリー)』(かなしろにゃんこ。:著、前川あさ美:監修・解説/講談社)は、発達障害について、イラスト解説やストーリー漫画を多用しながら、その特性や問題の解決策をわかりやすく紹介する1冊。
登場するのは、著者である母親と、現在20歳の息子。成人した我が子から、母親が「小学生の頃に感じていたこと」を聞きだしていくという異色のコミックだ。発達障害の当事者である息子が語る子ども時代のエピソードは、誰にとっても興味深い。大人から見ると心配な子どもでも、自分なりに考え行動しようとしている、その事実がよくわかる。
また、母親の対応のなかで「とても助けられたもの」についても話してくれるのも参考になる。どうして何時間も話し続けてしまうの? どうして感謝や謝罪ができないの? どうして授業中教室にいられないの? その回答は眼から鱗が落ちるものばかり。子どもの発達障害に悩む親たちにとって驚かされるものばかりだ。
集計期間:2019/01/01~2019/12/20
文=アサトーミナミ