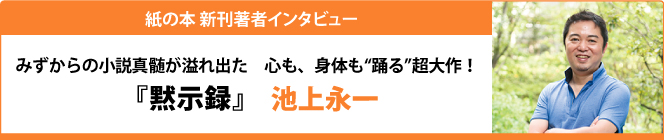みずからの小説真髄が溢れ出た 心も、身体も“踊る”超大作!
更新日:2013/12/4
「こんなことは小説を書いていて、初めてなのですが、了泉は僕自身なんです。雲胡にも3割くらい自分が入っている」
天真爛漫な明るさを持ちながら、欲しいものを手に入れるためには身も汚すし、あくどい手も使う。了泉は、池上作品には、見られなかったダークな部分を秘める主人公。それを生じさせたのは“踊り”だったという。
「小説のなかで人物が踊るためには、歌詞を読み解き、完全に自分が理解しなければならない。魅力的な生の踊りとして見せるには、“お前の身体を通して、俺が踊る”と、自分をそのまま出すしかなかったんです。だから彼に対して嘘がつけなくなったと同時に、自分のダークサイドと向き合わざるを得なくなってしまった。了泉を書いていて、“ここまでするか? 俺”って思ったけど(笑)、それはきっと自分が潜在的に持っているもの。雲胡の真面目さ、可愛くない潔癖さも」
楽童子として琉球を旅立った二人が、薩摩、難波、富士の山……と、ロードノベルの楽しみもたっぷりに江戸上りをする間も苛烈に争う花形の座。殺気にも似た心をつかい、型を追いかけていく了泉、一糸乱れぬ美しい型から、心を求めていく雲胡。だが、玉城朝薫が新たな芸能の発露を二人に委ねたことから、了泉と雲胡のベクトルは次第に絡まり合い、ひとつの様式美を生み出すものへと変化していく。
「僕は了泉と同じ、心優先のタイプで、デビューした頃は小説に型なんか必要ないと思っていたんですね。でも、型がないものというのは、剥き出しすぎて、暴力的なもの。ここで僕の言う心は、パーソナリティの心ではなく、自分の律動をつかった部分で、一番深いところにあるもの。作品の持つイデアの部分に潜り、そこの一番深い絃を鳴らしたもの。それを見せるには型が必要だった。どっちも僕にとって必要なものだった」
「了泉は“生きることは踊ること”って言っているけど、発信元の僕は“生きることは書くこと”」─本作は、舞踊を追求する二人を通し、池上さんの創作の真髄を生身のまま映し出した作品でもある。
物語に流れる昂揚感を生み出す本能とは?
数十年を追いかけていく物語のなかで、了泉が味わう壮絶な“天国”と“地獄”。そこにはみずからの作家人生も投影されているという。
「作家として成り立つまで僕は時間がかかったタイプで。いくつになっても、まったく売れず、やめる選択肢もあったけど、せっかく見つけた自分の心を出せるメディアを捨てることはできなかった。小説を手放したら、生きていられないという本能を持っていたんだと思います」
追い詰められ、自分の中に見た地獄。そして気付き。“組踊”誕生の物語でもある本作は、了泉と雲胡に一生に一度あるかないかの奇跡のような気付きをもたらし、読む者のカタルシスを刺激していく。
「僕は踊りをやっていないし、古典芸能に詳しいわけでもない。けれど、物語が持つ要素にきちんと和音を鳴らしていくことで、それは突然、登場人物に、僕に響いてきました。心と身体をつかっていくことで」
“人には言葉と同じように踊る本能が備わっている”。ラストに近い、ある象徴的な場面に重ねられる言葉─実は「無意識に書いちゃっていた(笑)」という、それは、池上さんの小説、そして読む者に見せてくれる世界そのもの。言葉を追っていくうちに湧きあがり、どこへ連れていかれるかわからない期待と不安が躍動する池上作品の昂揚感は、まさに“踊り”。だから惹きつけられ、心が動く。そのるつぼのなかで、宗教、精神性の域にまで流れ込んだストーリーは、“月しろ”の使命をひも解きながら、張り巡らせた様々な糸を鮮やかに収束していく。
「『テンペスト』が外圧の嵐だとすると、『黙示録』は心の嵐を描いた作品。文化が爛熟した、きらきら輝いた時代なのに、ここに出てくる人たちはまるで罰を受けているように悩み、苦しむ。それは何かを生み出しているから。そうして生まれたものは美しい。踊りは瞬間に生まれ、消える、人の記憶のなかに止まるものだけをつくろうとする独特の美意識がそこにはある」
それは圧倒的な密度で心に刻まれる、本作の美しさでもある。
取材・文=河村道子 写真=首藤幹夫
『黙示録』
池上永一 KADOKAWA 角川書店 1890円
18世紀前半、琉球王国に了泉という貧しい少年がいた。病に侵された母を抱える彼は、王府の踊奉行・石羅吾に拾われ、踊りの才能を伸ばしていく。一方、王を支える“月しろ”となる存在を探す蔡温の目にも留まった了泉だったが……。敵対、陰謀……すべての運命を呑みこみ、ひとりの天才舞踊家が到達するのは──。