生誕100年 安部公房の代表作『砂の女』ってどんな話? 絶えず砂が降り注ぐ穴の中の家に閉じ込められた男の救いとは
公開日:2024/4/3
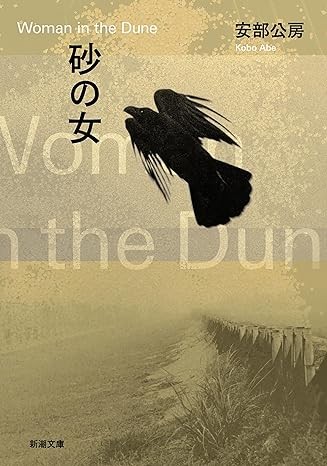
2024年は小説家・安部公房生誕100周年。本記事でご紹介するのは、同氏を世界的に有名な作家に押し上げた『砂の女(新潮文庫)』(安部公房/新潮社)です。
玉手箱、打ち出の小槌、桃……。時代を越えて読まれる物語には何かしらシンボルがあります。本作のシンボルは「砂」です。まずは、あらすじをご紹介しましょう。
ある8月の午後、31歳の教師・仁木順平は新種の虫を採集するために砂丘にある部落の一角に向かう。帰りのバスがなくなってしまったところ、寡婦が一人で住んでいる民家に泊まるよう案内される。アリ地獄のように、穴の中にあるその家に縄梯子で下りていく仁木。一夜明けると、縄梯子は取り外されていて、仁木は閉じ込められてしまう。女は砂嵐で夫と娘を亡くしていたが、「女手ひとつでは暮らしていけない」という理由から、部落の策略で女のパートナーとして仁木が乱暴にもあてがわれた。仁木は脱出を試みるも失敗。こうして、女との奇妙な共同生活が始まる…
本作において砂は「流動性」の象徴として描かれています。砂漠・砂丘というのは乾燥しているから植物が根づきにくいのではなく、砂というものが絶えず流動するために「不毛」という結果が生まれるのだと本作の冒頭で説明されています。そして仁木はその流動性が「年中しがみついていることを強要し続ける現実」と比べて、なんと理想的なのだろうと憧れにも近い感情を抱きます。
家というのは通常、不動産という言葉が示す通り、番地も敷地も決まっている非流動的な存在です。穴の中の家に、不運な境遇もあってこもってしまっている女もまた、非流動的な存在です。
「砂がねえ……」と、女もいっしょに、天井に目をやりながら、「振ってくるんですよ、どこからでも……一日掃除しないと、一寸もつもってしまいます。」
「屋根がこわれているのかな?」
「いいえ、まっさらの葺きたての屋根だって、あなた、砂はどんどん入り込んで来てしまいますよ……本当に、おそろしいったらありゃしない、木食い虫よりもたちがわるいんだから……」
物語が希望を示唆しているように感じるか、皮肉を表現しているように感じるか。その度合は読者によって大きく異なるだろうと思います。
希望が見出せたとするならば、「順応」というキーワードが物語を読み解く基軸となります。おそらく多くの人は、アリ地獄のような砂まみれの場所で生きたくはないでしょう。しかし、順応することによって、そうした環境の生活の中に喜びを見出すことも人間の精神には可能です。女の「流動性」(出産をする等の選択肢)が仁木の順応によって回復される。そうすると、仁木が「小さな救世主」となった、希望を秘めた話に見えるでしょう。
筆者は、「順応」というキーワードも思い浮かびながらも、痛烈な皮肉として本作を受け止めました。こちらの読み解き方の場合、「関心」というキーワードが物語を読み解く基軸となります。
教師である仁木は考え、考え、考え続けます。
その思いつきは、かなり唐突にやってきた。だが、なにも、時間をかけてねり上げた計画だけが、首尾よく成功するとはかぎらない。そこにたどりつくまでの道すじが、意識されていないというだけで、突然のひらめきにも、ひらめいたなりの、もとでがかかっているのである。
せっかく考えたのに、むしろ、考えたがゆえに、仁木の身には困難が重なります。終盤で仁木はある発明のタネを生みます。しかし、そこに乗っかって一緒に考えてくれたり、その考えに興味を持ってくれたりする人がいないと意味がありません(いかにも「いなそう」な感じで終わるように筆者には見えます)。本作は東京オリンピックの2年前の1962年に書かれましたが、急速に都市化が進み、人々の興味が成長・躍進にとらわれて、個人の心や存在自体への関心が薄れてきていたことでしょう。そんな急速な社会変化による歪みが、砂の流動性の奥底にこめられている作品です。
文=神保慶政
























