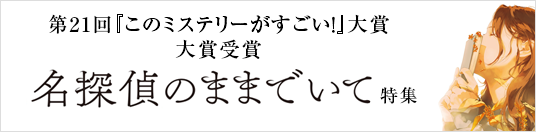「今朝は青い虎が入ってきたんだ」介護を受けながら暮らす祖父は、孫の楓が訪ねるといつも幻視の話ばかり/名探偵のままでいて①
更新日:2023/1/30
語るだけ語って満足したのだろう。
祖父の両の瞼が、ゆっくりと閉じていく。
日がな一日、祖父はこの部屋の電動式のリクライニング・チェアーに座っている。
長身痩軀の祖父に合わせて大きめのサイズを選んだのだが、想像以上に座り心地が良かったらしく、ほとんど椅子から離れないようになってしまったのは大きな誤算だった。
傍らのサイドテーブルには、移動に欠かせない木製の杖が立てかけられている。
だが、杖を勧めてくれたケアマネージャーからは、用を足すときはお使いになるのに本棚から本を選ぶときは面倒くさがってまるで使ってくださらないのよ、転倒が心配だわ、とため息まじりの愚痴を聞かされていた。
(今でも本が好きなんだ。でもおそらく内容は――)
ほとんど頭に入ってきていないんだろうな、という寂しい想像がよぎる。
本で埋め尽くされた書斎に、饐えたインクの香りが漂う。
それは、楓が好きな神保町の古本屋街を思い起こさせた。
気付くと窓から差す木漏れ日が迷彩模様となり、祖父の寝顔に落ちていた。
高い鼻梁と目尻に刻まれた皺が、七十一歳だというのになぜだかしみがまるでない顔の上に複雑な陰影をかたどっている。
昔に比べると顎や頰の肉は削げ落ちているが、それが逆に彫りの深さを際立たせていた。
広い額の真ん中から分けられた毛量たっぷりの長髪は、七割ほどの白髪が残りの黒髪とグラデーションを成していて、これまた古代ローマのコインに彫られた皇帝のような立体感を醸し出している。
孫娘目線という贔屓目を抜きにしても、堂々たる容貌に思えた。
(モテたんだろうな、きっと)
楓は、ずり落ちていたブランケットを祖父の細い首元までそっと掛け直した。
掃除を終え、石鹼の香りの抗菌スプレーを書棚の本に当たらないように注意しながら噴霧すると、もう理学療法士がリハビリのためにやってくる時間になっていた。
この抗菌スプレーは、単に部屋を清潔に保っておくためだけにあるのではない。
祖父は頻繁に、蚊のようなたぐいの小さな虫の幻覚を見る。
そうした場合、即席の〝殺虫剤〟の代わりにもなるのだ。
(じゃあね、おじいちゃん)
(――また来るね)
書斎の扉の脇には、亡き祖母から譲られたかたちとなっている鏡台があった。
経年劣化ならぬ経年進化とでもいうのだろうか。
鏡台の木目には積み重なった時間が複雑な色合いの化粧となって塗りこめられており、それが格別の味わい深さを醸し出していた。
楓は鏡台の引き出しからヘアブラシを出し、さっと髪を整えてから鏡を見て顔を作る。
(笑え)
かつては重厚な樫の木製だった書斎の扉は、そのうち祖父が車椅子に頼らざるを得なくなるときに備え、スライド式のそれにリフォーム済みだった。
楓は音を立てないようにそっと扉をスライドさせながら、碑文谷(ひもんや)の祖父の家を後にした。
<第2回に続く>