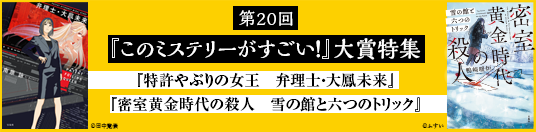クライアントのもとへ向かう弁理士の大鳳未来。電機メーカー・亀井製作所からの依頼とは?/特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来①
更新日:2022/3/3
仏頂面の皆川は、手下たちを怒鳴り付けた。
「馬鹿野郎が。呑気にYouTubeを見に来たわけじゃねえんだ!」
皆川は、黒ずんだ手でリモコンを弄びながら未来に主張した。
「亀井の奴は、俺たちの特許技術をまんまパクったテレビを製造してやがる。間違いなく特許侵害だ」
未来は皆川電工の特許を確認する。
「電源を投入したら、テレビ番組より先にインターネット接続用の画面、つまりブラウザを表示するテレビ。合っていますか」
皆川が口笛を吹いた。
「さすがは先生だ。きちんと我が社の特許を把握されていらっしゃる」
未来は小さく舌打ちをした。今回問題となった皆川電工の特許権は、筋が良すぎる。完全にこちらの分が悪い。
縋る目をする亀井に対し、未来は淡々と説明した。
「テレビなのに最初にインターネットを表示する。アイディアとしては昔からあったと聞きますが、大手電機メーカーから販売された例は、ほぼありません。一説によると、テレビ各局より相当な圧力があったとか」
皆川は、リモコンを手の上でくるくると回した。
「俺たち皆川電工はな、圧力なんて気にしねえんだ。そもそも、技術は多数決で決まる代物じゃねえ。現に時代を先取りして、十年前に特許も取っていた」
皆川がテレビ局から苦情を受けるわけはない、と未来は確信している。皆川電工も亀井製作所も、テレビ製造業者としての規模は極めて小さく、テレビ局が気にする規模ではない。
亀井が、すかさず反論する。
「ブラウザを表示するだけのテレビが、特許になるんですか!」
未来は淡々と答えた。
「新しければ特許されます。ただし、世間一般の基準での『新しさ』と、特許庁の審査官にとっての『新しさ』は、異次元レベルで異なります。新規性といいます。世の中の特許発明は、青色発光ダイオードの作り方のような大発明ばかりではありません」
皆川は、亀井の三倍は大きな声で反論した。
「新しいに決まってんだろ。文句があるなら、電源を点けたら真っ先にブラウザを立ち上げるテレビが、十年前に出ていたって証明してみろ」
亀井は呆然とし、口を半開きにしたまま硬直した。
亀井の心中は察しがつく。皆川電工は事実として特許権を取得している。
未来は、ハンドバッグからタブレットを取り出した。
「特許庁のデータベースで確認しました。特許庁の審査官は、皆川社長と同じ意見です」
亀井が泣きそうな表情で未来を問い詰めた。
「大鳳先生も、うちの製品が特許侵害だって仰るんですか」
未来はタブレットの上辺を確認した。現在、時刻は朝の十時半を回ったところだ。
「反論材料は探しました。例えば、十年前にそんなテレビが世の中に知られていたとしたら、特許は無効です。短時間ですが調査しました。しかし、証拠は見つかりませんでした」
亀井も必死になって反論する。
「たった一晩で、きちんと調べられるわけはありませんよね。無理に決まっています。きちんと時間をかければ、きっと見つかりますよね」
未来は正直に自分の印象を伝えた。
「十年前の特許出願です。当時の技術レベルを考えると、あと一か月調査を続けても無効の証拠は見つからないでしょう」
皆川が、わざとらしく手を叩きながら答えた。
「大した専門家だ! 素晴らしい先生を雇ったな、亀井。年貢の納め時だ。侵害品は全品処分しろ。なんなら武士の情けで廃棄処分代くらい持ってやってもいい」
未来は、皆川の手下たちの表情を見やった。皆川が歓喜している背後で、ふと皆、気の抜けた表情を見せている。
確信した。予想通り、皆川電工の従業員は全員、決死の覚悟で強面を演じている。
未来は、ジャケットの胸のポケットからスマホを取り出した。着信の履歴はない。
パートナー、姚愁林を信じて時間を稼ごう。未来は皆川を問い質した。
「皆川社長、たとえ侵害でも、あなたに認められる権利はテレビの廃棄と工場設備の取り除きまで。度を越えた行為は許されません」
煩わしい、と顔に書いてあるような表情で、皆川が答える。
「だから処分してやるっつってんだろ。どこが度を越えているってんだ」
未来は、皺とくすみの目立つ皆川の顔に、自分の顔を近づけた。
「着服は、廃棄とは全く異なるとご存じですか」
視界の隅で、皆川の手下の一人が、びくっと体を震わせた。
皆川は動じなかった。しかし皆川の澱んだ目の底に見えた、覚悟の片鱗を、未来は見逃さなかった。
皆川は静かに訊ねた。
「何の話だ、嬢ちゃん」
未来は、頭に叩き込んだばかりの情報を吐き出した。
「昨晩から朝まで、実は別の調べものをしていました。皆川さんは工場で大規模なリストラをしていますよね」
皆川がリモコンを床に叩きつけ、がちゃん、とプラスチックの割れる音が響いた。コンクリートの床に黒いプラスチックの破片と電池が散乱した。
皆川は静かに答えた。
「だからなんだ。今がどんな時代か知らねぇわけじゃねえよな」
未来は証拠のニュースサイトの記事を見せようとして、やめた。釈迦に説法だ。本人たちが一番よく知っている情報だ。
未来は概要を一息に説明した。
「リストラ直後、あなたが下請けをしている《紫禁電氣》より、大規模な製品製造発注がありましたね。あなたの工場の生産力を計算しましたが、とても間に合う数じゃない。おまけにリストラ直後で人も足りない。しかしあなたは受注した。引き受けなければ次の仕事はないからです。違いますか」
皆川は澱んだ目のまま、少しだけ、早口で答えた。
「うちの台所事情に首を突っ込まれる筋合いはねえ」
未来は、皆川を問い質した。
「亀井製作所のテレビも、皆川電工のテレビも、同じ三十二型。液晶も同じ液晶パネル製造会社から購入している。制御基板も、ほぼ同じ。違うところは、ガワと電源投入時のロゴだけ。あなたは考えた。亀井製作所の三十二型テレビを納品すればいい。皆川電工には特許権がある。だったら、亀井製作所のテレビを丸ごとブン獲って、ガワとソフトだけ入れ替えてしまえ」
皆川の手下たちが、顔を見合わせた。
皆川自身の額に脂汗が浮かんだ。
亀井が悲鳴に近い声を上げた。
「嘘だろ、酷過ぎる。認められるわけがない」
未来も即座に答えた。
「当たり前です。侵害品を没収して横流しするなんて、特許で認められる救済の範囲を超えています」
皆川の手下の一人が、力なく呼びかけた。
「社長やっぱり、いくらなんでも─」
皆川は手下を遮って怒鳴った。
「こっちはな、生きるか死ぬかを懸けてんだ! 嬢ちゃんも客商売なら分かるよな。発注ってのは絶対だ。納品できなきゃ首を吊るしか途はねえんだよ」
未来は冷徹に反駁した。
「生きるか死ぬかを懸けずに作る製品なんて、ありません。亀井製作所も同じです」
皆川は、形相を激しく変えた。
「こっちは特許があるんだ。ここにあるテレビは全部俺のもんだ。亀井、触るんじゃねえぞ。もし触ったらここの在庫、全部ぶっ壊して倉庫にガソリン撒いて火を点けてやる。ついでにてめえも地獄に道連れだ」
皆川が亀井に飛びかかろうとした瞬間、搬入口の扉が物凄い音を立てて動いた。
錆のせいで、ほとんど動かなかったスライド式の搬入口が完全に開け放たれている。
かつかつ、と音を立てて向かってくる、ほっそりとしたシルエットに、未来は覚えがあった。
とりあえず、文句を付けた。
「遅いわ、姚。ずいぶん時間がかかったわね。危うくクライアントが殴られるところだったわよ」
倉庫の中央に近づくにつれ、逆光で見えなかった顔が視認できた。
年齢は未来の一つ上、二十九歳。身長は百七十センチと、未来より十センチは高い。ヒールまで履くので見た目はさらに高くなる。真っ黒な髪をポニーテールで一纏めにし、均整の取れた顔立ちが際立つ。フレームのない眼鏡のせいで、より知的に見える。
未来を含めて二人のみの、ミスルトウ特許法律事務所のもう一人のメンバー、パートナー弁護士で所長の姚愁林だ。
姚はハスキーな声で、はっきりと断じた。
「皆川電工の弁護士の居場所がわかった。深圳だ。連絡も取れた。皆川社長は面倒な弁護士がいない間に、亀井製作所からテレビをぶん盗る気でいたんだ」
未来は、姚を睨みつけた。
「調査ありがとう。でも先に連絡をしなさい」
「連絡をしたって、殴り合いになっていたら無駄だ。未来の身を案じて駆け着けたんだ」
「殴り合いを前提にしないで」
「否認は無理だろう。あれは百パーセント、侵害だ」