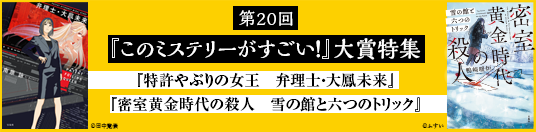今は亡き人気推理作家が作った“密室”。10年前、彼が披露した雪白館の「密室トリック」とは?/密室黄金時代の殺人 雪の館と六つのトリック①
更新日:2022/3/3
第1章 密室時代
女はひどく興奮しているようで、唾を飛ばしそうな勢いで『私』に捲し立てていた。かと思えば、妙にしんみりする時もある。情緒が不安定なのだ、と『私』は思った。
聞けば、女は集団自殺の生き残りであるらしい。自殺サイトで知り合ったメンバーたちと一緒に、彼女は山奥の廃屋に向かった。そこで水の入ったグラスを人数分用意する。そのグラスにアコニチンだか青酸カリだかテトロドトキシンだかを入れるのだが、実はそのグラスの中の一つには毒の代わりに睡眠薬が入っている。
「つまり、どういうことかわかりますか?」と女は言った。「一人だけ生き残るということです」
それはそうだろうな、と『私』は思った。
「そしてその睡眠薬を飲んだのが私です」
それはそうだろうな、と『私』は思った。
「まったく、面倒なことになりました。みんなで仲良く死ぬつもりが、私はこんなシケた場所で今もコーヒーを飲んでいます」
「良かったじゃないですか」と『私』は言った。「命は大切ですよ」
女は、にやりと笑った。
「あなたがそれを言いますか?」
『私』はコーヒーを一口飲んだ。まずいコーヒーだ。自分で入れたコーヒーだけど。どうやら『私』には、コーヒーを入れる才能はないらしい。
というよりも、『私』に得意なことなど一つしかないが。
密室を─、作ることだけ。
「とにかく、私は生き残った」と女は言った。「だから私は、あなたに会いに来たのです」
女は『私』の顔を指差す。
「『密室使い』さん、あなたに」
*
「香澄くん、ポッキー食べる?」
車窓の景色を眺めていると、向かいの席に座る朝比奈夜月がポッキーの箱を差し出してきた。僕は「食べる」と言って、彼女の手にした箱から一本摘む。それをくわえながら、再び窓に視線をやった。列車と同じ速度で十二月の景色が流れていく。雪は積もっていないけれど草木が枯れてうら寂しい。何となく、アンニュイな気持ちになる。
「何、アンニュイになってんだか」とポッキーを食べながら夜月が言った。「もしかして詩人を目指してるの? 毎日寝る前に自作の詩をノートに書き綴るタイプなの?」
とりあえず、こいつが詩人をバカにしてるのは伝わった。僕はあしらうように言う。
「詩なんて、中学の時以来書いてないよ」
「中学の時は書いてたんだ?」
「中学生は普通書くだろ」
「普通の基準がわかんない。香澄くんの基準と世間の基準を比べるのはやめてほしい」
何故だか怒られてしまった。ちなみに香澄というのは僕の下の名前で、名字は葛白。葛白香澄。だから小学生の時は一時期『くずかす』と呼ばれていた。『キムタク』と同じ要領なのだが、なんか全然違っていた。しまいには学級会で、先生から『葛白くんを、くずかすと呼ぶのはやめましょう』と皆がお叱りを受けたほどだ。僕はその学級会の間、とても悲しい気分だった。そのことを夜月に話すと、「『葛』に『かすみ』なわけだから、何だか俳句の季語っぽいよね」とよくわからない励まし方をしてくれた。
そんな夜月は僕の幼なじみで、二十歳の大学二年生─、高校二年生の僕より、三つ年上になる。髪の毛は肩までの長さの淡い茶色のゆるふわで、顔立ちはかなり整っている。「一日に七回スカウトされたことがある」というのが彼女の鉄板の自慢だった。そのうち四回はキャバクラで、二回は美容室のカットモデルだったが。「でも、残りの一回はちゃんとした芸能事務所だったんだよ」彼女はそう主張する。「おしかったなぁ。あっ、でも私、気まぐれな猫みたいな性格だから。やっぱり芸能界みたいな、しがらみの多い仕事には向いてないんだよね」
確かに夜月は気まぐれな猫で、そして芸能界には向いていないだろう。というより、働くことに向いていない。彼女には、どんなバイトでも一ヶ月でクビになるという特技があった。
そんな気まぐれな猫は、ポッキーを食べながらスマホを操作する。そして「あっ」と声を上げた。
彼女は、まじまじとスマホを眺めて言った。
「ねぇ、香澄くん、また密室殺人が起きたみたいだよ」
「えっ、マジで?」
「うん、青森で。県警刑事部の密室課が現在捜査中だって」
僕は自分のスマホを取り出し確認する。どうやら、マジらしい。相変わらずこの国では、密室殺人が氾濫している。
「妙な時代になったものだよねぇ」とポッキーを食べながら夜月が言った。
まったくだ、と僕は思う。一つの殺人事件を切っ掛けに、世の中は大きく変わってしまった。三年前に起きた日本で最初の密室殺人事件。それ以来、この国の犯罪は密室を中心に回っている。
*
目的の駅は無人駅だった。僕と夜月は誰もいないホームで大きく伸びをする。関節がポキポキと鳴った。家を出てから三時間─、それなりに長旅だった。
「それで、今日泊まる宿は?」
「えーとね」夜月に訊ねると、彼女は歩きスマホをしながら答える。「ここから車で山の中腹まで入って、そこで車道が途切れるから、そこからは歩きみたい」
「途中で車道が途切れるのか」
「そう。一時間くらい歩く」
「けっこう歩くのな」健康には良さそうではあるが。
二人で改札を抜けて、駅前のロータリーに出た。そこで一台のタクシーを拾う。
夜月はタクシーの運転手に目的地を告げた。
「雪白館までお願いします」