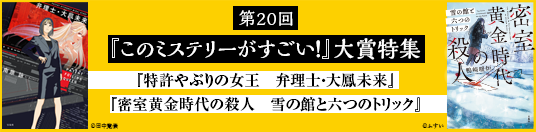今は亡き人気推理作家が作った“密室”。10年前、彼が披露した雪白館の「密室トリック」とは?/密室黄金時代の殺人 雪の館と六つのトリック①
更新日:2022/3/3

Prologue 日本で初めて密室殺人が起きてから三年が経った
男が殺されたのは三年前の冬のことで、それが日本で初めて起きた密室殺人事件だとされている。幸い犯人はすぐに捕まり、断ずる証拠も十分で、ただ現場の不可能状況をどう扱うのかだけが問題だった。
そう─、不可能状況だ。現場は完璧な密室で、警察や検察の誰一人として、その謎を解き明かすことはできなかったのだから。だからそれは事件における最も重要な事柄で、当然、裁判の争点もその密室が中心となった。
「現場が密室であったことは、重要な問題であるとは言えない」それが第一審における検察側の主張だった。「客観的な証拠に基づいて、被告が犯人であることは明らかです。ならば『どう殺したのか?』などというのは、些末な問題に過ぎません。『どうにかして殺した』のでしょう。被告が秘匿しているだけでその方法は確かに存在するはずで、現場の不可能状況が、被告の無罪を裏付ける根拠には絶対にならないはずです」
対して、弁護側はこう主張した。
「我が国の裁判制度において、本来、犯行の不可能性というのは重大な意味を持つはずです。その最たる例がアリバイで、仮に被告に完璧なアリバイがあった場合、我が国では必ず無罪になる。何故なら、被告に犯行が不可能だからです。今回の密室状況もそれと同じ─、現場が密室であった以上、それは被告のみならず、この世界のどんな人間にとっても犯行が不可能だということを意味しています。つまり現場が完璧な密室であることは、被告に完璧なアリバイがあることと同等の意味を持つということです。なのに密室の場合に限って『どうにかして殺した』『やり方はわからないが、どうにかしたのだろう』と黙殺するのは、ひどく一貫性がなく、他の刑事事件の判例と矛盾するのは明らかです」
こうして前代未聞の密室裁判は密室を中心に進んでいき、東京地裁の裁判官は結局、弁護側の主張を受け入れた。すなわち、『密室の不解証明は、現場の不在証明と同等の価値がある』─、被告に犯行が不可能であることを鑑み、無罪判決を下すことになったのだ。
第二審も一審を受けて無罪─、そして最高裁は検察側の上告を棄却した。
この判決は大きな衝撃をもって、国民へと受け入れられた。どんなに疑わしい状況であっても、現場が密室である限り無罪であることが担保される。それはある意味では、司法が密室というものの価値を認めた瞬間だった。『行うことに何の意味もない』─、数多の推理小説の中でそう蔑まれていた密室殺人というジャンルが、この判例により現実の中でその立場を逆転させたのだ。
それがこの事件における些細な『功』で、
そして『罪』はわかりやすい。地裁の判決が出てひと月も経たないうちに、密室殺人が四つも起きた。さらに翌月には七つ。密室は流行り病のように、社会へと浸透していく。
*
この三年で三〇二件の密室殺人事件が起きた。
それはこの国で一年に起きる殺人事件の三割が、密室殺人であることを意味している。