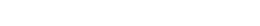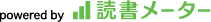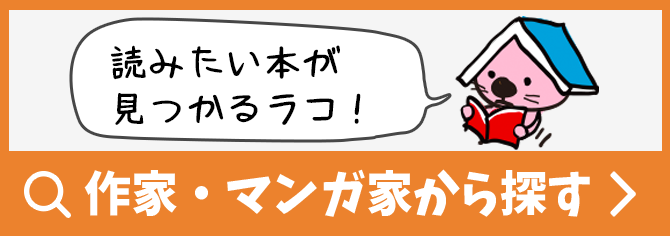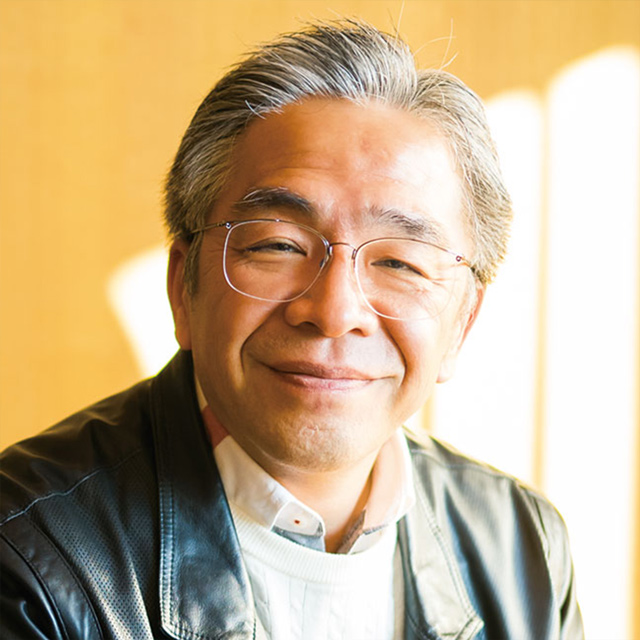顔の現象学 (講談社学術文庫)
顔の現象学 (講談社学術文庫) / 感想・レビュー
紫羊
通勤本に選んだのが間違いだった。電車に乗っているのは10分足らずなので、切れ切れにしか読めなかった。2ヶ月もかけて腑に落ちることなく読み終わってしまった。これは再読しても理解はできなさそう。取り上げられていたリルケや「箱男」は再読してみようかなとは思う。
2022/12/30
魚京童!
鷲田は考えさせるのだが、何を言っているかわからない。きっと本人もわかっていないのだろう。そんなことを思う。顔が見えなくなった。阪神大震災後もそうなのだろうが、今もそうだ。ネットを通じた感じ。しかもリアルタイムで修正することだってできる。顔を見る必要がなくなった。ノンバーバルコミュニケーションがいらなくなったこの世界で、もっと記号学を学ぶ必要があるように思う。すべては記号なのだ。それを学ばずしてやっていけないのだろう。マクロを組むように仕事をする。仕事ではないのだ。手配なのだ。調整するのがお仕事になる。
2021/07/18
ハイちん
他人の顔を見てぎょっとしたり、他人の顔を見ると落ち着かなくなったり、壁のシミに顔を見出したり、といった顔にまつわる現象ついて現象学の観点から論じていくという本。面白いのだが、怖い本だと思った。自分の顔を自分で見ることはできない。だから人は他人の顔に〈わたし〉の顔を写し取る。『表情』とは解釈されコード化された『だれでもない顔』であり、人がひげを剃ったり化粧をしたりするのも『だれでもない顔』になるための努力なのだ。模倣としての顔、他者のなかに埋没していくための〈わたし〉。そんなこと考えたこともなかった。
2016/08/22
ネムル
眼差しが出逢う時間的な出来事・現象学としての顔から、解釈・全体化の外部へと向けられたレヴィナスの非現象学的な顔を通過して、「見られることへの応答」を探る。着地点そのものは真っ当ではあるが、人類学や文学(顔文学といったら当然公房)、矢内原伊作にアウグスト・ザンダーと引用が多彩で面白い。その多彩さがそのまま顔の根源的な多様性への例証にも感じられてくる。
2020/07/21
YT
本書では前半で〈われわれ〉の内でのみ意味を持つものとして〈顔〉を考察をしていくが、レヴィナスの〈顔〉は外に現れる。 そうして意味と非意味の境界を越え続け、同一性への秩序を形成しながら〈同〉の外を目掛けて無限の彼方へ...これがレヴィナスの〈顔〉の倫理に対する著者の倫理的解釈なのだろうか? 〈顔〉が〈他者〉のまなざしを通してしか自らの〈顔〉の痕跡を辿れないのならば、ネットの発達やマスクで物理的にも顔との接触が減っている今、〈顔〉はどんどん見えなくなっていき、あげく自分すら見失ってしまう恐れがあるのかも...
2023/01/31
感想・レビューをもっと見る