ラットはカロリー制限で2倍長生きすることが判明。しかし、多くの人間はこの生活に耐えられない/最強脳のつくり方大全④
公開日:2024/4/7
『最強脳のつくり方大全』(ジェームズ・グッドウィン:著、森嶋マリ:翻訳/文藝春秋)第4回【全8回】
日々の「習慣」を変えれば「脳力」は伸ばせる! 脳トレは役に立たない。ビーガンの8割が疲れやすい理由。長時間座り続けると死亡率が上昇するなど…“自分史上最高の脳”になるために役立つ最新メソッドが詰まった決定版。本作は、運動、食事、睡眠、性欲、知力など…科学によって証明された「脳にとっていいこと」をすべて網羅できる一冊です。「習慣」を変えて「脳」も変えていく――。アメリカ大統領の健康アドバイザーも推薦する『最強脳のつくり方大全』をお楽しみください。
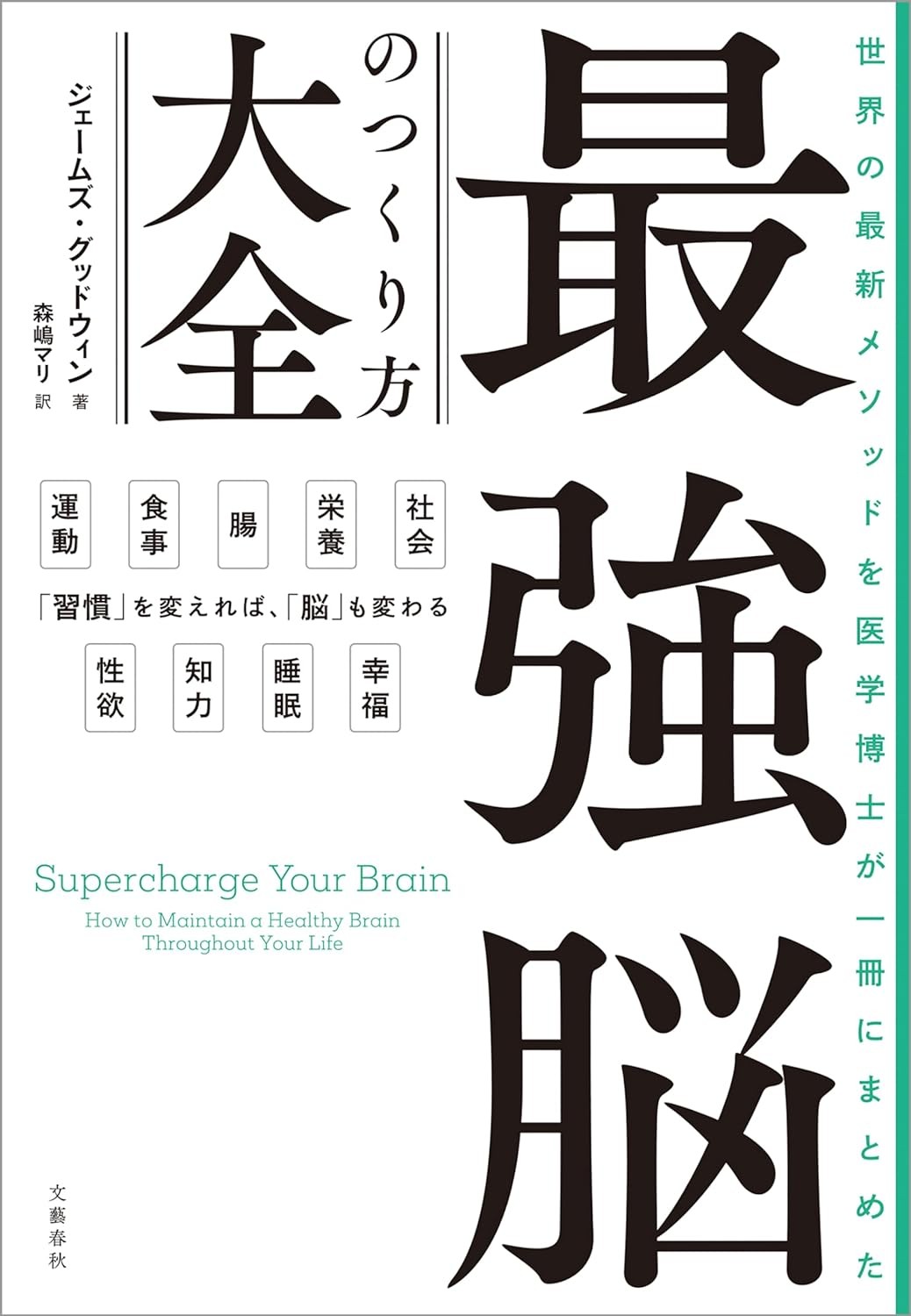
カロリー制限したラットは2倍長生きする
この章の冒頭で触れた通り、1日に必要なエネルギー量のゆうに20%が脳に送られる。たとえば40歳の女性であれば、その量は約400キロカロリーで、同じ歳の男性なら500キロカロリーとなる。どちらも、現代の典型的な朝食のエネルギー量だ。脳は毎日、1食分をひとり占めしているのだ。
1日のカロリー摂取量の制限に関する初の実験は、1944年のミネソタ飢餓実験と言われているが、それは間違いである。それより以前の1934年に画期的な論文が発表されていた。だが、それは50年もの間、ほとんど日の目を見ることがなかった。
そこには、〝餌のカロリーを制限した実験用ラットは、制限しなかったラットに比べて、約2倍長生きする〟という簡潔で確信を突く発見が記されていた。その論文を書いたのはコーネル大学の生物学教授クライヴ・マッケイだが、その名が広く知られるようになったのは、この実験結果のせいではなかった。戦時下での食糧配給量を研究し、その結果、第二次世界大戦中にパンの代用品として配給されたコーネル・パンで一躍注目を浴びたのだった。
マッケイが発見したカロリー制限の原理が、80年に及ぶ研究を経て、長生きのために、また、老化による病気の発症を遅らせるために、もっとも効果的な食事法として注目されるとはマッケイ本人には知る由もなかった。このカロリー制限は、酵母菌からミバエ、ミミズ、齧歯類、霊長類に至るまで、すべての生物に有効だ。果たして、人間にも効くのだろうか?
まずは、重要なことをはっきりさせておこう。
カロリー制限とは、痩せるためのダイエットを指す言葉ではない。栄養不良や必須栄養素の不足を引き起こすことなく、1日の平均摂取カロリーを、推奨されている摂取カロリーや習慣的な摂取カロリーより大幅に減らすという意味だ。
短期間の人体実験では、体重や血圧、血糖値、インスリン値、血中コレステロール値、中性脂肪値などの、極めて重要な健康の指針が改善されるという結果が出ている。さらに、血中や脳内のCRPなど、炎症マーカーも低下する。こういった研究では、被験者にカロリー摂取を20~30%減らすように求めた。
それによって、意図していないところで貴重な発見があった。それは、効果を得るために必要なレベルのカロリー制限に、大多数の人が耐えられないことだ。はてしない意志の力が必要で、空腹感やひもじさは耐えがたく、あまりにも辛くて惨めで、やる気をすっかりなくしてしまう。被験者はカロリー摂取量を平均して約10%減らすのが精一杯だった。
そんなことから、偽のカロリー制限の研究がはじまった。
具体的には、まず、カロリーを制限したときに細胞内で何が起きるのかを調べ、それと同じ効果を持つ物質を見つける。それを使って食べる量は変えずに、寿命を延ばし、病気にもかかりにくくするという研究だ。そんな虫のいい話があるわけない? いや、驚くなかれ、その可能性のあるいくつかの物質(アスピリン、クルクミン、ラパマイシン、メトホルミン、レスベラトロルなど)が発見されて、臨床試験もおこなわれているのだ。すでに、2000件を超える臨床試験が実施され、なんと、そういう物質を使った製品がインターネットで購入できる。
果たして、カロリー摂取量を減らせば、脳は健康になるのだろうか? すでに解説したように、ことエネルギーに関して脳は大喰らいだ。全体のエネルギーの20%を消費する。つまり、1日に2000キロカロリーを消費しているなら、そのうちの約400キロカロリーは脳が使っていることになる。脳を酷使すればそれ以上になる。といっても、痩せるために必死に頭を使っても、効果は薄い。そんなことをしても、消費されるカロリーは誤差程度でしかない。普段より、1日あたりわずか20キロカロリー余分に消費されるだけだ。そこで、疑問を違う方向から考えてみよう。食べすぎが脳機能の低下リスクを高めることはわかっている。
2012年に米国でおこなわれた70~92歳の1200人以上を対象にした研究では、中年以降の人が高カロリー(1日2143キロカロリー以上)を摂取した場合と、1日1526キロカロリー以下で抑えた場合を比べた。すると、前者では晩年の記憶障害のリスクが2倍になることがわかった。さらに過剰なカロリー摂取が脳に悪影響を及ぼすメカニズムもわかっている。それは主に、酸化物質のフリーラジカル(遊離基)が、脳細胞に大きな負荷をかけるからだ。
フリーラジカルは電気を帯びた粒子で、 余分な電子(余剰酸素など)を持っていて、細胞内の物質やDNAを攻撃し、酸化ストレスを引き起こす。
毎日、DNAはフリーラジカルから3万回以上の攻撃を受け、もちろん脳内でもそういったことが起きている。フリーラジカルは細胞の正常な生成物だが、数が増えすぎると代謝に悪影響を及ぼす。食べすぎると細胞内のミトコンドリア(エネルギー生産工場)が、有害なフリーラジカルを発生させる。だから食べすぎは絶対に良くないのだ。
一方で、食品の中にはフリーラジカルを退治する抗酸化物質を多く含むものがあり、健康的な食生活によって抗酸化物質を摂取できる。これについては第5章で解説する。
先の疑問に戻ろう。たとえば10%、あるいは11%でも摂取カロリーを減らすと、脳にいくつもの効果があることは、数多くの実験で証明されている。摂取カロリーを制限すると、抗炎症、酸化ストレスの減少、脳のシナプス可塑性の促進、神経栄養因子(第2章の運動の効能で触れたBDNFなど)の増加につながり、脳細胞の成長が促される。要は加齢による脳細胞へのダメージを防いでくれるのだ。
そのために、やるべきことはひとつだけ。少なめに食べる。これに尽きる。少なめとはどのぐらいの量なのか? 1日に1回はお腹がすいたと感じるようにすればいい。
裏づけとなるミュンスター実験を見てみよう。2008年にドイツのミュンスター大学でおこなわれた研究で、平均年齢60歳の健康な50人を3つのグループに分けた。ひとつのグループには、摂取カロリーを30%減らすように求めた(実際には、大半の被験者は約10%減らすのが精一杯だった)。もうひとつのグループは、食事で摂取する飽和脂肪を減らし、代わりに不飽和脂肪を摂るようにした。もうひとつのグループは対照群で、これまでどおりの食事を取った。実験期間は3か月で、開始時と終了時に、被験者は全員、記憶力テストを受けた。終了時の記憶力テストでは、カロリー制限をおこなったグループだけが、テストの成績が20%上がった。さらに、このグループはほかのグループに比べて、インスリン値が下がり(カロリー制限の特性)、炎症レベル(CRPの値)も低下した。
さて、この結果から何がわかるのだろう? 第一に、高カロリー摂取は心臓に悪いだけではなく、脳にも悪いことだ。第二に、摂取カロリーを減らせば、脳に良い効果がある。
ミュンスター実験の被験者は少人数だったが、その結果は世界中でのさまざまな研究プロジェクトで裏づけられている。そういったプロジェクトのひとつに沖縄式の食事がある。それは、腹八分目で食卓を離れるというものだ。沖縄式の食事を実践している人たちは、平均的な日本人に比べて、摂取カロリーが20%ほど少なくなる。第2章の冒頭で取りあげた通り、昔ながらの暮らしがいまなお残る沖縄は、世界有数のブルーゾーンで長寿の人が多く、アルツハイマー病患者は少ない。
カロリー摂取と脳についてわかっていることを、表3-2にまとめた。
<第5回に続く>3-2 カロリー制限と健康な脳
⚫摂取カロリーを20~30%減らすと、ほぼすべての生き物で寿命が延び、老化による病気の発症が遅れる。
⚫だが、このレベルのカロリー制限は食事療法として推奨できない。ほとんどの人は、ここまで厳しいカロリー制限に耐えられないからだ。
⚫現実的に考えると、いつもより摂取カロリーを10%ほど減らす。これなら、大半の人が実行できる。
⚫10%でも摂取カロリーを減らせば、さまざまな良い影響がある。肥満の改善、血圧の低下、血糖値、インスリン値、血中コレステロール値、中性脂肪値が改善され、血液中の炎症マーカーが減る。
⚫摂取カロリーを減らすと、記憶や学習などの認知機能が向上する。
⚫食べすぎ(1日2000キロカロリー以上)は、脳機能障害のリスクを高める。























